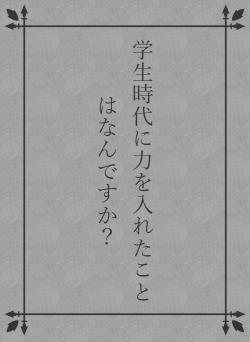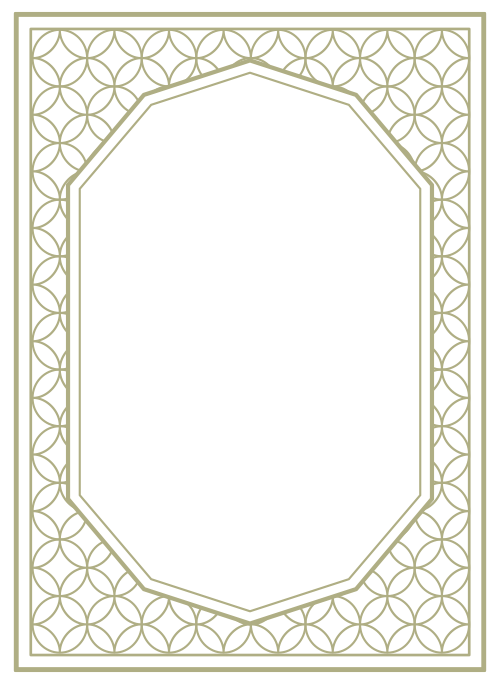***
丸窓の外から、さらさらとした光が降り注いでいた。
──朝だ。
そう思った瞬間、ばさりと起き上がろうとし、支度をしなければという焦りに駆られた。
けれども背中に違和感を覚えて振り返る。
「なんだ、もう起きるのか」
「あ、有真様!?」
昨夜、寝床は別々にしようと提案していたのは有真様のほうだった。
私はそれをありがたく受け取り、新しい屋敷の下で、なかなか眠りにつけない時間を過ごしてはようやく朝を迎えたというのに。
「いつからここに……」
「さあ、覚えていないな。ただ千代が恋しくなったことだけは覚えている」
躊躇いもなく、朝からなんてことはない口調で言うものだから手で顔を覆い隠す。
「どうした?」
「そ、そのようなもったいないお言葉は……」
朝は忙しく、寝床から飛び起きるようにして様々な支度を済ませてきた。
そんな生活から一変したことでさえまだ追いついていないというのに。
「それより、まだ時間も早いだろう。ゆっくり眠ればいい」
「そういうわけには……食事の支度もありますし」
「しなくていい。他の者が好んでやっているだろう」
他の者とは一体誰のことだろうか。
この屋敷に入る前には「人が出払っている」と言っていた。ということは、ここに住むのは有真様だけではないということだろう。
「千代、こっちに」
起き上がろうとすれば、抱き寄せられ、結果的に寝転んだ状態に戻されてしまう。
「あの、何かさせていただかないと……」
「それなら、ここで俺と一緒に二度寝をするのはどうだろう」
「に、二度寝……」
そんな夢のような話があっていいのだろうか。
ここに来る前であれば、何度か「このまま眠りにつきたい」と思ったことはあったけれど、それは決して許されるものではなかった。
「……罪悪感が」
「あるのか? なら一緒に起きよう」
「いいのですか?」
「二度寝はいつでもできる。千代が罪悪感を抱かなくなったときにすればいい」
優しく穏やかな声音。そのどれもが、私を責め立てることなく包み込まれるような温かさを持っていた。
衣の上で艶やかに光る紅い髪。結われることなく、背中で揺れているのをじっと見つめていると。
「せっかくなら手伝ってはくれないか」
振り返った有真様が、私を見てふっと微笑んだ。
男性の髪に触れたことなど、人生で一度もなかった。それなのに、今は私に背を向け「千代が結ってくれるならそれがいい」と目を閉じて待っている人がいる。
自分の髪でさえ、きちんと結ったことはない。唯一持っていた手鏡を美代に割られてしまってからというもの、確認できることがなく、不自然な位置でまとめていることが多かった。
手入れが行き届いたその髪は「特別なことは何もしていない」と聞いたばかりだ。それなのに、朝の光を受けて鮮やかな紅に光る髪に、そっと手を伸ばし、直前で止める。
「……本当に私が触れてしまってもいいのですか?」
「構わない、千代がいい」
立ち姿は私よりも背が高いため、つむじまで見えてしまうような光景に変な緊張感が走る。
「……とても綺麗な髪ですね」
遠慮がちに触れ、ゆっくりと毛先を持ち上げた。
「それは君も同じだろう」
有真様が振り向き、今度は私の毛先に触れた。
「美しい髪をしているなとずっと思っていた」
「そんな……」
それこそ、特別なことができるような環境ではなかった。それでも有真様は「綺麗だ」とまた口にした。
「たくさんのことを、この髪は見てきたのだろうな」
「え……」
「どんなときも、千代を守ってきたのだろう」
守られているという感覚を持ったことがなかった。愛着などなかった自分の髪が、有真様に触れてもらえたことで特別なものへと変わっていく。
心が安らぐような不思議な時間。いつまでも続いてほしいと、願ってしまう。
有真様の髪を結い終え、この近くを散歩してみようということになった。
屋敷の門を背にして歩き出すと、ひんやりとした風が頬を撫で、秋の訪れを感じさせた。道端の草むらからは虫たちのかすかな声が響き、まるで自分の歩みを見守るかのように寄り添っている。
砂利道を進むうちに、徐々に視界が開けた。その先に見えたのは、燃えるように鮮やかな赤で埋め尽くされた丘。彼岸花だ。
どこまでも広がるその光景は、まるで地上の炎のようで、どこか儚さを感じさせた。一輪一輪の花が風に揺れるたび、赤い波が波紋のように広がっていく。
遠くから見ると、まるで一枚の絵のように美しい。しかし近づいてみると、その花の茎には毒を秘めたような不思議な力が宿っているのがわかる。
かつて授業で、彼岸花は「死者の花」と呼ばれ、冥界への道を照らすものだと聞いたことを思い出す。だからこそ、この丘に咲く花々には、どこか触れてはならない神聖さが漂っているように思える。
ふと足を止めると、甘くもない、しかし清々しい香りが風に乗って漂ってきた。これが彼岸花の香りなのか、それとも土の匂いが混じった秋の風のせいなのか。そんなことを考えているうちに、胸の奥に不思議な静けさが広がっていくのを感じた。
私はそっと視線を足元に落とした。
小さい頃から、畦道や墓地のそばで揺れるこの赤い花を目にするたびに、不思議と引き寄せられるような気がしていた。まるでこの花が、自分を誘っているように思えたのだ。
もしこの花を口にすれば、すべてが終わり、解放されるのではないか――そんな考えが、幾度となく心をよぎった。しかし、同時にその後に起こることもよくわかっていた。自分が死ねば、別の誰かが生贄として選ばれてしまう。それだけは避けたかった。
「だから、通り過ぎるだけにしているんです。この花のそばを……」
言葉を絞り出すと、隣の彼はしばらく黙ったままだった。その沈黙に、胸がざわめく。何を思われているのだろう。
「これは見るだけでいい」
ふと、彼が低く穏やかな声でつぶやいた。
それが今では、綺麗だとついこぼれるように見えているなんて。
「じゃあ、天界に咲く花とも呼ばれていることも知ってるか?」
有真様が穏やかな声で問いかけた。その柔らかな調子に、少しだけ緊張がほぐれる。
「天界……それは知りませんでした」
「めでたいことが起こる兆しに、赤い花が天から降ってくるんだ」
「そんな言い伝えが……あ」
思わず声を詰まらせる。記憶の奥底から、一つの光景が浮かび上がったのだ。
駕籠の中に揺られていたあの日。まだ幼かった私は、山へと運ばれていく途中だった。駕籠の隙間から見える景色はどこか霞がかり、ぼんやりと赤い色が揺れていた。そのときはただ、赤い何かが風に乗って舞い降りてきたのだとしか思っていなかった。
けれど、あれは彼岸花だったのだろうか。あの燃えるような赤は、今目の前に広がるこの花々と同じ色をしていた気がする。
「駕籠に乗せられて、山に向かう途中のことです。隙間から見えた赤い花が、そうだったのでしょうか……」
自分でも思わず声に出していた。
有真様は少しだけ首を傾げ、考えるように視線を巡らせた。
「そうかもしれないな。そのとき、千代は何を思った?」
質問されると同時に、胸の奥に眠っていた感情が目を覚ます。あのときの私は――。
「……怖いと思いました。でも、なぜか美しいとも感じたんです。死に向かう自分を、誰かが祝福してくれているようで……変ですよね」
赤い花が空から降ってきたとき、不安と恐れの中で不思議な安らぎも覚えていた。あれはきっと、何かを終わらせ、新たな始まりを告げる兆しだったのかもしれない。
有真様はじっと私を見つめたあと、静かに頷いた。
「変じゃない。どんな花も、見る人の心次第で意味が変わるものだ。そのときの千代にとって、あの赤い花は……きっと、ただの彼岸花じゃなかったんだろうな」
「そうだと思います。きっと……有真様と会える兆しだったのですね」
「それは千代にとってはめでたいことだったかな」
「もちろんです」
ここに拾われていなければ、私はあのまま心を失い、そして身を滅ぼしていたことだろう。荒れ果てた心のまま、どこかで毒を持つと知りながら彼岸花を手折り、その赤い花弁を口にしていたに違いない。あの鮮烈な赤は、まるで終わりへの誘いのようだった。
しかし、そんな私を引き留め、ここへ導いてくれたのは紛れもない「縁」だったのだろう。それがどのような意味を持つものかはわからない。ただ、この場所にいる今だけは、確かに私は生きている──そんな実感があった。
目の前で彼岸花が風に揺れる中、有真様が微かに微笑んでつぶやいた。
「それならよかった。まあ、ここは天界ではないけどな」
その言葉にふっと胸が温かくなった。
「……いいえ、私にとっては天界です」
自分でも驚くほど自然に、言葉が口をついて出た。有真様が軽く目を見開き、次いで柔らかな微笑みを浮かべるのが見えた。
神がいる場所こそ天界だという人もいる。けれども、私にとってこの場所は天界と同じ意味を持っていた。
「あの村にいた頃とは違うんです。ここでは、少なくとも心が保たれていますから」
村での日々を思い出すたび、胸の奥が冷たくなる。あの場所にいる限り、私の心はいつか完全に壊れていただろう。それを思うと、今この場所にいることが奇跡のように思える。
有真様はしばらく黙っていたが、やがて静かに目を閉じると、低い声で言った。
「それがこの場所の役目だとしたら、ここに来た意味はきっとあるんだろうな」
その言葉はどこか遠くを見つめるようでありながら、私の胸に直接語りかけるようでもあった。
風が吹き抜け、彼岸花がざわりと揺れる。その音が、私をどこか遠い世界に連れ戻すような気がした。けれども今は、この地に足をつけて生きていこう──そんな想いが心に灯る。
「あれ、このお花……」
屋敷に戻ると、玄関に活けられていた彼岸花が、くたりと萎れているのに気づいた。花弁の鮮烈な赤は薄れ、茎も力を失っている。さっきまで丘で見たあの花の美しさが嘘のようだ。
「ああ、人間界で何か厄災でも起こっているんだろうな」
私が思案する間に、有真様が何気ない調子でそう言った。
「厄災……ですか?」
意味を飲み込めず、思わず首を傾げると、有真様はふと玄関の外へと続く道に目をやった。その横顔はどこか遠くを見るようで、言葉の先を考えているようにも見える。
「千代がいた村で起こっているんだろう。この花はあの村から取ってきたものだからな」
静かな口調でそう告げられ、胸がざわつく。
確かに私の故郷、あの村では彼岸花がよく咲いていた。畦道や墓地、村の至るところで燃えるような赤が揺れていたのを思い出す。有真様があの村へ足を運び、花を持ち帰ったのだろうか?
「あの、私の村で……何が起こっているのでしょうか?」
心がざわめくままに問いかける。家族や村の人々のことが頭をよぎる。私がここに来たあと、何かが変わってしまったのだろうか。
しかし、有真様は肩をすくめ、軽く笑っただけだった。
「なんだろうねえ。千代が来るまでは気にしていたけど、今となっては興味もない」
その言葉に、小さな衝撃が胸を打つ。軽い調子の裏には、何か意図があるのだろうか? それとも本当に、村のことはもう重要ではないのだろうか?
「気にする必要もない。お前はもうここにいるんだからな」
まるで自分に言い聞かせるように付け加えられたその言葉に、私は頷きかけたけれど。
「様子を見に行ってはいけませんか……?」
自分でも驚くほど静かな声でそう尋ねた。
ほんの少しでいい。村で何が起こっているのか知りたい。今も生きている家族が、無事であるのか。それを確かめられれば……。
けれど、有真様は私の言葉に返答せず、ただ玄関先に目を向けたままだった。その横顔は、どこか冷たさと優しさが混じり合っているように見えた。
「千代があの村に?」
私の願いを受けた有真様の声は、冷たく鋭く響いた。一瞬、その冷たさが自分に向けられているのかと怯えたが、次の瞬間、その声の向かう先はあの村そのものだと気づいた。有真様の瞳には、軽蔑の色が明らかだった。
「どうして気になるんだ。千代を生贄として俺の元に寄越した連中の集まりだろう」
その言葉に胸が痛んだ。けれど、有真様は構わず続けた。
「それに──」
ふいに一歩、私の方へと近づく。目の前で低い声が重く響いた。
「誰よりも千代を邪魔者扱いしたのは、ほかでもない千代の家族だ。あんな連中を気にかける必要などない」
「……それは」
言い返せなかった。喉元に詰まった言葉を飲み込む。
確かに、有真様の言う通りだった。私が村に戻ったところで、何かが変わるわけではない。あの人たちは私の帰りなど望んでいない。むしろ、あの村の平穏のために私がここにいることを願っているだろう。
それでも──。
「……ここまで生かしてもらった恩があるんです」
自分でも不思議なくらい静かに、けれどしっかりとした声が出た。
あの村では、いつ死んでもおかしくない運命だった。虐げられる日々は確かに苦しかった。それでも、彼らは私を家族として屋根の下に置いてくれた。もし、あの村で命を落としていたら、有真様に出会うこともできなかった。
「様子を見るだけです……逃げるつもりはございませんので」
顔を上げて、真っ直ぐに有真様の目を見る。彼の瞳が僅かに揺れたように見えた。
「そんなことは心配していない。ただ、本当に気になるのか?」
その問いに、私は小さく、けれど確かに頷いた。
「……わかった」
有真様は短く息を吐くと、やがて言った。
「千代の気が済むままにすればいい」
丸窓の外から、さらさらとした光が降り注いでいた。
──朝だ。
そう思った瞬間、ばさりと起き上がろうとし、支度をしなければという焦りに駆られた。
けれども背中に違和感を覚えて振り返る。
「なんだ、もう起きるのか」
「あ、有真様!?」
昨夜、寝床は別々にしようと提案していたのは有真様のほうだった。
私はそれをありがたく受け取り、新しい屋敷の下で、なかなか眠りにつけない時間を過ごしてはようやく朝を迎えたというのに。
「いつからここに……」
「さあ、覚えていないな。ただ千代が恋しくなったことだけは覚えている」
躊躇いもなく、朝からなんてことはない口調で言うものだから手で顔を覆い隠す。
「どうした?」
「そ、そのようなもったいないお言葉は……」
朝は忙しく、寝床から飛び起きるようにして様々な支度を済ませてきた。
そんな生活から一変したことでさえまだ追いついていないというのに。
「それより、まだ時間も早いだろう。ゆっくり眠ればいい」
「そういうわけには……食事の支度もありますし」
「しなくていい。他の者が好んでやっているだろう」
他の者とは一体誰のことだろうか。
この屋敷に入る前には「人が出払っている」と言っていた。ということは、ここに住むのは有真様だけではないということだろう。
「千代、こっちに」
起き上がろうとすれば、抱き寄せられ、結果的に寝転んだ状態に戻されてしまう。
「あの、何かさせていただかないと……」
「それなら、ここで俺と一緒に二度寝をするのはどうだろう」
「に、二度寝……」
そんな夢のような話があっていいのだろうか。
ここに来る前であれば、何度か「このまま眠りにつきたい」と思ったことはあったけれど、それは決して許されるものではなかった。
「……罪悪感が」
「あるのか? なら一緒に起きよう」
「いいのですか?」
「二度寝はいつでもできる。千代が罪悪感を抱かなくなったときにすればいい」
優しく穏やかな声音。そのどれもが、私を責め立てることなく包み込まれるような温かさを持っていた。
衣の上で艶やかに光る紅い髪。結われることなく、背中で揺れているのをじっと見つめていると。
「せっかくなら手伝ってはくれないか」
振り返った有真様が、私を見てふっと微笑んだ。
男性の髪に触れたことなど、人生で一度もなかった。それなのに、今は私に背を向け「千代が結ってくれるならそれがいい」と目を閉じて待っている人がいる。
自分の髪でさえ、きちんと結ったことはない。唯一持っていた手鏡を美代に割られてしまってからというもの、確認できることがなく、不自然な位置でまとめていることが多かった。
手入れが行き届いたその髪は「特別なことは何もしていない」と聞いたばかりだ。それなのに、朝の光を受けて鮮やかな紅に光る髪に、そっと手を伸ばし、直前で止める。
「……本当に私が触れてしまってもいいのですか?」
「構わない、千代がいい」
立ち姿は私よりも背が高いため、つむじまで見えてしまうような光景に変な緊張感が走る。
「……とても綺麗な髪ですね」
遠慮がちに触れ、ゆっくりと毛先を持ち上げた。
「それは君も同じだろう」
有真様が振り向き、今度は私の毛先に触れた。
「美しい髪をしているなとずっと思っていた」
「そんな……」
それこそ、特別なことができるような環境ではなかった。それでも有真様は「綺麗だ」とまた口にした。
「たくさんのことを、この髪は見てきたのだろうな」
「え……」
「どんなときも、千代を守ってきたのだろう」
守られているという感覚を持ったことがなかった。愛着などなかった自分の髪が、有真様に触れてもらえたことで特別なものへと変わっていく。
心が安らぐような不思議な時間。いつまでも続いてほしいと、願ってしまう。
有真様の髪を結い終え、この近くを散歩してみようということになった。
屋敷の門を背にして歩き出すと、ひんやりとした風が頬を撫で、秋の訪れを感じさせた。道端の草むらからは虫たちのかすかな声が響き、まるで自分の歩みを見守るかのように寄り添っている。
砂利道を進むうちに、徐々に視界が開けた。その先に見えたのは、燃えるように鮮やかな赤で埋め尽くされた丘。彼岸花だ。
どこまでも広がるその光景は、まるで地上の炎のようで、どこか儚さを感じさせた。一輪一輪の花が風に揺れるたび、赤い波が波紋のように広がっていく。
遠くから見ると、まるで一枚の絵のように美しい。しかし近づいてみると、その花の茎には毒を秘めたような不思議な力が宿っているのがわかる。
かつて授業で、彼岸花は「死者の花」と呼ばれ、冥界への道を照らすものだと聞いたことを思い出す。だからこそ、この丘に咲く花々には、どこか触れてはならない神聖さが漂っているように思える。
ふと足を止めると、甘くもない、しかし清々しい香りが風に乗って漂ってきた。これが彼岸花の香りなのか、それとも土の匂いが混じった秋の風のせいなのか。そんなことを考えているうちに、胸の奥に不思議な静けさが広がっていくのを感じた。
私はそっと視線を足元に落とした。
小さい頃から、畦道や墓地のそばで揺れるこの赤い花を目にするたびに、不思議と引き寄せられるような気がしていた。まるでこの花が、自分を誘っているように思えたのだ。
もしこの花を口にすれば、すべてが終わり、解放されるのではないか――そんな考えが、幾度となく心をよぎった。しかし、同時にその後に起こることもよくわかっていた。自分が死ねば、別の誰かが生贄として選ばれてしまう。それだけは避けたかった。
「だから、通り過ぎるだけにしているんです。この花のそばを……」
言葉を絞り出すと、隣の彼はしばらく黙ったままだった。その沈黙に、胸がざわめく。何を思われているのだろう。
「これは見るだけでいい」
ふと、彼が低く穏やかな声でつぶやいた。
それが今では、綺麗だとついこぼれるように見えているなんて。
「じゃあ、天界に咲く花とも呼ばれていることも知ってるか?」
有真様が穏やかな声で問いかけた。その柔らかな調子に、少しだけ緊張がほぐれる。
「天界……それは知りませんでした」
「めでたいことが起こる兆しに、赤い花が天から降ってくるんだ」
「そんな言い伝えが……あ」
思わず声を詰まらせる。記憶の奥底から、一つの光景が浮かび上がったのだ。
駕籠の中に揺られていたあの日。まだ幼かった私は、山へと運ばれていく途中だった。駕籠の隙間から見える景色はどこか霞がかり、ぼんやりと赤い色が揺れていた。そのときはただ、赤い何かが風に乗って舞い降りてきたのだとしか思っていなかった。
けれど、あれは彼岸花だったのだろうか。あの燃えるような赤は、今目の前に広がるこの花々と同じ色をしていた気がする。
「駕籠に乗せられて、山に向かう途中のことです。隙間から見えた赤い花が、そうだったのでしょうか……」
自分でも思わず声に出していた。
有真様は少しだけ首を傾げ、考えるように視線を巡らせた。
「そうかもしれないな。そのとき、千代は何を思った?」
質問されると同時に、胸の奥に眠っていた感情が目を覚ます。あのときの私は――。
「……怖いと思いました。でも、なぜか美しいとも感じたんです。死に向かう自分を、誰かが祝福してくれているようで……変ですよね」
赤い花が空から降ってきたとき、不安と恐れの中で不思議な安らぎも覚えていた。あれはきっと、何かを終わらせ、新たな始まりを告げる兆しだったのかもしれない。
有真様はじっと私を見つめたあと、静かに頷いた。
「変じゃない。どんな花も、見る人の心次第で意味が変わるものだ。そのときの千代にとって、あの赤い花は……きっと、ただの彼岸花じゃなかったんだろうな」
「そうだと思います。きっと……有真様と会える兆しだったのですね」
「それは千代にとってはめでたいことだったかな」
「もちろんです」
ここに拾われていなければ、私はあのまま心を失い、そして身を滅ぼしていたことだろう。荒れ果てた心のまま、どこかで毒を持つと知りながら彼岸花を手折り、その赤い花弁を口にしていたに違いない。あの鮮烈な赤は、まるで終わりへの誘いのようだった。
しかし、そんな私を引き留め、ここへ導いてくれたのは紛れもない「縁」だったのだろう。それがどのような意味を持つものかはわからない。ただ、この場所にいる今だけは、確かに私は生きている──そんな実感があった。
目の前で彼岸花が風に揺れる中、有真様が微かに微笑んでつぶやいた。
「それならよかった。まあ、ここは天界ではないけどな」
その言葉にふっと胸が温かくなった。
「……いいえ、私にとっては天界です」
自分でも驚くほど自然に、言葉が口をついて出た。有真様が軽く目を見開き、次いで柔らかな微笑みを浮かべるのが見えた。
神がいる場所こそ天界だという人もいる。けれども、私にとってこの場所は天界と同じ意味を持っていた。
「あの村にいた頃とは違うんです。ここでは、少なくとも心が保たれていますから」
村での日々を思い出すたび、胸の奥が冷たくなる。あの場所にいる限り、私の心はいつか完全に壊れていただろう。それを思うと、今この場所にいることが奇跡のように思える。
有真様はしばらく黙っていたが、やがて静かに目を閉じると、低い声で言った。
「それがこの場所の役目だとしたら、ここに来た意味はきっとあるんだろうな」
その言葉はどこか遠くを見つめるようでありながら、私の胸に直接語りかけるようでもあった。
風が吹き抜け、彼岸花がざわりと揺れる。その音が、私をどこか遠い世界に連れ戻すような気がした。けれども今は、この地に足をつけて生きていこう──そんな想いが心に灯る。
「あれ、このお花……」
屋敷に戻ると、玄関に活けられていた彼岸花が、くたりと萎れているのに気づいた。花弁の鮮烈な赤は薄れ、茎も力を失っている。さっきまで丘で見たあの花の美しさが嘘のようだ。
「ああ、人間界で何か厄災でも起こっているんだろうな」
私が思案する間に、有真様が何気ない調子でそう言った。
「厄災……ですか?」
意味を飲み込めず、思わず首を傾げると、有真様はふと玄関の外へと続く道に目をやった。その横顔はどこか遠くを見るようで、言葉の先を考えているようにも見える。
「千代がいた村で起こっているんだろう。この花はあの村から取ってきたものだからな」
静かな口調でそう告げられ、胸がざわつく。
確かに私の故郷、あの村では彼岸花がよく咲いていた。畦道や墓地、村の至るところで燃えるような赤が揺れていたのを思い出す。有真様があの村へ足を運び、花を持ち帰ったのだろうか?
「あの、私の村で……何が起こっているのでしょうか?」
心がざわめくままに問いかける。家族や村の人々のことが頭をよぎる。私がここに来たあと、何かが変わってしまったのだろうか。
しかし、有真様は肩をすくめ、軽く笑っただけだった。
「なんだろうねえ。千代が来るまでは気にしていたけど、今となっては興味もない」
その言葉に、小さな衝撃が胸を打つ。軽い調子の裏には、何か意図があるのだろうか? それとも本当に、村のことはもう重要ではないのだろうか?
「気にする必要もない。お前はもうここにいるんだからな」
まるで自分に言い聞かせるように付け加えられたその言葉に、私は頷きかけたけれど。
「様子を見に行ってはいけませんか……?」
自分でも驚くほど静かな声でそう尋ねた。
ほんの少しでいい。村で何が起こっているのか知りたい。今も生きている家族が、無事であるのか。それを確かめられれば……。
けれど、有真様は私の言葉に返答せず、ただ玄関先に目を向けたままだった。その横顔は、どこか冷たさと優しさが混じり合っているように見えた。
「千代があの村に?」
私の願いを受けた有真様の声は、冷たく鋭く響いた。一瞬、その冷たさが自分に向けられているのかと怯えたが、次の瞬間、その声の向かう先はあの村そのものだと気づいた。有真様の瞳には、軽蔑の色が明らかだった。
「どうして気になるんだ。千代を生贄として俺の元に寄越した連中の集まりだろう」
その言葉に胸が痛んだ。けれど、有真様は構わず続けた。
「それに──」
ふいに一歩、私の方へと近づく。目の前で低い声が重く響いた。
「誰よりも千代を邪魔者扱いしたのは、ほかでもない千代の家族だ。あんな連中を気にかける必要などない」
「……それは」
言い返せなかった。喉元に詰まった言葉を飲み込む。
確かに、有真様の言う通りだった。私が村に戻ったところで、何かが変わるわけではない。あの人たちは私の帰りなど望んでいない。むしろ、あの村の平穏のために私がここにいることを願っているだろう。
それでも──。
「……ここまで生かしてもらった恩があるんです」
自分でも不思議なくらい静かに、けれどしっかりとした声が出た。
あの村では、いつ死んでもおかしくない運命だった。虐げられる日々は確かに苦しかった。それでも、彼らは私を家族として屋根の下に置いてくれた。もし、あの村で命を落としていたら、有真様に出会うこともできなかった。
「様子を見るだけです……逃げるつもりはございませんので」
顔を上げて、真っ直ぐに有真様の目を見る。彼の瞳が僅かに揺れたように見えた。
「そんなことは心配していない。ただ、本当に気になるのか?」
その問いに、私は小さく、けれど確かに頷いた。
「……わかった」
有真様は短く息を吐くと、やがて言った。
「千代の気が済むままにすればいい」