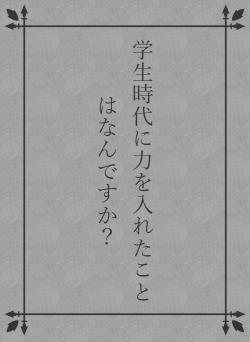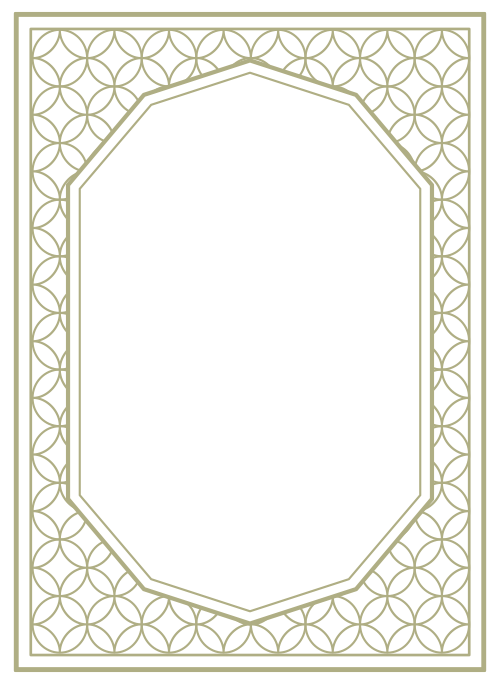***
目の前に広がっていたのは、想像を遥かに超える壮麗なお屋敷だった。どこまでも高い屋根は漆黒で、まるで夜空の一部のように輝いている。その軒先を彩るのは、金色の装飾。まばゆいばかりの輝きで、夜の闇をも跳ね返しているようだった。
思わず視線を引き寄せられたのは、大きく彫られた鳥の彫刻。その姿はまるで、今にも羽ばたき出しそうなほど精緻だった。いつの日かどこかで見た記憶がぼんやりとよみがえる。
「鳳凰だ」
隣を歩く男が、低い声でそう告げる。その一言が、彫刻に宿る気高さをさらに際立たせた。
そう言われて改めて見ると、男の纏う着物にも同じ意匠が織り込まれている。黒地に金と赤で描かれた鳳凰の姿が、まるで生きているようだ。布が揺れるたび、その羽が動いているかのように見え、無意識に息を飲む。
「その鳥なら……教科書で見たことがあります」
「伝説の生き物として?」
はい、と頷けば「ここにいればいつか会える」と男は楽しそうに言った。
「ここはあなたの……」
そこで、はたと気付く。
名前を聞いていなかった。男も同じことを考えたのだろう。
「有真だ。好きに呼ぶといい」
好きにと言われると困ってしまう。有真様と今は呼んだほうがいいのだろうか。
彼は屋敷の玄関扉を開けた。
「俺以外誰もいない。遠慮しないで」
こんな大きな屋敷に一人で……?
入った途端に、もしかしたら何かしらが起こるのではないかと怖くなる。例えば、足を踏み入れた瞬間に身が焼かれるだとか、とんでもない場所に飛ばされているだとか。
「怖がらなくても大丈夫」
私の不安を見通したようで、「緊張で……」と誤魔化して見せたが、それでも有真さんは「そうか」と見透かしたように微笑んでいる。
そっと敷地を跨いでみたが、どうにかなるということはなかった。
ほっと安心しながら、屋敷の中を見渡す。奥へと続く長い廊下が目の前にあり、玄関にはなぜか一輪挿しの花が活けられていた。
「彼岸花……」
「ああ、君が活けてくれたのを気に入ってそのままにしているんだ」
「私がですか?」
この屋敷に来たことはない。活けた記憶ももちろんないけれど。
「地蔵に供えたことがあるだろう?」
そう言われて、遠い記憶がふと蘇った。そういえば、そんなことが一度だけあったかもしれない。
「お地蔵様とここは繋がっているのですか?」
「同じようなものだ。さあ、中を案内しよう」
何が同じなのだろう。有真さんがふと漏らした言葉に、疑問が胸に浮かぶ。しかしその意味を尋ねる余裕もなく、彼の後を追って屋敷の奥へと進んでいった。
廊下は長く、天井が高い。柱や梁は黒檀のように深い色をしており、壁には金や朱の装飾が施されている。どこを見ても無駄がなく、すべてが計算された美しさでまとまっている。灯りは行灯が等間隔に置かれているだけだが、その柔らかい光が廊下を照らし、夜の静けさをより引き立てている。
歩みを進めるたびに、屋敷の中から香木の香りが漂ってきた。鼻をくすぐるその香りは心地よく、まるでこの空間が異世界であることを強調しているかのようだった。
「ここだ」
有真さんに促され、足を止めたのは広い部屋だった。部屋の中央には何もない。畳敷きが広がり、壁際には整然と並べられた掛け軸や屏風が置かれているだけだ。装飾の少なさがかえってこの空間の特別さを際立たせていた。
その先の開け放たれた障子の向こうには、手入れの行き届いた庭が広がっている。月明りを浴びて白砂が煌めき、苔むした石や水をたたえた池が美しい調和を見せている。遠くには一本の松の木が堂々とそびえ、その根元には鮮やかな紅色の椿が咲いていた。
「気に入ってもらえたようだな」
「は、はい」
池も花も木も、よく手入れされている。小鳥のさえずりがどこかから聞こえていた。
「そうだ。儀式をしないといけないな」
有真さんが思い出したように言った。
「儀式?」
「婚姻だ。面倒な習わしだし、千代が必要なければ別にすることもない」
そんな曖昧なものでいいのだろうか。私が「やりません」などと言えば、この人は「わかった」と簡単にうなずいてしまうだろう。
「し、従います……ここの仕来りに」
「そうか。じゃあ気が向いたときにでもしよう」
なんとも呆気なく話が流れてしまった。
一応は生贄としてやってきたつもりだけれど、今のところ辛い目に遭うようなことはない。
「あの……私はどうしていたらいいですか?」
「行きたいところはあるか?」
「え」
「今までの少女たちも、全員村に帰りたいか、別のところに行きたいかのどちらかだった」
殺されるかもしれないと聞いていたのに、この人からは殺気立ったものを一切感じない。今の話も本当なのだろう。
「……ないです。帰る家もありません」
「それならここにいるといい」
屋敷の中はどこまでも広く、そして人ならざるものの気配が佇んでいた。
人が出払っているというのは本当だろうけれど、何かがずっとこちらを覗いているような感覚がする。
「気味が悪い?」
「そ、そんな。なんとなく、視線が感じるというか……」
「ああ、すまない。新しい顔を気にしている輩が多いからな。遮断させよう」
そういって、指をぱちんと鳴らすと、その視線は綺麗さっぱりと消えてしまった。
「しかし、あの輩の視線を感じるだけの体質を持っているとはすごいな」
「あの、どなたなんですか?」
「あまりこう呼ぶのは好きではないが、わかりやすく言えば神たちだな」
「神……?」
「気にしなくていい。こちらには干渉させない」
どうして神がこちらを気にしていたのだろうか。もしかすると、ここの生贄になるということは、とても大きな意味合いがあったのではないかとさえ思えてくる。
「あの……いるだけでいいんですか?」
「もちろん。自由に過ごすといい」
そう言われてしまえば、それはありがたいような気もするが、だからといってなんだか落ち着かない。
「させていただくことはありませんか? お掃除でも、お料理でも……あ、ご飯は」
「食べるよ。でも、人間のように三食必要なわけでもないし、食べなくても平気だ」
自分と同じ感覚ではない。やはりこの人は人間ではないのだろうか。
「私にできることがあれば教えてください」
「そんなに気負うこともない」
けれど、私は今日に至るまで、生贄として捧げられるだけのために生きていた。
それだけが私の存在価値だというのに──。
「なぜ泣いている?」
「え……」
有真さんに問われて、すぐに頬へと触れれば、不思議なことに濡れていた。
「あれ……そんな……こんなことはなかったのに」
涙の流し方など、とうの昔に忘れてしまっていた。心が動いてしまえば終わりだと思い、過ごしてきたためか、いつしか本当に心が動かなくなってしまった。
どれだけ酷い仕打ちを受けようが、罵られようが、いくらでも耐えてこれたはずなのに。
「……私は、なんのために生きているのでしょうか」
この世に産まれ、すぐに殺されるはずの運命だった。
けれど、生贄という宿命を背負うことで私は生かされてきたのだ。
「理由が欲しいなら、俺の妻であればいい」
「妻……」
「これまでの生き方ではなく、俺の妻として共に歩んでほしい。もちろん、無理強いはさせない」
「無理強いだなんて……」
そんなことを思うはずもない。
「……いいのでしょうか、私は有馬様の妻になっても」
彼は私の言葉を受け、花が綻ぶように笑った。
「そうしてほしいと、俺が望んでいるんだ」
目の前に広がっていたのは、想像を遥かに超える壮麗なお屋敷だった。どこまでも高い屋根は漆黒で、まるで夜空の一部のように輝いている。その軒先を彩るのは、金色の装飾。まばゆいばかりの輝きで、夜の闇をも跳ね返しているようだった。
思わず視線を引き寄せられたのは、大きく彫られた鳥の彫刻。その姿はまるで、今にも羽ばたき出しそうなほど精緻だった。いつの日かどこかで見た記憶がぼんやりとよみがえる。
「鳳凰だ」
隣を歩く男が、低い声でそう告げる。その一言が、彫刻に宿る気高さをさらに際立たせた。
そう言われて改めて見ると、男の纏う着物にも同じ意匠が織り込まれている。黒地に金と赤で描かれた鳳凰の姿が、まるで生きているようだ。布が揺れるたび、その羽が動いているかのように見え、無意識に息を飲む。
「その鳥なら……教科書で見たことがあります」
「伝説の生き物として?」
はい、と頷けば「ここにいればいつか会える」と男は楽しそうに言った。
「ここはあなたの……」
そこで、はたと気付く。
名前を聞いていなかった。男も同じことを考えたのだろう。
「有真だ。好きに呼ぶといい」
好きにと言われると困ってしまう。有真様と今は呼んだほうがいいのだろうか。
彼は屋敷の玄関扉を開けた。
「俺以外誰もいない。遠慮しないで」
こんな大きな屋敷に一人で……?
入った途端に、もしかしたら何かしらが起こるのではないかと怖くなる。例えば、足を踏み入れた瞬間に身が焼かれるだとか、とんでもない場所に飛ばされているだとか。
「怖がらなくても大丈夫」
私の不安を見通したようで、「緊張で……」と誤魔化して見せたが、それでも有真さんは「そうか」と見透かしたように微笑んでいる。
そっと敷地を跨いでみたが、どうにかなるということはなかった。
ほっと安心しながら、屋敷の中を見渡す。奥へと続く長い廊下が目の前にあり、玄関にはなぜか一輪挿しの花が活けられていた。
「彼岸花……」
「ああ、君が活けてくれたのを気に入ってそのままにしているんだ」
「私がですか?」
この屋敷に来たことはない。活けた記憶ももちろんないけれど。
「地蔵に供えたことがあるだろう?」
そう言われて、遠い記憶がふと蘇った。そういえば、そんなことが一度だけあったかもしれない。
「お地蔵様とここは繋がっているのですか?」
「同じようなものだ。さあ、中を案内しよう」
何が同じなのだろう。有真さんがふと漏らした言葉に、疑問が胸に浮かぶ。しかしその意味を尋ねる余裕もなく、彼の後を追って屋敷の奥へと進んでいった。
廊下は長く、天井が高い。柱や梁は黒檀のように深い色をしており、壁には金や朱の装飾が施されている。どこを見ても無駄がなく、すべてが計算された美しさでまとまっている。灯りは行灯が等間隔に置かれているだけだが、その柔らかい光が廊下を照らし、夜の静けさをより引き立てている。
歩みを進めるたびに、屋敷の中から香木の香りが漂ってきた。鼻をくすぐるその香りは心地よく、まるでこの空間が異世界であることを強調しているかのようだった。
「ここだ」
有真さんに促され、足を止めたのは広い部屋だった。部屋の中央には何もない。畳敷きが広がり、壁際には整然と並べられた掛け軸や屏風が置かれているだけだ。装飾の少なさがかえってこの空間の特別さを際立たせていた。
その先の開け放たれた障子の向こうには、手入れの行き届いた庭が広がっている。月明りを浴びて白砂が煌めき、苔むした石や水をたたえた池が美しい調和を見せている。遠くには一本の松の木が堂々とそびえ、その根元には鮮やかな紅色の椿が咲いていた。
「気に入ってもらえたようだな」
「は、はい」
池も花も木も、よく手入れされている。小鳥のさえずりがどこかから聞こえていた。
「そうだ。儀式をしないといけないな」
有真さんが思い出したように言った。
「儀式?」
「婚姻だ。面倒な習わしだし、千代が必要なければ別にすることもない」
そんな曖昧なものでいいのだろうか。私が「やりません」などと言えば、この人は「わかった」と簡単にうなずいてしまうだろう。
「し、従います……ここの仕来りに」
「そうか。じゃあ気が向いたときにでもしよう」
なんとも呆気なく話が流れてしまった。
一応は生贄としてやってきたつもりだけれど、今のところ辛い目に遭うようなことはない。
「あの……私はどうしていたらいいですか?」
「行きたいところはあるか?」
「え」
「今までの少女たちも、全員村に帰りたいか、別のところに行きたいかのどちらかだった」
殺されるかもしれないと聞いていたのに、この人からは殺気立ったものを一切感じない。今の話も本当なのだろう。
「……ないです。帰る家もありません」
「それならここにいるといい」
屋敷の中はどこまでも広く、そして人ならざるものの気配が佇んでいた。
人が出払っているというのは本当だろうけれど、何かがずっとこちらを覗いているような感覚がする。
「気味が悪い?」
「そ、そんな。なんとなく、視線が感じるというか……」
「ああ、すまない。新しい顔を気にしている輩が多いからな。遮断させよう」
そういって、指をぱちんと鳴らすと、その視線は綺麗さっぱりと消えてしまった。
「しかし、あの輩の視線を感じるだけの体質を持っているとはすごいな」
「あの、どなたなんですか?」
「あまりこう呼ぶのは好きではないが、わかりやすく言えば神たちだな」
「神……?」
「気にしなくていい。こちらには干渉させない」
どうして神がこちらを気にしていたのだろうか。もしかすると、ここの生贄になるということは、とても大きな意味合いがあったのではないかとさえ思えてくる。
「あの……いるだけでいいんですか?」
「もちろん。自由に過ごすといい」
そう言われてしまえば、それはありがたいような気もするが、だからといってなんだか落ち着かない。
「させていただくことはありませんか? お掃除でも、お料理でも……あ、ご飯は」
「食べるよ。でも、人間のように三食必要なわけでもないし、食べなくても平気だ」
自分と同じ感覚ではない。やはりこの人は人間ではないのだろうか。
「私にできることがあれば教えてください」
「そんなに気負うこともない」
けれど、私は今日に至るまで、生贄として捧げられるだけのために生きていた。
それだけが私の存在価値だというのに──。
「なぜ泣いている?」
「え……」
有真さんに問われて、すぐに頬へと触れれば、不思議なことに濡れていた。
「あれ……そんな……こんなことはなかったのに」
涙の流し方など、とうの昔に忘れてしまっていた。心が動いてしまえば終わりだと思い、過ごしてきたためか、いつしか本当に心が動かなくなってしまった。
どれだけ酷い仕打ちを受けようが、罵られようが、いくらでも耐えてこれたはずなのに。
「……私は、なんのために生きているのでしょうか」
この世に産まれ、すぐに殺されるはずの運命だった。
けれど、生贄という宿命を背負うことで私は生かされてきたのだ。
「理由が欲しいなら、俺の妻であればいい」
「妻……」
「これまでの生き方ではなく、俺の妻として共に歩んでほしい。もちろん、無理強いはさせない」
「無理強いだなんて……」
そんなことを思うはずもない。
「……いいのでしょうか、私は有馬様の妻になっても」
彼は私の言葉を受け、花が綻ぶように笑った。
「そうしてほしいと、俺が望んでいるんだ」