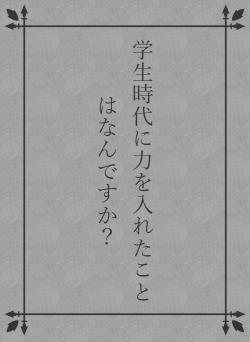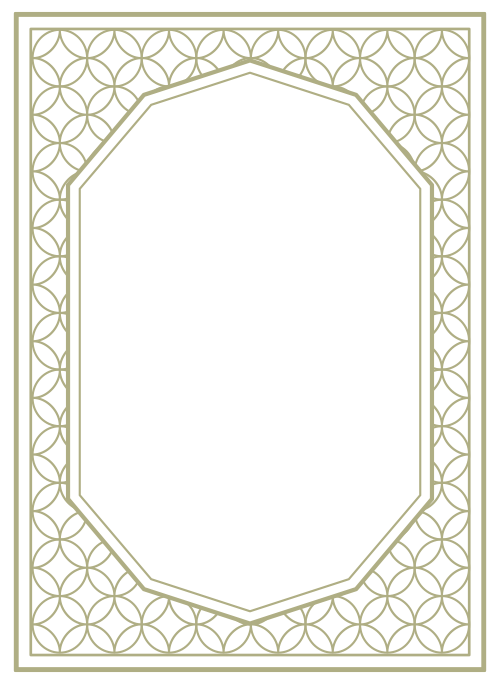***
ごとごとと揺られていた。一畳もないこの狭さは、言ってしまえばずっと私の人生そのものでしかなかった。
「可哀想になあ、実の親に売られちまうなんて」
「しっ、聞こえるぞ。ただでさえ、双子として忌み嫌われてたんだ」
山に入るには、生贄は駕籠に入り、担がれていくのが習わしだった。
人生で初めて化粧を施してもらったが、あまり似合っているようには思えなかった。
こんな私を供えられて、鬼は怒らないだろうか。
「俺は、まさか地獄の花嫁行列に参加するとは思わなかったよ」
「鬼の嫁入りするんだ。俺たちだって生きて帰れるだろうか」
「お前さん、嫁をもらったばかりだっていうのにな」
私は鬼に嫁がされる。それは産まれたときから決まっていた。
もう怖いなどと思わない。
私は山に捨て置かれ、そして結界があることで山からは出られない。
ふと隙間から赤い何かが降ってくるのが見えた。あれはなんだろうか。
「お、おい……なんか変じゃないか」
一人の男が言った。
「ここ、通ったよな?」
隙間から見えたのは、狼狽する村人たちの姿だった。彼らは何かに怯えるように右往左往している。一体何があったのだろうか。その光景に胸がざわつき不安が広がる。
突然、地鳴りのような低い音が響き渡った。それは次第に大きくなり、まるで山そのものが怒りを発しているようだった。その直後、足元が激しく揺れ始める。地震だ。
駕籠が大きく揺れ、担ぎ手たちの叫び声が上がった。その衝撃で駕籠が地面に落ち、どすんと鈍い音が響く。籠の中で体が傾き、衝撃で息を呑んだ。
「どうなってるんだ!」
外からは混乱した声が聞こえてくる。地面の揺れはしばらく続き、揺れが治まるまでの間、ただ籠の中で身を縮めて耐えるしかなかった。
揺れが収まったころ、外から誰かが駕籠に近づいてくる気配がした。その足音は一つだ。何かが起きている。私は、胸の鼓動が高鳴るのを抑えながら、次に起こることを待つしかなかった。
「まさか、鬼神様か!?」
「まずいぞ! 俺たちはまだ山から出てねえんだ!」
その瞬間、耳を塞ぎたくなるような男たちの叫び声が響いた。
何が起こっているというの……!?
そうかと思えば、辺りはしんと静まり返っている。恐る恐る外を見れば、暗闇で何も見えない。
「出ておいで」
優しい声だった。こんな人、さっきまでいただろうか。
ゆっくりと外に出てみれば、黒い髪に紅い瞳をした男が立っていた。雲で隠されていた月が空を照らすと、月明りに照らされたその顔はどこかで見覚えがある。
「……え」
そうして、駕籠の外で何があったのかがようやく見えた。
血があちらこちらで広がっていた。そこに横たわる村人たちの姿。
「た、助けてくれ……」
呻くように村人の一人が言った。
「生きているの……?」
「殺してはいない」
男が鼻歌をうたうように言った。
「千代が殺してほしいというのなら、トドメを刺すだけだ」
「どうして私の名を……」
「知ってるよ。待っていたんだから」
待っていた? 私のことを?
そのとき、着物の裾を引っ張られるような感覚がして視線を下げると、村人の一人が懇願するような目で私を見上げていた。
「頼む……嫁が……待ってるんだ」
さっき会話が聞こえていた。この人だったのか。
「……この人たちのことは、殺さないでください」
「どうして?」
男の黒い髪が風に揺れる。
「君を生贄として差し出した連中だ。生贄とは、つまり死だということをこいつらが理解していないはずはない」
わかっている。この人たちが私の死を望んでいることを。
中には、私と同じ年齢の娘を持つ父もいるだろう。
「君を差し出すことで自分たちは生きながらえようとした。そんな人間を救いたいとでも?」
「……それでも、殺していい理由にはならないです」
そこに意味を見いだせるだろうか。清々するだろうか。そんなことはない。
「生かしてあげてください」
「そ。君がそう言うならそうしよう」
その言葉を聞いた途端、村人たちは立ち上がり、慌てふためくように山を降りていく。
「あれま、人間として終わってるな」
「……いいんです、無事で帰れたら」
あの人たちを待つ家族の元に帰れればそれでいい。
「あの……あなたは?」
はは、と軽く笑う。
「言ってなかったか。すまない、嫁ぎ先は俺の元だ」
「……え?」
ごとごとと揺られていた。一畳もないこの狭さは、言ってしまえばずっと私の人生そのものでしかなかった。
「可哀想になあ、実の親に売られちまうなんて」
「しっ、聞こえるぞ。ただでさえ、双子として忌み嫌われてたんだ」
山に入るには、生贄は駕籠に入り、担がれていくのが習わしだった。
人生で初めて化粧を施してもらったが、あまり似合っているようには思えなかった。
こんな私を供えられて、鬼は怒らないだろうか。
「俺は、まさか地獄の花嫁行列に参加するとは思わなかったよ」
「鬼の嫁入りするんだ。俺たちだって生きて帰れるだろうか」
「お前さん、嫁をもらったばかりだっていうのにな」
私は鬼に嫁がされる。それは産まれたときから決まっていた。
もう怖いなどと思わない。
私は山に捨て置かれ、そして結界があることで山からは出られない。
ふと隙間から赤い何かが降ってくるのが見えた。あれはなんだろうか。
「お、おい……なんか変じゃないか」
一人の男が言った。
「ここ、通ったよな?」
隙間から見えたのは、狼狽する村人たちの姿だった。彼らは何かに怯えるように右往左往している。一体何があったのだろうか。その光景に胸がざわつき不安が広がる。
突然、地鳴りのような低い音が響き渡った。それは次第に大きくなり、まるで山そのものが怒りを発しているようだった。その直後、足元が激しく揺れ始める。地震だ。
駕籠が大きく揺れ、担ぎ手たちの叫び声が上がった。その衝撃で駕籠が地面に落ち、どすんと鈍い音が響く。籠の中で体が傾き、衝撃で息を呑んだ。
「どうなってるんだ!」
外からは混乱した声が聞こえてくる。地面の揺れはしばらく続き、揺れが治まるまでの間、ただ籠の中で身を縮めて耐えるしかなかった。
揺れが収まったころ、外から誰かが駕籠に近づいてくる気配がした。その足音は一つだ。何かが起きている。私は、胸の鼓動が高鳴るのを抑えながら、次に起こることを待つしかなかった。
「まさか、鬼神様か!?」
「まずいぞ! 俺たちはまだ山から出てねえんだ!」
その瞬間、耳を塞ぎたくなるような男たちの叫び声が響いた。
何が起こっているというの……!?
そうかと思えば、辺りはしんと静まり返っている。恐る恐る外を見れば、暗闇で何も見えない。
「出ておいで」
優しい声だった。こんな人、さっきまでいただろうか。
ゆっくりと外に出てみれば、黒い髪に紅い瞳をした男が立っていた。雲で隠されていた月が空を照らすと、月明りに照らされたその顔はどこかで見覚えがある。
「……え」
そうして、駕籠の外で何があったのかがようやく見えた。
血があちらこちらで広がっていた。そこに横たわる村人たちの姿。
「た、助けてくれ……」
呻くように村人の一人が言った。
「生きているの……?」
「殺してはいない」
男が鼻歌をうたうように言った。
「千代が殺してほしいというのなら、トドメを刺すだけだ」
「どうして私の名を……」
「知ってるよ。待っていたんだから」
待っていた? 私のことを?
そのとき、着物の裾を引っ張られるような感覚がして視線を下げると、村人の一人が懇願するような目で私を見上げていた。
「頼む……嫁が……待ってるんだ」
さっき会話が聞こえていた。この人だったのか。
「……この人たちのことは、殺さないでください」
「どうして?」
男の黒い髪が風に揺れる。
「君を生贄として差し出した連中だ。生贄とは、つまり死だということをこいつらが理解していないはずはない」
わかっている。この人たちが私の死を望んでいることを。
中には、私と同じ年齢の娘を持つ父もいるだろう。
「君を差し出すことで自分たちは生きながらえようとした。そんな人間を救いたいとでも?」
「……それでも、殺していい理由にはならないです」
そこに意味を見いだせるだろうか。清々するだろうか。そんなことはない。
「生かしてあげてください」
「そ。君がそう言うならそうしよう」
その言葉を聞いた途端、村人たちは立ち上がり、慌てふためくように山を降りていく。
「あれま、人間として終わってるな」
「……いいんです、無事で帰れたら」
あの人たちを待つ家族の元に帰れればそれでいい。
「あの……あなたは?」
はは、と軽く笑う。
「言ってなかったか。すまない、嫁ぎ先は俺の元だ」
「……え?」