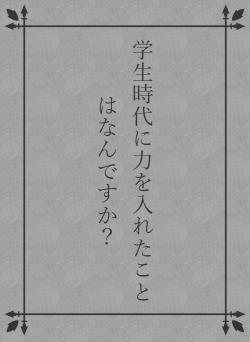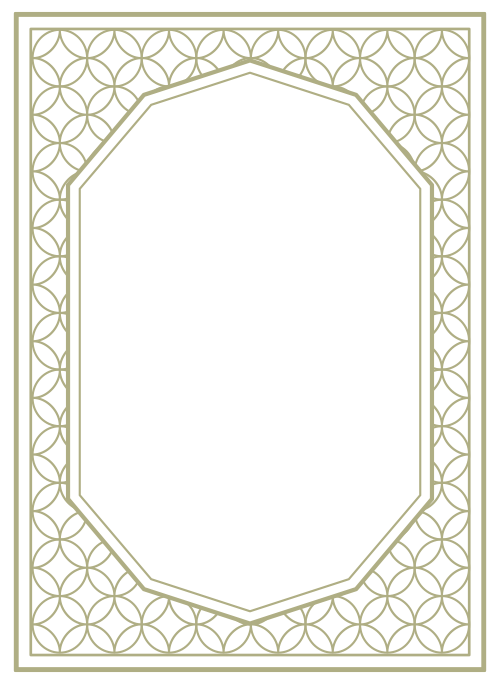***
「ついに儀式の日が決まったぞ!」
今朝から村は興奮していた。女学院もまた同じだ。
「ようやくいなくなるわね」「美代さんも相当耐えていらしたもの」「そもそも生贄の分際でしゃしゃり出るなんて」
ひそひそと交わされる小噺。
「同じ家から生贄が出るなんて美代さんも不憫ね」
姉である美代に話が振られる。彼女は私以上に悲しみに暮れたような顔をしていた。その目には涙さえ浮かんでいる。
「……私なんて。それよりも千代が選ばれてしまうなんて……食事も喉を通らないの」
まあ、と同情が美代に寄せられる。
喉を通らないと言っていたが、しっかりと食べていたように見える。美味しくないとは言うものの、残っていたことなど一度もない。きっと、残り物が私に流れてしまうことが許せないのだろう。私の食事はいつだって残り物だ。
「普段あれだけ冷たくされているのに美代さんは優しいわ」
「冷たくなんて……あれは千代からの愛情ですから」
愛情。それは私にはとても程遠いものだ。
実の両親から愛されることはなく、こうして生贄の日程が決まったときでさえも晴れ晴れとしたような顔を見せていた。ようやく邪魔者がいなくなる。そう内心では思っていたかもしれない。
時期に村人たちから感謝の品を多くもらい受けるだろう。生贄を出してくれてありがとうと。自分の家の娘を出さずに済んだと。
「私たちの中から選ばれなくて本当によかったわ」「ええ、あの山に行けば生きて帰られないんですから」「結界を張り直せば、それを破ることなんて誰にもできないみたいよ」
儀式は明日。私は生贄として鬼王山に向かう。
「ねえ、最後に最高の悪役を演じてくれない?」
昼休み、美代に呼び出されたかと思えばこれだ。
「生贄に決まったあなたのことを、少し憐れんでいる人も出てきたみたいなの」
確かに、もしかしたら自分だったかもしれないと思えば、私に同情する人は少なからず出てくるだろう。
それが美代は気に食わないらしい。
私には最後まで、徹底的に悪でいてほしいという。
「今さら、いい人でいたいわけでもないでしょう?」
「……努力はします」
「あら、千代なら努力なんてしなくても素でできるでしょう」
嘲笑うようなその顔。そうかもしれない。最初こそは躊躇いがあったけれど、今となってはもうそれができない。
「だから、最後は私の頬を叩いて」
「……え?」
「生贄に選ばれたことで自暴自棄になるっていう筋書きを予定しているの」
そんなことは知らない。なぜ私がそうしなければならないのだろう。
「思いっきりでいいのよ。そうすれば、全員がお姉さんの生贄に納得できるんだから」
なぜここまでしなければならないのだろう。
そうして、美代が用意した舞台は完璧だった。
教室には見物客がぞろぞろと集まっていた。きっかけは美代が「やめて……!」と叫んだこと。
「ねえ、今なんて言ったの……?」
美代の怯えた目が私を見ている。そうして事前に仕込まれていたセリフを口にする。
「だから、生贄はあんたが変わってと言ってるの」
私の言葉に、周囲が青ざめていくのがわかった。
「私が生贄になるなんて許せない。双子なら、あんたがなったって一緒でしょ」
「そ、そんなこと言われても、もう決まってしまったことだから……」
本当に、美代の演技力には脱帽する。これが全て作り話だというのに、周囲を引き込み信じ込ませてしまうだけの力があった。
「お願い……! なんでもするから! だから許して……!」
そう懇願する美代に、今度は思いっきりビンタをすることになっていた。
「……」
それができなかったのは、人を痛めつけたくないという心が働いたから。
今まで痛めつけられてきたことは何度もあるけど、自分からしたことはない。
もし失敗すれば、酷い仕打ちが待っているかもしれない。そもそも、いくら演技とはいえ、このことを母や父が知ったら、私を放ってはおかないはず。
そう思うと手が出せなかった。それを見て、周囲は「どうしたの?」と首を傾げ始める。
小声で美代が「早くしなさいよ」と急かしてくるが、私はその場から逃げ出すように教室を飛び出した。
できない。ごめんなさい。
口にできない代わりに心の中で何度も謝罪を繰り返す。
どちらにしても救いようがない。家に帰れば美代はきっと暴れるだろう。
「この! 役立たず!」
案の定、先に帰っていた美代に思いっきりビンタされる。この痛みを、美代は本当に待っていたというのだろうか。
「どうしてできないの! あなたの評価が上がったらダメなのよ!」
馬鹿、最低、そんな言葉が呪いのように降りかかってくる。
部屋は散乱し、飛んできた花瓶の破片が当たったのか、頬には血が垂れていた。
「どうせいなくなるんだからいいでしょ」
スッキリしたのか美代は、ふっと笑って部屋を出て行った。
それを一つずつ片付けていく。いなくなったとしても、誰かがこの部屋を片付けなければならない。それなら私がやっておいたほうがいい。
要らないものなど何一つとしてなかった。最低限のものだけが置かれた部屋。
風呂敷に包むぐらいで荷物は全て整ってしまった。
「……どうか、私でこの生贄の儀式が終わりますように」
それだけの力がないことなんてわかってはいるけれど。
生贄として選ばれるなら、ただ供えられて終わりにはしたくない。
生贄を選ばなくてもいいぐらいの封印力があったらいいのに。
「ないか……私には」
今までやってきたことは、ただ悪として生き、生贄の対象になること。それだけだった。
特別な力なんてない。こんな私が、生贄の制度を止めることなんてできない。
「ついに儀式の日が決まったぞ!」
今朝から村は興奮していた。女学院もまた同じだ。
「ようやくいなくなるわね」「美代さんも相当耐えていらしたもの」「そもそも生贄の分際でしゃしゃり出るなんて」
ひそひそと交わされる小噺。
「同じ家から生贄が出るなんて美代さんも不憫ね」
姉である美代に話が振られる。彼女は私以上に悲しみに暮れたような顔をしていた。その目には涙さえ浮かんでいる。
「……私なんて。それよりも千代が選ばれてしまうなんて……食事も喉を通らないの」
まあ、と同情が美代に寄せられる。
喉を通らないと言っていたが、しっかりと食べていたように見える。美味しくないとは言うものの、残っていたことなど一度もない。きっと、残り物が私に流れてしまうことが許せないのだろう。私の食事はいつだって残り物だ。
「普段あれだけ冷たくされているのに美代さんは優しいわ」
「冷たくなんて……あれは千代からの愛情ですから」
愛情。それは私にはとても程遠いものだ。
実の両親から愛されることはなく、こうして生贄の日程が決まったときでさえも晴れ晴れとしたような顔を見せていた。ようやく邪魔者がいなくなる。そう内心では思っていたかもしれない。
時期に村人たちから感謝の品を多くもらい受けるだろう。生贄を出してくれてありがとうと。自分の家の娘を出さずに済んだと。
「私たちの中から選ばれなくて本当によかったわ」「ええ、あの山に行けば生きて帰られないんですから」「結界を張り直せば、それを破ることなんて誰にもできないみたいよ」
儀式は明日。私は生贄として鬼王山に向かう。
「ねえ、最後に最高の悪役を演じてくれない?」
昼休み、美代に呼び出されたかと思えばこれだ。
「生贄に決まったあなたのことを、少し憐れんでいる人も出てきたみたいなの」
確かに、もしかしたら自分だったかもしれないと思えば、私に同情する人は少なからず出てくるだろう。
それが美代は気に食わないらしい。
私には最後まで、徹底的に悪でいてほしいという。
「今さら、いい人でいたいわけでもないでしょう?」
「……努力はします」
「あら、千代なら努力なんてしなくても素でできるでしょう」
嘲笑うようなその顔。そうかもしれない。最初こそは躊躇いがあったけれど、今となってはもうそれができない。
「だから、最後は私の頬を叩いて」
「……え?」
「生贄に選ばれたことで自暴自棄になるっていう筋書きを予定しているの」
そんなことは知らない。なぜ私がそうしなければならないのだろう。
「思いっきりでいいのよ。そうすれば、全員がお姉さんの生贄に納得できるんだから」
なぜここまでしなければならないのだろう。
そうして、美代が用意した舞台は完璧だった。
教室には見物客がぞろぞろと集まっていた。きっかけは美代が「やめて……!」と叫んだこと。
「ねえ、今なんて言ったの……?」
美代の怯えた目が私を見ている。そうして事前に仕込まれていたセリフを口にする。
「だから、生贄はあんたが変わってと言ってるの」
私の言葉に、周囲が青ざめていくのがわかった。
「私が生贄になるなんて許せない。双子なら、あんたがなったって一緒でしょ」
「そ、そんなこと言われても、もう決まってしまったことだから……」
本当に、美代の演技力には脱帽する。これが全て作り話だというのに、周囲を引き込み信じ込ませてしまうだけの力があった。
「お願い……! なんでもするから! だから許して……!」
そう懇願する美代に、今度は思いっきりビンタをすることになっていた。
「……」
それができなかったのは、人を痛めつけたくないという心が働いたから。
今まで痛めつけられてきたことは何度もあるけど、自分からしたことはない。
もし失敗すれば、酷い仕打ちが待っているかもしれない。そもそも、いくら演技とはいえ、このことを母や父が知ったら、私を放ってはおかないはず。
そう思うと手が出せなかった。それを見て、周囲は「どうしたの?」と首を傾げ始める。
小声で美代が「早くしなさいよ」と急かしてくるが、私はその場から逃げ出すように教室を飛び出した。
できない。ごめんなさい。
口にできない代わりに心の中で何度も謝罪を繰り返す。
どちらにしても救いようがない。家に帰れば美代はきっと暴れるだろう。
「この! 役立たず!」
案の定、先に帰っていた美代に思いっきりビンタされる。この痛みを、美代は本当に待っていたというのだろうか。
「どうしてできないの! あなたの評価が上がったらダメなのよ!」
馬鹿、最低、そんな言葉が呪いのように降りかかってくる。
部屋は散乱し、飛んできた花瓶の破片が当たったのか、頬には血が垂れていた。
「どうせいなくなるんだからいいでしょ」
スッキリしたのか美代は、ふっと笑って部屋を出て行った。
それを一つずつ片付けていく。いなくなったとしても、誰かがこの部屋を片付けなければならない。それなら私がやっておいたほうがいい。
要らないものなど何一つとしてなかった。最低限のものだけが置かれた部屋。
風呂敷に包むぐらいで荷物は全て整ってしまった。
「……どうか、私でこの生贄の儀式が終わりますように」
それだけの力がないことなんてわかってはいるけれど。
生贄として選ばれるなら、ただ供えられて終わりにはしたくない。
生贄を選ばなくてもいいぐらいの封印力があったらいいのに。
「ないか……私には」
今までやってきたことは、ただ悪として生き、生贄の対象になること。それだけだった。
特別な力なんてない。こんな私が、生贄の制度を止めることなんてできない。