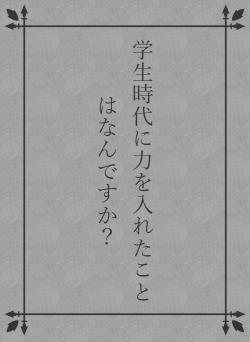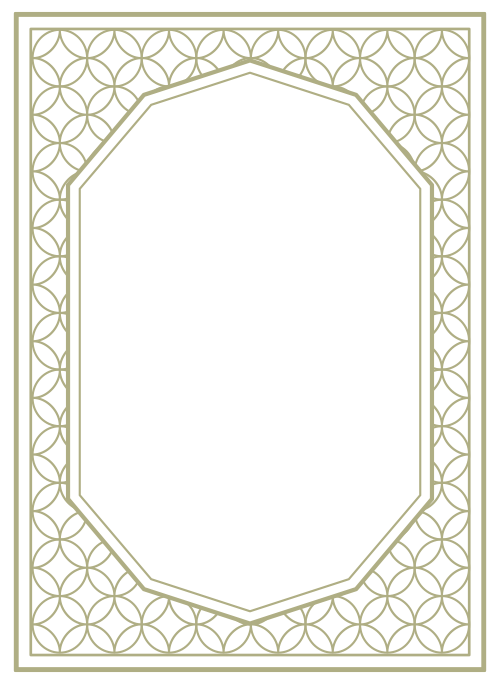「邪魔ばかりしないでっ!」
どん、とした衝撃とともに、床に手をつき、怯えた顔で私を見上げるのは姉の美代だ。
そして、それを仁王立ちして見つめる私。
「またやってるわ」「美代さんが不憫で仕方ないわ」
こそこそと聞こえてくる会話に耳を塞ぎたくなる。
大丈夫、あと少し。用意されたセリフを口にするだけだ。
「あの人の婚約者は私だったはずなのよ。奪うなんて最低」
「そ、そんなつもりはなかったのです……どうかお許しください」
傍から見れば、姉を虐げる妹に見えているだろう。それでいい。作戦通りだ。
私が離れると、一斉に美代に駆け寄った女学生の人たち。
「大丈夫、いつものことだから」と、か細くも穏やかな美代の声を背に、人気のない廊下の突き当りまで進んでいく。胸に手を当て、深呼吸を繰り返しながら「もう少し、あと少し」と自分に言い聞かせる。
私の人生は産まれた瞬間から決まっていた。
この村には古くから恐ろしい風習が伝わっている。五十年に一度、山の頂に住むとされる鬼に娘を嫁がせるのだ。それは、村に災いをもたらさぬよう鬼の怒りを鎮めるためだと言われている。もし風習に従わなければ、鬼の力によって謎の病が村全体に広がる──そんな言い伝えが、世代を超えて語り継がれてきた。
生贄に選ばれるのは、いつも十六歳になった少女の中の誰かだ。その年齢を迎えた娘たちは、生贄に選ばれる恐怖を抱きながら日々を過ごす。それが村の宿命であり、逆らう者は許されない。しかし、今回の五十年に一度の選出では、珍しいことにその「誰か」が既に決まっていた。
それが私だった。
この村では双子は忌み嫌われる存在とされている。双子は災いを呼ぶ、不吉な象徴だと信じられていたからだ。本来なら、私は姉より数秒遅れただめ、生まれてすぐに殺されるはずだった。しかし、鬼への生贄という役割があったため、私の命は見逃された。
「千代は、生かされているだけありがたく思いなさい」
村の者からそう言われ続けてきた。姉の美代は、私とは対照的に愛されて育った。美代は美しく聡明で、村の希望そのものだった。それに比べ、私は必要最低限の食事と衣服しか与えられず、存在そのものが村の負担のように扱われていた。
「双子の片割れなんて、存在するだけで災いを呼ぶんだ」
何度その言葉を聞かされたかわからない。私は何も悪いことをしていない。ただ産まれた。それだけなのに、私は村の不幸の根源のように見られていた。
生贄に選ばれた瞬間、村中が安堵のため息をついたのを覚えている。「これで災いを払える」と口々に言う大人たちの声。それがどれほど私の心を抉ったか、彼らは知る由もない。
しかし、その風習に従わねばならないのは私自身も同じだった。この村で生きる限り、私は逆らうことはできない。それが、双子として産まれた私の宿命だった。
美代は私を哀れむどころか、どこか安堵したような顔をしていた。むしろ「当然の結果」とでも言いたげな、冷たい目で私を見下ろしていた。
こうして、私は鬼の嫁として、村を去ることを命じられた。嫁ぐ――その言葉は、私にとって未来への希望を意味しない。ただ、どこへ向かうとも知れぬ死への道のりだった。
「……もうすぐ、いなくなれるんだから」
もう心が痛むことはない。感情はとうに失っていた。それもこれも、生贄として扱われてきたこれまでの影響だろう。
「今日の千代ったら、ものすごく迫力があったわ」
家に戻れば、美代の上機嫌な声が響いていた。玄関の靴を並べてから、足音ひとつ立てないよう気を付ける。
「ふふ、それはそうよ。悪役になるために産まれてきたような人なんですから」
美代とそっくりな声と話し方で母もまた笑っていた。
この二人を前にするとき、私はできるだけ心を無にするよう気を付ける。油断すると平気で心がズタボロになっていく。
「ただいま戻りました」
このままいっそ気付かないでほしいと願っていたが、美代が「あら、いらっしゃい」と私に声をかけた。同じ家なのに「おかえり」と言われたことは一度もない。
「ねえ、生贄に選ばれる気分を詳しく教えてちょうだい」
「あら、それは最後まで取っておきましょう」
「それもそうね」
ははは、と甲高い笑い声。俯きながら「失礼します」と廊下を進み、物置小屋となっている自室へと入った。
どれだけ掃除しても埃臭く、次々に運ばれてくる荷物の匂いがあるせいか、ここはどうにも落ち着かない部屋だった。
それでも、部屋を与えられただけでも十分だ。そのことに感謝して、食事の支度をする。
姉や母だけでなく、父もまた私を生贄として扱う人だった。生かしてやってるのだから、料理、洗濯、掃除は全て私が担うことになっている。
「ねえ、いつになったら美味しく作れるのかしら」
美代は不服そうに味噌汁を啜っていた。それから「美味しく作れる前には死んでしまうわね」と楽しそうな表情を見せる。私はただ「申し訳ございません」と隅の方で小さくなりながら、片付けを済ませていく。
家事を全てこなす頃には日付が変わっている。手抜きをしようものなら、酷い仕打ちが待っている。
「ああ、明日の朝食の下準備を忘れてた……今戻ってやれば少しは眠れるけど」
力が尽きたように寝床に腰をおろせば、瞼がゆっくりと落ちてくる。
「起きないと……」
なんとか意識を保とうとしていると、ふと声が聞こえてきた。
──私の花嫁 あなたの花婿 交わされる約束
「誰……?」
まるで頭の中だけで響いているようだった。
心地の良い鈴のような音。「もうすぐだ」と誰かが囁く声。さっき聞こえていたのが幼い声だとしたら、今のははっきりと男の声のように聞こえた。
そのまま意識は遠のいていく。そのまま寝てもいいと、言ってもらえているような感覚だった。
翌朝、女学校に向かう途中で地蔵が目に入った。そこには、活けられていた花が無残に荒らされている。
「……どうしてこんなことを」
すぐに花を集めるが、花びらが破れ、とてもじゃないが活け直すにしても粗末なものになっていた。
「これを供えられても嬉しくないか」
ぽつ、と手に当たったのは雨だった。それは次第に本降りになっていく。
「いけない……戻って洗濯ものを入れないと」
そう思うのに、立ち上がることができない。
無残な花の姿を見て、酷い言葉をかけられたわけではないのに、心が痛かった。
「私も……こうして捨てられてしまうのかな」
鬼の供物となっても、必要がないと思われてしまえば私はどうなってしまうのだろうか。
考えないようにしようと思ってはいても、ふとした瞬間、不安へと襲われる。
雨に混じって涙が滲む。こんなところで泣いていたら、悪役はそんなことしないと美代の機嫌を損ねてしまう。昔から美代は私の何かが気に入らないらしい。だから生きている間はずっと悪を演じろと根気強く言われてきた。
生贄はただ生かされているだけ。私は泣いていない。これは雨。
「冷えるでしょう」
さっと頭上に差し出されたのは漆黒の傘だった。雨粒を弾くその布地は、どこかしっとりと艶めき、内側には金色の模様が繊細に描かれている。その煌びやかさに目を奪われつつも、私はそっと視線を傘を差し出してくれた人へ向けた。
ハッと息を呑む。
そこに立っていたのは、驚くほど美しい人だった。傘と同じ漆黒の髪が風に揺れ、瞳もまた深い闇のような黒だ。肌は陶器のように白く、どこまでも滑らかで、顔立ちは作り物のように整っていた。高く通った鼻梁と薄い唇の調和は完璧で、彼を見つめるだけで言葉を失ってしまう。
彼の身に纏う黒い衣もまた、ただの布ではなかった。重厚感のある上質な生地に、赤い刺繍で大きな鳥の模様が描かれている。その刺繍がどこか威厳を漂わせ、彼の存在を一層際立たせていた。
しかし、それだけではない。目を引いたのは彼の手首だ。上質な衣にそぐわない、女物の布が一巻きされている。それは何かの模様が描かれているが、古びており、豪華な衣装とはまるで釣り合っていなかった。その布は彼の柔らかな指と強い手にきつく巻きつけられている。
彼の端整な顔立ちからは感情を読み取ることができない。その美しさの中には、どこか冷たさを感じさせるものがあった。それでも私は、彼の姿に目を離すことができなかった。この人は一体誰なのだろう――そして、なぜこんなところにいるのだろうか?
「鳳凰だ」
私が布を見ていたことを知りながらも、男は鳥の名を口にした。
「あ……ありがとうござ──」
そこまで言って、人前でどう振る舞わなければいけないのかを思い出す。
「……迷惑です。傘は必要ありませんので」
村人に目撃でもされ、美代に告げ口されてしまってはお仕置きが待っている。感情は失ったはずなのに、痛みに慣れることはなかった。
「それは失礼」
男は微笑んで、それから地蔵へと視線を流した。
花も荒れたままだ。もしかしたら、私が荒らしたと思われているかもしれない。
けれどそれでいい。この人に弁解したところで何になると言うのだろう。
「ところで道を訊ねてもいいかな」
しかし地蔵に振れることなく、男は私に聞いた。
「道……?」
「鬼王山へはここからどう行くのが近いんだろうか」
その山の名を聞いて怯えた。
生贄の儀式以外に、あの山に近づく者は誰一人としていない。近づけば人はさらわれてしまう。
「久しぶりにこっちに来てみたんだが、帰りがわからなくなってしまってね」
鬼王山を超えた村だろうか。
向こうに村があると聞いたことはない。たとえあったとしても、鬼王山を通るなど無謀だ。
子どもが山に迷い込まないようにと、村のお坊さんが山道の入口でお経を唱えている。しかし、近頃は生贄の儀式が近づいていることもあり、山への結界が一時的に薄れているという噂が広まっていた。普段ならば、鬼の棲む山と村の境を隔てる結界は強固で、誰もがその存在に安心していたが、この時期だけは事情が異なるらしい。
結界が弱まる原因について、村人たちは恐る恐る話題にするだけで、それ以上は深く触れようとしない。それは、あの山がただの山ではなく、何か得体の知れない力を秘めているからだ。
村の大人でさえ、山には入ろうとしないというのに。
この人は村の人ではないのだろうか。そうだとしたら、悪をそこまで徹底する必要はないかもしれない。
「……悪いことは言いません。近づかないほうが身のためです」
「なぜ?」
「その山には、名の通り鬼の王がいます。昔から、神からも恐れられるほどの存在だと言われているんです」
「神からもなんて、どうして?」
この話をすれば、大抵の人が恐れおののく。絶対的な神でさえも太刀打ちできない相手とは一体どんな存在なのかと。
「……昔、鬼と神はどちらが人から敬われるのに相応しいか対決をしたそうです。結果として鬼が勝ちました」
「なるほど、面白い言い伝えだ。でも、俺が知ってる話とはずいぶんと違うな」
「知ってるんですか?」
「神は人を操って鬼を滅ぼそうとした。全てが正しいと思っているのが神だ。よって人を駒として扱うことも厭わない」
「……それが本当なら、神を敬いたくないです」
「そうだろう。俺も思う」
はは、と笑った男はどこか遠くを見つめていた。そして、静かに言った。
「あなたはその鬼のことをどう思う?」
「どう……わかりません。会ったことがないですし……」
ただ、と思う。
「人が神を敬うように、人を敬っていたのが鬼だとしたら……とてもいい人だったと思います」
神は人を意のままにしようとし、それを阻止して神に勝ったのだとしたら、鬼は賞賛されるべきだ。
「面白いね。いい人かどうかはわからないけど」
遠くを見ていた男は、気付けば私を見ていた。普段であればここまで話し込むことなんて一度もないのに。なぜかこの人を前にすると、すらすらと言葉が出ていた。
男は傘を少しずらして空を見上げた。
「雨が止んだみたいだ。そろそろ帰らないと」
「え、あの」
「親切にどうも」
去っていく背中は、少し離れたところで立ち止まると、振り返って大きく手を振った。
私に、あれほど親身な笑顔を向ける人など初めてだ。
なんだか、まともに人と話したのは初めてのような気がする。
「……不思議な人」
どん、とした衝撃とともに、床に手をつき、怯えた顔で私を見上げるのは姉の美代だ。
そして、それを仁王立ちして見つめる私。
「またやってるわ」「美代さんが不憫で仕方ないわ」
こそこそと聞こえてくる会話に耳を塞ぎたくなる。
大丈夫、あと少し。用意されたセリフを口にするだけだ。
「あの人の婚約者は私だったはずなのよ。奪うなんて最低」
「そ、そんなつもりはなかったのです……どうかお許しください」
傍から見れば、姉を虐げる妹に見えているだろう。それでいい。作戦通りだ。
私が離れると、一斉に美代に駆け寄った女学生の人たち。
「大丈夫、いつものことだから」と、か細くも穏やかな美代の声を背に、人気のない廊下の突き当りまで進んでいく。胸に手を当て、深呼吸を繰り返しながら「もう少し、あと少し」と自分に言い聞かせる。
私の人生は産まれた瞬間から決まっていた。
この村には古くから恐ろしい風習が伝わっている。五十年に一度、山の頂に住むとされる鬼に娘を嫁がせるのだ。それは、村に災いをもたらさぬよう鬼の怒りを鎮めるためだと言われている。もし風習に従わなければ、鬼の力によって謎の病が村全体に広がる──そんな言い伝えが、世代を超えて語り継がれてきた。
生贄に選ばれるのは、いつも十六歳になった少女の中の誰かだ。その年齢を迎えた娘たちは、生贄に選ばれる恐怖を抱きながら日々を過ごす。それが村の宿命であり、逆らう者は許されない。しかし、今回の五十年に一度の選出では、珍しいことにその「誰か」が既に決まっていた。
それが私だった。
この村では双子は忌み嫌われる存在とされている。双子は災いを呼ぶ、不吉な象徴だと信じられていたからだ。本来なら、私は姉より数秒遅れただめ、生まれてすぐに殺されるはずだった。しかし、鬼への生贄という役割があったため、私の命は見逃された。
「千代は、生かされているだけありがたく思いなさい」
村の者からそう言われ続けてきた。姉の美代は、私とは対照的に愛されて育った。美代は美しく聡明で、村の希望そのものだった。それに比べ、私は必要最低限の食事と衣服しか与えられず、存在そのものが村の負担のように扱われていた。
「双子の片割れなんて、存在するだけで災いを呼ぶんだ」
何度その言葉を聞かされたかわからない。私は何も悪いことをしていない。ただ産まれた。それだけなのに、私は村の不幸の根源のように見られていた。
生贄に選ばれた瞬間、村中が安堵のため息をついたのを覚えている。「これで災いを払える」と口々に言う大人たちの声。それがどれほど私の心を抉ったか、彼らは知る由もない。
しかし、その風習に従わねばならないのは私自身も同じだった。この村で生きる限り、私は逆らうことはできない。それが、双子として産まれた私の宿命だった。
美代は私を哀れむどころか、どこか安堵したような顔をしていた。むしろ「当然の結果」とでも言いたげな、冷たい目で私を見下ろしていた。
こうして、私は鬼の嫁として、村を去ることを命じられた。嫁ぐ――その言葉は、私にとって未来への希望を意味しない。ただ、どこへ向かうとも知れぬ死への道のりだった。
「……もうすぐ、いなくなれるんだから」
もう心が痛むことはない。感情はとうに失っていた。それもこれも、生贄として扱われてきたこれまでの影響だろう。
「今日の千代ったら、ものすごく迫力があったわ」
家に戻れば、美代の上機嫌な声が響いていた。玄関の靴を並べてから、足音ひとつ立てないよう気を付ける。
「ふふ、それはそうよ。悪役になるために産まれてきたような人なんですから」
美代とそっくりな声と話し方で母もまた笑っていた。
この二人を前にするとき、私はできるだけ心を無にするよう気を付ける。油断すると平気で心がズタボロになっていく。
「ただいま戻りました」
このままいっそ気付かないでほしいと願っていたが、美代が「あら、いらっしゃい」と私に声をかけた。同じ家なのに「おかえり」と言われたことは一度もない。
「ねえ、生贄に選ばれる気分を詳しく教えてちょうだい」
「あら、それは最後まで取っておきましょう」
「それもそうね」
ははは、と甲高い笑い声。俯きながら「失礼します」と廊下を進み、物置小屋となっている自室へと入った。
どれだけ掃除しても埃臭く、次々に運ばれてくる荷物の匂いがあるせいか、ここはどうにも落ち着かない部屋だった。
それでも、部屋を与えられただけでも十分だ。そのことに感謝して、食事の支度をする。
姉や母だけでなく、父もまた私を生贄として扱う人だった。生かしてやってるのだから、料理、洗濯、掃除は全て私が担うことになっている。
「ねえ、いつになったら美味しく作れるのかしら」
美代は不服そうに味噌汁を啜っていた。それから「美味しく作れる前には死んでしまうわね」と楽しそうな表情を見せる。私はただ「申し訳ございません」と隅の方で小さくなりながら、片付けを済ませていく。
家事を全てこなす頃には日付が変わっている。手抜きをしようものなら、酷い仕打ちが待っている。
「ああ、明日の朝食の下準備を忘れてた……今戻ってやれば少しは眠れるけど」
力が尽きたように寝床に腰をおろせば、瞼がゆっくりと落ちてくる。
「起きないと……」
なんとか意識を保とうとしていると、ふと声が聞こえてきた。
──私の花嫁 あなたの花婿 交わされる約束
「誰……?」
まるで頭の中だけで響いているようだった。
心地の良い鈴のような音。「もうすぐだ」と誰かが囁く声。さっき聞こえていたのが幼い声だとしたら、今のははっきりと男の声のように聞こえた。
そのまま意識は遠のいていく。そのまま寝てもいいと、言ってもらえているような感覚だった。
翌朝、女学校に向かう途中で地蔵が目に入った。そこには、活けられていた花が無残に荒らされている。
「……どうしてこんなことを」
すぐに花を集めるが、花びらが破れ、とてもじゃないが活け直すにしても粗末なものになっていた。
「これを供えられても嬉しくないか」
ぽつ、と手に当たったのは雨だった。それは次第に本降りになっていく。
「いけない……戻って洗濯ものを入れないと」
そう思うのに、立ち上がることができない。
無残な花の姿を見て、酷い言葉をかけられたわけではないのに、心が痛かった。
「私も……こうして捨てられてしまうのかな」
鬼の供物となっても、必要がないと思われてしまえば私はどうなってしまうのだろうか。
考えないようにしようと思ってはいても、ふとした瞬間、不安へと襲われる。
雨に混じって涙が滲む。こんなところで泣いていたら、悪役はそんなことしないと美代の機嫌を損ねてしまう。昔から美代は私の何かが気に入らないらしい。だから生きている間はずっと悪を演じろと根気強く言われてきた。
生贄はただ生かされているだけ。私は泣いていない。これは雨。
「冷えるでしょう」
さっと頭上に差し出されたのは漆黒の傘だった。雨粒を弾くその布地は、どこかしっとりと艶めき、内側には金色の模様が繊細に描かれている。その煌びやかさに目を奪われつつも、私はそっと視線を傘を差し出してくれた人へ向けた。
ハッと息を呑む。
そこに立っていたのは、驚くほど美しい人だった。傘と同じ漆黒の髪が風に揺れ、瞳もまた深い闇のような黒だ。肌は陶器のように白く、どこまでも滑らかで、顔立ちは作り物のように整っていた。高く通った鼻梁と薄い唇の調和は完璧で、彼を見つめるだけで言葉を失ってしまう。
彼の身に纏う黒い衣もまた、ただの布ではなかった。重厚感のある上質な生地に、赤い刺繍で大きな鳥の模様が描かれている。その刺繍がどこか威厳を漂わせ、彼の存在を一層際立たせていた。
しかし、それだけではない。目を引いたのは彼の手首だ。上質な衣にそぐわない、女物の布が一巻きされている。それは何かの模様が描かれているが、古びており、豪華な衣装とはまるで釣り合っていなかった。その布は彼の柔らかな指と強い手にきつく巻きつけられている。
彼の端整な顔立ちからは感情を読み取ることができない。その美しさの中には、どこか冷たさを感じさせるものがあった。それでも私は、彼の姿に目を離すことができなかった。この人は一体誰なのだろう――そして、なぜこんなところにいるのだろうか?
「鳳凰だ」
私が布を見ていたことを知りながらも、男は鳥の名を口にした。
「あ……ありがとうござ──」
そこまで言って、人前でどう振る舞わなければいけないのかを思い出す。
「……迷惑です。傘は必要ありませんので」
村人に目撃でもされ、美代に告げ口されてしまってはお仕置きが待っている。感情は失ったはずなのに、痛みに慣れることはなかった。
「それは失礼」
男は微笑んで、それから地蔵へと視線を流した。
花も荒れたままだ。もしかしたら、私が荒らしたと思われているかもしれない。
けれどそれでいい。この人に弁解したところで何になると言うのだろう。
「ところで道を訊ねてもいいかな」
しかし地蔵に振れることなく、男は私に聞いた。
「道……?」
「鬼王山へはここからどう行くのが近いんだろうか」
その山の名を聞いて怯えた。
生贄の儀式以外に、あの山に近づく者は誰一人としていない。近づけば人はさらわれてしまう。
「久しぶりにこっちに来てみたんだが、帰りがわからなくなってしまってね」
鬼王山を超えた村だろうか。
向こうに村があると聞いたことはない。たとえあったとしても、鬼王山を通るなど無謀だ。
子どもが山に迷い込まないようにと、村のお坊さんが山道の入口でお経を唱えている。しかし、近頃は生贄の儀式が近づいていることもあり、山への結界が一時的に薄れているという噂が広まっていた。普段ならば、鬼の棲む山と村の境を隔てる結界は強固で、誰もがその存在に安心していたが、この時期だけは事情が異なるらしい。
結界が弱まる原因について、村人たちは恐る恐る話題にするだけで、それ以上は深く触れようとしない。それは、あの山がただの山ではなく、何か得体の知れない力を秘めているからだ。
村の大人でさえ、山には入ろうとしないというのに。
この人は村の人ではないのだろうか。そうだとしたら、悪をそこまで徹底する必要はないかもしれない。
「……悪いことは言いません。近づかないほうが身のためです」
「なぜ?」
「その山には、名の通り鬼の王がいます。昔から、神からも恐れられるほどの存在だと言われているんです」
「神からもなんて、どうして?」
この話をすれば、大抵の人が恐れおののく。絶対的な神でさえも太刀打ちできない相手とは一体どんな存在なのかと。
「……昔、鬼と神はどちらが人から敬われるのに相応しいか対決をしたそうです。結果として鬼が勝ちました」
「なるほど、面白い言い伝えだ。でも、俺が知ってる話とはずいぶんと違うな」
「知ってるんですか?」
「神は人を操って鬼を滅ぼそうとした。全てが正しいと思っているのが神だ。よって人を駒として扱うことも厭わない」
「……それが本当なら、神を敬いたくないです」
「そうだろう。俺も思う」
はは、と笑った男はどこか遠くを見つめていた。そして、静かに言った。
「あなたはその鬼のことをどう思う?」
「どう……わかりません。会ったことがないですし……」
ただ、と思う。
「人が神を敬うように、人を敬っていたのが鬼だとしたら……とてもいい人だったと思います」
神は人を意のままにしようとし、それを阻止して神に勝ったのだとしたら、鬼は賞賛されるべきだ。
「面白いね。いい人かどうかはわからないけど」
遠くを見ていた男は、気付けば私を見ていた。普段であればここまで話し込むことなんて一度もないのに。なぜかこの人を前にすると、すらすらと言葉が出ていた。
男は傘を少しずらして空を見上げた。
「雨が止んだみたいだ。そろそろ帰らないと」
「え、あの」
「親切にどうも」
去っていく背中は、少し離れたところで立ち止まると、振り返って大きく手を振った。
私に、あれほど親身な笑顔を向ける人など初めてだ。
なんだか、まともに人と話したのは初めてのような気がする。
「……不思議な人」