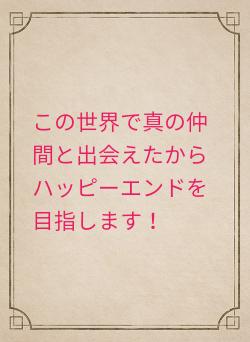──ガルズ視点。
「どうであった?」
シャーリー嬢が部屋へと下がり、一同を男爵の執務部屋に集めた。
男爵とその夫人、わたしと妻、あと、シャーリー嬢を部屋と案内した妻の側近とも言える侍女長だ。
「なんと言いますか、不思議なお嬢さんでしたね」
最初に口を開いたのは男爵夫人だ。大人しそうな見た目ではあるが、観察眼は妻も一目を置いている。我らには見えないものも見えているのだろう。
「そうね。若い娘を国外に出すくらいなのですから並みではないはずです。ですが、やはり、なんと言うか、世間とずれたところがあるように思えます」
妻も男爵夫人と似た感想のようだ。
「ザンバドリ侯爵家、と言うのが判断を難しくさせているな」
カルビラス王国を何十年と支えて来たザンバドリ侯爵家。その影響力は周辺国にも及ぶ。今回の大使団もザンバドリ侯爵家の長男と第二王女の婚礼参加が主である。
「薄紫の髪、あれはシャルニアート王国に多い髪ですよね?」
「ええ。ですが、毛先が濃い紫です。染めてる様子もなかったですし、地毛だとすると特殊な血筋ではないでしょうか?」
珍しい髪の色だとは思ったが、妻が言ったようにシャルニアート王国とも交易はしているし、流れて来る者もいる。わたしも薄紫の髪は見た記憶がある。
「特殊な血筋は間違いないだろうな。領域回復できる魔力など聖女級だ。本人は力技だと言ってたがな」
回復魔法を力技だと言い切る者を初めて見た。教会の者が聞いたら憤慨することだろうよ。
「一人で旅をしているのだから、回復魔法だけではないでしょうな」
だろうな。ここまでなにで来たかわからないが、なにも起こらず来れるほど安全な道程ではない。騎士や兵士に護衛された我々ですら魔物の襲撃を受けてるのだからな。
「あの、シャーリー嬢が腰に下げていたもの、武器であろうな」
なんであるかはわからないが、手に持つものだった。
「ですな。抜きやすそうな位置にありましたし」
今は恰幅がよい姿だが、若い頃は軍に所属していた男爵だ。なんであるかわからなくても武器であることは位置でわかるのだろう。
「ただ、戦いに慣れた感じはしませんでしたな」
凄みもなく隠している気配もない。常に自然体でいて、こちらをまったく警戒していなかった。
「どう言う立場なんだか……」
隠密ならもっと隠すだろう。なのに、シャーリー嬢はあるがままを出している。それがまた判断を難しくするのだ。
身なりや立ち振舞い、口調から貴族並みの教育を受けていることはわかる。が、令嬢の教育ではないのもわかる。いったいどんな家に生まれ、どう育てたらああなるのやら?
「なんにせよ、シャーリー嬢はザンバドリ侯爵家と繋がりがあるのは間違いないないだろう」
証拠を持っていたわけではないが、彼女の言葉に偽りはない。言葉の端々に侯爵との繋がりの強さを感じるのだ。
「そうですな。あの領域回復だけ見てもただの主従関係と思えない」
「ええ。かなり強い繋がりがあるか、関係の近いところにいると思います」
「わたしも同意見です」
男爵、男爵夫人、妻の意見は一致した。
「となると、どう接するかだな」
侯爵家との繋がりが強いが、シャーリー嬢は侍女と言っている。侯爵家に仕えている。
こちらは外国の者で大使団だ。侍女相手に令嬢扱いをしてはサンビレス王国としての面子にもかかわる。
だからと言って完全に侍女扱いは不味い。不当に扱うのもダメだ。ザンバドリ侯爵家を敵にはできないのだから。
「兵士たちを回復してくれたのですから客人として扱うのではいいのでは?」
と、妻が口にした。
「それがよいかと。ただ、仲を深めるためにも侍女と一緒にさせるのがよいと思います」
とは男爵夫人。女性のことは女性に任せたほうがよいのかもしれんな。
「では、シャーリー嬢のことはアリータに任せる。上手く仲を繋いでくれ。わたしもできる限りのことはするから」
「はい。お任せください」
今はこれが精々か。まったく、カルビラス王国に入る前にこれとはな。運が良いと思い努力するしかないか……。
「出発までよろしく頼む」
全員が力強く頷いた。
さて。わたしもやれることをやるとしようか。
「どうであった?」
シャーリー嬢が部屋へと下がり、一同を男爵の執務部屋に集めた。
男爵とその夫人、わたしと妻、あと、シャーリー嬢を部屋と案内した妻の側近とも言える侍女長だ。
「なんと言いますか、不思議なお嬢さんでしたね」
最初に口を開いたのは男爵夫人だ。大人しそうな見た目ではあるが、観察眼は妻も一目を置いている。我らには見えないものも見えているのだろう。
「そうね。若い娘を国外に出すくらいなのですから並みではないはずです。ですが、やはり、なんと言うか、世間とずれたところがあるように思えます」
妻も男爵夫人と似た感想のようだ。
「ザンバドリ侯爵家、と言うのが判断を難しくさせているな」
カルビラス王国を何十年と支えて来たザンバドリ侯爵家。その影響力は周辺国にも及ぶ。今回の大使団もザンバドリ侯爵家の長男と第二王女の婚礼参加が主である。
「薄紫の髪、あれはシャルニアート王国に多い髪ですよね?」
「ええ。ですが、毛先が濃い紫です。染めてる様子もなかったですし、地毛だとすると特殊な血筋ではないでしょうか?」
珍しい髪の色だとは思ったが、妻が言ったようにシャルニアート王国とも交易はしているし、流れて来る者もいる。わたしも薄紫の髪は見た記憶がある。
「特殊な血筋は間違いないだろうな。領域回復できる魔力など聖女級だ。本人は力技だと言ってたがな」
回復魔法を力技だと言い切る者を初めて見た。教会の者が聞いたら憤慨することだろうよ。
「一人で旅をしているのだから、回復魔法だけではないでしょうな」
だろうな。ここまでなにで来たかわからないが、なにも起こらず来れるほど安全な道程ではない。騎士や兵士に護衛された我々ですら魔物の襲撃を受けてるのだからな。
「あの、シャーリー嬢が腰に下げていたもの、武器であろうな」
なんであるかはわからないが、手に持つものだった。
「ですな。抜きやすそうな位置にありましたし」
今は恰幅がよい姿だが、若い頃は軍に所属していた男爵だ。なんであるかわからなくても武器であることは位置でわかるのだろう。
「ただ、戦いに慣れた感じはしませんでしたな」
凄みもなく隠している気配もない。常に自然体でいて、こちらをまったく警戒していなかった。
「どう言う立場なんだか……」
隠密ならもっと隠すだろう。なのに、シャーリー嬢はあるがままを出している。それがまた判断を難しくするのだ。
身なりや立ち振舞い、口調から貴族並みの教育を受けていることはわかる。が、令嬢の教育ではないのもわかる。いったいどんな家に生まれ、どう育てたらああなるのやら?
「なんにせよ、シャーリー嬢はザンバドリ侯爵家と繋がりがあるのは間違いないないだろう」
証拠を持っていたわけではないが、彼女の言葉に偽りはない。言葉の端々に侯爵との繋がりの強さを感じるのだ。
「そうですな。あの領域回復だけ見てもただの主従関係と思えない」
「ええ。かなり強い繋がりがあるか、関係の近いところにいると思います」
「わたしも同意見です」
男爵、男爵夫人、妻の意見は一致した。
「となると、どう接するかだな」
侯爵家との繋がりが強いが、シャーリー嬢は侍女と言っている。侯爵家に仕えている。
こちらは外国の者で大使団だ。侍女相手に令嬢扱いをしてはサンビレス王国としての面子にもかかわる。
だからと言って完全に侍女扱いは不味い。不当に扱うのもダメだ。ザンバドリ侯爵家を敵にはできないのだから。
「兵士たちを回復してくれたのですから客人として扱うのではいいのでは?」
と、妻が口にした。
「それがよいかと。ただ、仲を深めるためにも侍女と一緒にさせるのがよいと思います」
とは男爵夫人。女性のことは女性に任せたほうがよいのかもしれんな。
「では、シャーリー嬢のことはアリータに任せる。上手く仲を繋いでくれ。わたしもできる限りのことはするから」
「はい。お任せください」
今はこれが精々か。まったく、カルビラス王国に入る前にこれとはな。運が良いと思い努力するしかないか……。
「出発までよろしく頼む」
全員が力強く頷いた。
さて。わたしもやれることをやるとしようか。