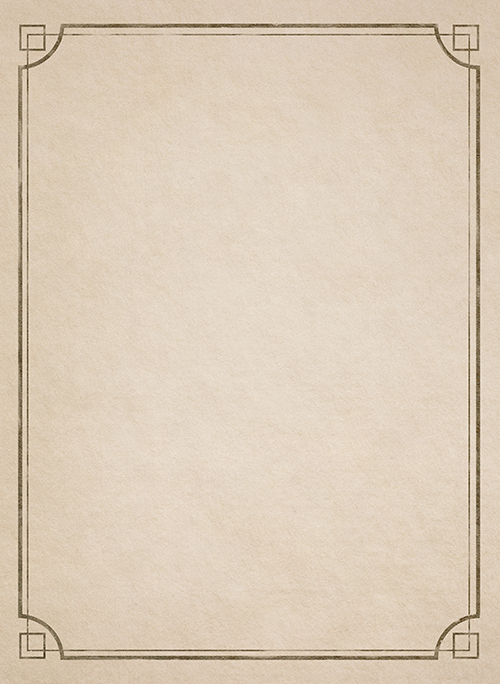八
しかし状況は一変した。
洛陽の西、潼関へ進軍すると、安禄山軍の快進撃もここで止められたのである。
山岳と黄河に挟まれたこの要害は、まず封常清と高仙芝の二将軍に守られ、その後、哥舒翰という猛将に替わった。
唐の朝廷から兵馬副元帥に任ぜられたこの哥舒翰は、徒に戦おうとせず、関門を堅く閉ざす戦法を採った。安禄山軍は何度挑んでも、ここを突破できない。
結局、膠着したまま日は流れ、翌年(天宝十五載、西暦七五六年)の正月。
安禄山は業を煮やし、取って置きの手段に踏み切った。
洛陽の地で、帝位に就いたのである。
隣の長安をにらみながら、我こそは唐に替わる新たな皇帝である、と宣言した。
国号は、大燕とした。
本拠地の范陽が、古くは燕という地名なのにちなんでいる。
「もう後へは戻れなくなった。しかし殿は……いや陛下は、本当に唐を倒せるだろうか?」
雷梧は、兵舎の部屋でつぶやいた。
景気よく皇帝を名乗りはしたが、昨年末あたりから各地で唐軍の抵抗が強くなっている。顔真卿、郭子儀などの名将によって、これまでの占領地が奪回され始めていた。
しかし、洛陽には大量の穀物を蓄えた穀倉地帯があり、安禄山はその食料を繋ぎにして、潼関を落とす機を窺っている。
それでも戦況は動かず、半年が過ぎた。
六月七日。
雷梧は部隊を率いて、潼関に向かって馬を歩かせていた。
「しかし雷将軍、唐の兵は弱いですね。うちの子供よりも腕が細いし」
ひげ面の第一部隊長・縻刻が言うと、雷梧も笑って頷いた。
「全くだね。あいつら、ろくに武器も使えない。潼関を落とすのなんて、時間の問題かな」
雷梧は、縻刻とだらだら無駄話をした。後ろには、旗を寝かせて勝手に休憩している兵士もいるが、雷梧は注意もしない。
崔乾祐という上司が、潼関攻めの総督をしている。
最近の雷梧は、彼の下で斥候を兼ねた計略の役目に就いていた。いつも関門のすぐそばまで探りに来るが、わざとだらしなく、やる気のない軍を演じて帰る。――燕国の軍(安禄山軍)は勝ちに慣れて油断している、と思わせる作戦だった。
だが、関門は沈黙したままである。
潼関は山岳と黄河の間にあるが、そこに至る百里(約五○キロ)の道は、馬車もすれ違えないほど狭い。攻める側には不利な地形であった。
「ずっと守りを固めたまま、という敵はやりにくいですね」
若禿げな第二部隊長・費賢登が、瓢箪酒を飲むふりをしながら言った。
雷梧も頷く。
「こうも道が狭いと、大軍は突入ができない。僕が守将でも、やはり待つ作戦を採る」
攻める側としては、時間がかかるほど軍糧も体力も減る。だから敵の出陣を促し、内側へなだれ込む作戦なのだが、それは向こうも承知だった。
「戻ろう。今日も無人のように静かだった、と報告だ」
雷梧が馬首を返そうとした時、潼関の門がゆっくりと開いた。まさかと思っていると、門は開ききり、続々と唐の兵が現れた。
「雷将軍、で、出てきましたね?」
費賢登が、驚いて目をこする。
「数も多い。これは唐の本軍が出てきたな」
雷梧はすばやく、敵の規模を目で測った。
「唐兵を捕らえ、状況を聞き出せました」
斥候に出た、宇文平からの伝令も来た。
「戻るぞ。なぜ出てきたのかは分からないが」
雷梧は馬上で合図を出し、本営に帰った。
潼関攻略部隊の本陣が、外に帷幕を広げている。総督の崔乾祐は将軍たちを集め、この辺り一帯の地図を眺めていた。
「やっと出てきたな。開戦は明日の朝だろう」
崔乾祐は、地図の上にいくつも丸を描き、兵の配備を伝えた。
「唐軍は二十万もいるらしいが、臆せず作戦どおりにやれ。――雷梧、お前の兵を一万に増やす。明日は俺に隊を合わせろ」
会議は終わった。
雷梧は、大きな合戦になる予感がして、思わず身震いした。
翌朝、雷梧は崔乾祐に従い、北へと移動した。黄河を渡り、広い森に隠れて待機する。
辰の刻(午前八時)になると、哥舒翰の方から攻撃を開始してきた。潼関の東、霊宝の西原での開戦である。
「唐軍には存分に攻めさせろ。自分たちは強いんだと思わせてやれ」
崔乾祐は、余裕の笑みを浮かべている。彼のそばにいるおかげで、雷梧は戦況を詳しく知ることができた。
やがて唐軍の先鋒・王思礼が五万の兵で攻めて来たという報告が届く。
崔乾祐は、燕軍をわざと逃げさせ、勢いに乗って追い込ませるよう仕向けた。
「よし。王思礼を隘路に誘え」
崔乾祐はあらかじめ、山頂に伏兵を配置していた。狭い道に誘い込んだ王思礼の軍に、巨石や丸太を投下させる。
やがて伝令が来て、相手は大混乱に陥っていると告げた。
「今だ。雷梧、騎兵を出せ」
突然命じられた雷梧は、驚いて言う。
「確かに好機ですが、ここからでは遠すぎませんか」
「王思礼ではない、討つのは哥舒翰だ。自分が攻撃されるとは思っていまい」
崔乾祐は始めから、哥舒翰の居場所を知っていたらしい。了解した雷梧は、隊を整え、森を飛び出した。
確かに、森を越えるとすぐ、哥舒翰の軍旗が見える。それを目指し、雷梧は全軍に突進の合図をした。
しかし哥舒翰の軍は、驚きながらも兵を左右に開く。次に、雷鳴のような大音と共に、大きな何かが走って来た。
魔獣かと見紛う、巨大な戦車。四頭の鎧馬を御者が操り、戟手と弓手を乗せている。車体からは無数の刃が突き出し、竜虎を描いた織物を纏っていた。
「何だあれは。いっぱいいるぞ」
雷梧は驚いた。戦車は続々と現れ、燕軍の兵を斬り、跳ね飛ばす。
「噂に聞いた『氈車』ですね。金に物を言わせた、えげつない兵器ですよ」
宇文平が、呆れた声で解説した。彼の平静さを見て、雷梧は氈車を今一度よく見る。
瞬時に、弱点に気付いた。
「火だ。柴を燃やした台車で突っ込もう」
「ですね。あの織物が仇になりますよ」
たちまち松明が回され、火を積んだ台車がずらりと揃った。
雷梧が火矢を射ると、一台の氈車が燃え上がって谷へ落ちる。
それを合図に、一斉の火攻めが始まった。折りも良く、東風が強く吹き、炎が万余の兵にも勝って暴れてくれる。
炎に巻かれた魔獣は無力だった。多数の味方を巻き込んで炎上し、やがて捨てられる。
雷梧は兜の紐を締め直すと、闇鵬の腹を蹴り、混乱する唐軍に突入した。
手柄を立てたい。
将として認められ、安禄山を諫める立場に昇る。残っていた希望は、もうそれくらいだった。
炎は更に勢いを増し、森と氈車を焼き続けている。