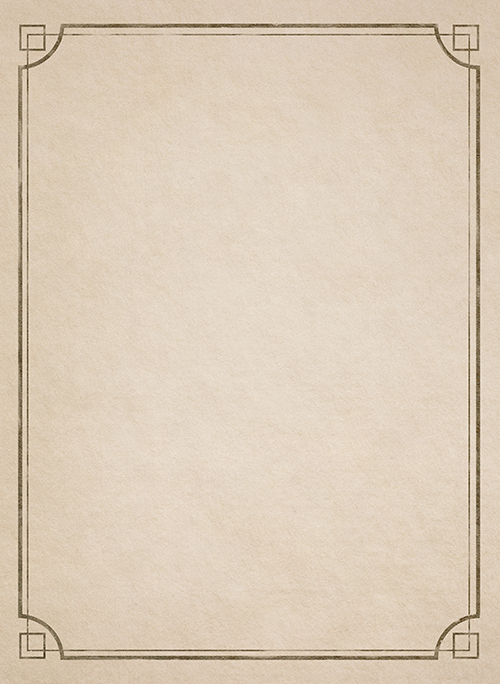七
陳留を出発した安禄山軍は、進路を西へ転じ、十二月十二日、東都・洛陽に到着した。
封常清という将軍がここを守っており、郊外で開戦の準備をしているという。
「ようやく骨のある奴が出てきたな。よし、徹底的に叩き潰せ」
安禄山が、顎をしゃくる。全軍が、猛攻撃を始めた。
雷梧も、部隊を率いて唐の軍に迫る。
賊軍を是としたわけではないが、かと言って唐が不動の正義であるわけでもない。そう解釈することに決めた。どちらが正しいかは、戦の中で見極める。剣を振る手にも、力を込めた。
ところが、この唐軍が、てんで弱い。
攻め込めば逃げ散り、剣を振ればだいたい斬れている。
「弱すぎる。北方の契丹族の方が遙かに手強かった。これで唐の内地を守れるつもりか」
唐兵は精強な安禄山軍とは違い、ろくに訓練もされていないし、護国の覇気も見えない。護られる立場とはこうも惰弱なのかと、雷梧は苛立った。
洛陽を守護する封常清は、有能な将軍だった。しかし率いる兵が弱すぎて、役に立たない。結局洛陽を放棄して、その西の潼関という関所まで退いた。
雷梧は、以前に長安へ行った際、洛陽を通っていた。古来から何度も王朝の都となった要地で、寺院が多く、文化と芸術の発展した街だった。
安禄山軍はその洛陽城内に乗り込み、またも際限の無い虐殺と略奪を始めた。もう理性も理想も見えはしない。
雷梧はやはり、これに納得できなかった。
あてがわれた兵舎で休んでいると、日の暮れかかった頃、宇文平が仲間を連れて外へ出ようとしている。
慌てて追いすがり、声をかけた。
「待て、宇文平。僕の部隊には凶行を許さない。従わない者には罰を与えると言っておけ」
強く言ったのだが、宇文平は目をそらせた。
「お気持ちは分かりますが、兵たちの楽しみを奪ってしまうのもどうかと」
「無闇に人を傷つけて、何が楽しみだ」
どうして分からないのだ、と目を怒らせた。宇文平たちは苦笑しながら、舎内へ戻る。
雷梧は自ら見張りになって、兵舎の入り口に立った。
近隣の兵舎からは、歪んだ笑顔の兵士がぞろぞろ出かけていく。
遠くから、騒がしい音がした。
「椋鳥かな」
そうつぶやいてから、雷梧は頭を振る。
「違う。これは」
あまりにも多くの、人の悲鳴だった。
雷梧は夕陽をにらむ。
沈んでいく姿が美しいのは、太陽だけだ。皮肉な名を持つ洛陽は、こんなにも惨めに暮れてしまう。
だがここは、安禄山が定めた目的地だ。
これからは良くなる。
かもしれない。
王朝の交代は、幾度も行われてきたことだ。
どうにか納得したかったが、絶え間なく響く悲鳴は、何にも勝る真実だった。