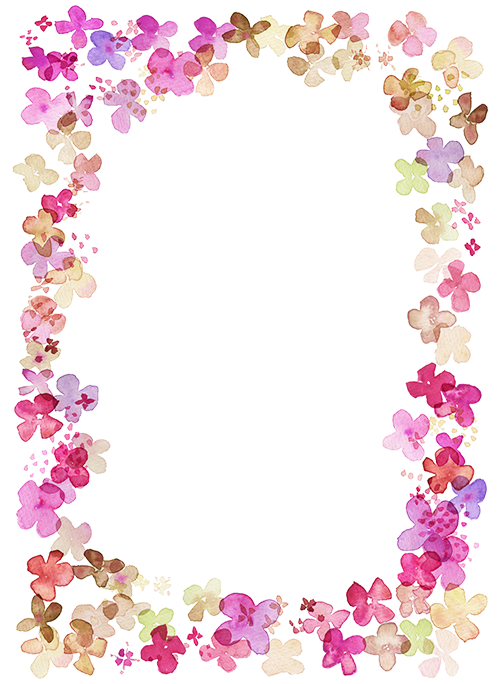夜が明けようとしていた。
几帳の向こうで鳥の声が聞こえる。けれど几帳を開く気配はまだ、ない。
後宮の朝は遅い。それも病弱なこの部屋の主のために、帝がなるべくゆったりとした朝をと命じているのが効いている。
琥珀色の几帳にうっすらと光がさす。そのさまを、涼子はまだ自由が効かない体を床に横たえながら見ていた。
寝床に座って、兄帝の華沙が涼子の頭をなでている。黒い単衣を涼子の肩にかけて、冷えないようにしていた。
華沙の濡れたような漆黒の髪は、宵那国の帝の血を引く証だ。けれど華沙の母は身分の低い女房だったために、帝位につくには困難が伴った。
彼は兄皇子たちとの激しい争いの末、帝位についた。色白で端正な顔立ちに反して、灰色がかった瞳は凍てつく冬のように厳しい。
ただ涼子にとって恐ろしい兄だったかというと、決してそうではなかった。
涼子は顔を上げないまま彼を呼ぶ。
「兄上」
涼子の頭をなでる手が止まって、華沙が何か言おうとする気配がした。
涼子はそれを聞かずに言葉を続ける。
「もう私を放っておいてください」
ぽつりと虚空にこぼした言葉に、華沙は几帳ごしに外の光をみつめて動かなかった。
炭櫃の火が音を立てて落ちる。何度か女官が来て炭を足していって、夜中燃えていた。
涼子が見上げた華沙の横顔は、ずっと何かを考え込んでいるようだった。
そういうとき、涼子は言葉を挟まない。ただ目を逸らして、華沙と几帳の外の光を見まいとした。
ふいに頭に置かれていた華沙の手が動いて、涼子の首に触れた。
そこは包帯で巻かれて、血はにじんではいなかったが、熱で少し湿っていた。
華沙は涼子の首の包帯を触って、血が確かに止まっていることを確認する。
夜中、数えきれないくらい同じ触れ方をしたのに、今度も時間をかけて確かめていた。
華沙は涼子の肩に手をやって自分の方を向かせる。
涼子が見上げた華沙の灰色の瞳は、何か言いたげだった。涼子はそれに気づいていながら目を逸らそうとした。
それをとがめるように、華沙は涼子の両脇に手をついて身を屈める。
華沙はいつも、涼子の薄い唇を傷つけないようにとでもいうように静かに唇を合わせる。
けれど兄妹の口づけというには長く、甘い。
涼子から少し顔を離して、華沙は問う。
「何が欲しい?」
涼子の頬をなでて、華沙は言葉を続ける。
「言ってみよ、すず。宝石でも離宮でも、そなたの望むとおりにしよう」
言葉の甘さに反して、涼子には真綿で首を絞められているような心地がした。
涼子はかすれた声で告げる。
「……消えたいのです」
華沙は首を横に振ると、哀しく笑った。
「許さぬ」
涼子の耳元で子どもをあやすように言って、こめかみに口づける。
几帳の向こうで声が聞こえた。女官が涼子の具合を見に来たのだろう。
兄上と、涼子は小さく声を上げて、離れようと身をよじる。
華沙はひとつ息をついて、身を起こした。気が進まない声音で女官を呼ぶ。
「入れ」
華沙の黒髪が裸の首筋を流れる様がなまめかしかった。
女官は断りを入れて部屋に踏み込む。
「失礼いたします」
涼子付きの女官はすべて華沙が選んだ者だから、ここに帝の姿があるのを当然のように受け入れている。
華沙はいつものように、女官へ涼子のことを事細かに命じた。
「まだ体温が低い。部屋を暖め、滋養のあるものを食べさせてやるよう」
「かしこまりました」
華沙は自分で身支度を整えると、女官に支えられて身を起こした涼子を振り向く。
涼子の頬を両手で包むと、華沙は額を合わせて低く言う。
「もう自分を傷つけるでないぞ。よいな?」
子どもに言い聞かせるようでいて、それは命令だった。
「一時は本当に危なかったのだ。この細い手で、そこまでの力をこめて」
少しも笑っていない目で、華沙は涼子の目を射抜く。
「体か、心か。痛むところを教えてほしい。自分で傷つける前に。私がそれを取り除くゆえ」
涼子は目を伏せて、答えなかった。
その沈黙を華沙がどうとらえたか、涼子にはわからなかった。
ふいに華沙は目を閉じて告げた。
「……暖かいな」
華沙は涼子の頬から首に手をすべらせる。
「昨日よりよほど暖かい。今はそれだけでよい。すず、愛している。私の」
妹、とつぶやいた声は、独り言のようだった。
華沙は涼子の頭に口づけると、体を離す。
「ゆるりと過ごせ。夜に、また」
そう言って去っていく華沙を、涼子は見送った。
几帳の向こうで鳥の声が聞こえる。けれど几帳を開く気配はまだ、ない。
後宮の朝は遅い。それも病弱なこの部屋の主のために、帝がなるべくゆったりとした朝をと命じているのが効いている。
琥珀色の几帳にうっすらと光がさす。そのさまを、涼子はまだ自由が効かない体を床に横たえながら見ていた。
寝床に座って、兄帝の華沙が涼子の頭をなでている。黒い単衣を涼子の肩にかけて、冷えないようにしていた。
華沙の濡れたような漆黒の髪は、宵那国の帝の血を引く証だ。けれど華沙の母は身分の低い女房だったために、帝位につくには困難が伴った。
彼は兄皇子たちとの激しい争いの末、帝位についた。色白で端正な顔立ちに反して、灰色がかった瞳は凍てつく冬のように厳しい。
ただ涼子にとって恐ろしい兄だったかというと、決してそうではなかった。
涼子は顔を上げないまま彼を呼ぶ。
「兄上」
涼子の頭をなでる手が止まって、華沙が何か言おうとする気配がした。
涼子はそれを聞かずに言葉を続ける。
「もう私を放っておいてください」
ぽつりと虚空にこぼした言葉に、華沙は几帳ごしに外の光をみつめて動かなかった。
炭櫃の火が音を立てて落ちる。何度か女官が来て炭を足していって、夜中燃えていた。
涼子が見上げた華沙の横顔は、ずっと何かを考え込んでいるようだった。
そういうとき、涼子は言葉を挟まない。ただ目を逸らして、華沙と几帳の外の光を見まいとした。
ふいに頭に置かれていた華沙の手が動いて、涼子の首に触れた。
そこは包帯で巻かれて、血はにじんではいなかったが、熱で少し湿っていた。
華沙は涼子の首の包帯を触って、血が確かに止まっていることを確認する。
夜中、数えきれないくらい同じ触れ方をしたのに、今度も時間をかけて確かめていた。
華沙は涼子の肩に手をやって自分の方を向かせる。
涼子が見上げた華沙の灰色の瞳は、何か言いたげだった。涼子はそれに気づいていながら目を逸らそうとした。
それをとがめるように、華沙は涼子の両脇に手をついて身を屈める。
華沙はいつも、涼子の薄い唇を傷つけないようにとでもいうように静かに唇を合わせる。
けれど兄妹の口づけというには長く、甘い。
涼子から少し顔を離して、華沙は問う。
「何が欲しい?」
涼子の頬をなでて、華沙は言葉を続ける。
「言ってみよ、すず。宝石でも離宮でも、そなたの望むとおりにしよう」
言葉の甘さに反して、涼子には真綿で首を絞められているような心地がした。
涼子はかすれた声で告げる。
「……消えたいのです」
華沙は首を横に振ると、哀しく笑った。
「許さぬ」
涼子の耳元で子どもをあやすように言って、こめかみに口づける。
几帳の向こうで声が聞こえた。女官が涼子の具合を見に来たのだろう。
兄上と、涼子は小さく声を上げて、離れようと身をよじる。
華沙はひとつ息をついて、身を起こした。気が進まない声音で女官を呼ぶ。
「入れ」
華沙の黒髪が裸の首筋を流れる様がなまめかしかった。
女官は断りを入れて部屋に踏み込む。
「失礼いたします」
涼子付きの女官はすべて華沙が選んだ者だから、ここに帝の姿があるのを当然のように受け入れている。
華沙はいつものように、女官へ涼子のことを事細かに命じた。
「まだ体温が低い。部屋を暖め、滋養のあるものを食べさせてやるよう」
「かしこまりました」
華沙は自分で身支度を整えると、女官に支えられて身を起こした涼子を振り向く。
涼子の頬を両手で包むと、華沙は額を合わせて低く言う。
「もう自分を傷つけるでないぞ。よいな?」
子どもに言い聞かせるようでいて、それは命令だった。
「一時は本当に危なかったのだ。この細い手で、そこまでの力をこめて」
少しも笑っていない目で、華沙は涼子の目を射抜く。
「体か、心か。痛むところを教えてほしい。自分で傷つける前に。私がそれを取り除くゆえ」
涼子は目を伏せて、答えなかった。
その沈黙を華沙がどうとらえたか、涼子にはわからなかった。
ふいに華沙は目を閉じて告げた。
「……暖かいな」
華沙は涼子の頬から首に手をすべらせる。
「昨日よりよほど暖かい。今はそれだけでよい。すず、愛している。私の」
妹、とつぶやいた声は、独り言のようだった。
華沙は涼子の頭に口づけると、体を離す。
「ゆるりと過ごせ。夜に、また」
そう言って去っていく華沙を、涼子は見送った。