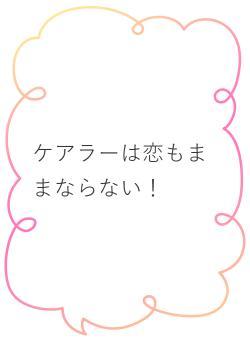「ひとつ、米を炊くこと。ふたつ、味噌汁は出汁濃いめ。みっつ朝は魚」
思いつくままに花狩灯は即席数え歌を歌う。
実家は窮屈で窮屈で、人間の家に嫁ぐことで威厳ある振る舞いをしなくてもいいと考え、実際に良き新妻となるべくおさんどんに励んでいた。
鬼の頭領の家に生まれた花狩灯は自由に焦がれていた。年頃になって一族の誰かと婚姻を結ぶかという時に、人間と婚姻する鬼の募集が掛かった。
鬼は人間に嫁ぎ、人間は鬼に嫁ぐ。人質交換をして和平を結ぼうというよくある話だ。
花狩灯は花嫁に立候補したものの位が高い男に気に入る者はいなかった。そこで恭枋が出てきた。
気に入ったからには妻として尽くそう。そう考え婚約期間中に花嫁修業に励み、一通りの家事を覚えた。
もちろん同族には大変不評だったが、花狩灯は気にしなかった。そうした同族は大抵花狩灯より弱かったからだ。
嫁ぎ、どうやら恭枋はこの婚姻を形式的なものだと思っているらしかった。同じ部屋に布団を並べて眠っても手出しはない。
ならば理解らせてやろうと思った。誰が妻で、誰が夫か。
通いの家事手伝いに暫くこなくていいと朝一番に伝え、朝食の準備を始めた。
炊事場の外で、七輪で秋刀魚を焼いていると浴衣のままの恭枋が現れる。
厳つい顔をぽかんとさせ、暫くの沈黙の後に声を絞り出した。
「……何をなさっておいでですか、姫」
「まあ、夫婦になったのですから花とお呼びください。旦那様」
質問に答えず、こちらの要望を伝える。
「では花、何をなさっておいでで」
言い直した恭枋にまずはひとつ丸だ。
七輪をうちわで扇いでにっこりと笑う。
「おさんどん、です」
恭枋は秋刀魚が焼き上がるまでたっぷり沈黙した。
きっと頭の中は政争とか権力争いとか家の立場とか鬼への面目とかでぐるぐるしていたことだろう。鬼には好きに花嫁をさせてくれと言い含めてきたので心配ないのだが、やはり同族が面倒か。
面倒な付き合いに煩わされるくらいなら、首を刎ねてしまおう。それで恭枋の憂いはなくなるはずだ。
「さあ、旦那様。お召し替え手伝いますから少々お待ちを」
「……!! 自分で着替えます」
硬直していたのが嘘のように室内へ引っ込んで行った。
手伝えないのが残念だが、朝食はいい具合である。
膳に盛り付け、居間へ向かった。
「いただきます」
「どうぞ、召し上がれ」
用意したものは食べてくれるらしい。
上品に食べる姿は貧乏武家の当主というより、もっと立派な家の出のように見えた。
「花は食べないのですか」
「あら、旦那様に見蕩れておりました。いただきます」
頬を染めて見せると、彼は瞠目し意を決したように口を開く。
「謁見の時とお人柄が違っておられるようにお見受けするのですが」
直球で訊ねられ、そう言う性根が好ましいと思った。
「こちらが素です。貴方のために尽くしたい私、それが花。貴方のために政敵の首を刎ねてしまいたい私、それが花狩灯。そのような理解がよろしいかと」
ごくりと息を呑む音がする。
「ですから、お互いのために私を花でいさせてくださいね」
愛を込めて伝えると、恭枋は僅かに身を竦ませた。
「善処します」
何でもない振りをして彼は味噌汁を啜る。少し目を輝かせたことを見逃さない。
出汁濃いめ、当たりだ。
「しかし、何も家事をする必要はないのでは」
「旦那様の爪先から毛髪の先、身に纏うものから、住む環境、全て私で染め上げたいと願うことはそんなに罪作りでしょうか?」
今度こそ隠さずにぎょっとしている。
重たいのは自覚がある。だがこの鷹はそこまでする価値があると踏んでいた。
「そこまで、好かれる覚えがないのですが……」
「一目惚れ、という言葉をご存じないでしょうか。旦那様はまるで鷹のよう。脆弱な人の身で鬼に立ち向かってしまえそうで。私が容易に殺したくないと思った、そのことが全てです」
うっとりと謡い上げると、愛と共に殺気を向けてみる。
恭枋はさっと傍らに置いた刀を取り鯉口を切った。本能的な行動をして、相手が誰だったか思い出したらしい。
すぐに刀を置いた。
「申し訳ありません」
「いいえ、旦那様。それが正解ですよ」
気にすることもなく食事を続ける。
愛と殺伐は、紙一重だ。
思いつくままに花狩灯は即席数え歌を歌う。
実家は窮屈で窮屈で、人間の家に嫁ぐことで威厳ある振る舞いをしなくてもいいと考え、実際に良き新妻となるべくおさんどんに励んでいた。
鬼の頭領の家に生まれた花狩灯は自由に焦がれていた。年頃になって一族の誰かと婚姻を結ぶかという時に、人間と婚姻する鬼の募集が掛かった。
鬼は人間に嫁ぎ、人間は鬼に嫁ぐ。人質交換をして和平を結ぼうというよくある話だ。
花狩灯は花嫁に立候補したものの位が高い男に気に入る者はいなかった。そこで恭枋が出てきた。
気に入ったからには妻として尽くそう。そう考え婚約期間中に花嫁修業に励み、一通りの家事を覚えた。
もちろん同族には大変不評だったが、花狩灯は気にしなかった。そうした同族は大抵花狩灯より弱かったからだ。
嫁ぎ、どうやら恭枋はこの婚姻を形式的なものだと思っているらしかった。同じ部屋に布団を並べて眠っても手出しはない。
ならば理解らせてやろうと思った。誰が妻で、誰が夫か。
通いの家事手伝いに暫くこなくていいと朝一番に伝え、朝食の準備を始めた。
炊事場の外で、七輪で秋刀魚を焼いていると浴衣のままの恭枋が現れる。
厳つい顔をぽかんとさせ、暫くの沈黙の後に声を絞り出した。
「……何をなさっておいでですか、姫」
「まあ、夫婦になったのですから花とお呼びください。旦那様」
質問に答えず、こちらの要望を伝える。
「では花、何をなさっておいでで」
言い直した恭枋にまずはひとつ丸だ。
七輪をうちわで扇いでにっこりと笑う。
「おさんどん、です」
恭枋は秋刀魚が焼き上がるまでたっぷり沈黙した。
きっと頭の中は政争とか権力争いとか家の立場とか鬼への面目とかでぐるぐるしていたことだろう。鬼には好きに花嫁をさせてくれと言い含めてきたので心配ないのだが、やはり同族が面倒か。
面倒な付き合いに煩わされるくらいなら、首を刎ねてしまおう。それで恭枋の憂いはなくなるはずだ。
「さあ、旦那様。お召し替え手伝いますから少々お待ちを」
「……!! 自分で着替えます」
硬直していたのが嘘のように室内へ引っ込んで行った。
手伝えないのが残念だが、朝食はいい具合である。
膳に盛り付け、居間へ向かった。
「いただきます」
「どうぞ、召し上がれ」
用意したものは食べてくれるらしい。
上品に食べる姿は貧乏武家の当主というより、もっと立派な家の出のように見えた。
「花は食べないのですか」
「あら、旦那様に見蕩れておりました。いただきます」
頬を染めて見せると、彼は瞠目し意を決したように口を開く。
「謁見の時とお人柄が違っておられるようにお見受けするのですが」
直球で訊ねられ、そう言う性根が好ましいと思った。
「こちらが素です。貴方のために尽くしたい私、それが花。貴方のために政敵の首を刎ねてしまいたい私、それが花狩灯。そのような理解がよろしいかと」
ごくりと息を呑む音がする。
「ですから、お互いのために私を花でいさせてくださいね」
愛を込めて伝えると、恭枋は僅かに身を竦ませた。
「善処します」
何でもない振りをして彼は味噌汁を啜る。少し目を輝かせたことを見逃さない。
出汁濃いめ、当たりだ。
「しかし、何も家事をする必要はないのでは」
「旦那様の爪先から毛髪の先、身に纏うものから、住む環境、全て私で染め上げたいと願うことはそんなに罪作りでしょうか?」
今度こそ隠さずにぎょっとしている。
重たいのは自覚がある。だがこの鷹はそこまでする価値があると踏んでいた。
「そこまで、好かれる覚えがないのですが……」
「一目惚れ、という言葉をご存じないでしょうか。旦那様はまるで鷹のよう。脆弱な人の身で鬼に立ち向かってしまえそうで。私が容易に殺したくないと思った、そのことが全てです」
うっとりと謡い上げると、愛と共に殺気を向けてみる。
恭枋はさっと傍らに置いた刀を取り鯉口を切った。本能的な行動をして、相手が誰だったか思い出したらしい。
すぐに刀を置いた。
「申し訳ありません」
「いいえ、旦那様。それが正解ですよ」
気にすることもなく食事を続ける。
愛と殺伐は、紙一重だ。