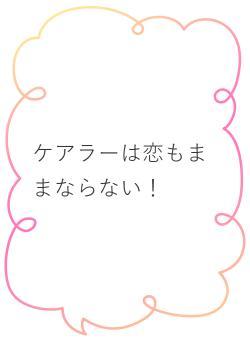鬼女は旦那様に尽くしたい
「これらに坐す鬼の姫、花狩灯姫命様に拝謁願います」
御簾越しにすっと頭を下げた男を見遣る。
この御簾を上げれば実質婚姻となることは部屋付きの鬼全てが理解していた。
男は肩に着くほどの黒髪を流し、程よく厳つい顔つきをしている。中肉中背に見えるが実際は鍛えられていそうだ。
この男、深田恭枋は深田家の中でも没落している家の当主らしい。鬼の姫を娶るのに貧乏人とは侮辱である、と血気盛んな者は言う。だが他の深田や家柄の良い者と顔を合わせても、花狩灯は何も思わなかった。強いて言えば、爪の一振りで始末出来るだろうと思ったくらいで。
恭枋は油断ない。今も平伏したまま緊張を解かない。殺されても不思議ではないことを理解している。さぞ仕事の出来ることだろう。
没落したのは恭枋の親の代だというし、鳶は鷹を生んだらしい。
花狩灯は延々と繰り返される見合いに厭いていた。これまでの男たちが雛なら、鷹でいいのではないか。
右手を一振りし、部屋付きに御簾を上げるよう指示する。
部屋中に緊張が走った。
驚いている者、不満そうな者、恭枋を害しそうな者、様々だがみな不満のようだ。
「其方ら、婿殿に対して不敬であるぞ」
警告を発すると恭枋の肩が僅かに揺れた。
「恭枋と言ったな。面を上げよ」
「はっ」
恭枋が顔を上げる。紋付き袴の良く似合うこと。
この着物も僅かな財産から捻りだしたのかと思うと憐憫を誘う。
「花狩灯と申す」
黒茶の瞳と対峙した。
意志の強そうな切れ長の目は心を躍らせる。
「意味は解るな」
訊ねると恭枋は再び平伏した。
「まこと有り難き幸せ」
それが恭枋との出会いだった。
「これらに坐す鬼の姫、花狩灯姫命様に拝謁願います」
御簾越しにすっと頭を下げた男を見遣る。
この御簾を上げれば実質婚姻となることは部屋付きの鬼全てが理解していた。
男は肩に着くほどの黒髪を流し、程よく厳つい顔つきをしている。中肉中背に見えるが実際は鍛えられていそうだ。
この男、深田恭枋は深田家の中でも没落している家の当主らしい。鬼の姫を娶るのに貧乏人とは侮辱である、と血気盛んな者は言う。だが他の深田や家柄の良い者と顔を合わせても、花狩灯は何も思わなかった。強いて言えば、爪の一振りで始末出来るだろうと思ったくらいで。
恭枋は油断ない。今も平伏したまま緊張を解かない。殺されても不思議ではないことを理解している。さぞ仕事の出来ることだろう。
没落したのは恭枋の親の代だというし、鳶は鷹を生んだらしい。
花狩灯は延々と繰り返される見合いに厭いていた。これまでの男たちが雛なら、鷹でいいのではないか。
右手を一振りし、部屋付きに御簾を上げるよう指示する。
部屋中に緊張が走った。
驚いている者、不満そうな者、恭枋を害しそうな者、様々だがみな不満のようだ。
「其方ら、婿殿に対して不敬であるぞ」
警告を発すると恭枋の肩が僅かに揺れた。
「恭枋と言ったな。面を上げよ」
「はっ」
恭枋が顔を上げる。紋付き袴の良く似合うこと。
この着物も僅かな財産から捻りだしたのかと思うと憐憫を誘う。
「花狩灯と申す」
黒茶の瞳と対峙した。
意志の強そうな切れ長の目は心を躍らせる。
「意味は解るな」
訊ねると恭枋は再び平伏した。
「まこと有り難き幸せ」
それが恭枋との出会いだった。