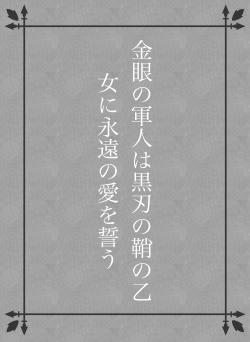「うわあ……」
展望台広場から眺める大パノラマに瑞希は歓声を上げた。
眼下には見渡す限りエメラルドグリーンの湖。
遅めの春が訪れたばかりの湖畔には、若芽が青々と芽吹いている。
雲が大きな影をつくり、ときおり強めの風が吹いたら、水面がさざ波を打つ。
想像以上の絶景だった。
ポスターで見た無機質な写真とは比べ物にならない。
(来てよかった)
瑞希は帽子が飛ばされないように、手で押さえながら、念願の光景を目に焼きつける。
木綿子はなにも言わず、蓬莱湖を眺める瑞希の隣に立ち、手すりに身体を預けていた。
風で流れていく雲をいくつも見送り、吹き荒ぶ風に吹かれること数分。
ふと、展望台広場の一角に人が集まっているのが目の端に留まる。
「あれ、なんですかね?」
トイレや売店があるわけでもない、なんの変哲もない場所に登山者が賑々しく列をなしている。
「あそこのあるハート型の岩の前で写真を撮ると願いが叶うって、最近SNSで評判らしいよ」
木綿子は理由を知っていたのか、澱みなく答えた。
やたら若い女性の登山者が多いと思ったら、そういう理由だったのか。
「私たちも並ぶ?」
木綿子に聞かれた瑞希は首を横に振った。
「私は大丈夫です」
パワースポットにあやかりたくて龍河谷に来たわけではない。
瑞希にとっては自分の足でこの地に立てたことが一番誇らしい。
「それならご飯にしましょう。お腹空いたよね」
空いているテーブルベンチに陣取るなり、木綿子はバックパックをゴソゴソ漁り出し、あるものを取り出した。
「こ、これが噂の……」
「点けてみる?」
木綿子がテーブルに置いたのは、ガス缶とガス缶に直接取り付けるタイプのバーナーだ。
瑞希は木綿子に教わりながらアタッチメント部分をガス缶に取り付け、折り畳まれていたバーナーの四つ脚部分を広げた。
点火用のスイッチを軽く回せば、簡単に火がつく。
「おー!」
無事に点火の儀を終えた瑞希は小さく拍手をした。
木綿子は持参したコッヘルに水を入れ、お湯を沸かし始めた。
取っ手が折りたためるステンレス鋼の深胴コッヘルは、バーナーと並ぶクライマーの必需品だ。
昼ごはんは、コンビニのおにぎりとインスタントのお味噌汁。
お味噌汁をひと口飲んだ瑞希は、ほうっと息を吐き出した。
「あったまる〜!」
遮蔽物のない山頂は文句なしに寒い。
疲れた身体に味噌汁の塩分と温かみが染み渡り、いつもの何倍も美味しく感じられた。
しかし、木綿子はどうにも不満げな様子だ。
「本当はああいうオシャレなやつもやりたいんだけどねー。私、どうにも料理が苦手で……」
木綿子は羨ましそうに背後を指差した。
鼻をすんすんと鳴らせば、どこからか香ばしい匂いが漂ってくる。
後ろのグループは木綿子のものより大きなガス缶とバーナーを持ち込み、メスティンでソーセージを焼いている。
ソーセージを炙ったコッペパンにインすれば、ホットドッグの出来上がりだ。
「私もメスティン買おうかなあ。でもひとりだとあんまり使わないし……」
よほど羨ましいのか木綿子はまだなにごとか、ぶつぶつ呟いている。
(いや、もうこれ。絶対買うやつじゃん)
言い訳が下手くそか。
でも、だんだん木綿子のことがわかってきた。
仕事では原価と販売値をシビアに判断できるのに、登山に関しては財布の紐がゆるゆるになりタガが外れてしまう。
木綿子にも抜けたところがあるのだとわかると、なんだかホッとする。
「お味噌汁も充分美味しいですよ」
お世辞ではなく本気でそう伝えると木綿子は、にへら〜と相好を崩した。
「ねえねえ、まだお腹空いてるでしょ? 実はとっておきのチョコレートを持ってきたの!」
木綿子はバックパックからいそいそと小綺麗な小箱を取り出した。
蓋を開ければ、美しく光沢のあるチョコレートが現れる。
見た目からして山登りの最中に消費するには、高級過ぎるチョコレートだ。
「いいんですか? こんなところで食べちゃって」
「疲れているときに食べた方がより美味しく感じるでしょ? むしろ今が食べどきだよ」
「たしかに……」
「他にもいろいろ持ってきてるの。ナッツクッキーでしょ、インスタントのカフェラテに紅茶のティーパックと――」
「藤峰さんのリュックはなんでも入ってますね」
さっきもらった栗羊羹といい、木綿子のバックパックには美味しいものがたくさん入っている。
ふふっと笑うと、木綿子もつられて笑みをこぼす。
「あははっ。行動食は登山中の活力だからね。カフェラテと紅茶、どっちにする?」
「じゃあカフェラテで!」
おにぎりと味噌汁で腹を満たした後は、即席のお茶会が始まる。
「最近、社食の定食のラインナップが変わったと思わない?」
「福利厚生の一環で、ヘルシー志向に転換したらしいですよ」
「えー! そうなの!? 全然気づかなかった〜。前の方が絶対美味しかったのに」
木綿子は不服そうに頬を膨らませた。
(こういう感じ、久しぶりかも)
この二年は婚活に時間を取られていたせいで、友人と出掛けたり、たわいもない話をする時間が目に見えて減っていた。
高級ホテルのアフタヌーンティーもいいけれど、絶景を見ながら頬張るチョコレートも悪くない。
何時間も険しい道のりを共にした仲間と一緒ならなおさらだ。
(ふたりで来てよかった)
絶えず冷たい風が吹き荒んでいるし、薄曇りで天気はいまいちはっきりしない。
展望台広場は賑やかで、あちこちから笑い声が聞こえてくる。
想像とはまるで違う風景だけれど、これはこれで楽しい。
チョコレートとカフェラテが、あっという間になくなっていく。
「今日はありがとうございました」
「いいえ、こちらこそ。魚谷さんのおかげでとっても楽しかったよ」
「瑞希でいいです」
瑞希は気がつくと、そう口を滑らせていた。
言ってしまったあとで、ハタと気がつく。
他部署とはいえ木綿子は、瑞希よりも上の立場の人間だ。
登山て距離が近づいたからといって、名前で呼んでほしいと口走ったら困るに決まっている。
ところが木綿子は、ニンマリと口の端を上げたのだった。
「じゃあ、私のことも木綿子って呼んでね」
クラス替えの初日みたいに、互いの呼び方を確かめあうのは少し照れがある。
「お茶も飲み終わったし、そろそろ行きましょうか」
木綿子は使ったカップをカラビラに引っ掛けると、おもむろにバックパックを背負い始めた。
「あの、木綿子さん! 帰る前に写真を撮りませんか?」
「あ、やっぱり並んどく?」
木綿子はいまだに絶えない行列を指差した。
「パワースポットは関係なしに木綿子さんとふたりで撮りたいんです」
写真を撮りたいというのは単なる思いつきだった。
なぜだかわからないけれど、このまま帰るのがもったいないと感じたのだ。
「別にいいけど……」
木綿子はバックパックを下ろし、そわそわと恥ずかしそうに帽子と強風で乱れた髪を整え始めた。
顔を寄せあい、スマホを横にしてインカメラに変更する。
「せーの!」
シャッターは瑞希が切った。
写真は得意な方ではないが、まずまずの出来だろう。
「ちょっと待って。私、変な顔してない?」
「大丈夫ですよ。いつも通りお綺麗です」
「白目剥いてたら、ちゃんと加工してね!」
「だから平気ですって」
木綿子はこの世の終わりみたいに、ひたすら写真写りを気にしている。
「瑞希ちゃんはともかく、私は今年で三十五歳なのよ! 小皺とくすみが気になるの! 最近のスマホは本当に高性能なんだから油断できないわ!」
「えー。全然、気にすることないと思いますけど」
「ダメ! やっぱり撮り直しましょう!」
登山道では頼もしい限りだったのに、写真ひとつでこうも大騒ぎするとは。
写真は誰にも見せないからと時間をかけて説得すると、木綿子は徐々に落ち着きを取り戻した。
我に返った木綿子はコホンとひとつ咳払いをする。
「さて。今から下山するわけだけど、登山は帰りの方が油断していて危ないから気をつけましょう」
木綿子が神妙な顔つきであればあるほど、笑いが込み上げてきて瑞希は変な気持ちになった。
結局、帰りは三分の二ほどの時間で無事に下山できた。
車の助手席に身体を埋めると、ホッと息を吐き出す。
「明日は怖いわよ。全身筋肉痛で疲労困憊だから」
運転席に座るの木綿子が、さも楽しげに瑞希をからかってくる。
「あはは、覚悟してます……」
登山に慣れている木綿子と違い、瑞希の足腰は貧弱そのもの。
明日のことを考えると恐ろしいけれど、今は達成感の方が大きい。
怪我なく登山を終えられたのは、木綿子のおかげだ。
(ん?)
帰路に着く道中、瑞希のスマホにあるメッセージが届く。
【魚谷さんの条件に合う人が見つかりました。ぜひご連絡を】
メッセージは例の婚活アドバイザーからだった。
瑞希は躊躇なくメッセージを削除した。
(正式な退会手続きは今度にしよう)
瑞希に足りなかったのは、人とは違う道を歩むという覚悟だ。
憑き物をおとされた今となっては、あれほど必死になっていたのが馬鹿みたいだ。
婚活はもうこりごり。
「木綿子さんの人生の最終目標ってなんですか?」
自分の一歩先を行く木綿子になんとなく尋ねた。
「んー? やりたいことをやり尽くして大往生で死ぬことかな?」
「あははっ」
予想の斜め上を行く回答に瑞希は思わず吹き出す。
Tシャツの上で猫とチンアナゴも笑った気がした。