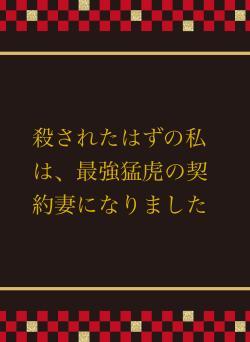現在、午後の十五時を回った。
四階の音楽室から、アルトサックスを練習する音が微かに聞こえてくる。グラウンドでは、サッカー部がランニングしながら声を掛け合っていた。
塁の三者面談の開始時刻まで、あと一時間という頃。
「塁くん! 顔が下向いてきたよ、まっすぐまっすぐ!」
(うるせぇぇぇぇ)
「口角も下がった! 上げて上げて!」
(うぜぇぇぇぇ)
イーゼルの向こう側からひょっこり顔を出した雪が、塁を何度も注意した。
横顔のモデルをしている最中の塁は、椅子に座り前方を見据えたまま動いてはいけない。同じ姿勢を続けている塁の表情が、苦痛により歪んできた。
「……顔に似合わず、遠慮ねぇな」
「そういう塁くんこそ、意外と忍耐弱いんだね」
雪のおとなしそうな顔立ちからは想像もできないスパルタ指導に、塁が愚痴をこぼす。そして雪も負けじと辛辣な言葉を放ち、にこりと微笑む。
悔しさと苛立ちから、塁のこめかみに血管が浮かび眉間には自然と縦線が刻まれた。
「ああ! も〜美しい横顔が台無しだよ〜」
美しさを保っていない塁の横顔に、雪の文句は止まらない。塁の心情や体の負担より、美しい横顔維持が最優先らしい。
それを知って、ついに鬱憤が溜まった塁は芸人ばりのツッコミをお見舞いする。
「誰のせいだよ!」
「あはは! 塁くんの顔鬼みたい、ウケる」
塁と対等に会話する雪が、面白おかしく笑い声を上げた。姿勢の維持に加えて雪との会話にも疲れてきた塁は、大きなため息しか出ない。
早く描き終われ。そして早く美術室を出たい。
塁が思っていたとき、不意に記憶を辿りながら雪が話しはじめた。
「……噂では知っていたよ。うちみたいな真面目な高校に“ヤンキーが入学してきた”ってね」
一年前の春、塁がこの学校の新一年生として入学してきた。当時高校二年生だった雪は、校内がざわついた様子を塁に教える。
入学したての一年生が髪を染めて登校していたら、それは目立つに決まっている。それでも好きなのだから仕方ないと割り切って、二年生の今までこのスタイルを貫いてきた塁。
そんな後輩のことを、雪は毛嫌いすることも責めることもなく。ただ笑顔で楽しそうに語る。
「美術室って二年の教室と同じ階にあるでしょ? だから昼休みや放課後に、塁くんの後ろ姿をよく見かけていたんだ」
画用紙の上で鉛筆を滑らせる雪が、懐かしむように囁く。先ほどのふざけた会話が嘘のように、穏やかな雰囲気が周囲に漂った。
塁の疲れがふっと消え去ってしまうほどの、ゆったりとした時間。
そう思っていたら――。
「もっと早くに塁くんの素晴らしい横顔に気づけていたら、クラスまでスカウトに行っていたのにな〜」
「絶対やめろ」
急に悔しそうに本音を漏らす雪に、塁は眉をひそめて心底嫌そうな顔をした。
まともに相手していても、やはり疲れるだけ。だからこちらも本音でぶつかっていこうと塁は決めた。
「……ほんと変わってんな、“雪先輩”は」
慣れない様子で、わざと強調するように“雪先輩”と初めて呼んでみた。
それが予想外すぎた雪は、虚をつかれたような顔をイーゼルからゆっくりと出す。
ちゃんと言いつけを守って横顔をキープしたままの塁の視線は、どこか寂しげに窓を向いていた。
「誰も俺と関わろうとしねーのに。あんただけだよ、こんなに絡んでくんの」
「そうなの? 塁くん、別に怖い人じゃないのにね?」
塁を“怖い人”だという人の気持ちが理解できない雪が、首を傾げて考えている。そんな雪にも素直に疑問を抱く塁が、あえて尋ねた。
「今日初めて会話したのに、なんでそんな断言できんの」
塁の異名を知っていたのなら、多少は怖いイメージを持っていたに違いない。そう思っている塁が、適当なことを言い続ける雪に冷たい視線を送った。
確かに見た目は怖いかもしれない。けれど雪には自分で導き出した答えがあった。
「だって、僕に横顔描かせてくれてるじゃん」
「っ……!」
「だから塁くんは、とても優しい人だよ」
その言葉を最後に、雪は再び視線を戻して塁の横顔を描くことに集中した。
しかし塁の胸中は今、とてつもない照れに支配され集中力が欠けている。それを雪に悟られるわけにはいかない塁は、歯を食いしばって耐え凌いだ。
そうして穏やかで静かな時間が流れる中、徐々に落ち着きを取り戻していく。
ひだまりの美術室に、鉛筆の芯が紙を擦る音だけが響き。それを心地良いと感じた塁は、胸がじんわりと温まっていくのを覚えた。
(鉛筆の音、嫌いだったのにな……)
幼少の頃から、教育熱心な母に付き合わされてきた。学習机に向かい何時間も勉強させられて、いつしかノートに書き込む鉛筆の音が嫌いになった。
塁に中学受験の道を用意した母は、成績にうるさく塾や家庭教師もつける。
ついに母から逃げ出したくなった塁は、受験日の会場に姿を現さなかった。
(あれからだ。あの人が俺に興味持たなくなったのは)
塁は結局、学区内の中学校、そして県立の高校へと進学した。
母の期待を裏切り呪縛から解放された結果、唯一の親である母に見放されている。あれほどうるさかった成績や勉強についても、今はもう知ろうともしない。
だから今日の三者面談、おそらく母は来ないと予想している。
「――塁くん?」
呼ばれてハッと意識を戻すと、デッサンしていたはずの雪が塁の隣に立っていた。
陽の光を背にして、椅子に腰掛ける塁を心配そうに見つめてくる。
「っ……なに」
「いや、なんか悲しそうな横顔に見えたから」
塁の心情を横顔から読み取った雪が、そう声をかけた。
自分がそんな顔をしていたなんて自覚がなかった塁は、もちろんすぐに否定する。
「なんでもねぇよ。それよりデッサンはもう終わったのか」
「うん。仕上げはまだだけど――」
「じゃあもう付き合う必要はねぇよな」
ガタッと椅子の音を鳴らして立ち上がった塁は、同じ姿勢で居続けていた体をほぐす。
腕を回し首を左右に倒していると、雪は冷静な声で一言。
「あと十秒で十六時になるよ」
「へぇ…………はあ⁉︎」
もうそんなに時間が経っていたのかと驚いた塁が、つい大声を上げてしまう。
それよりも、三者面談の開始時刻まで残り十秒というタイミングで、雪が冷静だったことにも腹が立った。
そうしている今も時間は経過する。時間を過ぎれば、柴にまた何を言われるかわからない。
塁は自分の鞄を乱暴に掴み、雪が描いた絵も確認しないまま美術室を飛び出していった。
「あらら」
廊下を走る足音が遠ざかっていく中、雪は他人事のような顔で塁の背中を見送った。そうして、ゆっくりとイーゼル前の椅子に腰掛ける。
そっと視線をあげて、手がけていた塁の横顔のデッサンを眺めていた。
まだ完成していないそれは、もう少し立体感を出すために描き込む作業を残す。ただ、塁と交わした契約を果たすため、雪は突如妙案を思いつき一人で感心する。
「僕、天才かも。そうと決まればここをこうして……」
何やら塁の横顔に追加で描きはじめた雪は、楽しそうに鉛筆を滑らせていく。
一体どんな絵が完成するのか。今ごろ三者面談中の塁には、想像するのも難しい。