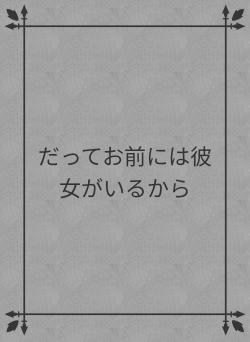「俺、お前のこと好きだ」
それは、この幼馴染がよく使う言葉だ。事あるごとに好きだという言葉を使い、僕も慣れたものだった。
しかし、この日。好きと口にした晴紅の目を見た瞬間。
僕は自分の中で何かが変わる気がした。あまりに優しそうに微笑む姿が、いつもの乱雑な様子と違って。
そこで唐突に分かった。晴紅は、僕のことが好きだと言っている。冗談めかしているけれど、きっと本気だ。本気で、僕のことを。
そう理解したとたん、ぐるぐるといろんな考えが押し寄せて、僕の思考を奪った。混乱して何も考えられなくなった僕は、晴紅と一緒に遊んでいたのにもかかわらず、家へと逃げた。
◆
柴崎晴紅という男は、昔から大人びていた。どこか一歩引いて物事を見ており、表情はあまり変わらなかった。
それでも、ずっと一緒にいるのだ。楽しそうだとか、嬉しそうだとか、顔を見ていたら僕には分かった。
晴紅のことを格好いいとか、クールなのが好きとかクラスの女子は言っていた。僕だけが、意外に負けず嫌いなこととか、意外と熱心になりやすいということを知っていた。
それを少しだけ誇らしくなることもあった。
晴紅とはずっと一緒にいれる。そういう確信があった。だからこそ、恋に憧れた僕は女の子に興味を持つこともあったし、男友達もいっぱい作った。
だって、晴紅は離れていかないから。僕の恥ずかしい話も情けない話も全部知っていて、それでもずっと隣にいてくれたから。
僕のことを晴紅が知っているのと同様、僕は晴紅のことなら何でも知っていると思っていた。それでも、僕に好きだと言った晴紅の顔を僕は知らない。見たことがない。
家に帰っても、晴紅の顔が脳裏から離れなかった。好きって何だろうか? 僕は晴紅のことをどう思っているんだろうか。
どくりと脈打つ心臓の音が答えだった。僕は晴紅のことが好きなんだ。
僕は、晴紅の顔を見るのが何となく気まずくて、心臓が変になるのが嫌でその後も逃げまくった。
晴紅のことは好きだ。それを今回の件で唐突に自覚した。それでも、これを伝えるのはいいことなのだろうか?
晴紅が僕のことを好きで、僕は晴紅のことが好きで、その後は? それがどうなる?
付き合うのか? それで付き合ったら、その後は?
通常の恋愛では結婚をするか別れるかのどちらかだ。それでは、僕と晴紅はどうなる?
男同士で結婚することはできない。それなら、別れる以外、ないのではないか?
急速に身体が冷えた。外の気温はさほど低くないはずなのに、身体の芯から冷気が襲ってきた。僕は、浅く息を吸った。
嫌だ。嫌だ。それだけは嫌。晴紅と二度と連絡が取らなくなるだなんて、耐えられない。
晴紅に決定的な言葉を言わせてはいけない。全てが、終わってしまう。だから晴紅を避けるのを止めなかった。
それなのに、晴紅は簡単に僕が引いた線を越えてくる。
「お前、なんで避けんだよ」
「お前に避けられんのが1番きつい」
向けられる言葉はどれも真剣で、僕の心に真っ直ぐ刺さった。それでも、僕は何も言えない。それにしても、晴紅はこんなに格好良かっただろうか? その嘘のない顔に、息が難しいほどに胸が締め付けられる。
だんだんと頬が熱くなっていく。それ以上この場にいると、自分が何を言うか分からなくて。
結局僕はまた逃げ出した。
◆
結局、次の日も晴紅に捕まり、本音をぶつけられたし、僕も本音を伝えることができた。
「お前のことが好きだ」
「……お前が俺と付き合いたくないのなら、それでも構わない。もう一度言う。俺は、お前の隣に居られれば名称なんてどうでもいい」
「うるせえ。俺の幸せをお前が決めるな」
晴紅の口から出る低い声は、あまりにも嘘がなくて。それでも僕の意思を尊重しようとしてくれて。晴紅は本気で。本気で僕のことが好きなのだ、と分かった。
結局のところ、晴紅の願いも僕のものと一緒だった。僕が勝手に怖がって逃げていただけだった。それが晴紅と話をすれば、その恐怖なくなった。晴紅はちゃんと話をきいたし、僕は自分の本音を伝えることができた。
晴紅となら、何かが変わったとしても、一緒にいられる。
その安心感から、変わることがあまり怖くなくなった。そうして、僕は晴紅と付き合うことになったのだ。
◆
付き合っても、何も変わらない。そう思っていたけれど。
「泉」
「何? 晴紅」
「俺、お前のこと好きだ」
「うん、僕も好きだよ」
そう答えたら、晴紅が満面の笑みを浮かべる。そんな晴紅に、心を掴まれたような感覚がした。
え? かわいい。笑顔がかわいい。これが僕の恋人? 本当に? かっこいいだけじゃなくてかわいいとか最強では?
「ねえ、晴紅」
「なんだ?」
未来なんて誰にも分からない。それでも、今この瞬間にこの目の前のいる男が愛おしい。その事実だけが、僕の心を穏やかにする。
「好きだよ」
「俺も好き」
何回目か分からない言葉を伝える。それでも晴紅は嫌そうな様子を少しも見せずに笑みを浮かべる。
この気持ちをなんて表したらいいんだろう。愛おしいという気持ちが心の中でぽんとはじけて、じっとしていられなくなる。思わず顔を覆った。
「泉、どうした?」
「このまま時間が止まればいいのに」
「俺は止まってほしくないな」
「そう?」
晴紅は柔らかい笑みを浮かべた。
「一緒に年をとっていく泉をみたいから」
「……おじいちゃんになっても?」
「ああ」
あまりにも晴紅が当たり前のようにそういうから、僕は口元を緩めた。晴紅は一緒に歩む未来を望んでいる。それを少し想像してみると、晴紅と一緒なら楽しいかもと思えた。
「いいね。それ」
「だろう?」
どうか死のその瞬間まで、一緒にいられますように。目の前で無邪気さを含んだ笑みを浮かべる晴紅を見ながら、祈りのような感情がわきあがった。
それは、この幼馴染がよく使う言葉だ。事あるごとに好きだという言葉を使い、僕も慣れたものだった。
しかし、この日。好きと口にした晴紅の目を見た瞬間。
僕は自分の中で何かが変わる気がした。あまりに優しそうに微笑む姿が、いつもの乱雑な様子と違って。
そこで唐突に分かった。晴紅は、僕のことが好きだと言っている。冗談めかしているけれど、きっと本気だ。本気で、僕のことを。
そう理解したとたん、ぐるぐるといろんな考えが押し寄せて、僕の思考を奪った。混乱して何も考えられなくなった僕は、晴紅と一緒に遊んでいたのにもかかわらず、家へと逃げた。
◆
柴崎晴紅という男は、昔から大人びていた。どこか一歩引いて物事を見ており、表情はあまり変わらなかった。
それでも、ずっと一緒にいるのだ。楽しそうだとか、嬉しそうだとか、顔を見ていたら僕には分かった。
晴紅のことを格好いいとか、クールなのが好きとかクラスの女子は言っていた。僕だけが、意外に負けず嫌いなこととか、意外と熱心になりやすいということを知っていた。
それを少しだけ誇らしくなることもあった。
晴紅とはずっと一緒にいれる。そういう確信があった。だからこそ、恋に憧れた僕は女の子に興味を持つこともあったし、男友達もいっぱい作った。
だって、晴紅は離れていかないから。僕の恥ずかしい話も情けない話も全部知っていて、それでもずっと隣にいてくれたから。
僕のことを晴紅が知っているのと同様、僕は晴紅のことなら何でも知っていると思っていた。それでも、僕に好きだと言った晴紅の顔を僕は知らない。見たことがない。
家に帰っても、晴紅の顔が脳裏から離れなかった。好きって何だろうか? 僕は晴紅のことをどう思っているんだろうか。
どくりと脈打つ心臓の音が答えだった。僕は晴紅のことが好きなんだ。
僕は、晴紅の顔を見るのが何となく気まずくて、心臓が変になるのが嫌でその後も逃げまくった。
晴紅のことは好きだ。それを今回の件で唐突に自覚した。それでも、これを伝えるのはいいことなのだろうか?
晴紅が僕のことを好きで、僕は晴紅のことが好きで、その後は? それがどうなる?
付き合うのか? それで付き合ったら、その後は?
通常の恋愛では結婚をするか別れるかのどちらかだ。それでは、僕と晴紅はどうなる?
男同士で結婚することはできない。それなら、別れる以外、ないのではないか?
急速に身体が冷えた。外の気温はさほど低くないはずなのに、身体の芯から冷気が襲ってきた。僕は、浅く息を吸った。
嫌だ。嫌だ。それだけは嫌。晴紅と二度と連絡が取らなくなるだなんて、耐えられない。
晴紅に決定的な言葉を言わせてはいけない。全てが、終わってしまう。だから晴紅を避けるのを止めなかった。
それなのに、晴紅は簡単に僕が引いた線を越えてくる。
「お前、なんで避けんだよ」
「お前に避けられんのが1番きつい」
向けられる言葉はどれも真剣で、僕の心に真っ直ぐ刺さった。それでも、僕は何も言えない。それにしても、晴紅はこんなに格好良かっただろうか? その嘘のない顔に、息が難しいほどに胸が締め付けられる。
だんだんと頬が熱くなっていく。それ以上この場にいると、自分が何を言うか分からなくて。
結局僕はまた逃げ出した。
◆
結局、次の日も晴紅に捕まり、本音をぶつけられたし、僕も本音を伝えることができた。
「お前のことが好きだ」
「……お前が俺と付き合いたくないのなら、それでも構わない。もう一度言う。俺は、お前の隣に居られれば名称なんてどうでもいい」
「うるせえ。俺の幸せをお前が決めるな」
晴紅の口から出る低い声は、あまりにも嘘がなくて。それでも僕の意思を尊重しようとしてくれて。晴紅は本気で。本気で僕のことが好きなのだ、と分かった。
結局のところ、晴紅の願いも僕のものと一緒だった。僕が勝手に怖がって逃げていただけだった。それが晴紅と話をすれば、その恐怖なくなった。晴紅はちゃんと話をきいたし、僕は自分の本音を伝えることができた。
晴紅となら、何かが変わったとしても、一緒にいられる。
その安心感から、変わることがあまり怖くなくなった。そうして、僕は晴紅と付き合うことになったのだ。
◆
付き合っても、何も変わらない。そう思っていたけれど。
「泉」
「何? 晴紅」
「俺、お前のこと好きだ」
「うん、僕も好きだよ」
そう答えたら、晴紅が満面の笑みを浮かべる。そんな晴紅に、心を掴まれたような感覚がした。
え? かわいい。笑顔がかわいい。これが僕の恋人? 本当に? かっこいいだけじゃなくてかわいいとか最強では?
「ねえ、晴紅」
「なんだ?」
未来なんて誰にも分からない。それでも、今この瞬間にこの目の前のいる男が愛おしい。その事実だけが、僕の心を穏やかにする。
「好きだよ」
「俺も好き」
何回目か分からない言葉を伝える。それでも晴紅は嫌そうな様子を少しも見せずに笑みを浮かべる。
この気持ちをなんて表したらいいんだろう。愛おしいという気持ちが心の中でぽんとはじけて、じっとしていられなくなる。思わず顔を覆った。
「泉、どうした?」
「このまま時間が止まればいいのに」
「俺は止まってほしくないな」
「そう?」
晴紅は柔らかい笑みを浮かべた。
「一緒に年をとっていく泉をみたいから」
「……おじいちゃんになっても?」
「ああ」
あまりにも晴紅が当たり前のようにそういうから、僕は口元を緩めた。晴紅は一緒に歩む未来を望んでいる。それを少し想像してみると、晴紅と一緒なら楽しいかもと思えた。
「いいね。それ」
「だろう?」
どうか死のその瞬間まで、一緒にいられますように。目の前で無邪気さを含んだ笑みを浮かべる晴紅を見ながら、祈りのような感情がわきあがった。