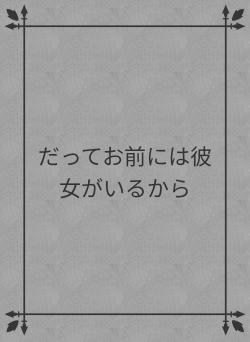その次の日。俺は泉の家の前で待ち伏せをした。ここなら、確実に逃げられないことを知っているから。
スマートフォンを見ながら、壁にもたれて待っていると、帰ってきた泉が、俺を見て立ち止まった。
「泉」
「……なに?」
「話がある」
「でも……」
「時間がないわけないよな?」
泉は俺と同じで部活に入っていない。テストが近いわけでもない。今は時間があるはずだ。
「……」
「俺の部屋へ行くぞ」
有無を言わせないように、できるだけ低い声を出す。泉は俺の方を一瞬見たが、目を伏せて頷いた。
俺の部屋に入って、すぐに俺は口火を切る。
「なあ、泉」
「……なに?」
「俺はもう冗談にしない」
「……」
俺は気持ちを言葉に忍ばせて伝えることで、満足していたけれど、その気持ちを伝えられた方はたまったもんじゃないだろう。人の感情なんて、重いだけだ。
だから、もう誤魔化さない。はっきり伝える。泉に引導を渡そう。
「お前のことが好きだ」
泉は俺を数秒間凝視した。目を伏せると、少し考えた後で口を開く。
「いつから?」
「さあ」
「さあって……」
俺の答えに泉は呆れた声を出す。俺は肩をすくめた。
「今好きだという事実以外に、何がいるんだ? お前のことが好き、それだけだ」
そう言い切ると、泉はぽかんとした顔でこちらを見た。そして、表情を緩めると静かに笑う。
「確かに。晴紅の言う通りだ。いつからとかは関係ないか」
「そうだろう?」
だから、どうか本音がほしい。嘘偽りのない、泉の気持ちが。
「なあ、お前は何が嫌で逃げるんだ?」
「別に……」
「逃げていない、なんていう嘘は通じない」
何年一緒にいると思っている? 正確な年月も分からないくらいだ。泉がいくら忙しくなったからって、俺に何も言わないような人間じゃないってわかっている。
「俺のせいなら、何でも言ってくれ。お前が嫌なことは全部直すし、俺が変わる必要があるのなら全部変える」
「……違う」
「え?」
泉の掠れた声に、思わず聞き返した。泉が真っ直ぐにこちらを見つめる。その瞳に焼かれそうなほどの強い感情が押し寄せてくる気がして、思わず息を呑んだ。
「変わったら、困るんだ」
「何を言って」
「僕たちの関係が、壊れるのが怖い」
俺の言葉を遮るように、泉ははっきりと言い切る。泉の表情は憂いを帯びていて、その表情はいつもより大人びていた。
「仮に付き合って、そしたらその後は? 男同士で結婚はできない。そしたら、別れしかないんじゃない?」
付き合う。結婚。その言葉をきいて、だんだん頬が熱くなってきた。右手で顔を覆う。
「え、晴紅。何その反応?」
「だって、お前が俺との未来を想定してくれたんだろう?」
それは俺が欲して止まなかったものだ。それを泉も想像したとなると、顔がにやけそうになる。
「もう、晴紅。真面目に話をしているのに」
「俺だって真面目だが」
「そんな緩んだ顔で言われても説得力ないよ」
そんなに緩んでいるんだろうか。ジトッとした目で睨んでくる泉を見ながら、両頬をぐるっと動かした。
頬から手を外し、言葉を探していると、泉が弱々しい笑みを浮かべた。
「……僕は晴紅とずっと仲良くしていたいよ。仮に付き合って別れたら、もう馬鹿みたいに笑いあえなくなるかもしれないよね?」
それは真実なのだろう。全く以て泉の言う通り。それでも、俺は驚きでいっぱいだった。まさか、泉がそんなことを考えているとは想定外だった。
「お前の言いたいことは分かった」
正直、付き合うだの何だのそれができる未来をあまり考えたことがなかった。泉の言わんとすることは分かる。それでも。
「俺にとって、お前と付き合うことは目標じゃない。ただ、お前の隣にいたいだけだ。高校を卒業して大学生になっても。社会人になっても。年をとっても。そして死の直前にお前の顔が見たい。ただ、それだけなんだ。その名前なんてどうだっていい」
それが俺の望みだ。実現することができたらどんなに幸せだろうか。死の直前まで一緒にいる。それが俺にとっての最高の死の迎え方だ。
「……お前が俺と付き合いたくないのなら、それでも構わない。もう一度言う。俺は、お前の隣に居られれば名称なんてどうでもいい」
それは勿論、恋人という名称の方が、曖昧ではなく、分かりやすいだろう。それに憧れないと言えば嘘になる。それでも泉がそうなるのが怖い、と思うのなら。俺たちの関係に名前がなくてもいい。幼馴染と言い続けても構わない。
「好きだ、とは言ったけど、付き合おうとは言っていないだろう?」
「確かにそうだけど……。じゃあ、晴紅は俺と付き合う気はないの?」
「そりゃあ、できるのなら付き合いたい」
『恋人』というものに、漠然とした憧れはある。俺が永遠に手にすることはない、と諦めていたものだから。俺の憧れを押しつける気なんてない。
「俺たち2人の話だ。お前が嫌がることはしない」
「……」
黙り込んだ泉に向かって、俺は言葉を重ねる。
「俺はお前に嫌われるのが怖いし、拒絶されるのが怖い。お前と、二度と話せないのも怖い」
「それは僕だって同じだよ。でも……」
何かを言いかけた泉は、言葉を探しているのだろう。俺は黙って、泉を待つ。
「それでも、僕は晴紅にはみんなから祝われるような形で幸せになってほしい」
「みんなに?」
「お前は、女子から人気あるじゃないか。僕だって、知っているんだ。お前が女子に何度も呼びだされていることを」
それは確かに、何度か呼び出され、告白のようなものをされたことはある。
泉が息を深く吸った。彼は今、どこを見ているのだろうか。
「結婚して、家族を持って。そんな形の方が、目に見えて分かりやすい『幸せな光景』じゃないか?」
幸せな光景? 泉が口にするその光景に苛立って、一周回って笑いそうになる。
「うるせえ。俺の幸せをお前が決めるな」
俺は両手で泉の両頬を掴んだ。しっかりと目を合わせる。泉の丸くなった瞳が俺を凝視する。俺もその目をしっかりと見つめ返した。
「俺を見ろ。お前に惚れ込んでいる目の前の男を見ろ。不幸に見えるか? お前といる俺が不幸に見えていたのか?」
俺は、泉が好きだ。泉と一緒にいるのが他の何よりも楽しい。それが泉に伝わっていないとは言わせない。
泉が一番俺のことを理解しているのだ。
「……見えない」
しっかりと返事をした泉の頬から手を放す。
「そうだろう? 俺はお前がいるだけで幸せだ。今までお前を好きになったことを後悔したことはない」
それは俺の中で、はっきりとしている。泉と会えたことが、一緒に過ごせたことが大事な大事な思い出で、宝物だ。
泉が息を呑んだ。そして緊張が解けたように、彼の表情は柔らかくなる。
「……晴紅、かっこいいなあ」
「俺は必死なだけだ」
好きな人の前では、格好をつけたいという気持ちはもちろんある。それでも今口にしたことは紛れもない本音だ。
本気で伝えたら「今までどおり」でなくなってしまうと思って押し込んでいたが、伝えないほうが変わらない日々が消えてしまいそうだったから。
自分の中にとどめて置くはずだった感情を言葉にするのは簡単ではなかったため、必死だった。
泉が眉を下げて俺の方を見る。
「僕、たくさん逃げて、晴紅のこと傷つけたよね? ごめん」
「お前になら、傷つけられてもいい」
「僕が傷つけたくないんだけど」
「それでも、近くにいればいるほど、互いを傷つけてしまうこともあるだろう。俺だって今まで傷つけたことはあるだろうし。だから、おあいこだ」
「……確かに、僕も晴紅になら傷つけられてもいいのかもしれない。それを修復できる関係でありたい」
泉の方を見て、笑う。そんな俺をみて、泉も笑みを浮かべた。
「僕だって晴紅のことが大切なんだ」
「……ああ」
知っている。少なくとも、泉の中で俺という存在が強くあることは知っている。そして、先ほどまでの会話の内容から、俺の想像以上に俺のことを考えてくれていたのも分かった。
「晴紅。僕は晴紅が好きだよ」
「うん」
「好き」
「うん。俺も好き。好きだ」
好きという言葉を口にするだけで、ふわふわとした感覚が広がる。好きという気持ちをきくだけで、脳が麻痺するようなぼんやりとした心地に包まれた。
一生この時間が続けばいいのに。
「泉」
「うん」
「俺はこの時間が永遠だといいと思う」
「うん。僕も」
好き、という気持ちが互いにあるのは分かった。それでこれからどうするか。
「今後の約束という意味では付き合いたい。それでも、お前が嫌ならそれ以上は望まない。お前に好きと言ってもらえた。それだけで生きていける」
「嫌だよ。僕だって晴紅と一緒に生きていきたいんだから」
俺は思わず言葉を詰まらせた。それは嬉しい。一緒に、生きたい。
泉が口元を緩める。
「……なんか、いろいろ1人で考えていたのが馬鹿らしくなってきた」
泉が深く深呼吸をした。俺の方を見る。その視線の柔らかさに心を掴まれたような気分だった。
「晴紅。僕も君が好きだよ。だから、付き合おう」
「……いいんだな?」
泉の声が、心地良く耳に響く。それに意識を取られそうになって、泉の言葉を飲み込むのが遅れた。彼の言葉を理解してから、反射的に聞き返す。
泉ははっきりと頷いた。
「うん。だって、晴紅は僕のことを尊重してくれるでしょう? だから、また何か不安も不満も他のこともあれば言うよ。晴紅も言ってね。そうやって、2人で考えていきたい」
「そうだな。そうしていきたい」
泉となら、それができるだろう。今日みたいにまた話し合って、お互いに納得する形を考えていきたい。泉のことなら、どれだけでも時間をかけても嫌だと感じない。
「これからは恋人としてよろしく、泉」
「こちらこそ、よろしく。晴紅」
幼なじみから恋人へと名前は変化した俺たちだが、一緒にいるという事実はきっと変わらない。俺たちの関係が今後の約束をできるものになった。好きという感情を隠さなくてよくなった。それが嬉しい。
スマートフォンを見ながら、壁にもたれて待っていると、帰ってきた泉が、俺を見て立ち止まった。
「泉」
「……なに?」
「話がある」
「でも……」
「時間がないわけないよな?」
泉は俺と同じで部活に入っていない。テストが近いわけでもない。今は時間があるはずだ。
「……」
「俺の部屋へ行くぞ」
有無を言わせないように、できるだけ低い声を出す。泉は俺の方を一瞬見たが、目を伏せて頷いた。
俺の部屋に入って、すぐに俺は口火を切る。
「なあ、泉」
「……なに?」
「俺はもう冗談にしない」
「……」
俺は気持ちを言葉に忍ばせて伝えることで、満足していたけれど、その気持ちを伝えられた方はたまったもんじゃないだろう。人の感情なんて、重いだけだ。
だから、もう誤魔化さない。はっきり伝える。泉に引導を渡そう。
「お前のことが好きだ」
泉は俺を数秒間凝視した。目を伏せると、少し考えた後で口を開く。
「いつから?」
「さあ」
「さあって……」
俺の答えに泉は呆れた声を出す。俺は肩をすくめた。
「今好きだという事実以外に、何がいるんだ? お前のことが好き、それだけだ」
そう言い切ると、泉はぽかんとした顔でこちらを見た。そして、表情を緩めると静かに笑う。
「確かに。晴紅の言う通りだ。いつからとかは関係ないか」
「そうだろう?」
だから、どうか本音がほしい。嘘偽りのない、泉の気持ちが。
「なあ、お前は何が嫌で逃げるんだ?」
「別に……」
「逃げていない、なんていう嘘は通じない」
何年一緒にいると思っている? 正確な年月も分からないくらいだ。泉がいくら忙しくなったからって、俺に何も言わないような人間じゃないってわかっている。
「俺のせいなら、何でも言ってくれ。お前が嫌なことは全部直すし、俺が変わる必要があるのなら全部変える」
「……違う」
「え?」
泉の掠れた声に、思わず聞き返した。泉が真っ直ぐにこちらを見つめる。その瞳に焼かれそうなほどの強い感情が押し寄せてくる気がして、思わず息を呑んだ。
「変わったら、困るんだ」
「何を言って」
「僕たちの関係が、壊れるのが怖い」
俺の言葉を遮るように、泉ははっきりと言い切る。泉の表情は憂いを帯びていて、その表情はいつもより大人びていた。
「仮に付き合って、そしたらその後は? 男同士で結婚はできない。そしたら、別れしかないんじゃない?」
付き合う。結婚。その言葉をきいて、だんだん頬が熱くなってきた。右手で顔を覆う。
「え、晴紅。何その反応?」
「だって、お前が俺との未来を想定してくれたんだろう?」
それは俺が欲して止まなかったものだ。それを泉も想像したとなると、顔がにやけそうになる。
「もう、晴紅。真面目に話をしているのに」
「俺だって真面目だが」
「そんな緩んだ顔で言われても説得力ないよ」
そんなに緩んでいるんだろうか。ジトッとした目で睨んでくる泉を見ながら、両頬をぐるっと動かした。
頬から手を外し、言葉を探していると、泉が弱々しい笑みを浮かべた。
「……僕は晴紅とずっと仲良くしていたいよ。仮に付き合って別れたら、もう馬鹿みたいに笑いあえなくなるかもしれないよね?」
それは真実なのだろう。全く以て泉の言う通り。それでも、俺は驚きでいっぱいだった。まさか、泉がそんなことを考えているとは想定外だった。
「お前の言いたいことは分かった」
正直、付き合うだの何だのそれができる未来をあまり考えたことがなかった。泉の言わんとすることは分かる。それでも。
「俺にとって、お前と付き合うことは目標じゃない。ただ、お前の隣にいたいだけだ。高校を卒業して大学生になっても。社会人になっても。年をとっても。そして死の直前にお前の顔が見たい。ただ、それだけなんだ。その名前なんてどうだっていい」
それが俺の望みだ。実現することができたらどんなに幸せだろうか。死の直前まで一緒にいる。それが俺にとっての最高の死の迎え方だ。
「……お前が俺と付き合いたくないのなら、それでも構わない。もう一度言う。俺は、お前の隣に居られれば名称なんてどうでもいい」
それは勿論、恋人という名称の方が、曖昧ではなく、分かりやすいだろう。それに憧れないと言えば嘘になる。それでも泉がそうなるのが怖い、と思うのなら。俺たちの関係に名前がなくてもいい。幼馴染と言い続けても構わない。
「好きだ、とは言ったけど、付き合おうとは言っていないだろう?」
「確かにそうだけど……。じゃあ、晴紅は俺と付き合う気はないの?」
「そりゃあ、できるのなら付き合いたい」
『恋人』というものに、漠然とした憧れはある。俺が永遠に手にすることはない、と諦めていたものだから。俺の憧れを押しつける気なんてない。
「俺たち2人の話だ。お前が嫌がることはしない」
「……」
黙り込んだ泉に向かって、俺は言葉を重ねる。
「俺はお前に嫌われるのが怖いし、拒絶されるのが怖い。お前と、二度と話せないのも怖い」
「それは僕だって同じだよ。でも……」
何かを言いかけた泉は、言葉を探しているのだろう。俺は黙って、泉を待つ。
「それでも、僕は晴紅にはみんなから祝われるような形で幸せになってほしい」
「みんなに?」
「お前は、女子から人気あるじゃないか。僕だって、知っているんだ。お前が女子に何度も呼びだされていることを」
それは確かに、何度か呼び出され、告白のようなものをされたことはある。
泉が息を深く吸った。彼は今、どこを見ているのだろうか。
「結婚して、家族を持って。そんな形の方が、目に見えて分かりやすい『幸せな光景』じゃないか?」
幸せな光景? 泉が口にするその光景に苛立って、一周回って笑いそうになる。
「うるせえ。俺の幸せをお前が決めるな」
俺は両手で泉の両頬を掴んだ。しっかりと目を合わせる。泉の丸くなった瞳が俺を凝視する。俺もその目をしっかりと見つめ返した。
「俺を見ろ。お前に惚れ込んでいる目の前の男を見ろ。不幸に見えるか? お前といる俺が不幸に見えていたのか?」
俺は、泉が好きだ。泉と一緒にいるのが他の何よりも楽しい。それが泉に伝わっていないとは言わせない。
泉が一番俺のことを理解しているのだ。
「……見えない」
しっかりと返事をした泉の頬から手を放す。
「そうだろう? 俺はお前がいるだけで幸せだ。今までお前を好きになったことを後悔したことはない」
それは俺の中で、はっきりとしている。泉と会えたことが、一緒に過ごせたことが大事な大事な思い出で、宝物だ。
泉が息を呑んだ。そして緊張が解けたように、彼の表情は柔らかくなる。
「……晴紅、かっこいいなあ」
「俺は必死なだけだ」
好きな人の前では、格好をつけたいという気持ちはもちろんある。それでも今口にしたことは紛れもない本音だ。
本気で伝えたら「今までどおり」でなくなってしまうと思って押し込んでいたが、伝えないほうが変わらない日々が消えてしまいそうだったから。
自分の中にとどめて置くはずだった感情を言葉にするのは簡単ではなかったため、必死だった。
泉が眉を下げて俺の方を見る。
「僕、たくさん逃げて、晴紅のこと傷つけたよね? ごめん」
「お前になら、傷つけられてもいい」
「僕が傷つけたくないんだけど」
「それでも、近くにいればいるほど、互いを傷つけてしまうこともあるだろう。俺だって今まで傷つけたことはあるだろうし。だから、おあいこだ」
「……確かに、僕も晴紅になら傷つけられてもいいのかもしれない。それを修復できる関係でありたい」
泉の方を見て、笑う。そんな俺をみて、泉も笑みを浮かべた。
「僕だって晴紅のことが大切なんだ」
「……ああ」
知っている。少なくとも、泉の中で俺という存在が強くあることは知っている。そして、先ほどまでの会話の内容から、俺の想像以上に俺のことを考えてくれていたのも分かった。
「晴紅。僕は晴紅が好きだよ」
「うん」
「好き」
「うん。俺も好き。好きだ」
好きという言葉を口にするだけで、ふわふわとした感覚が広がる。好きという気持ちをきくだけで、脳が麻痺するようなぼんやりとした心地に包まれた。
一生この時間が続けばいいのに。
「泉」
「うん」
「俺はこの時間が永遠だといいと思う」
「うん。僕も」
好き、という気持ちが互いにあるのは分かった。それでこれからどうするか。
「今後の約束という意味では付き合いたい。それでも、お前が嫌ならそれ以上は望まない。お前に好きと言ってもらえた。それだけで生きていける」
「嫌だよ。僕だって晴紅と一緒に生きていきたいんだから」
俺は思わず言葉を詰まらせた。それは嬉しい。一緒に、生きたい。
泉が口元を緩める。
「……なんか、いろいろ1人で考えていたのが馬鹿らしくなってきた」
泉が深く深呼吸をした。俺の方を見る。その視線の柔らかさに心を掴まれたような気分だった。
「晴紅。僕も君が好きだよ。だから、付き合おう」
「……いいんだな?」
泉の声が、心地良く耳に響く。それに意識を取られそうになって、泉の言葉を飲み込むのが遅れた。彼の言葉を理解してから、反射的に聞き返す。
泉ははっきりと頷いた。
「うん。だって、晴紅は僕のことを尊重してくれるでしょう? だから、また何か不安も不満も他のこともあれば言うよ。晴紅も言ってね。そうやって、2人で考えていきたい」
「そうだな。そうしていきたい」
泉となら、それができるだろう。今日みたいにまた話し合って、お互いに納得する形を考えていきたい。泉のことなら、どれだけでも時間をかけても嫌だと感じない。
「これからは恋人としてよろしく、泉」
「こちらこそ、よろしく。晴紅」
幼なじみから恋人へと名前は変化した俺たちだが、一緒にいるという事実はきっと変わらない。俺たちの関係が今後の約束をできるものになった。好きという感情を隠さなくてよくなった。それが嬉しい。