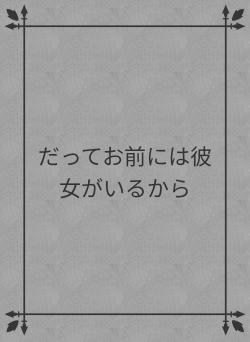「俺、やっぱお前のこと好きだ」
「うん、僕も好きだよ」
にこにこと笑うこいつを見て、俺は内心やれたれとため息をついた。やっぱりこいつは気がつかない。俺の愛に塗れた告白をきいても、響かない。こいつにとって、俺は恋愛の対象ではないのだろう。告白するとは露程にも思っていないのだろう。
――そう思っていたのに。
「ご、ごめん。最近はちょっと忙しくて」
こいつはなんでこんなによそよそしいんだ? まるで。まるで。
俺のことを意識しているかのような態度だ。
◆
終礼が終わった途端、隣のクラスの幼なじみの泉が教室の中を覗き込んだ。俺が声をかけるよりも先に、泉が俺に向かって叫ぶ。
「なあ、晴紅(はく)。今日も昨日と一緒のゲームしようぜ」
「おお」
俺はすぐに鞄の中に荷物を突っ込み、肩にかけた。ドアから教室を覗きながらにこにこと笑う泉のもとへと向かう。
「お前の教室、いつも終礼短いよな」
「本当にそう。2-Bが高2の中でも1番長い。僕、いつも晴紅のこと待ってんだけど」
「別に先帰っててもいいけど」
「なんだよー、一緒の方が楽しいじゃん」
こいつはさらっとこういうことを言う。思わず黙り込んだ俺をみて、泉は楽しげに笑った。
「ねえ、晴紅。照れてる?」
「うるせえ」
からかい混じりの声で言う泉に、俺は表情を変えないようにしながら返す。
照れているか? そんなの当たり前だろう。こっちはバクバクうるさい心臓の音を聞かれないように必死だというのに。
俺はこの幼なじみ、和田泉のことが好きだ。ずっと昔から。
◆
俺は出会った年齢さえ覚えていない。隣の家に住んでいて、物心つく頃には一緒に遊んでいた。それくらい長い仲だ。
和田泉は明るい人気者だ。部活に入っていないはずなのに友達が多く、どうやって仲良くなったかは分からないが、先輩にも親しい人がいるらしい。
昔からそうだった。上手く周囲になじめない俺の手を引いて、輪の中心になっていく。きらきらとした笑顔でみんなをまとめ、気がつけば周囲の人間は和田泉という人間を中心に動くようになっている。
だから泉は多くの人に慕われ、友達が多かった。それでも、俺を蔑ろにすることはなかった。俺の隣からいなくなることはなかった。気がつけば戻ってきていた。
隣にいるのが当たり前で。ずっとそんな日々が続くと思っていた。こいつが中学生のときに好きな人ができたと言い出すまでは。
「僕、同じクラスの三島さんが好きなんだよね」
「へえ」
何でもないように答えたけれど、ずきりと痛む胸に自分で驚いた。もやもやと嫌な心地がして、無性に腹が立った。それを表に出さないように必死だったけれど、こいつは何にも気がつく様子はなかった。
「だからさ、放課後に機会を見計らって三島さんと話をしてみようと思うんだ。だからしばらくは晴紅と帰れない」
「好きにしろよ」
「えー。晴紅は寂しくないの?」
寂しいと喚けば、行かないのか。今まで通り一緒に帰って遊びたいと言い募れば、こいつはどこにも行かないのだろうか。
そんなことはないだろう。きっと、今回は上手くいかなかったとしても、泉はいつか俺の側からいなくなる。
永遠なんて、どこにもないのだ。それをまざまざと見せつけられた。
俺は全部の感情を隠して笑った。
「今、お前と一緒にいるのは俺だからいい」
真っ赤な嘘だ。嫌だ、俺だけを見ろと喚きたかった。彼女なんて作るな、俺がいればいいだろうと言ってしまいそうになった。
それでも、泉の前では格好つけたかった。そこで唐突に理解した。
俺は、泉のことが好きなんだ。
俺が恋を自覚をしたのはこのときであるが、きっと自覚する前から好きだったのだろう。いつからか好きだったかは自分でも分からない。それくらい俺の人生の中で、泉と一緒にいることは当たり前であり、好きという言葉では表現できないくらいの気持ちを抱えている。
この恋が多数の人間と違うことはだんだん分かってきた。それでもよかった。だって、これが「恋」であることが悟られなければ問題がないのだ。ただの仲の良い幼馴染。それでいいじゃないか。何度もそう言い聞かせた。
ちなみに、泉は三島さんと付き合うことはなかったと思う。少なくとも俺は聞いていない。俺と泉の仲が疎遠になることはなく、同じように過ごしていた。
それでも俺の中では何かが変わってしまった。
好きなのだ。その気持ちは押し込めるのが難しい。泉と話をしていると、不意に喉が締め付けられるような感覚が沸き起こる。最初は見ないフリをしていた。それでも、呼吸の苦しさを放っておくこともできなくなった。
だから、ちょっとだけ。好きという言葉を、重さを取っ払って伝えることにした。それでも、好きだと伝える恥ずかしさと、身勝手な恋心を持ったという申し訳なさから、泉の目を見ながら言うことはできなかったけれど。
「お前といるのが一番気を遣わなくて済むから好きだ」
「まじ? 珍しいな、お前がそんなことを言うのは」
最初は驚かれたけれど、二人だけの場で似たような言葉を繰り返すうちに、泉は特に気にしなくなってきた。
「俺、泉のことが好きだ」
「うん。僕も晴紅のこと好きだよ」
それくらいの言葉を言い合うくらいには慣れた。もちろん、泉のいう「好き」は幼なじみとしての物であり、俺への恋愛感情はないということを知っている。
◆
最近は、一緒に進めているゲームがある。2人で協力してゴールするものであり、1人ではできないものだ。今日もそれをやるために、泉は家へと来ていた。
「晴紅、これあげる。好きだったよね?」
ゲームの準備をしていると、泉が何かを取り出した。それは俺の好きな種類のクッキーだった。クッキーの中にチョコレートが入っているお菓子だ。
このお菓子を見かけたら、泉は俺のことを思い出す。それくらい、泉の生活の中に俺がいて。反対に、俺の生活の中にも泉がいる。心の中にぶわりと嬉しさが広がった。胸が苦しくなるほどの衝動に浅く息を吸った。
「泉のことが好きだ」
いつもと違い、泉の目を見ながら言った。泉が何度か瞬きをして俺を見つめる。
「……ありがとう」
あれ、いつもと反応が違うような……。きっと気のせいだろう。今まで何回好きだと言ってきたのか。好きだと言ったくらいで何かが変わるような関係じゃない。
「ごめん。用事思い出したから帰るね」
「おお。また明日な」
「……うん」
泉が急に立ち上がって自分の家へと帰っていく。忘れていた宿題でも思い出したのだろうか。まあゲームの続きは明日にだってできる。
俺はそう思っていたが。
次の日から、泉はぱたりと来なくなった。
◆
「泉、今日は家に……」
「ごめん、忙しくて」
「泉、今日の帰りは……」
「ごめん、一緒に帰れない」
泉の教室に行くも、すぐに逃げられてしまう。1日、2日のことならそういう日もあるが、で話は済むが、今日で1週間だ。流石に俺だって気がつく。
どうしたんだろうか。最後に泉が家に来た日を考える。何か変わったことはあっただろうか。いつも通りゲームをして、泉が用事を思い出したとか言って帰った。それだけだったはずだ。
うん。いつも通りだな。何も変わったことはない。
俺がゲーム下手すぎて嫌になった? それとも、俺と遊ぶのに飽きた?
そんな可能性は浮かんだものの、あまりしっくりこない。昔からずっと一緒に遊んでいたから、俺の不器用さは知っているはずだし、遊ぶのに飽きたとしたらここまで露骨に避けないだろう。
やっぱり変わったことはない気がする。
あ、好きだとは言ったかもしれないけど、それは別にいつものことだし……。関係がなさそうだ。
そこで、唐突に1つ思い当たることがあった。
泉は、好きな人ができたんじゃないか。だから、忙しくなったんじゃないか。
なんだ。きっとそうだ。泉も言ってくれればいいのに。少し悲しいけれど、直接恋愛相談をされるのも苦しいから、良かったのかもしれない。
身体が一気に重くなったような感覚は、きっと勘違いだ。
◆
もう1週間経っても、泉との関係は元に戻らなかった。流石に俺のことを避けすぎだ。俺は放課後に泉のことを捕まえた。終礼は泉のクラスの方が終わるのは早い。それなら、泉が掃除当番の日に待ち伏せをすればいいのだ。
泉のクラスの掃除当番の周期は把握している。待ち伏せなんて余裕だ。
「おい、泉」
「なに? 晴紅」
「お前、なんで俺を避けんだよ」
「避けてなんて……」
泉は否定をしようとしているけれど、全然目があわない。ぐっと胸を抉られたかのような感覚で、絞り出すように声を出す。
「俺が何かしたなら言ってくれ。なんでも、直すから」
「晴紅は悪くないよ」
「じゃあ、なんで?」
「……」
「俺はお前に避けられんのが1番きつい」
下を向いた泉に顔を近づける。ちらりとこちらを見た泉とぱちりと目があった。
徐々に顔が朱に染まっていくのをみて、俺は時間が止まったような気がした。
なぜ、こいつはこんな顔をする? まるで。まるで。
俺のことが好きみたいじゃないか。
「いず」
「ごめん」
俺が名前を呼び切る前にぱっと泉は逃げ出した。
泉が出ていった扉を呆然と眺める。今、何が起こった?
「え、まじで?」
口元をおさえる。じわじわと頬の体温が上昇して、熱い。全身の力が抜けて思わずしゃがみ込む。
俺はこの恋が叶うことを願ったことはなかったし、想定したこともなかった。
それが覆るかもしれない。その事実を俺はどう受け止めたらいいのだろう。
そこまで考えて冷静になる。それでも、泉がこの調子で逃げ続けたら? 俺と泉の間にできた溝は一生このままか?
俺は好きだと伝えることが目的だったのではない。ただ、ずっと一緒にいたくて、それに名称をつけるとしたら「好き」というだけだ。
はっきり言おう。俺は今のこの状況が1番気に入らない。
泉と遊べない。話せない。今までは共有していた景色も、楽しいことも、嫌なことも共有できない。それが1番気に入らない。
もし、隣に立つことが当たり前じゃなくなるのが、俺の気持ちのせいだとしたら。この気持ちは心の奥底にしまい込もう。
それが俺にとっての愛だから。美しい物も、おいしい物も、楽しい物も全部、泉に渡したい。
だからこそ、このままではいられない。
「うん、僕も好きだよ」
にこにこと笑うこいつを見て、俺は内心やれたれとため息をついた。やっぱりこいつは気がつかない。俺の愛に塗れた告白をきいても、響かない。こいつにとって、俺は恋愛の対象ではないのだろう。告白するとは露程にも思っていないのだろう。
――そう思っていたのに。
「ご、ごめん。最近はちょっと忙しくて」
こいつはなんでこんなによそよそしいんだ? まるで。まるで。
俺のことを意識しているかのような態度だ。
◆
終礼が終わった途端、隣のクラスの幼なじみの泉が教室の中を覗き込んだ。俺が声をかけるよりも先に、泉が俺に向かって叫ぶ。
「なあ、晴紅(はく)。今日も昨日と一緒のゲームしようぜ」
「おお」
俺はすぐに鞄の中に荷物を突っ込み、肩にかけた。ドアから教室を覗きながらにこにこと笑う泉のもとへと向かう。
「お前の教室、いつも終礼短いよな」
「本当にそう。2-Bが高2の中でも1番長い。僕、いつも晴紅のこと待ってんだけど」
「別に先帰っててもいいけど」
「なんだよー、一緒の方が楽しいじゃん」
こいつはさらっとこういうことを言う。思わず黙り込んだ俺をみて、泉は楽しげに笑った。
「ねえ、晴紅。照れてる?」
「うるせえ」
からかい混じりの声で言う泉に、俺は表情を変えないようにしながら返す。
照れているか? そんなの当たり前だろう。こっちはバクバクうるさい心臓の音を聞かれないように必死だというのに。
俺はこの幼なじみ、和田泉のことが好きだ。ずっと昔から。
◆
俺は出会った年齢さえ覚えていない。隣の家に住んでいて、物心つく頃には一緒に遊んでいた。それくらい長い仲だ。
和田泉は明るい人気者だ。部活に入っていないはずなのに友達が多く、どうやって仲良くなったかは分からないが、先輩にも親しい人がいるらしい。
昔からそうだった。上手く周囲になじめない俺の手を引いて、輪の中心になっていく。きらきらとした笑顔でみんなをまとめ、気がつけば周囲の人間は和田泉という人間を中心に動くようになっている。
だから泉は多くの人に慕われ、友達が多かった。それでも、俺を蔑ろにすることはなかった。俺の隣からいなくなることはなかった。気がつけば戻ってきていた。
隣にいるのが当たり前で。ずっとそんな日々が続くと思っていた。こいつが中学生のときに好きな人ができたと言い出すまでは。
「僕、同じクラスの三島さんが好きなんだよね」
「へえ」
何でもないように答えたけれど、ずきりと痛む胸に自分で驚いた。もやもやと嫌な心地がして、無性に腹が立った。それを表に出さないように必死だったけれど、こいつは何にも気がつく様子はなかった。
「だからさ、放課後に機会を見計らって三島さんと話をしてみようと思うんだ。だからしばらくは晴紅と帰れない」
「好きにしろよ」
「えー。晴紅は寂しくないの?」
寂しいと喚けば、行かないのか。今まで通り一緒に帰って遊びたいと言い募れば、こいつはどこにも行かないのだろうか。
そんなことはないだろう。きっと、今回は上手くいかなかったとしても、泉はいつか俺の側からいなくなる。
永遠なんて、どこにもないのだ。それをまざまざと見せつけられた。
俺は全部の感情を隠して笑った。
「今、お前と一緒にいるのは俺だからいい」
真っ赤な嘘だ。嫌だ、俺だけを見ろと喚きたかった。彼女なんて作るな、俺がいればいいだろうと言ってしまいそうになった。
それでも、泉の前では格好つけたかった。そこで唐突に理解した。
俺は、泉のことが好きなんだ。
俺が恋を自覚をしたのはこのときであるが、きっと自覚する前から好きだったのだろう。いつからか好きだったかは自分でも分からない。それくらい俺の人生の中で、泉と一緒にいることは当たり前であり、好きという言葉では表現できないくらいの気持ちを抱えている。
この恋が多数の人間と違うことはだんだん分かってきた。それでもよかった。だって、これが「恋」であることが悟られなければ問題がないのだ。ただの仲の良い幼馴染。それでいいじゃないか。何度もそう言い聞かせた。
ちなみに、泉は三島さんと付き合うことはなかったと思う。少なくとも俺は聞いていない。俺と泉の仲が疎遠になることはなく、同じように過ごしていた。
それでも俺の中では何かが変わってしまった。
好きなのだ。その気持ちは押し込めるのが難しい。泉と話をしていると、不意に喉が締め付けられるような感覚が沸き起こる。最初は見ないフリをしていた。それでも、呼吸の苦しさを放っておくこともできなくなった。
だから、ちょっとだけ。好きという言葉を、重さを取っ払って伝えることにした。それでも、好きだと伝える恥ずかしさと、身勝手な恋心を持ったという申し訳なさから、泉の目を見ながら言うことはできなかったけれど。
「お前といるのが一番気を遣わなくて済むから好きだ」
「まじ? 珍しいな、お前がそんなことを言うのは」
最初は驚かれたけれど、二人だけの場で似たような言葉を繰り返すうちに、泉は特に気にしなくなってきた。
「俺、泉のことが好きだ」
「うん。僕も晴紅のこと好きだよ」
それくらいの言葉を言い合うくらいには慣れた。もちろん、泉のいう「好き」は幼なじみとしての物であり、俺への恋愛感情はないということを知っている。
◆
最近は、一緒に進めているゲームがある。2人で協力してゴールするものであり、1人ではできないものだ。今日もそれをやるために、泉は家へと来ていた。
「晴紅、これあげる。好きだったよね?」
ゲームの準備をしていると、泉が何かを取り出した。それは俺の好きな種類のクッキーだった。クッキーの中にチョコレートが入っているお菓子だ。
このお菓子を見かけたら、泉は俺のことを思い出す。それくらい、泉の生活の中に俺がいて。反対に、俺の生活の中にも泉がいる。心の中にぶわりと嬉しさが広がった。胸が苦しくなるほどの衝動に浅く息を吸った。
「泉のことが好きだ」
いつもと違い、泉の目を見ながら言った。泉が何度か瞬きをして俺を見つめる。
「……ありがとう」
あれ、いつもと反応が違うような……。きっと気のせいだろう。今まで何回好きだと言ってきたのか。好きだと言ったくらいで何かが変わるような関係じゃない。
「ごめん。用事思い出したから帰るね」
「おお。また明日な」
「……うん」
泉が急に立ち上がって自分の家へと帰っていく。忘れていた宿題でも思い出したのだろうか。まあゲームの続きは明日にだってできる。
俺はそう思っていたが。
次の日から、泉はぱたりと来なくなった。
◆
「泉、今日は家に……」
「ごめん、忙しくて」
「泉、今日の帰りは……」
「ごめん、一緒に帰れない」
泉の教室に行くも、すぐに逃げられてしまう。1日、2日のことならそういう日もあるが、で話は済むが、今日で1週間だ。流石に俺だって気がつく。
どうしたんだろうか。最後に泉が家に来た日を考える。何か変わったことはあっただろうか。いつも通りゲームをして、泉が用事を思い出したとか言って帰った。それだけだったはずだ。
うん。いつも通りだな。何も変わったことはない。
俺がゲーム下手すぎて嫌になった? それとも、俺と遊ぶのに飽きた?
そんな可能性は浮かんだものの、あまりしっくりこない。昔からずっと一緒に遊んでいたから、俺の不器用さは知っているはずだし、遊ぶのに飽きたとしたらここまで露骨に避けないだろう。
やっぱり変わったことはない気がする。
あ、好きだとは言ったかもしれないけど、それは別にいつものことだし……。関係がなさそうだ。
そこで、唐突に1つ思い当たることがあった。
泉は、好きな人ができたんじゃないか。だから、忙しくなったんじゃないか。
なんだ。きっとそうだ。泉も言ってくれればいいのに。少し悲しいけれど、直接恋愛相談をされるのも苦しいから、良かったのかもしれない。
身体が一気に重くなったような感覚は、きっと勘違いだ。
◆
もう1週間経っても、泉との関係は元に戻らなかった。流石に俺のことを避けすぎだ。俺は放課後に泉のことを捕まえた。終礼は泉のクラスの方が終わるのは早い。それなら、泉が掃除当番の日に待ち伏せをすればいいのだ。
泉のクラスの掃除当番の周期は把握している。待ち伏せなんて余裕だ。
「おい、泉」
「なに? 晴紅」
「お前、なんで俺を避けんだよ」
「避けてなんて……」
泉は否定をしようとしているけれど、全然目があわない。ぐっと胸を抉られたかのような感覚で、絞り出すように声を出す。
「俺が何かしたなら言ってくれ。なんでも、直すから」
「晴紅は悪くないよ」
「じゃあ、なんで?」
「……」
「俺はお前に避けられんのが1番きつい」
下を向いた泉に顔を近づける。ちらりとこちらを見た泉とぱちりと目があった。
徐々に顔が朱に染まっていくのをみて、俺は時間が止まったような気がした。
なぜ、こいつはこんな顔をする? まるで。まるで。
俺のことが好きみたいじゃないか。
「いず」
「ごめん」
俺が名前を呼び切る前にぱっと泉は逃げ出した。
泉が出ていった扉を呆然と眺める。今、何が起こった?
「え、まじで?」
口元をおさえる。じわじわと頬の体温が上昇して、熱い。全身の力が抜けて思わずしゃがみ込む。
俺はこの恋が叶うことを願ったことはなかったし、想定したこともなかった。
それが覆るかもしれない。その事実を俺はどう受け止めたらいいのだろう。
そこまで考えて冷静になる。それでも、泉がこの調子で逃げ続けたら? 俺と泉の間にできた溝は一生このままか?
俺は好きだと伝えることが目的だったのではない。ただ、ずっと一緒にいたくて、それに名称をつけるとしたら「好き」というだけだ。
はっきり言おう。俺は今のこの状況が1番気に入らない。
泉と遊べない。話せない。今までは共有していた景色も、楽しいことも、嫌なことも共有できない。それが1番気に入らない。
もし、隣に立つことが当たり前じゃなくなるのが、俺の気持ちのせいだとしたら。この気持ちは心の奥底にしまい込もう。
それが俺にとっての愛だから。美しい物も、おいしい物も、楽しい物も全部、泉に渡したい。
だからこそ、このままではいられない。