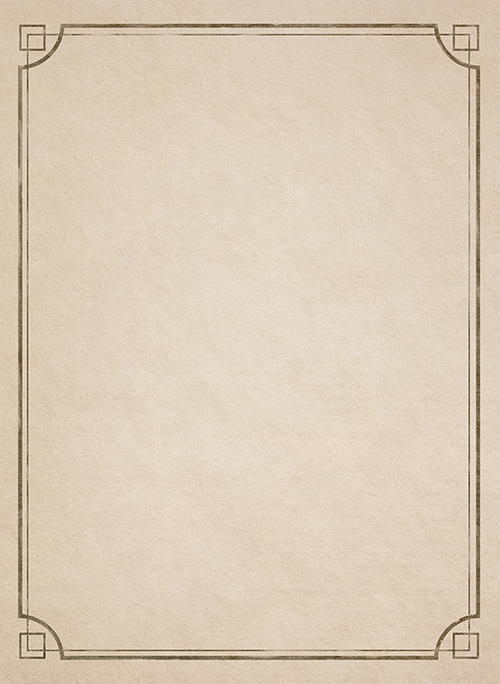第十七話
日が経つにつれ、ヒナコちゃんとハナちゃんの関係は悪化する一方だった。
二人は互いに避け合うようになった。
今となったは、私を介しての会話しかない状態へと陥っていた。
ある休み時間だった。
私はクラス委員の仕事に関して、先生に呼ばれ職員室にいった。
それから教室へ帰ってきたとき。
教室に入ると、ハナちゃんが教室の窓際に一人でいた。
窓の外を見ている。
その様子は、何かに黄昏ているように見えた。
いつも騒がしく元気なハナちゃんが?と、私は思った。
「あっ、アイリちゃん」
ハナちゃんは私に気がついた。
それから、私はハナちゃんと話を始めた。
大したことはない。
だけど、今のハナちゃんとは話しておくべきなのだ、きっと。
しばらくして、ヒナコちゃんが教室に入ってきた。
彼女は私たちの方をちらりと見たが、すぐに自分の席に向かった。
「二人とも、どうしてこんなことになったの?」
思い切って私は、聞いてみる。
できるだけ穏やかな声。
ハナちゃんは少し困ったような表情を浮かべた。
「別に…何もないよ?」
ハナちゃんは、そっけない返事をした。
「ハナちゃん?」
私が言いかけると、ハナちゃんは言葉を遮るように話し始めた。
「アイリちゃん、気にしないで。」
ハナちゃんは、そう言って微笑んだ。
私はそれ以上の追及をやめた。
それから、私とハナちゃんとはいつもの時間が流れた。
授業中、私は何度もヒナコちゃんとハナちゃんの様子を気にした。
二人とも、一生懸命に授業を聞いているようだった。
その様子は普段と変わらない。
昼休み、私はいつものように二人を誘おうとした。
「ねえ、一緒にお昼食べない?」
私の言葉に、ヒナコちゃんは一瞬顔を見合わせた。
「アイリ、すまない。私はちょっと、やることがあってな。」
ヒナコちゃんは、そう言って立ち上がった。
私がヒナコちゃんと話していると、いつの間にかハナちゃんは、教室から出て行っていたようだ。
ハナちゃんは教室にいない。
しかたなく、私は一人で昼食を取ることになった。
放課後、私はクラス委員の仕事を終えて教室を出ようとしていた。
そのとき、廊下でヒナコちゃんがいた。
「ヒナコちゃん。部活は?」
「ああ、今日はもう終わりだ。」
溌溂とした感じで彼女はそういった。
「そうなのね?私もクラス委員の仕事が終わったところなの。」
「そうか、アイリ。じゃあ、一緒に帰るか。」
「ええ。」
私がそう言うと、ヒナコちゃんとの会話を続けようとした。
そのとき、廊下の向こうからハナちゃんが歩いてきた。
ハナちゃんは私たちの方を見ると、一瞬足を止めた。
その表情は、どこか嫌そうなものが見て取れた。
でも、すぐに笑顔を作って近づいてきた。
「アイリちゃん、まだ帰ってないの?」
ハナちゃんは、私に話しかけてきた。
隣にいるヒナコちゃんのことは無視している。
私は、その様子を見ていることしかできなかった。
二人の間に流れる空気は、冷たく重いものだった。
ヒナコちゃんは無表情で私とハナちゃんを見ていた。
私は、何か言わなければと思った。
でも、最適な言葉が見つからない。
むしろ、黙っているのも手段の一つだ、と思えるくらいの雰囲気だった。
ハナちゃんが小さく息を吸い込む音が聞こえた。
何か言いたげな表情だ。
でも、結局何も言わずに立ち去ろうとする。
ヒナコちゃんも、その場を離れようとしていた。
私は、このまま二人を行かせてしまうのは、取り返しのつかないことになる。
そう、直感的に感じた。
「ちょっと、待って!」
私の声が、廊下に響いた。
二人は足を止め、驚いたように私を見た。
「今日、私は、みんなで一緒に帰りたいな。」
私は、できるだけ明るく笑顔を作った。
でも、私が近づくと二人は急に態度を変えた。
「あ、アイリちゃん!分かったよ!」
ハナちゃんが、無理に明るく声をかけてくる。
「分かった、アイリ。じゃあ、帰るか。」
ヒナコちゃんも、普段通りを装おうとしている。
私は、その様子を見ていて、とても奇妙に思う。
今、私の目の前には、ハナちゃん、アイリちゃんがいる。
私は、二人と仲が良い。
しかし、ハナちゃんとアイリちゃんは仲が悪い。
だから、二人は、私の前で、その関係を当たり前かのように振る舞っている。
「二人とも…私のことで喧嘩しないで。」
ヒナコちゃんとハナちゃんは、一瞬驚いたような顔をした。
「違うよ、アイリちゃん。私たち、喧嘩なんてしてないよ。」
ハナちゃんが慌てて否定する。
「そうだ。気にするなって。」
ヒナコちゃんも、そう言った。
でも、その言葉が逆に二人の仲の悪さを証明しているようだった。
三人で帰り道を歩きながら、私はいろいろと考えていた。
答えが見つからないまま、私たちはいつもの別れ道に着いた。
「じゃあね、アイリちゃん。」
「また明日な、アイリ。」
二人は、私に向かって笑顔を作る。
でも、お互いには目を合わせようとしない。
私は、そんな二人の様子を観察する。
そして、これ以上、私が望まない方向にいかないように祈るしかなかった。
日が経つにつれ、ヒナコちゃんとハナちゃんの関係は悪化する一方だった。
二人は互いに避け合うようになった。
今となったは、私を介しての会話しかない状態へと陥っていた。
ある休み時間だった。
私はクラス委員の仕事に関して、先生に呼ばれ職員室にいった。
それから教室へ帰ってきたとき。
教室に入ると、ハナちゃんが教室の窓際に一人でいた。
窓の外を見ている。
その様子は、何かに黄昏ているように見えた。
いつも騒がしく元気なハナちゃんが?と、私は思った。
「あっ、アイリちゃん」
ハナちゃんは私に気がついた。
それから、私はハナちゃんと話を始めた。
大したことはない。
だけど、今のハナちゃんとは話しておくべきなのだ、きっと。
しばらくして、ヒナコちゃんが教室に入ってきた。
彼女は私たちの方をちらりと見たが、すぐに自分の席に向かった。
「二人とも、どうしてこんなことになったの?」
思い切って私は、聞いてみる。
できるだけ穏やかな声。
ハナちゃんは少し困ったような表情を浮かべた。
「別に…何もないよ?」
ハナちゃんは、そっけない返事をした。
「ハナちゃん?」
私が言いかけると、ハナちゃんは言葉を遮るように話し始めた。
「アイリちゃん、気にしないで。」
ハナちゃんは、そう言って微笑んだ。
私はそれ以上の追及をやめた。
それから、私とハナちゃんとはいつもの時間が流れた。
授業中、私は何度もヒナコちゃんとハナちゃんの様子を気にした。
二人とも、一生懸命に授業を聞いているようだった。
その様子は普段と変わらない。
昼休み、私はいつものように二人を誘おうとした。
「ねえ、一緒にお昼食べない?」
私の言葉に、ヒナコちゃんは一瞬顔を見合わせた。
「アイリ、すまない。私はちょっと、やることがあってな。」
ヒナコちゃんは、そう言って立ち上がった。
私がヒナコちゃんと話していると、いつの間にかハナちゃんは、教室から出て行っていたようだ。
ハナちゃんは教室にいない。
しかたなく、私は一人で昼食を取ることになった。
放課後、私はクラス委員の仕事を終えて教室を出ようとしていた。
そのとき、廊下でヒナコちゃんがいた。
「ヒナコちゃん。部活は?」
「ああ、今日はもう終わりだ。」
溌溂とした感じで彼女はそういった。
「そうなのね?私もクラス委員の仕事が終わったところなの。」
「そうか、アイリ。じゃあ、一緒に帰るか。」
「ええ。」
私がそう言うと、ヒナコちゃんとの会話を続けようとした。
そのとき、廊下の向こうからハナちゃんが歩いてきた。
ハナちゃんは私たちの方を見ると、一瞬足を止めた。
その表情は、どこか嫌そうなものが見て取れた。
でも、すぐに笑顔を作って近づいてきた。
「アイリちゃん、まだ帰ってないの?」
ハナちゃんは、私に話しかけてきた。
隣にいるヒナコちゃんのことは無視している。
私は、その様子を見ていることしかできなかった。
二人の間に流れる空気は、冷たく重いものだった。
ヒナコちゃんは無表情で私とハナちゃんを見ていた。
私は、何か言わなければと思った。
でも、最適な言葉が見つからない。
むしろ、黙っているのも手段の一つだ、と思えるくらいの雰囲気だった。
ハナちゃんが小さく息を吸い込む音が聞こえた。
何か言いたげな表情だ。
でも、結局何も言わずに立ち去ろうとする。
ヒナコちゃんも、その場を離れようとしていた。
私は、このまま二人を行かせてしまうのは、取り返しのつかないことになる。
そう、直感的に感じた。
「ちょっと、待って!」
私の声が、廊下に響いた。
二人は足を止め、驚いたように私を見た。
「今日、私は、みんなで一緒に帰りたいな。」
私は、できるだけ明るく笑顔を作った。
でも、私が近づくと二人は急に態度を変えた。
「あ、アイリちゃん!分かったよ!」
ハナちゃんが、無理に明るく声をかけてくる。
「分かった、アイリ。じゃあ、帰るか。」
ヒナコちゃんも、普段通りを装おうとしている。
私は、その様子を見ていて、とても奇妙に思う。
今、私の目の前には、ハナちゃん、アイリちゃんがいる。
私は、二人と仲が良い。
しかし、ハナちゃんとアイリちゃんは仲が悪い。
だから、二人は、私の前で、その関係を当たり前かのように振る舞っている。
「二人とも…私のことで喧嘩しないで。」
ヒナコちゃんとハナちゃんは、一瞬驚いたような顔をした。
「違うよ、アイリちゃん。私たち、喧嘩なんてしてないよ。」
ハナちゃんが慌てて否定する。
「そうだ。気にするなって。」
ヒナコちゃんも、そう言った。
でも、その言葉が逆に二人の仲の悪さを証明しているようだった。
三人で帰り道を歩きながら、私はいろいろと考えていた。
答えが見つからないまま、私たちはいつもの別れ道に着いた。
「じゃあね、アイリちゃん。」
「また明日な、アイリ。」
二人は、私に向かって笑顔を作る。
でも、お互いには目を合わせようとしない。
私は、そんな二人の様子を観察する。
そして、これ以上、私が望まない方向にいかないように祈るしかなかった。