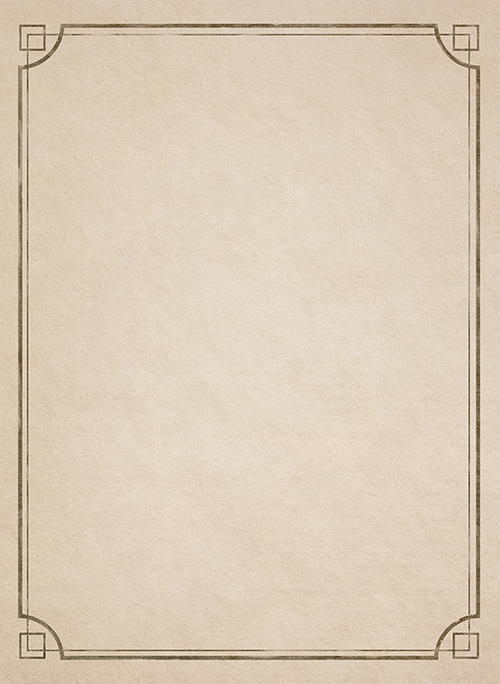第十六話
カリンちゃんが停学処分となってから、しばらく経った。
彼女が、学校に登校する日がいつ来るのかを、私は知らない。
もし、彼女が再び、学校に登校するようになったとして。
カリンちゃんと、どういう風に向かい合えばいいのだろうか?
そんなことを考えつつも、私はいつも通りに教室のドアを開けた。
朝の教室には、すでに何人かのクラスメイトがいた。
私が入ってくると、彼らは一瞬こちらを見たが、すぐに目をそらした。
どうやら、彼らの友人ではなかった、ということらしい。
もちろん、そのとおりだ。
そのまま、自分の席に向かう。
座りながら、ふと周囲を見る。
カリンちゃんの席は、空いたままだった。
ということは、彼女はまだこの学校の生徒なのだ。
少なくとも、今は。
私は自席に座った。
時が過ぎるのを待つ。
私の友人が教室へ入ってくるのを待つのだ。
さきほど、私を見てから、目をそらしたクラスメイトのように。
教室の外から、ドタバタとした足音が聞こえた。
その元気な足音。
これはきっと…。
私が予想をしていると、その足音の主が教室へと入ってきた。
ハナちゃん。
それは、私の予想した通りだった。
彼女は、教室にいる私を見ると手を振る。
ハナちゃんは自分の席に荷物をドサッとおいて、私へ近づいてきた。
「おはよう、アイリちゃん。」
「おはよう、ハナちゃん」
私は柔らかく微笑み返す。
いつもの光景だった。
それから、私とハナちゃんは、ふたりで話をする。
いつもの時間になる、はずだった。
「ヒナコちゃん、最近変だと思わない?」
その突然なハナちゃんの言葉。
私は一瞬、言葉を失った。
…確かに、ヒナコちゃんは変わってしまった。
でも、それを改めて指摘されると、どういえばいいのか迷ってしまう。
「そうね…。でも、何か理由があるのよ、きっと。」
私は無難な答えを返す。
「そうかな?だって…。」
ハナちゃんは不満そうに話をし始めた。
どうやら、本格的にヒナコちゃんのことを嫌っているようだ。
私は、ハナちゃんの言葉を曖昧に聞いていた。
そうしていると、時間が経過していった。
やがて、朝練をしている生徒たちが練習を終えて、教室へ入ってくる時間となった。
ヒナコちゃんは、無言で教室に入ってきた。
その様子をハナちゃんは、見ているだけだった。
ヒナコちゃんもこちらを見ているだけで、何も言ってこない。
最近の二人の様子はずっとこんな感じだ。
奇妙なことに、ヒナコちゃんとハナちゃんの間に微妙な距離感が生まれていた。
あるとすれば、あの日の帰り道での言い争いが、まだ尾を引いているのかもしれない。
はじめ、私は二人の様子にどう振る舞えばいいのかと、思った。
しかし、すぐにそれは解決してしまった。
私は、慣れてしまったのだ。
その結果、今のような距離感が構築されていった。
そんなことを思い出していると、教室の後ろの方で、ヒナコちゃんが一人で座っているのが目に入った。
彼女は、さり気なく、私とハナちゃんを見ているようだった。
緊張というほどもない。
特にカリンちゃんとの関係と比べれば。
私はそんなことを思いながら、ハナちゃんの話を聞いていた。
朝の時間。
その終わりを告げるチャイムが鳴った。
ホームルーム。
私は、クラス委員としてホームルームを進行させる。
そのあと、授業が始まった。
私は、黒板に向かって何かを書いている先生の背中を見つめながら、授業とは別のことを考えていた。
カリンちゃんは今、何をしているのだろう。
家で一人で過ごしているのかな。
それとも…。
授業中、何度か目に入ってしまった。
ヒナコちゃんの姿だ。
彼女は真剣に授業を聞いているようだった。
でも、その表情にはどこか重く息苦しいような雰囲気だった。
昼休み。
最近の私は、ハナちゃんと一緒に食べていた。
もちろん、私の近くにはヒナコちゃんはいない。
私は、ハナちゃんは二人でお弁当を広げていた。
「ねえねえ、アイリちゃん。」
ハナちゃんが、小声で私に話しかけてきた。
「何かしら?」
私は、ハナちゃんの方を見た。
「あの、ヒナコちゃんって…。」
やはりハナちゃんは、ヒナコちゃんについて、あまりよく思っていないようだ。
私はそのハナちゃんの言葉を聞くだけに留める。
ヒナコちゃんは、一人で教室の隅で食べていた。
私たちの間にある、この言いようのない距離感が表現されているかのようだった。
「ねえ、アイリちゃん」
ハナちゃんが、またも小さな声で話しかけてきた。
私は曖昧でどうとでも取れるような回答を繰り返すしかない。
正直、ハナちゃんとヒナコちゃんの間に入るのは、繊細な作業だ。
「うん…。でも、アイリちゃんのこと、あんまり心配してないみたいで…」
ハナちゃんの声には、少し不満げな響きがあった。
「そんなことないわ。ヒナコちゃんは、きっと彼女なりの方法で心配してくれているのよ。」
私は、ヒナコちゃんを擁護するように言った。
ハナちゃんは、私の言葉に小さく頷いたが、おそらく納得していない。
私は、ふとヒナコちゃんの方を見た。彼女は一人で黙々と弁当を食べていた。
放課後になった。
手芸部にいるハナちゃん。
私はクラス委員の仕事を終えて、フリーだった。
そして、なぜか教室に来たヒナコちゃん。
つまりそれは、私にとって珍しくヒナコちゃんと二人きりになる機会だった。
「ヒナコちゃん。」
「ん?なんだ、アイリ?」
ヒナコちゃんは、なんともないかのように振る舞う。
「最近、ハナちゃんと何かあったの?」
私が尋ねると、ヒナコちゃんは一瞬硬い表情を見せた。
「別に…何もない。」
「そう?」
私は、これ以上追及することをやめた。
おそらく、ヒナコちゃんの性格では、これ以上何も話してくれないだろう。
「あの…。私は、これから、手芸部があるから。」
「ああ、じゃあな。」
私は、ヒナコちゃんと別れた。
カリンちゃんが停学処分となってから、しばらく経った。
彼女が、学校に登校する日がいつ来るのかを、私は知らない。
もし、彼女が再び、学校に登校するようになったとして。
カリンちゃんと、どういう風に向かい合えばいいのだろうか?
そんなことを考えつつも、私はいつも通りに教室のドアを開けた。
朝の教室には、すでに何人かのクラスメイトがいた。
私が入ってくると、彼らは一瞬こちらを見たが、すぐに目をそらした。
どうやら、彼らの友人ではなかった、ということらしい。
もちろん、そのとおりだ。
そのまま、自分の席に向かう。
座りながら、ふと周囲を見る。
カリンちゃんの席は、空いたままだった。
ということは、彼女はまだこの学校の生徒なのだ。
少なくとも、今は。
私は自席に座った。
時が過ぎるのを待つ。
私の友人が教室へ入ってくるのを待つのだ。
さきほど、私を見てから、目をそらしたクラスメイトのように。
教室の外から、ドタバタとした足音が聞こえた。
その元気な足音。
これはきっと…。
私が予想をしていると、その足音の主が教室へと入ってきた。
ハナちゃん。
それは、私の予想した通りだった。
彼女は、教室にいる私を見ると手を振る。
ハナちゃんは自分の席に荷物をドサッとおいて、私へ近づいてきた。
「おはよう、アイリちゃん。」
「おはよう、ハナちゃん」
私は柔らかく微笑み返す。
いつもの光景だった。
それから、私とハナちゃんは、ふたりで話をする。
いつもの時間になる、はずだった。
「ヒナコちゃん、最近変だと思わない?」
その突然なハナちゃんの言葉。
私は一瞬、言葉を失った。
…確かに、ヒナコちゃんは変わってしまった。
でも、それを改めて指摘されると、どういえばいいのか迷ってしまう。
「そうね…。でも、何か理由があるのよ、きっと。」
私は無難な答えを返す。
「そうかな?だって…。」
ハナちゃんは不満そうに話をし始めた。
どうやら、本格的にヒナコちゃんのことを嫌っているようだ。
私は、ハナちゃんの言葉を曖昧に聞いていた。
そうしていると、時間が経過していった。
やがて、朝練をしている生徒たちが練習を終えて、教室へ入ってくる時間となった。
ヒナコちゃんは、無言で教室に入ってきた。
その様子をハナちゃんは、見ているだけだった。
ヒナコちゃんもこちらを見ているだけで、何も言ってこない。
最近の二人の様子はずっとこんな感じだ。
奇妙なことに、ヒナコちゃんとハナちゃんの間に微妙な距離感が生まれていた。
あるとすれば、あの日の帰り道での言い争いが、まだ尾を引いているのかもしれない。
はじめ、私は二人の様子にどう振る舞えばいいのかと、思った。
しかし、すぐにそれは解決してしまった。
私は、慣れてしまったのだ。
その結果、今のような距離感が構築されていった。
そんなことを思い出していると、教室の後ろの方で、ヒナコちゃんが一人で座っているのが目に入った。
彼女は、さり気なく、私とハナちゃんを見ているようだった。
緊張というほどもない。
特にカリンちゃんとの関係と比べれば。
私はそんなことを思いながら、ハナちゃんの話を聞いていた。
朝の時間。
その終わりを告げるチャイムが鳴った。
ホームルーム。
私は、クラス委員としてホームルームを進行させる。
そのあと、授業が始まった。
私は、黒板に向かって何かを書いている先生の背中を見つめながら、授業とは別のことを考えていた。
カリンちゃんは今、何をしているのだろう。
家で一人で過ごしているのかな。
それとも…。
授業中、何度か目に入ってしまった。
ヒナコちゃんの姿だ。
彼女は真剣に授業を聞いているようだった。
でも、その表情にはどこか重く息苦しいような雰囲気だった。
昼休み。
最近の私は、ハナちゃんと一緒に食べていた。
もちろん、私の近くにはヒナコちゃんはいない。
私は、ハナちゃんは二人でお弁当を広げていた。
「ねえねえ、アイリちゃん。」
ハナちゃんが、小声で私に話しかけてきた。
「何かしら?」
私は、ハナちゃんの方を見た。
「あの、ヒナコちゃんって…。」
やはりハナちゃんは、ヒナコちゃんについて、あまりよく思っていないようだ。
私はそのハナちゃんの言葉を聞くだけに留める。
ヒナコちゃんは、一人で教室の隅で食べていた。
私たちの間にある、この言いようのない距離感が表現されているかのようだった。
「ねえ、アイリちゃん」
ハナちゃんが、またも小さな声で話しかけてきた。
私は曖昧でどうとでも取れるような回答を繰り返すしかない。
正直、ハナちゃんとヒナコちゃんの間に入るのは、繊細な作業だ。
「うん…。でも、アイリちゃんのこと、あんまり心配してないみたいで…」
ハナちゃんの声には、少し不満げな響きがあった。
「そんなことないわ。ヒナコちゃんは、きっと彼女なりの方法で心配してくれているのよ。」
私は、ヒナコちゃんを擁護するように言った。
ハナちゃんは、私の言葉に小さく頷いたが、おそらく納得していない。
私は、ふとヒナコちゃんの方を見た。彼女は一人で黙々と弁当を食べていた。
放課後になった。
手芸部にいるハナちゃん。
私はクラス委員の仕事を終えて、フリーだった。
そして、なぜか教室に来たヒナコちゃん。
つまりそれは、私にとって珍しくヒナコちゃんと二人きりになる機会だった。
「ヒナコちゃん。」
「ん?なんだ、アイリ?」
ヒナコちゃんは、なんともないかのように振る舞う。
「最近、ハナちゃんと何かあったの?」
私が尋ねると、ヒナコちゃんは一瞬硬い表情を見せた。
「別に…何もない。」
「そう?」
私は、これ以上追及することをやめた。
おそらく、ヒナコちゃんの性格では、これ以上何も話してくれないだろう。
「あの…。私は、これから、手芸部があるから。」
「ああ、じゃあな。」
私は、ヒナコちゃんと別れた。