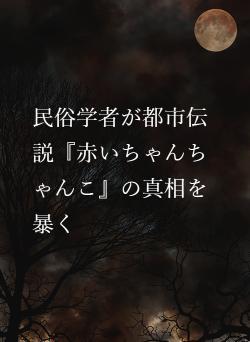手元に見えるは真新しいタンブラー。
いつものように、出勤して熱々のコーヒーを飲む柊さんは、わたしとおそろいの水筒型ボトルではなくて、コップ型のメタリックな赤い容器を手に持っていた。
あの形、そして上に向かって色が薄くなっていくグラデーション。どこかで見たことがある。
「見過ぎだぞ、ウエハラ」
たしかに凝視しすぎだと思わず視線をそらす。
耳元で声をかけてきたのはニシジマだった。ちょっと不服そうに、じとっとした視線を送ってくる。
「ウエハラがなにもいわないものだからさ」
「なんのこと?」
「柊さんのこと、どうかなって聞いてもなにもいわないし、いいってことだよね、わたしが近づいても」
そうだ。ニシジマのタンブラーだった。ブルーのグラデーションで、イルカを形取った白いシールが貼ってあり、印象が違うが同じ形の色違いだ。
わたしがちょっと近づきつつあるのが柊さんだってこと、バレていたのだ。
それであのとき、柊さんの名前を出してかまをかけてみたのか。
わたしが手を出さないでと制さなかったのをいいことに、アプローチに打って出たらしい。
「それで。同じの、プレゼントしたの?」
「プレゼントじゃないよ。ご飯食べて、買い物行った」
平然といってのけるニシジマがたくましく見える。
「すること早いな」
「まだしてないよ」
「そりゃあ、そうでしょうよ」
あきれているとニシジマはクククと喉の奥で笑いを鳴らす。
「そっちが同級生との交流を深めている間にね」
葉亜斗のことか。
インスタにタコライスを載せたのだから、葉亜斗に会いに行ったことをニシジマも知っていて当然だった。
ひょっとして、出し抜くために旧友と遊ぶことを勧めていたのだろうか。
わたしはあのあと草木染めの彼女と遭遇し、タコライスを買って帰った。終わるまで待ってるのと聞かれたが、手伝いもしないのにウロウロと待っているのもおかしい。
あれ? 手伝うのが正解だったのか?
さすがにそこまでするのは余計なお世話だよね。アルバイト募集の張り紙でもあったら名乗りを上げてもいいのだが。
勘のいいニシジマはぐいと迫ってきた。
「まさか、次なる作戦はキッチンカーで巡って恋人探しとか?」
「キッチンカーとはいえね、忙しくてそれどころじゃないんだから」
肩でニシジマを押し返すも、再びすり寄ってくる。
「でも実際、声かけて交流が始まったじゃない。新たな出会いを探すにはぴったり」
「人となりがわかる社内恋愛のほうがいいって結論出たでしょ」
「まぁね。また偶然よく知ってる同級生と出会うとかないだろうからね」
ニシジマはわたしの肩をポンと叩き、柊さんのもとへ向かった。
うまくいってるときってのは、重力が半分くらいになるらしい。ニシジマの足取りが軽やかだった。
連絡先を聞かれるまであとちょっとと思っていた柊さんは幻に終わったようだ。
ニシジマは正しかった。
気のあるそぶりでうまくいくのなら、すでにほしいものを手にしていたはずだった。
向こうもわたしがどの程度の情熱かを見抜いていたのかも。
すでにゆし豆腐が恋しい。
ヒグラシヒガッチのインスタは、いつでも葉亜斗の居場所を知らせてくれていた。
いつものように、出勤して熱々のコーヒーを飲む柊さんは、わたしとおそろいの水筒型ボトルではなくて、コップ型のメタリックな赤い容器を手に持っていた。
あの形、そして上に向かって色が薄くなっていくグラデーション。どこかで見たことがある。
「見過ぎだぞ、ウエハラ」
たしかに凝視しすぎだと思わず視線をそらす。
耳元で声をかけてきたのはニシジマだった。ちょっと不服そうに、じとっとした視線を送ってくる。
「ウエハラがなにもいわないものだからさ」
「なんのこと?」
「柊さんのこと、どうかなって聞いてもなにもいわないし、いいってことだよね、わたしが近づいても」
そうだ。ニシジマのタンブラーだった。ブルーのグラデーションで、イルカを形取った白いシールが貼ってあり、印象が違うが同じ形の色違いだ。
わたしがちょっと近づきつつあるのが柊さんだってこと、バレていたのだ。
それであのとき、柊さんの名前を出してかまをかけてみたのか。
わたしが手を出さないでと制さなかったのをいいことに、アプローチに打って出たらしい。
「それで。同じの、プレゼントしたの?」
「プレゼントじゃないよ。ご飯食べて、買い物行った」
平然といってのけるニシジマがたくましく見える。
「すること早いな」
「まだしてないよ」
「そりゃあ、そうでしょうよ」
あきれているとニシジマはクククと喉の奥で笑いを鳴らす。
「そっちが同級生との交流を深めている間にね」
葉亜斗のことか。
インスタにタコライスを載せたのだから、葉亜斗に会いに行ったことをニシジマも知っていて当然だった。
ひょっとして、出し抜くために旧友と遊ぶことを勧めていたのだろうか。
わたしはあのあと草木染めの彼女と遭遇し、タコライスを買って帰った。終わるまで待ってるのと聞かれたが、手伝いもしないのにウロウロと待っているのもおかしい。
あれ? 手伝うのが正解だったのか?
さすがにそこまでするのは余計なお世話だよね。アルバイト募集の張り紙でもあったら名乗りを上げてもいいのだが。
勘のいいニシジマはぐいと迫ってきた。
「まさか、次なる作戦はキッチンカーで巡って恋人探しとか?」
「キッチンカーとはいえね、忙しくてそれどころじゃないんだから」
肩でニシジマを押し返すも、再びすり寄ってくる。
「でも実際、声かけて交流が始まったじゃない。新たな出会いを探すにはぴったり」
「人となりがわかる社内恋愛のほうがいいって結論出たでしょ」
「まぁね。また偶然よく知ってる同級生と出会うとかないだろうからね」
ニシジマはわたしの肩をポンと叩き、柊さんのもとへ向かった。
うまくいってるときってのは、重力が半分くらいになるらしい。ニシジマの足取りが軽やかだった。
連絡先を聞かれるまであとちょっとと思っていた柊さんは幻に終わったようだ。
ニシジマは正しかった。
気のあるそぶりでうまくいくのなら、すでにほしいものを手にしていたはずだった。
向こうもわたしがどの程度の情熱かを見抜いていたのかも。
すでにゆし豆腐が恋しい。
ヒグラシヒガッチのインスタは、いつでも葉亜斗の居場所を知らせてくれていた。