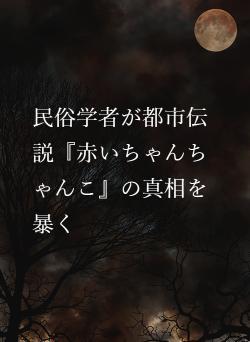10円というせこい賽銭は相変わらずながら、電子決済が主流になりつつあるこのご時世で、小銭を確保することこそが難儀だった。
現金支払いでおつりをもらうつもりが、ついうっかり小銭を出そうと硬化を数えはじめて、「ああそうだ」とまた大きいお金を財布から出す。
レジ店員の「早くしろ」という視線にも耐えつつ、毎日の参拝は滞りなく続いていた。
今までなんのこだわりも持たずに暮らし、ルーティン動画にも面白さを見いだせなかったわたしであるが、あの神社で目撃する見知らぬ女子高生に心動かされるとは不思議なものだ。
カラコロと賽銭箱に転がっていく10円玉。
神頼みの10円といっても、それはまだ自分の未来を悲観していない証だ。
その無記名の証は賽銭箱の底に溜まり続けた。
比嘉葉亜斗のキッチンカーは『ヒグラシヒガッチ』というとんでもないセンスの屋号で、本当にその日暮らしをしているかのような不定期で営業しているらしかった。
フォローして「サルサがほどよい辛さと酸味で最高」とコメントをつけたら、「タコライスも最高なんだから!」と返信がきて、また来てほしいということなのかなと深読みをしていると、すぐにその時はやってきた。
土曜日。場所はうちの会社近くにある公園。フリーマーケットが開催されるという。
出店するので来ないかという誘いがDMで届いた。
ランチメニューは一種なのだが、試しに「ゆし豆腐」も提供してみるという。
休みの日にバスに乗ってそこまで向かうのは初めてだった。
いつもと違う時間だからか、さすがに女子高生とは出会わなかった。
わたしだって休日の参拝はサボっている。
今日は奮発して100円だ。
1枚賽銭箱に放り投げる。
跳ねるように吸い込まれていく100円玉を見ながら、そういえば最初から特定の願掛けしていたわけではなかったと気づく。
なんとなく。幸せでありますように。
手を合わせながら、浮かんだ顔は髪をひとつにまとめて清潔感のある笑顔でまっすぐ見据えてくる比嘉葉亜斗。
柊さんごめんなさいって、まだなにもはじまってないのに、いわれたほうも困惑だろう。
葉亜斗のことはずいぶんと前から知っているようでいて、その実、初対面のような探り探りのやりとりに終始した。
わたしは葉亜斗のことをもっと知りたいのだろうか。
見た目の『なぜ』を解明したいからだとするなら、それは失礼な話なのかもしれない。
でも、向こうから誘ってくれるということは、不愉快なやりとりではなかったのではないかと、良い方に受け止める。
バスが停留し、空調のない炎天下に降り立った。
手に持っていたつばの広い帽子をかぶる。日傘の方がよかったかもしれない。まだ朝といえる時間帯でもすでに暑かった。
キッチンカーのようなエンジンのかかってない車内って実はものすごく暑いんじゃないだろうか。
開口部分が広いとはいえ、通常の店舗のような快適さはなさそう。
会社の近所はマンションが建ち並んでいるような土地柄、ファミリー層も多い。
マンションに囲まれた中にある公園は、ほどよく植樹されていて木陰もありながら見通しがいい。
出店者は準備に追われ、お客さんもちらほら歩いている。
バザーのような気軽な出店から昔ながらの古物商、ハンドメイド風の小物や朝採り野菜などなど、雑多に並ぶ。
葉亜斗のキッチンカーはすぐに見つかった。レモン色とスカイブルーのツートンカラーが目立つ。
朝でもお昼でのないという時間帯。並んでいる客はまだなかった。
やはり葉亜斗ひとりで切り盛りしているようだ。
車内で鍋の様子を見ている。
レモン色のスカーフで髪を結い、スカイブルーのエプロンを着けていて、先日よりもやる気出してるっぽい。
やっぱり女性の姿をしている葉亜斗が見慣れずに、緊張して息をつく。
初めて行くお店の暖簾をくぐるような気持ちで一歩踏み出す。
「まだ準備中?」
声をかけると葉亜斗はわたしに気づいて破顔した。両手を振ってくるのでわたしもそれに応える。
「いらっしゃい。ひとり?」
「この前一緒にいた同僚、デートなんだって。いつの間に?ってかんじだよ」
「その愚痴の吐き方。さては?」
「もう、わかってるなら聞かないでよ」
恋人がいないという近況報告を冗談として昇華させるとわたしたちは笑い合った。
葉亜斗はいつからその姿をしているのだろう。
今、この瞬間に初めて出会ったのだとするなら、必要のない情報でぐるぐると思考を巡らせることもないのに。それくらい葉亜斗は見た目とのギャップがない。
だけどわたしがよく知る三枚目の葉亜斗が背中合わせに存在しているようで、やっぱり少し落ち着かなかった。
この前と同様に自分について葉亜斗は語らない。
「お腹すいてる? ゆし豆腐ならすぐに出せるよ」
「じゃあ、いただく」
「トッピングも考えてみたんだ。これね」
葉亜斗は車の中から身を乗り出してメニュー書きを指した。
名称は『うちなーゆし豆腐』にしたようだ。
あたたかいだし汁におぼろ豆腐がたっぷり入ったおかゆ感覚の沖縄ソウルフードという説明があり、小口ネギがのっている写真があった。
別料金のトッピングは明太子、おぼろ昆布、もずくのナムル風、油揚げの醤油焼き。どれもおいしそうだ。
「入れてみたことないから、もずくにしようかな」
「さすが。もずくはもちろん、沖縄産ね」
「いいねぇ」
沖縄ではできたての温かいままの豆腐を売っているから、だし汁をかけるだけですぐに完成するが、やはりおぼろ豆腐をだし汁で煮たのだろうか。葉亜斗は慣れた手つきで寸胴から豆腐をすくって器に盛っている。
見とれていたら葉亜斗がちらりと振り返った。
「ねぇ。タコスミートもトッピングとしてありかな?」
ひき肉をチリソースで味付けしたメキシコ料理だけど、ご飯にかけたタコライスは沖縄でよく食べていた。
沖縄をウリにするならよさそうだ。
「ありだよ。ロコモコ丼のハンバーグとゆし豆腐もおいしかったもん。いや、むしろそぼろ状のほうが豆腐とマッチして食べやすそう」
「実はヘルシーだしね。タコスミートも、このあいだのハンバーグも、大豆ミートを混ぜてるんだ」
「ええ? そうなの? 普通に肉だと思ってた」
「大豆ミートのクセを消すのはちょっと苦戦したけどね」
おまたせと、どんぶり鉢に入ったゆし豆腐が差し出された。
琥珀色のだし汁からおぼろ豆腐が顔を出し、脇のほうに小口ネギともずくがのっている。ゆらめく湯気に、もずくナムルのごま油がふわりと香った。
「おいしそう。久しぶりのゆし豆腐」
支払いをするしないの一悶着があって、結局サービスということで宣伝に貢献することにした。
「ごゆっくり。とはいっても、テーブルが1つしか用意できてないんだけど」
葉亜斗が用意したのかと、キッチンカーの目の前にある円形のテーブルを見やると、すでにひとり座っていた。
立ち食いでもよかったのだが、目が合い「よければどうぞ」といわれてしまっては断りにくい。
「すみません、相席させてもらいます」
先客はわたしよりも少し年上に見える女性だった。
ひとりできたのだろうか。ウェーブした短い髪をひとつに結い、薄化粧の上品な顔立ち。黒い日傘を椅子に引っかけている。
彼女もゆし豆腐を食べたのか、空のどんぶり鉢とレンゲがひとつテーブルに置かれている。
4つある椅子の向かい側に腰掛けて、まずはだし汁と豆腐をすくって口に運ぶ。
かつお節がきいたシンプルな出汁。
豆腐はややしっかりしていて、沖縄の豆腐より塩味が少ない。
もずくはレンゲですくっても食べやすいように刻んであった。
濃いめの味付けでこれもだし汁とよく合う。忙しい朝でも、真夏の暑い日でも、また食べたくなるやさしい味だった。
だし汁まで飲み干せば、しっかり食事を取ったような満足感が得られた。
「わたしは油揚げにしたんですよ」
わたしが空になったどんぶり鉢をテーブルに置くと、女性は話しかけてきた。
「大豆ばっかりになっちゃったなと思ったけど、まったく別の食感だからおもしろかったわ」
「沖縄ではそばにも豆腐を入れますから、きっと豆腐ってなんにでも合いますよ」
「へぇ。そうね。いわれてみれば豆腐って何にでも合いそう。温かくても冷たくてもいいし。そういえば、ハートさんも沖縄出身っていってたけど、お知り合い?」
あまりに親しげな呼び方になんのことかと一瞬頭をひねったが、ハートといったら比嘉葉亜斗しかない。なんとなくマウントを取られているような気がしたが、勘ぐりすぎだろう。
そもそも彼女は葉亜斗をどこまで知っているのか。
待って。そもそもでいうなら、そもそも目の前の彼女も『彼女』という呼び方でいいのか?
混乱してきたものの、小さいときの葉亜斗の話題になったら困るので適当に答える。
「……えぇ、まぁ」
「そうなんだ。わたし、ハートさんの料理が好きでよく食べるの」
常連なのか。わたしよりも早く来て一番乗りでゆし豆腐を食すくらいにハマっているようだ。
葉亜斗はなにきっかけでこのメニューの着想を得たか話したのだろうか。わたしがそのきっかけだと気がついたからこその相席か。
だが、彼女は探りを入れるどころか自分のことばかりを話しはじめた。
「それでね、どんな食材が使われてるか食べながら検証しているうちにふと思いついたの。あ、これ使えるなって」
「家での料理にってことですか?」
「まぁ、そういうこともあるけど、染め物にね」
「染め物?」
どう繋がっていくのか、我々の関係性のように未知である。
彼女は目を細めて饒舌に語った。
「草木染めのワークショップをやってて。身近にある自然のもので布を染めるのよ。こんな都会でも外を歩いていたら使えるものが結構あってね。選定している枝葉をもらったり、料理人からは玉ねぎの皮とか」
「ええ? そんなものでも?」
「玉ねぎって意外と黄色っぽいきれいな色が出るの。だから、今度は紫玉ねぎの皮はどうだろうと思って。このあいだはサラダに紫玉ねぎが入ってたから、また使うことがあったら皮がほしいってお願いしてたんだ。とにかく、たくさん必要だから」
想像以上の常連だ。
不特定の場所へ追いかけていくのだから、葉亜斗にとってもうれしい客のはず。
「今日は紫玉ねぎをタコライスに使うらしいよ。お腹いっぱいになっちゃったから、それは持って帰ることにしたけどね、楽しみ」
まだ居座るつもりか。
彼女は人のよさそうな笑みを浮かべてキッチンカーを振り返った。葉亜斗は仕込みに集中していて、こちらの会話を気にかけている様子もない。
もし、不用意にわたしが葉亜斗の幼少時代を語り出したらとか、心配ではないのかな。
やっぱり彼女はすべてを知っている?
だとしても、こちらから聞いてみることはできない。
「全部売れるといいね」
彼女はそういって向き直った。それはもちろん率直にいって売れ残りがないほうがいい。
「ハートさんの作る料理って、なんか違うんだよね。お母さんが家族のために作る料理と、料理人が客のために作る料理と、やっぱりなにかが違うでしょ。ハートさんの料理はわたしのために作ってくれている気がしてきちゃうの」
わかる気がします、と相づちを打っているうちに、独り相撲をしているようで気抜けしてきた。
そもするとストーカーじみていて怖い。でも、きっと彼女は違う。
葉亜斗のバックボーンなんて関係なく、彼女は単純に『ヒグラシヒガッチ』のファンなのだ。親心みたいなもので、儲け度外視なところを心配しつつ、ずっと葉亜斗が好きなことを続けられたらいいのにって。わたしだってそう願ってる。
「あなたがゆし豆腐を食べているあいだ、ちらちら様子をうかがってたわよ」
「そうなんですか」
味わうのに夢中で全然気づかなかった。
「同郷の友人として、かな。もちろん料理人の目線も持ってるだろうけどね」
「……葉亜斗が料理に興味あったなんて、全然知らなかったです」
わたしには、そういうの、なにもない。
ルーティンどころじゃなく、趣味もやりたいこのもなにもないのだ。
その日暮らしをしているような葉亜斗を半人前扱いして、自分は定職に就いているというだけで、一日をただやり過ごしているにすぎない。
休みの日に出かけるのも久しぶり。テレビをネットに繋いでいたら、ついにレンタル店に出向くこともなくなったのだ。
別にいいんだよ。なにもなくたって。
普通に仕事しているだけで自分を褒めてあげられるんだけどさ。
たまに青臭く生きることの意味を問いたくなっちゃう。
そんな心情を察したわけじゃないだろうが、彼女はイスにかけてあったバッグを探ると一枚の名刺を差し出した。
「自然に触れながら丁寧に暮らすのも悪くないかもよ? 興味あったら」
あいまいにうなずきながら受け取った。
正直、興味はない。
面倒な行程が目白押しなんだろうなと、突っ込んで話しを聞くのも長くなりそうで、腰が引けていた。
丁寧な暮らしってのもわたしにはピンとくるワードじゃなくて、突き返したくなってくる。
だったらなにをすれば満足なんだろう。
もうすぐ30歳になるっていうのに、自分の機嫌の取り方も知らない。
あいまいな自分にずっとモヤモヤしている。
待っていたら誰かが開けた道を運んでくるわけじゃない。伴侶となる人がわたしを幸せにするって、そんな都合良くいくわけがない。
彼女は前のめりに勧めてくる。
「やってみておもしろいと初めて気づくこともあるじゃない。最初から興味あったらすでにやってるんだし。あとは実行。恋愛だってそうでしょ?」
「たしかに、そうですけど……」
ため息交じりになってしまった。
彼女は慰めてくれているらしい。重い空気にならないようにひとりで話し続ける。
「ハートさんね、あなたが明確に来るか来ないか返信しなかったから、どうなのかなぁって、心配してたよ」
迷ったのは事実だ。
断ると違う意味で避けていると勘違いされないかなとか、義理でいくほど親しくもないなとか。
でも結局重い腰上げて休日にまで出向いてきたのは、葉亜斗のことが気にかかったからだ。
キッチンカーで巡って営業している原動力はなんなのか。
わたしが今まで自分の幸せを願って頑張ってきた道筋は間違っていなかったのか。
そんなこと聞かれたって葉亜斗にわかるわけもないけど。
でも、葉亜斗が選んでここまでたどり着いた道筋にはすごく意味を感じたのだ。
勝手に。
勝手すぎて聞けない。
彼女はわたしを凝視して詮索を続けていた。
「やってくるのがどんな人なのかなって、空想で埋めたんだけどね」
彼女は口元に手を当てていたずらっぽく笑った。
よく見れば、その指には指輪があった。どうやら既婚者らしい。
「当てが外れたわ」
残念そうに首を振った。
つまり、男性が来ると想像していたってことか。
葉亜斗がいじらしく意中の人について語っていると思い込んでいたのだ。
この分では結婚しているのか恋人はいるのか根掘り葉掘り聞いているのではないか。それこそ親戚のおばちゃんみたいなお節介を焼いて葉亜斗を困らせてそうだ。
ひとしきり話して話題も尽きたのか、彼女は昼時まで時間を潰してくるといって会場内に消えていった。
人と会話するのがこんなにしんどいとは。
けれども、次に彼女と顔を合わせることがあれば案外会釈程度で終わるのかもと思っていた。
わたしがどんぶり鉢を持ってキッチンカーへ戻ると、葉亜斗はわたしの瞳の奥をのぞき込むようにいった。
「どうだった?」
どうだったとはあの彼女のことではなく食事の感想だろう。
わたしはゆし豆腐を口にしたときの温かくてほっとする時間を思い起こした。
「おいしかったよ。懐かしさを超えておいしかった。朝だけじゃなくて、休憩のコーヒー代わりにもいけるんじゃないかってくらい、お出汁もおいしい」
葉亜斗は一言も聞き漏らすまいとばかりに真顔でうなずいていが、途中で「ん?」と視線を斜めに見上げた。
「コーヒー……?」
「ああ、半分くらい冗談入っちゃったけど」
おどけてみせると、葉亜斗はハッとしたように両手を振った。
「ごめん、ごめん。なかなか率直にいってもらえることもないからさ、真に受けてどういうことか考えちゃった」
「こっちこそ伝わりにくくてごめん。ええと、だから……石焼き芋屋さんのように巡ってきたらいつでも食べたくなっちゃう恋しさ。いや違うな。焼き芋はたまにだから食べたいんだ。ゆし豆腐は毎日でもいい。こんなふうに他にお店が出ていて食べ歩きでも合間に入れられる軽い食事だし」
「なるほど、朝食にちょうど良くても、ランチにこれひとつではちょっともの足らない感じだね」
「ランチだったら汁物としてつけるとかかな」
「別に容器が必要になるね」
「そっか、そういう視点もね」
文化祭のノリでキッチンカーを始めていたらえらいことになる。
余らせないよう食材を発注し、使い捨ての容器を使うのならコストもそれだけかかる。持ちかえる側の不便さとか、コンビニ弁当や飲食店と比べての価格設定だったり、考慮すべき点はたくさんだ。
「石焼き芋屋さんの発想はいいね。いろんなところに巡回して、たまにやってきたとき、また食べたいって思われるのはうれしい」
「神出鬼没だっていわれてるみたいだけど」
ひとをオバケみたいにと、葉亜斗は不服そうに口をとがらせながらも目元は笑っていた。
「あまり一ヶ所にいたくなくて。接客業をしているのにふしぎに思うだろうけど、人と深く関わるのが苦手っていうか。常連さんとお話しているうちに、どんどん自分のことを話さないといけないような気がして、追い込まれるんだよね」
ギクリとした。卒業してからの葉亜斗がどう変わっていったのか、興味がないわけではなかった。
「それはわかる」と、わたしは悟られないようしみじみといった。
「人と話しをしてると疲れてくるときがあるじゃない。でもさ、ひとりぼっちが恥ずかしいなんて思う年代は過ぎたけど、今度はひとりだと寂しく思うこともあって。葉亜斗がどんな一日を過ごしているのか気になったんだよね。わたしなんか職場と自宅の往復で、関わりあるのも同僚で。子供のころ描いていた大人の世界と全然違う。大人って、もっと大きくて楽しい世界にいるのかと思ってた」
「上原さんって、なんか壮大だよね」
意外な返答に驚く。今、思いっきりこぢんまりとした話しをしたのに、葉亜斗にはそう聞こえなかったらしい。
「小学生のころ、わたしが児童会長に立候補したこと覚えてる?」
「むしろ、それを真っ先に思い出したよ」
やっぱりと葉亜斗はうなずいた。
「みんなやめとけって、からかってたけど、上原さんは違ったんだよね。優秀だから会長やりなよってやらされる人より、情熱的な人が会長やった方がおもしろい学校になりそうって」
「覚えてないなぁ……」
いい加減なわたしに葉亜斗はケラケラと笑う。
「おもしろい学校になりそうだよ? 児童会長にそんなプロジェクトを任せるのかって、ますます燃えちゃった」
「えぇ! わたしが焚きつけちゃった?」
「だね」
思わぬ昔話にあせる。
けれども葉亜斗は良き思い出の1ページとして記憶しているようだった。わたしのことが苦手なら最初から知らぬフリもできたのだから、わたしの対応は間違っていなかったらしい。
「結局、学校ではなにもおもしろいことはできなかったんだけどね」
重くなりすぎないようにか、葉亜斗はおどけた。
「今は?」
わたしは葉亜斗のキッチンカーを見渡した。
機能も充実していて、手書きのメニュー表も即席っぽいけど味があってかわいい。
葉亜斗にはキッチンカーがある。
葉亜斗はカウンターをひとなでした。
「おもしろくなってきてるかな。でもこうやって考えてみれば、なにかがきっかけというより、ひとつひとつの出会いが重なって、今、こうなってるのかも。上原さんに焚きつけられたときからずっとくすぶって、今はもうメラメラだよ」
薪をくべてくれるひとがいたのだろう。
葉亜斗はいいひとたちと出会ってきたんだなと、少しうらやましく思った。
現金支払いでおつりをもらうつもりが、ついうっかり小銭を出そうと硬化を数えはじめて、「ああそうだ」とまた大きいお金を財布から出す。
レジ店員の「早くしろ」という視線にも耐えつつ、毎日の参拝は滞りなく続いていた。
今までなんのこだわりも持たずに暮らし、ルーティン動画にも面白さを見いだせなかったわたしであるが、あの神社で目撃する見知らぬ女子高生に心動かされるとは不思議なものだ。
カラコロと賽銭箱に転がっていく10円玉。
神頼みの10円といっても、それはまだ自分の未来を悲観していない証だ。
その無記名の証は賽銭箱の底に溜まり続けた。
比嘉葉亜斗のキッチンカーは『ヒグラシヒガッチ』というとんでもないセンスの屋号で、本当にその日暮らしをしているかのような不定期で営業しているらしかった。
フォローして「サルサがほどよい辛さと酸味で最高」とコメントをつけたら、「タコライスも最高なんだから!」と返信がきて、また来てほしいということなのかなと深読みをしていると、すぐにその時はやってきた。
土曜日。場所はうちの会社近くにある公園。フリーマーケットが開催されるという。
出店するので来ないかという誘いがDMで届いた。
ランチメニューは一種なのだが、試しに「ゆし豆腐」も提供してみるという。
休みの日にバスに乗ってそこまで向かうのは初めてだった。
いつもと違う時間だからか、さすがに女子高生とは出会わなかった。
わたしだって休日の参拝はサボっている。
今日は奮発して100円だ。
1枚賽銭箱に放り投げる。
跳ねるように吸い込まれていく100円玉を見ながら、そういえば最初から特定の願掛けしていたわけではなかったと気づく。
なんとなく。幸せでありますように。
手を合わせながら、浮かんだ顔は髪をひとつにまとめて清潔感のある笑顔でまっすぐ見据えてくる比嘉葉亜斗。
柊さんごめんなさいって、まだなにもはじまってないのに、いわれたほうも困惑だろう。
葉亜斗のことはずいぶんと前から知っているようでいて、その実、初対面のような探り探りのやりとりに終始した。
わたしは葉亜斗のことをもっと知りたいのだろうか。
見た目の『なぜ』を解明したいからだとするなら、それは失礼な話なのかもしれない。
でも、向こうから誘ってくれるということは、不愉快なやりとりではなかったのではないかと、良い方に受け止める。
バスが停留し、空調のない炎天下に降り立った。
手に持っていたつばの広い帽子をかぶる。日傘の方がよかったかもしれない。まだ朝といえる時間帯でもすでに暑かった。
キッチンカーのようなエンジンのかかってない車内って実はものすごく暑いんじゃないだろうか。
開口部分が広いとはいえ、通常の店舗のような快適さはなさそう。
会社の近所はマンションが建ち並んでいるような土地柄、ファミリー層も多い。
マンションに囲まれた中にある公園は、ほどよく植樹されていて木陰もありながら見通しがいい。
出店者は準備に追われ、お客さんもちらほら歩いている。
バザーのような気軽な出店から昔ながらの古物商、ハンドメイド風の小物や朝採り野菜などなど、雑多に並ぶ。
葉亜斗のキッチンカーはすぐに見つかった。レモン色とスカイブルーのツートンカラーが目立つ。
朝でもお昼でのないという時間帯。並んでいる客はまだなかった。
やはり葉亜斗ひとりで切り盛りしているようだ。
車内で鍋の様子を見ている。
レモン色のスカーフで髪を結い、スカイブルーのエプロンを着けていて、先日よりもやる気出してるっぽい。
やっぱり女性の姿をしている葉亜斗が見慣れずに、緊張して息をつく。
初めて行くお店の暖簾をくぐるような気持ちで一歩踏み出す。
「まだ準備中?」
声をかけると葉亜斗はわたしに気づいて破顔した。両手を振ってくるのでわたしもそれに応える。
「いらっしゃい。ひとり?」
「この前一緒にいた同僚、デートなんだって。いつの間に?ってかんじだよ」
「その愚痴の吐き方。さては?」
「もう、わかってるなら聞かないでよ」
恋人がいないという近況報告を冗談として昇華させるとわたしたちは笑い合った。
葉亜斗はいつからその姿をしているのだろう。
今、この瞬間に初めて出会ったのだとするなら、必要のない情報でぐるぐると思考を巡らせることもないのに。それくらい葉亜斗は見た目とのギャップがない。
だけどわたしがよく知る三枚目の葉亜斗が背中合わせに存在しているようで、やっぱり少し落ち着かなかった。
この前と同様に自分について葉亜斗は語らない。
「お腹すいてる? ゆし豆腐ならすぐに出せるよ」
「じゃあ、いただく」
「トッピングも考えてみたんだ。これね」
葉亜斗は車の中から身を乗り出してメニュー書きを指した。
名称は『うちなーゆし豆腐』にしたようだ。
あたたかいだし汁におぼろ豆腐がたっぷり入ったおかゆ感覚の沖縄ソウルフードという説明があり、小口ネギがのっている写真があった。
別料金のトッピングは明太子、おぼろ昆布、もずくのナムル風、油揚げの醤油焼き。どれもおいしそうだ。
「入れてみたことないから、もずくにしようかな」
「さすが。もずくはもちろん、沖縄産ね」
「いいねぇ」
沖縄ではできたての温かいままの豆腐を売っているから、だし汁をかけるだけですぐに完成するが、やはりおぼろ豆腐をだし汁で煮たのだろうか。葉亜斗は慣れた手つきで寸胴から豆腐をすくって器に盛っている。
見とれていたら葉亜斗がちらりと振り返った。
「ねぇ。タコスミートもトッピングとしてありかな?」
ひき肉をチリソースで味付けしたメキシコ料理だけど、ご飯にかけたタコライスは沖縄でよく食べていた。
沖縄をウリにするならよさそうだ。
「ありだよ。ロコモコ丼のハンバーグとゆし豆腐もおいしかったもん。いや、むしろそぼろ状のほうが豆腐とマッチして食べやすそう」
「実はヘルシーだしね。タコスミートも、このあいだのハンバーグも、大豆ミートを混ぜてるんだ」
「ええ? そうなの? 普通に肉だと思ってた」
「大豆ミートのクセを消すのはちょっと苦戦したけどね」
おまたせと、どんぶり鉢に入ったゆし豆腐が差し出された。
琥珀色のだし汁からおぼろ豆腐が顔を出し、脇のほうに小口ネギともずくがのっている。ゆらめく湯気に、もずくナムルのごま油がふわりと香った。
「おいしそう。久しぶりのゆし豆腐」
支払いをするしないの一悶着があって、結局サービスということで宣伝に貢献することにした。
「ごゆっくり。とはいっても、テーブルが1つしか用意できてないんだけど」
葉亜斗が用意したのかと、キッチンカーの目の前にある円形のテーブルを見やると、すでにひとり座っていた。
立ち食いでもよかったのだが、目が合い「よければどうぞ」といわれてしまっては断りにくい。
「すみません、相席させてもらいます」
先客はわたしよりも少し年上に見える女性だった。
ひとりできたのだろうか。ウェーブした短い髪をひとつに結い、薄化粧の上品な顔立ち。黒い日傘を椅子に引っかけている。
彼女もゆし豆腐を食べたのか、空のどんぶり鉢とレンゲがひとつテーブルに置かれている。
4つある椅子の向かい側に腰掛けて、まずはだし汁と豆腐をすくって口に運ぶ。
かつお節がきいたシンプルな出汁。
豆腐はややしっかりしていて、沖縄の豆腐より塩味が少ない。
もずくはレンゲですくっても食べやすいように刻んであった。
濃いめの味付けでこれもだし汁とよく合う。忙しい朝でも、真夏の暑い日でも、また食べたくなるやさしい味だった。
だし汁まで飲み干せば、しっかり食事を取ったような満足感が得られた。
「わたしは油揚げにしたんですよ」
わたしが空になったどんぶり鉢をテーブルに置くと、女性は話しかけてきた。
「大豆ばっかりになっちゃったなと思ったけど、まったく別の食感だからおもしろかったわ」
「沖縄ではそばにも豆腐を入れますから、きっと豆腐ってなんにでも合いますよ」
「へぇ。そうね。いわれてみれば豆腐って何にでも合いそう。温かくても冷たくてもいいし。そういえば、ハートさんも沖縄出身っていってたけど、お知り合い?」
あまりに親しげな呼び方になんのことかと一瞬頭をひねったが、ハートといったら比嘉葉亜斗しかない。なんとなくマウントを取られているような気がしたが、勘ぐりすぎだろう。
そもそも彼女は葉亜斗をどこまで知っているのか。
待って。そもそもでいうなら、そもそも目の前の彼女も『彼女』という呼び方でいいのか?
混乱してきたものの、小さいときの葉亜斗の話題になったら困るので適当に答える。
「……えぇ、まぁ」
「そうなんだ。わたし、ハートさんの料理が好きでよく食べるの」
常連なのか。わたしよりも早く来て一番乗りでゆし豆腐を食すくらいにハマっているようだ。
葉亜斗はなにきっかけでこのメニューの着想を得たか話したのだろうか。わたしがそのきっかけだと気がついたからこその相席か。
だが、彼女は探りを入れるどころか自分のことばかりを話しはじめた。
「それでね、どんな食材が使われてるか食べながら検証しているうちにふと思いついたの。あ、これ使えるなって」
「家での料理にってことですか?」
「まぁ、そういうこともあるけど、染め物にね」
「染め物?」
どう繋がっていくのか、我々の関係性のように未知である。
彼女は目を細めて饒舌に語った。
「草木染めのワークショップをやってて。身近にある自然のもので布を染めるのよ。こんな都会でも外を歩いていたら使えるものが結構あってね。選定している枝葉をもらったり、料理人からは玉ねぎの皮とか」
「ええ? そんなものでも?」
「玉ねぎって意外と黄色っぽいきれいな色が出るの。だから、今度は紫玉ねぎの皮はどうだろうと思って。このあいだはサラダに紫玉ねぎが入ってたから、また使うことがあったら皮がほしいってお願いしてたんだ。とにかく、たくさん必要だから」
想像以上の常連だ。
不特定の場所へ追いかけていくのだから、葉亜斗にとってもうれしい客のはず。
「今日は紫玉ねぎをタコライスに使うらしいよ。お腹いっぱいになっちゃったから、それは持って帰ることにしたけどね、楽しみ」
まだ居座るつもりか。
彼女は人のよさそうな笑みを浮かべてキッチンカーを振り返った。葉亜斗は仕込みに集中していて、こちらの会話を気にかけている様子もない。
もし、不用意にわたしが葉亜斗の幼少時代を語り出したらとか、心配ではないのかな。
やっぱり彼女はすべてを知っている?
だとしても、こちらから聞いてみることはできない。
「全部売れるといいね」
彼女はそういって向き直った。それはもちろん率直にいって売れ残りがないほうがいい。
「ハートさんの作る料理って、なんか違うんだよね。お母さんが家族のために作る料理と、料理人が客のために作る料理と、やっぱりなにかが違うでしょ。ハートさんの料理はわたしのために作ってくれている気がしてきちゃうの」
わかる気がします、と相づちを打っているうちに、独り相撲をしているようで気抜けしてきた。
そもするとストーカーじみていて怖い。でも、きっと彼女は違う。
葉亜斗のバックボーンなんて関係なく、彼女は単純に『ヒグラシヒガッチ』のファンなのだ。親心みたいなもので、儲け度外視なところを心配しつつ、ずっと葉亜斗が好きなことを続けられたらいいのにって。わたしだってそう願ってる。
「あなたがゆし豆腐を食べているあいだ、ちらちら様子をうかがってたわよ」
「そうなんですか」
味わうのに夢中で全然気づかなかった。
「同郷の友人として、かな。もちろん料理人の目線も持ってるだろうけどね」
「……葉亜斗が料理に興味あったなんて、全然知らなかったです」
わたしには、そういうの、なにもない。
ルーティンどころじゃなく、趣味もやりたいこのもなにもないのだ。
その日暮らしをしているような葉亜斗を半人前扱いして、自分は定職に就いているというだけで、一日をただやり過ごしているにすぎない。
休みの日に出かけるのも久しぶり。テレビをネットに繋いでいたら、ついにレンタル店に出向くこともなくなったのだ。
別にいいんだよ。なにもなくたって。
普通に仕事しているだけで自分を褒めてあげられるんだけどさ。
たまに青臭く生きることの意味を問いたくなっちゃう。
そんな心情を察したわけじゃないだろうが、彼女はイスにかけてあったバッグを探ると一枚の名刺を差し出した。
「自然に触れながら丁寧に暮らすのも悪くないかもよ? 興味あったら」
あいまいにうなずきながら受け取った。
正直、興味はない。
面倒な行程が目白押しなんだろうなと、突っ込んで話しを聞くのも長くなりそうで、腰が引けていた。
丁寧な暮らしってのもわたしにはピンとくるワードじゃなくて、突き返したくなってくる。
だったらなにをすれば満足なんだろう。
もうすぐ30歳になるっていうのに、自分の機嫌の取り方も知らない。
あいまいな自分にずっとモヤモヤしている。
待っていたら誰かが開けた道を運んでくるわけじゃない。伴侶となる人がわたしを幸せにするって、そんな都合良くいくわけがない。
彼女は前のめりに勧めてくる。
「やってみておもしろいと初めて気づくこともあるじゃない。最初から興味あったらすでにやってるんだし。あとは実行。恋愛だってそうでしょ?」
「たしかに、そうですけど……」
ため息交じりになってしまった。
彼女は慰めてくれているらしい。重い空気にならないようにひとりで話し続ける。
「ハートさんね、あなたが明確に来るか来ないか返信しなかったから、どうなのかなぁって、心配してたよ」
迷ったのは事実だ。
断ると違う意味で避けていると勘違いされないかなとか、義理でいくほど親しくもないなとか。
でも結局重い腰上げて休日にまで出向いてきたのは、葉亜斗のことが気にかかったからだ。
キッチンカーで巡って営業している原動力はなんなのか。
わたしが今まで自分の幸せを願って頑張ってきた道筋は間違っていなかったのか。
そんなこと聞かれたって葉亜斗にわかるわけもないけど。
でも、葉亜斗が選んでここまでたどり着いた道筋にはすごく意味を感じたのだ。
勝手に。
勝手すぎて聞けない。
彼女はわたしを凝視して詮索を続けていた。
「やってくるのがどんな人なのかなって、空想で埋めたんだけどね」
彼女は口元に手を当てていたずらっぽく笑った。
よく見れば、その指には指輪があった。どうやら既婚者らしい。
「当てが外れたわ」
残念そうに首を振った。
つまり、男性が来ると想像していたってことか。
葉亜斗がいじらしく意中の人について語っていると思い込んでいたのだ。
この分では結婚しているのか恋人はいるのか根掘り葉掘り聞いているのではないか。それこそ親戚のおばちゃんみたいなお節介を焼いて葉亜斗を困らせてそうだ。
ひとしきり話して話題も尽きたのか、彼女は昼時まで時間を潰してくるといって会場内に消えていった。
人と会話するのがこんなにしんどいとは。
けれども、次に彼女と顔を合わせることがあれば案外会釈程度で終わるのかもと思っていた。
わたしがどんぶり鉢を持ってキッチンカーへ戻ると、葉亜斗はわたしの瞳の奥をのぞき込むようにいった。
「どうだった?」
どうだったとはあの彼女のことではなく食事の感想だろう。
わたしはゆし豆腐を口にしたときの温かくてほっとする時間を思い起こした。
「おいしかったよ。懐かしさを超えておいしかった。朝だけじゃなくて、休憩のコーヒー代わりにもいけるんじゃないかってくらい、お出汁もおいしい」
葉亜斗は一言も聞き漏らすまいとばかりに真顔でうなずいていが、途中で「ん?」と視線を斜めに見上げた。
「コーヒー……?」
「ああ、半分くらい冗談入っちゃったけど」
おどけてみせると、葉亜斗はハッとしたように両手を振った。
「ごめん、ごめん。なかなか率直にいってもらえることもないからさ、真に受けてどういうことか考えちゃった」
「こっちこそ伝わりにくくてごめん。ええと、だから……石焼き芋屋さんのように巡ってきたらいつでも食べたくなっちゃう恋しさ。いや違うな。焼き芋はたまにだから食べたいんだ。ゆし豆腐は毎日でもいい。こんなふうに他にお店が出ていて食べ歩きでも合間に入れられる軽い食事だし」
「なるほど、朝食にちょうど良くても、ランチにこれひとつではちょっともの足らない感じだね」
「ランチだったら汁物としてつけるとかかな」
「別に容器が必要になるね」
「そっか、そういう視点もね」
文化祭のノリでキッチンカーを始めていたらえらいことになる。
余らせないよう食材を発注し、使い捨ての容器を使うのならコストもそれだけかかる。持ちかえる側の不便さとか、コンビニ弁当や飲食店と比べての価格設定だったり、考慮すべき点はたくさんだ。
「石焼き芋屋さんの発想はいいね。いろんなところに巡回して、たまにやってきたとき、また食べたいって思われるのはうれしい」
「神出鬼没だっていわれてるみたいだけど」
ひとをオバケみたいにと、葉亜斗は不服そうに口をとがらせながらも目元は笑っていた。
「あまり一ヶ所にいたくなくて。接客業をしているのにふしぎに思うだろうけど、人と深く関わるのが苦手っていうか。常連さんとお話しているうちに、どんどん自分のことを話さないといけないような気がして、追い込まれるんだよね」
ギクリとした。卒業してからの葉亜斗がどう変わっていったのか、興味がないわけではなかった。
「それはわかる」と、わたしは悟られないようしみじみといった。
「人と話しをしてると疲れてくるときがあるじゃない。でもさ、ひとりぼっちが恥ずかしいなんて思う年代は過ぎたけど、今度はひとりだと寂しく思うこともあって。葉亜斗がどんな一日を過ごしているのか気になったんだよね。わたしなんか職場と自宅の往復で、関わりあるのも同僚で。子供のころ描いていた大人の世界と全然違う。大人って、もっと大きくて楽しい世界にいるのかと思ってた」
「上原さんって、なんか壮大だよね」
意外な返答に驚く。今、思いっきりこぢんまりとした話しをしたのに、葉亜斗にはそう聞こえなかったらしい。
「小学生のころ、わたしが児童会長に立候補したこと覚えてる?」
「むしろ、それを真っ先に思い出したよ」
やっぱりと葉亜斗はうなずいた。
「みんなやめとけって、からかってたけど、上原さんは違ったんだよね。優秀だから会長やりなよってやらされる人より、情熱的な人が会長やった方がおもしろい学校になりそうって」
「覚えてないなぁ……」
いい加減なわたしに葉亜斗はケラケラと笑う。
「おもしろい学校になりそうだよ? 児童会長にそんなプロジェクトを任せるのかって、ますます燃えちゃった」
「えぇ! わたしが焚きつけちゃった?」
「だね」
思わぬ昔話にあせる。
けれども葉亜斗は良き思い出の1ページとして記憶しているようだった。わたしのことが苦手なら最初から知らぬフリもできたのだから、わたしの対応は間違っていなかったらしい。
「結局、学校ではなにもおもしろいことはできなかったんだけどね」
重くなりすぎないようにか、葉亜斗はおどけた。
「今は?」
わたしは葉亜斗のキッチンカーを見渡した。
機能も充実していて、手書きのメニュー表も即席っぽいけど味があってかわいい。
葉亜斗にはキッチンカーがある。
葉亜斗はカウンターをひとなでした。
「おもしろくなってきてるかな。でもこうやって考えてみれば、なにかがきっかけというより、ひとつひとつの出会いが重なって、今、こうなってるのかも。上原さんに焚きつけられたときからずっとくすぶって、今はもうメラメラだよ」
薪をくべてくれるひとがいたのだろう。
葉亜斗はいいひとたちと出会ってきたんだなと、少しうらやましく思った。