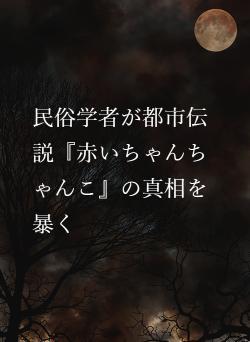そろそろ昼休みが終わる。
しゃべりたおしたニシジマは満足げに立ち上がった。
「あー、おいしかった。玉子のってなかったけど、ロコモコ丼におぼろ豆腐とか、はじめて食べた」
「え? あれ、おぼろ豆腐っていうの?」
「ほかになんていうのよ」
「ゆし豆腐。だし汁とかに入ってて、温かいのが普通だけど」
「そうなの? ゆし豆腐? 聞いたことないけど」
わたしたちはお互いに顔を見合わせて答えの出ないまま首をかしげた。
「ウエハラって、沖縄出身だっけ?」
「うん。ゆし豆腐って沖縄の方言かな。それとも、実際、違う製法で別ものなのかな」
「どうだろ。せっかくだからキッチンカーの人に聞いてみようか」
ニシジマはお店の人にも気さくに声をかけるタイプだった。
料理に興味があるのかといったらそうでもないようで、顔なじみになって損はないという理屈らしい。
キッチンカーの女性はちょうど片付けをしているところだった。
用意した分はすべてはけたのだろう。まだ粘ってみようかなという後ろ髪引かれる思いではなさそう。
外に出したボードなどをテキパキと片付けている。
さっきはよく見ていなかったけど、どうやらひとりで営業しているようだ。
わたしたちと同年代くらい。思い切ったことをするもんだなぁと感心した。
500円のランチってどれだけ売れば儲けが出るのか。
手軽にはじめられるのがキッチンカーとはいうけれど、仕入れからなにから全部ひとりでやるとなったら、経験のない者が手軽にはじめようだなんて、それはそれで軽率すぎるだろう。
「ごちそうさまでした」
ニシジマが声をかけると女性は「ああ、どうも。どうでしたか?」と愛想よく答えた。
「おいしかったですよ。あれだけ色とりどりそろえて料理しようと思ったら、ムリってなっちゃいますし。今日はゲットできてラッキーでした」
「それはよかった」
「あの豆腐っておぼろ豆腐ですよね。汲み上げたてってかんじがおいしくて」
「そうなんですよ。知り合いの豆腐屋が朝から作ってて。自分もそのおいしさに感動して。実は自分、沖縄出身で――」
言い終わらないうちにニシジマは「え! うそ! この子も沖縄」とわたしの背中を押した。同郷だからって縁をつなげようとしていることに戸惑いつつ、「どうも」と頭を下げた。
すると女性は「ああ、やっぱり!」と見開いた目でこちらを見つめた。
なにがやっぱりなのか、わたしは沖縄出身であることを当てられることはないくらいには薄い顔をしている。
例の振られた彼には幸まで薄いといわれほどだ。
女性は無遠慮にまじまじとわたしの顔を見る。
「上原さんだよね?」
いきなり名前を呼ばれてちょっとビビる。どこかで会ったことがあるのだろうか。
さらに戸惑っていると女性は気まずそうに頭をかいた。
「比嘉だけど……」
ひが、ひがひがひが……。
知り合いの比嘉さんが多すぎてわからない。
けれども相手もわたしと同じくらいの年格好だから、同級生かその姉妹といったところか。
曖昧に笑ってすごそうかともしたが、わりと近しい人だったら困るなと考えあぐねていたら先方は察してくれたようだった。
「小学校と中学校が一緒だった、比嘉葉亜斗……」
その名前にハッとなって、思い当たった。
ハート。
そんなキラキラネーム、忘れるはずがない。
そこからするすると思い出していった。
そう、比嘉葉亜斗。小学生の時、周囲の同意を得られぬまま児童会長に立候補したものの、あまりに予想通りの展開過ぎて笑いの渦の中落選した比嘉葉亜斗ではないか。
本人はとても満足そうに「ありがとう」と、手当たり次第に握手を求めて、わたしもその手をしっかり握られたひとりだった。
いつも楽しそうで、どんなことにもめげなかった比嘉葉亜斗。
あの存在感があった太い眉は整えられていて、別人のような顔つきに見えるが、人懐こい目元はたしかに面影がある。
ぽっちゃり気味だった体型も、痩せはしていないが、かっちりとした体躯に変貌して、すっかり出来る調理人風情。
年に何度か帰郷しても顔を合わせたことも噂話も聞いたことがなかったのに、こんなところで出くわすとは。すぐに思いつかなかったはずである。
って。
いやいや、そうじゃない。比嘉葉亜斗は男の子だったよ?
目の前にいる女性は手慣れたメイクをしている。
少しばかりエキゾチックな印象を持つが華やかな笑顔で応対してくれて、声も男性っぽくはない。
パッと見たときから自然に女性だと受け止めていた。
小中学生のころの比嘉葉亜斗を思い起こしても、ああ、やっぱりなぁって、全然まったく思わない。
どうして?と、いきなりそんなことも問えずに取りなす。
「……ごめん。気づかずに通り過ごすところだった」
「そっか。接客しているときから視線送ってたんだけどな」
「そうなの? 全然気づかなかった」
そばでやりとりを見ていたニシジマからも笑みがこぼれるほど葉亜斗はおおらかだった。
やっぱり変わってないところは変わってない。
なんかこういう三枚目なところがあった。いじられキャラではあったけど、大人となった今では懐の深さを感じる。
「これだから。仕事でもうっかりさんで」
ニシジマに軽口たたかれ、「ちょっと」と小突く。
だがこの場でわたしが気づけなかった理由を明かすわけにもいかず、口ごもった。
ニシジマは気にもせずにぐいぐい迫る。
「比嘉さんは店舗は持ってないんですか」
「今のところ、キッチンカーだけで。小回りきくかんじが性分に合ってるみたいなんです。おかげで、バイト掛け持ちから抜け出せないですけど」
自嘲気味にいうが、どこか楽しげで、帳簿を睨みつけるような毎日ではないことがうかがえる。
そういう暮らしなら所帯持ちではなさそう――というのも、わたしの物差しで見ているだけなのかもしれないが。
結婚するならちゃんと収入があること。
将来家族となる子供のことを考えればそうなるんだけど。
どう生きていくのか。同じ方を向いた人と出会えたら、それが一番。
そうはいっても、出会いからして難しい。
ニシジマじゃないが、結婚に関するもろもろをすりあわせしてから付き合い始めるなんて、非現実的だ。
そう考えればマッチングアプリは手間もかからず合理的ということになる。
『同郷』という項目があるのなら、偶然の再会も故意的に用意できそう。
開運じゃなくて超現実的だ。マッチングアプリもありだな。
「ちょっと」
ニシジマに小突かれて我に返る。整えられた眉根を寄せてこちらを見ていた。
「沖縄出身なら、さっきいってた、なんだっけ? なに豆腐?」
「ゆし豆腐」
即答すると葉亜斗は「ああ、そうそうゆし豆腐」と懐かしそうにうなずいた。
「島豆腐とかもよく食べたよなぁ」
島豆腐か。まさにふるさとの味を思い起こしてそれにすがりたくなってきた。
「モーニングとかやってないの? だし汁に入ったあったかいゆし豆腐、食べたいんだけど。おかゆみたいでほっとするんだよね」
何気なくいったらニシジマが横から割り込んでくる。
「そうだったらモーニングとかいってないで、比嘉さんところに行って、朝、作ってもらえばいいじゃない」
「な、なに、いってるの」
さらりととんでもないこと言い出すニシジマにしどろもどろになる。
モーニングだよ。行くってもうそれは泊まって朝食べるってことにならないか。
ニシジマは葉亜斗が男性だって気づいているのだろうか。やけに押してくる。
だとしても、葉亜斗が女性を恋愛対象としているかわからないし、友達になるにしたって、たとえば、家まで遊びに行ってこちらは友達のつもりでも、男の家に泊まりに来ておいてそんなつもりはなかったとか言うのかよとか、何らかの齟齬があったり。どう確認すべきなのかわからない。
そう、わからないのだ。突然すぎて葉亜斗とどう接したらいいのか。
否定的な感情ではない。ただただわからない。
「うん、いいね」
葉亜斗は営業用とは思えない笑顔を向けた。ちょっとばかりドキッとする。
「うん、モーニング、いいね。『うちなーゆし豆腐がゆ』とか沖縄っぽい名前つけて」
……ん? メニューの話し? うちに来いよとかじゃなくて? なにげにさらりとかわされている?
ひとりジタバタ舞い上がっただけなのかと恥ずかしくなる。
気づかれぬよう、ふんふんとうなずく。
「試作品ができたら食べに来てよ」
わたしの中ではいまだ三枚目の比嘉葉亜斗なのに、スマートな誘い方に心がざわめく。
それはうちに来てほしいということだろうかと、逡巡した。
するとすぐさま葉亜斗が言葉を繋ぐ。
「あ、いや、朝とかじゃなくても、なんだったら時間外のキッチンカーで作るし」
ようやく着地点が見えてきてわたしもそれに答える。
「うれしい。食べたいよ。インスタも見てるし。いつでも誘って」
実のところインスタをチェックしているのはニシジマだが、あとで教えてもらおう。
まだなにも始まってない柊さん。
そして偶然再会を果たした比嘉葉亜斗。
わたしのことが気になるならしっかりたぐり寄せてくれって、それはさすがに自分のことを買いかぶりすぎか。
もし、この先を一生一緒に過ごすとなれば、もっともっと知っておきたいことがある。
お互いの心が少しずつ近づいていくのなら、見えてなかったこともわかるものなのかな。
「神社の願掛けはどうなりそう?」
葉亜斗と別れたあと、ニシジマは耳打ちしてきた。
「うちの社員なんでしょう?」
ニシジマには同じ人を狙っているという予感みたいなのがあるのだろうか。それには曖昧にはぐらかした。
「それこそご縁があればね」
「やっぱりウエハラはウエハラだ。のんきすぎるよ」
やっぱりなのはニシジマだ。なんもわかってなかった。鍵を握っているのはわたしたちの方じゃないってことを。
しゃべりたおしたニシジマは満足げに立ち上がった。
「あー、おいしかった。玉子のってなかったけど、ロコモコ丼におぼろ豆腐とか、はじめて食べた」
「え? あれ、おぼろ豆腐っていうの?」
「ほかになんていうのよ」
「ゆし豆腐。だし汁とかに入ってて、温かいのが普通だけど」
「そうなの? ゆし豆腐? 聞いたことないけど」
わたしたちはお互いに顔を見合わせて答えの出ないまま首をかしげた。
「ウエハラって、沖縄出身だっけ?」
「うん。ゆし豆腐って沖縄の方言かな。それとも、実際、違う製法で別ものなのかな」
「どうだろ。せっかくだからキッチンカーの人に聞いてみようか」
ニシジマはお店の人にも気さくに声をかけるタイプだった。
料理に興味があるのかといったらそうでもないようで、顔なじみになって損はないという理屈らしい。
キッチンカーの女性はちょうど片付けをしているところだった。
用意した分はすべてはけたのだろう。まだ粘ってみようかなという後ろ髪引かれる思いではなさそう。
外に出したボードなどをテキパキと片付けている。
さっきはよく見ていなかったけど、どうやらひとりで営業しているようだ。
わたしたちと同年代くらい。思い切ったことをするもんだなぁと感心した。
500円のランチってどれだけ売れば儲けが出るのか。
手軽にはじめられるのがキッチンカーとはいうけれど、仕入れからなにから全部ひとりでやるとなったら、経験のない者が手軽にはじめようだなんて、それはそれで軽率すぎるだろう。
「ごちそうさまでした」
ニシジマが声をかけると女性は「ああ、どうも。どうでしたか?」と愛想よく答えた。
「おいしかったですよ。あれだけ色とりどりそろえて料理しようと思ったら、ムリってなっちゃいますし。今日はゲットできてラッキーでした」
「それはよかった」
「あの豆腐っておぼろ豆腐ですよね。汲み上げたてってかんじがおいしくて」
「そうなんですよ。知り合いの豆腐屋が朝から作ってて。自分もそのおいしさに感動して。実は自分、沖縄出身で――」
言い終わらないうちにニシジマは「え! うそ! この子も沖縄」とわたしの背中を押した。同郷だからって縁をつなげようとしていることに戸惑いつつ、「どうも」と頭を下げた。
すると女性は「ああ、やっぱり!」と見開いた目でこちらを見つめた。
なにがやっぱりなのか、わたしは沖縄出身であることを当てられることはないくらいには薄い顔をしている。
例の振られた彼には幸まで薄いといわれほどだ。
女性は無遠慮にまじまじとわたしの顔を見る。
「上原さんだよね?」
いきなり名前を呼ばれてちょっとビビる。どこかで会ったことがあるのだろうか。
さらに戸惑っていると女性は気まずそうに頭をかいた。
「比嘉だけど……」
ひが、ひがひがひが……。
知り合いの比嘉さんが多すぎてわからない。
けれども相手もわたしと同じくらいの年格好だから、同級生かその姉妹といったところか。
曖昧に笑ってすごそうかともしたが、わりと近しい人だったら困るなと考えあぐねていたら先方は察してくれたようだった。
「小学校と中学校が一緒だった、比嘉葉亜斗……」
その名前にハッとなって、思い当たった。
ハート。
そんなキラキラネーム、忘れるはずがない。
そこからするすると思い出していった。
そう、比嘉葉亜斗。小学生の時、周囲の同意を得られぬまま児童会長に立候補したものの、あまりに予想通りの展開過ぎて笑いの渦の中落選した比嘉葉亜斗ではないか。
本人はとても満足そうに「ありがとう」と、手当たり次第に握手を求めて、わたしもその手をしっかり握られたひとりだった。
いつも楽しそうで、どんなことにもめげなかった比嘉葉亜斗。
あの存在感があった太い眉は整えられていて、別人のような顔つきに見えるが、人懐こい目元はたしかに面影がある。
ぽっちゃり気味だった体型も、痩せはしていないが、かっちりとした体躯に変貌して、すっかり出来る調理人風情。
年に何度か帰郷しても顔を合わせたことも噂話も聞いたことがなかったのに、こんなところで出くわすとは。すぐに思いつかなかったはずである。
って。
いやいや、そうじゃない。比嘉葉亜斗は男の子だったよ?
目の前にいる女性は手慣れたメイクをしている。
少しばかりエキゾチックな印象を持つが華やかな笑顔で応対してくれて、声も男性っぽくはない。
パッと見たときから自然に女性だと受け止めていた。
小中学生のころの比嘉葉亜斗を思い起こしても、ああ、やっぱりなぁって、全然まったく思わない。
どうして?と、いきなりそんなことも問えずに取りなす。
「……ごめん。気づかずに通り過ごすところだった」
「そっか。接客しているときから視線送ってたんだけどな」
「そうなの? 全然気づかなかった」
そばでやりとりを見ていたニシジマからも笑みがこぼれるほど葉亜斗はおおらかだった。
やっぱり変わってないところは変わってない。
なんかこういう三枚目なところがあった。いじられキャラではあったけど、大人となった今では懐の深さを感じる。
「これだから。仕事でもうっかりさんで」
ニシジマに軽口たたかれ、「ちょっと」と小突く。
だがこの場でわたしが気づけなかった理由を明かすわけにもいかず、口ごもった。
ニシジマは気にもせずにぐいぐい迫る。
「比嘉さんは店舗は持ってないんですか」
「今のところ、キッチンカーだけで。小回りきくかんじが性分に合ってるみたいなんです。おかげで、バイト掛け持ちから抜け出せないですけど」
自嘲気味にいうが、どこか楽しげで、帳簿を睨みつけるような毎日ではないことがうかがえる。
そういう暮らしなら所帯持ちではなさそう――というのも、わたしの物差しで見ているだけなのかもしれないが。
結婚するならちゃんと収入があること。
将来家族となる子供のことを考えればそうなるんだけど。
どう生きていくのか。同じ方を向いた人と出会えたら、それが一番。
そうはいっても、出会いからして難しい。
ニシジマじゃないが、結婚に関するもろもろをすりあわせしてから付き合い始めるなんて、非現実的だ。
そう考えればマッチングアプリは手間もかからず合理的ということになる。
『同郷』という項目があるのなら、偶然の再会も故意的に用意できそう。
開運じゃなくて超現実的だ。マッチングアプリもありだな。
「ちょっと」
ニシジマに小突かれて我に返る。整えられた眉根を寄せてこちらを見ていた。
「沖縄出身なら、さっきいってた、なんだっけ? なに豆腐?」
「ゆし豆腐」
即答すると葉亜斗は「ああ、そうそうゆし豆腐」と懐かしそうにうなずいた。
「島豆腐とかもよく食べたよなぁ」
島豆腐か。まさにふるさとの味を思い起こしてそれにすがりたくなってきた。
「モーニングとかやってないの? だし汁に入ったあったかいゆし豆腐、食べたいんだけど。おかゆみたいでほっとするんだよね」
何気なくいったらニシジマが横から割り込んでくる。
「そうだったらモーニングとかいってないで、比嘉さんところに行って、朝、作ってもらえばいいじゃない」
「な、なに、いってるの」
さらりととんでもないこと言い出すニシジマにしどろもどろになる。
モーニングだよ。行くってもうそれは泊まって朝食べるってことにならないか。
ニシジマは葉亜斗が男性だって気づいているのだろうか。やけに押してくる。
だとしても、葉亜斗が女性を恋愛対象としているかわからないし、友達になるにしたって、たとえば、家まで遊びに行ってこちらは友達のつもりでも、男の家に泊まりに来ておいてそんなつもりはなかったとか言うのかよとか、何らかの齟齬があったり。どう確認すべきなのかわからない。
そう、わからないのだ。突然すぎて葉亜斗とどう接したらいいのか。
否定的な感情ではない。ただただわからない。
「うん、いいね」
葉亜斗は営業用とは思えない笑顔を向けた。ちょっとばかりドキッとする。
「うん、モーニング、いいね。『うちなーゆし豆腐がゆ』とか沖縄っぽい名前つけて」
……ん? メニューの話し? うちに来いよとかじゃなくて? なにげにさらりとかわされている?
ひとりジタバタ舞い上がっただけなのかと恥ずかしくなる。
気づかれぬよう、ふんふんとうなずく。
「試作品ができたら食べに来てよ」
わたしの中ではいまだ三枚目の比嘉葉亜斗なのに、スマートな誘い方に心がざわめく。
それはうちに来てほしいということだろうかと、逡巡した。
するとすぐさま葉亜斗が言葉を繋ぐ。
「あ、いや、朝とかじゃなくても、なんだったら時間外のキッチンカーで作るし」
ようやく着地点が見えてきてわたしもそれに答える。
「うれしい。食べたいよ。インスタも見てるし。いつでも誘って」
実のところインスタをチェックしているのはニシジマだが、あとで教えてもらおう。
まだなにも始まってない柊さん。
そして偶然再会を果たした比嘉葉亜斗。
わたしのことが気になるならしっかりたぐり寄せてくれって、それはさすがに自分のことを買いかぶりすぎか。
もし、この先を一生一緒に過ごすとなれば、もっともっと知っておきたいことがある。
お互いの心が少しずつ近づいていくのなら、見えてなかったこともわかるものなのかな。
「神社の願掛けはどうなりそう?」
葉亜斗と別れたあと、ニシジマは耳打ちしてきた。
「うちの社員なんでしょう?」
ニシジマには同じ人を狙っているという予感みたいなのがあるのだろうか。それには曖昧にはぐらかした。
「それこそご縁があればね」
「やっぱりウエハラはウエハラだ。のんきすぎるよ」
やっぱりなのはニシジマだ。なんもわかってなかった。鍵を握っているのはわたしたちの方じゃないってことを。