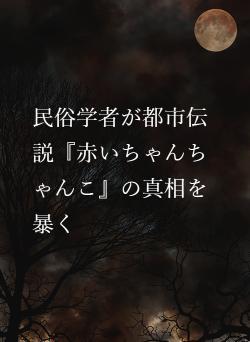「あれだけ就活に労力を注いだっていうのに」
「もはや仕事にも飽きている」
生まれも育ちも違うけれど、上の句詠んだら的確な下の句が返ってくるっていうくらい、同期のニシジマはわたしとそっくりな女だった。
とにかくちゃんとした仕事にありつかないと人生の転落が始まるとばかりに身を粉にして就活していたのに、「ちゃんとした」なんて釈然としない思いの丈でつかんだ仕事は、人生の繋ぎでしかなくなっていた。
どこかの政治家がいいだした『輝いてる女性』とはすべての人を指すわけではない。
輝いている女性になるためには働きながら恋愛をし、結婚をし、出産をし、育児をして完成されるというすり込みに、わたしたちはまんまと感化されていたのである。
二十代であるわたしは、結婚しないという幸せについては考えてみたことがないし、誰もそれを応援していない。
自分が輝いていることを証明するために、結婚という道を選ばず、ひとりで生きたきゃ勝手に生きればいいじゃんって、それはそうなんだけど。
次なる人生の分岐点はずばり、結婚。
結婚するかしないか。それはどこの会社に勤めるかよりも重大な選択なのだ。たぶん。
「いろいろ試してわかったのは、合コンで知り合った男より社内婚がベストだってことね」
「そうだね」と同意をしておく。
昼休み、広場に設けられたパラソルの下、キッチンカーのワンコインランチを運良く手にしたわたしとニシジマは舌鼓を打っていた。
メニューはひとつ。
その日によって違うらしいが、きょうのメニューは『彩り野菜と肉々しく変身したロコモコ豆腐』。
タイトルに全部詰め込まれたライトノベルみたいにそのまんまだった。
サイズは小さめだけど、ひとつのカップに全部入っている。
ご飯のかわりによそってあるのはゆし豆腐。その上にはベビーリーフと紫玉ねぎのスライスを合わせたサラダと、ミニサイズのハンバーグ。サルサ風のトマトドレッシングがかかっていて、どこをすくい取っても堪能できる。
ゆし豆腐は温かいものだって思っていたけど、スパイスがきいたドレッシングとよくあって、冷たくてもおいしい。
ハンバーグも冷めてはいるが、硬くなく、しょうがが効いていて、食感がまさに肉々しい。なのに油っぽくなくて、あっさりめだ。
お得感でつい饒舌になってしまいそうだが、そろそろ屋外での飲食が厳しくなってきているこの暑さ。やっぱり冷房のついた室内に戻ればよかった。
だというのに、早めに切り上げて戻ろうともせず、ニシジマは猛烈に話しはじめた。
「ミキちゃんのことは手近な男ですませちゃってなんて思ってたけど、同僚ってのはある程度人となりがわかるし、身元もはっきりとしてて、会社にも毎日来てることも知ってて、給料もどの程度かわかるでしょ。もっとあればいいと思うけど、少なくとも職業偽ってたり、詐欺ってことはない。自分だって焦る年齢ではないけど、もしかしてこの人自分に興味あるんじゃないの?って人に出会うと、どういうわけか焦るのよ。相手がどんな人なのか、自分が本当はどう思っているか、そんなことよりなんかしら発展しそうなら引き留めなきゃって、焦ってくるの。こんなチャンス二度とないって」
言っちゃ悪いがニシジマは普通の女だ。
わたしも同類だからわかる。気のあるそぶりをされて困るほどモテはしない。
だからといってすぐに食いつくのは考えものだ。一生一緒に過ごす相手をそう易々と決められない。けれども簡単に運命の出会いなんてない。
そんな堂々巡り。
「どこかでスパッと決めなきゃなんないのよ」
ニシジマは固く握りしめたスプーンで一文字に空を切るような仕草をした。
それはまるで恋愛不得手なわたしにレクチャーしているみたいだったが、ニシジマとて浮いた話はまるでない。
あるのなら恋愛自慢のひとつやふたつするだろう。
「そんなこといって、言い寄られてつなぎ止めておきたくなるような男と出会った経験あるの?」
「あるからいってるんでしょ。貢いだのがボーナス程度で助かった」
「いや、助かってないし」
意外な失敗談を聞かされて、ニシジマもやはりわたしと同様、男を見る目がないことが知れた。
わたしには大学生時代からずるずると付き合ってきた恋人がいた。
思い返せば講義の時にたまたま隣の席に座っただけという簡単な出会いであったが、このまま続いていくことにもどういうわけか不安はなかった。
ただ、向こうはそうは思っていなかったらしい。
わたしよりちょっぴり結婚願望が強くて少しばかり従順そうな女を見つけると、あっさりわたしに別れを言い渡して結婚してしまったのだった。
腹を立てるのは惨めだと思っていた。
将来のことを具体的に話したことはない。
まさか捨てられるとは想定していなかったけど、今はまだ行き遅れにならなかったのが幸いだと許してしまうわたしにニシジマはあきれていた。
「慰謝料を取れるくらいの口約束はしておくべきだったわね」と。
だが、逆にむしり取られていたとは。
おしゃれなランチばかりしていたら資金が尽きたといっていたが、なるほど、ランチ代をケチりたくなるわけだ。
わたしたち、ツイてないだけなのかな……。
アスファルトの照り返しを避けるように天を仰ぐ。パラソルの骨組みが見えただけだった。
つられるようにしてニシジマもパラソルを見上げるそぶりをしているのが視界に入ってきた。
そんなところに神様なんているわけない。だけど……。
「わたしもね、合コンより神頼みだなって思ってたの」
そういうとニシジマは「いやいや」と、喉をつまらせそうになりながら首を振った。
「話聞いてた? 合コンより社内恋愛だねっていってたんだよ。まったく共感できないんだけど」
ツレないニシジマの気持ちはよくわかる。
いい加減なようでいて、わりと現実的に人生の節目を通り抜けてきたわたしたちが、紆余曲折辿り着いたよりどころが『神頼み』だなんて。
「神頼みってどういうことよ?」
ニシジマは声が裏返る寸前になりながら問いただす。だが、急にハッとしたように付け加えた。
「べつにいいのよ。宗教観はひとそれぞれだし、何を信じて何を心のよりどころにするのか、いいんだけど。突然さみしい女に見えてきてちょっとびっくりしただけ」
そうなのか。さみしい女に見えたのか。
それをハッキリ言うニシジマもどうかと思うが、理解はできる。
長く付き合っていた恋人と別れたことを知られているだけに、勝手に脳内補完されてしまったんだな。
「気にしないで。ルーティーンみたいなものだから」
軽くあしらうと、ニシジマはぽかんとしていた。
「最近ね、家の近くの神社で毎日顔を合わせる女子高生がいるの」
「ちょっと待って、男子高校生でもなく、女子高生?」
「話しは最後まで聞きなさいよ」
違う方向へ勘違いしはじめたニシジマを制して話しを続けた。
住んでいるアパートからバス停までの道のりには神社がある。
実家を出てからずっとそのアパートに住み続けているわたしにとっては何度も前を通り過ごしていた馴染みある神社だが、祀られているのがどんな神なのかも知らない。
どこにでもありそうな簡素な神社だから、古事記に出てくるような有名な神様を祀っているというのではなく、この土地の氏神や鎮守といったところだろう。
その女子高生は学校に行く前に立ち寄っているようで、制服姿に大きなトートバッグを肩にかけ、神社の階段を下りてくるところによく出くわす。
きっと近くに住んでいて、一番近くにある神社だからついでに参拝しているのだろう。
「足繁く通ってるから大学受験祈願ってところかな。案外、恋愛成就ってことも考えられるけど。それとも普通に小さいころからの日課かな。でも、今どきめずらしいよね、毎日神社に参拝なんて」
「ウエハラ、あなた忘れてるよ。自分が高校を卒業してからもう10年が経とうとしていることに」
10年という年月がさらりと過ぎ去っていることにおののくも、「べつに、女子高生気取ってるわけじゃないし」と、もの申しておく。
ニシジマは諭すように身を乗り出した。
「あのね。もはや高校生なんて異次元だから。移り変わりの早い世の中で、唐突にあそこは御利益あるとかいう都市伝説が生まれたりするし、そもそも彼女たちの間でお百度参りが流行ってるのかもしれない」
「お百度参り?」
「毎日毎日、百日かけて参拝して願い事を成就させること。百日もかけてられないときとか、緊急を要するときは一日で百回お参りするの。鳥居から拝殿の前までを行き来してね」
「神頼みに否定的なのに、そんなことは知ってるのね」
「普通の女子並みにパワースポットとか興味ないわけじゃないよ。でもそれって『すがる』というよりレジャー感覚だよね」
へぇ、と相づちを打つ。
まぁ確かに、占いとかおまじないとか、女子が一度は通る道だ。
スマホを片時も離さず常に情報をチェックしているニシジマなら、やってみようとは思わなくても知っていそうではあった。今日も、お目当てのキッチンカーがここへやってくる情報も得ていたし。
ニシジマは最後までとっておいたミニトマトを名残惜しそうにかみしめた。
「それで。どんな神が祀られているかもわからない神社なのに、その女子高生に感化されてウエハラも参拝を?」
「まぁね。二、三分早く出てくればいいだけのことだし、なんだか、ピピッてきたしね」
「毎日目の前を通っていた神社にいきなり運命感じるとかよくわかんないけど」
わたしとニシジマの間に共感は生まれなかったようだ。
じゃあわたしもやってみようというフットワークの軽い年代はもう過ぎ去ったのかもしれない。
ニシジマは現実的なことを聞いてきた。
「ちなみにお賽銭はいくら?」
「一回十円」
「せこくない?」
ニシジマは甲高い声を上げた。わたしは頬を膨らませて抗議する。
「そんなもんでしょ。それこそ百回で千円だよ。千円の賽銭なんてしたことある?」
「百回も参拝したの?」
「お百度参りなんて知らなかったから数えてないけどさ」
「……ウエハラ。なににやけてるの」
にやけるわたしになにかを察知したのか、ニシジマは背もたれにのけぞって露骨に不機嫌な顔をした。
「別に」と、しらを切る。
「御利益があったのか」
詰め寄るニシジマに首をかしげてすっとぼける。
「やっぱり。やっぱり職場か」
「そんなんじゃないよ」
とぼけてみるが、ニシジマには通用しなかったようだ。すべてを悟って悔しそうに顔をゆがめた。
「わたしより早く当たりを付けていたとは」
「人聞き悪いな。こういうのはね、ピピピだよ。ニシジマもお百度参りしてみなよ。ピピッときた神社ならどこでもいいんだよ。こう、引き寄せるっていうかさ――」
「もういい、もういいよ。神社行くぐらいなら開運アプリでも探すわ」
本当にそのつもりなのか、テーブルに伏せておいたスマホを取って慣れたように片手で操作する。
焦ってないと余裕をかましながら、これはつけ込まれるフラグが立ってるんじゃないかと心配になってくる。
「ねぇ、そのうちマッチングアプリを開運アプリとかいったりしないよね?」
ニシジマは顔も上げず余裕ぶって答える。
「まさか。出会いは社内で求めることにしたんだから。ミキちゃんもそうだけど、ウエハラまで情報をつかんでいなかったとは。不覚だわ」
「情報っていわれても……付き合ってるとかじゃないよ? そんな噂なんてまだなにも――」
「なにのんきなこといってんの。まだ始まってもいないなら、こっちはそのつもりっていうオーラ全開でいきなさいよ。一度失敗してるんだから」
「ニシジマにいわれたくないわ」
口先だけは怒っておいて、腹の中はそうでもなかった。
給湯室で入れてきたマイボトルの冷たいお茶を飲み干す。
実は最近ちょっと接近中のひとがいる。経理部の柊さんだ。
大きくもない会社だから柊さんの顔は前から知っていた。
給湯室で顔を合わせたこともある。
エレベーターで乗り合わせたときにふたりだけの気まずい空間をやり過ごしたこともある。
ついでのように誘われた飲み会で向かい合ったこともある。
駅のホームで肩がぶつかって頭を下げたら柊さんだったこともある。
コピー機の用紙がつまったとき、たまたま通りかかった柊さんが対応してくれて、初めてまともに会話した。
正直いって最初から意識していたわけではない。なのに、柊さんとはなんとなく誰よりも顔を合わせているような気がしていた。
マイボトルはおそろいだ。
とはいっても、一緒に買いに行ったのではない。わたしが持っているのを見て柊さんがちょうどいいサイズ感だと気に入り、どこで購入したかを聞かれたのだ。
コツコツと参拝しているような積み重ねに、「こっちはそのつもり」っていうオーラをまとわりつかせなくても、連絡先を聞かれるまであとちょっとかなって勝手に思っている。
きついこと言われてもニヤついているわたしに気づき、とうとうニシジマは顔を上げた。
「ちょっと、なによ、その余裕。本当の本当にこっちはそんなつもりなかった、ごめんなんて言われたらどうするの。相手は悪くないなんて、かわいこぶってる場合じゃないんだから」
それもわかっている。ドラマじゃないんだから何があっても揺るがない運命の人なんてそういない。
恋愛なんて紙一重で、ちょっとしたことでどう転がっていくかわからない。
マニュアル通りの男がいたらそれはそれで怖いくらいだし。
「ニシジマこそどうなの。うちの会社で、そうそういい人もう残ってないんじゃないの」
「実は、なんだけど……」
ニシジマは急に声を潜めた。
「経理部の柊さんって知ってる?」
「えっ」
「驚くことないでしょ。たしかに、顔は普通だし、どうってことないかもしれないけど、悪い噂聞かないじゃない。可も不可もないけど、いい人そうだもん」
これはまいった。
わたしはこっそりとマイボトルをバッグにしまった。
ニシジマと柊さんを取り合うことになったら泥仕合になりかねない。
ここでズバッといっておかなければニシジマとの間に亀裂が生じるのは避けられないし、だからといって柊さんに興味を持たれていなければ騒ぎ立てても恥をかくだけだ。
そもそもわたし、ちゃんと柊さんに恋してるのかな。柊さんに愛されたいのかな。
ニシジマはやけにすっきりした表情でスマホをポケットにしまった。
「柊さん情報、なんかつかんだから教えてよね」
そんなこといわれても、マイボトル情報なんていえないし。
ニシジマの柊さんに対する本気度も見抜けないわたしは、結局、態度を保留したままになってしまった。
「もはや仕事にも飽きている」
生まれも育ちも違うけれど、上の句詠んだら的確な下の句が返ってくるっていうくらい、同期のニシジマはわたしとそっくりな女だった。
とにかくちゃんとした仕事にありつかないと人生の転落が始まるとばかりに身を粉にして就活していたのに、「ちゃんとした」なんて釈然としない思いの丈でつかんだ仕事は、人生の繋ぎでしかなくなっていた。
どこかの政治家がいいだした『輝いてる女性』とはすべての人を指すわけではない。
輝いている女性になるためには働きながら恋愛をし、結婚をし、出産をし、育児をして完成されるというすり込みに、わたしたちはまんまと感化されていたのである。
二十代であるわたしは、結婚しないという幸せについては考えてみたことがないし、誰もそれを応援していない。
自分が輝いていることを証明するために、結婚という道を選ばず、ひとりで生きたきゃ勝手に生きればいいじゃんって、それはそうなんだけど。
次なる人生の分岐点はずばり、結婚。
結婚するかしないか。それはどこの会社に勤めるかよりも重大な選択なのだ。たぶん。
「いろいろ試してわかったのは、合コンで知り合った男より社内婚がベストだってことね」
「そうだね」と同意をしておく。
昼休み、広場に設けられたパラソルの下、キッチンカーのワンコインランチを運良く手にしたわたしとニシジマは舌鼓を打っていた。
メニューはひとつ。
その日によって違うらしいが、きょうのメニューは『彩り野菜と肉々しく変身したロコモコ豆腐』。
タイトルに全部詰め込まれたライトノベルみたいにそのまんまだった。
サイズは小さめだけど、ひとつのカップに全部入っている。
ご飯のかわりによそってあるのはゆし豆腐。その上にはベビーリーフと紫玉ねぎのスライスを合わせたサラダと、ミニサイズのハンバーグ。サルサ風のトマトドレッシングがかかっていて、どこをすくい取っても堪能できる。
ゆし豆腐は温かいものだって思っていたけど、スパイスがきいたドレッシングとよくあって、冷たくてもおいしい。
ハンバーグも冷めてはいるが、硬くなく、しょうがが効いていて、食感がまさに肉々しい。なのに油っぽくなくて、あっさりめだ。
お得感でつい饒舌になってしまいそうだが、そろそろ屋外での飲食が厳しくなってきているこの暑さ。やっぱり冷房のついた室内に戻ればよかった。
だというのに、早めに切り上げて戻ろうともせず、ニシジマは猛烈に話しはじめた。
「ミキちゃんのことは手近な男ですませちゃってなんて思ってたけど、同僚ってのはある程度人となりがわかるし、身元もはっきりとしてて、会社にも毎日来てることも知ってて、給料もどの程度かわかるでしょ。もっとあればいいと思うけど、少なくとも職業偽ってたり、詐欺ってことはない。自分だって焦る年齢ではないけど、もしかしてこの人自分に興味あるんじゃないの?って人に出会うと、どういうわけか焦るのよ。相手がどんな人なのか、自分が本当はどう思っているか、そんなことよりなんかしら発展しそうなら引き留めなきゃって、焦ってくるの。こんなチャンス二度とないって」
言っちゃ悪いがニシジマは普通の女だ。
わたしも同類だからわかる。気のあるそぶりをされて困るほどモテはしない。
だからといってすぐに食いつくのは考えものだ。一生一緒に過ごす相手をそう易々と決められない。けれども簡単に運命の出会いなんてない。
そんな堂々巡り。
「どこかでスパッと決めなきゃなんないのよ」
ニシジマは固く握りしめたスプーンで一文字に空を切るような仕草をした。
それはまるで恋愛不得手なわたしにレクチャーしているみたいだったが、ニシジマとて浮いた話はまるでない。
あるのなら恋愛自慢のひとつやふたつするだろう。
「そんなこといって、言い寄られてつなぎ止めておきたくなるような男と出会った経験あるの?」
「あるからいってるんでしょ。貢いだのがボーナス程度で助かった」
「いや、助かってないし」
意外な失敗談を聞かされて、ニシジマもやはりわたしと同様、男を見る目がないことが知れた。
わたしには大学生時代からずるずると付き合ってきた恋人がいた。
思い返せば講義の時にたまたま隣の席に座っただけという簡単な出会いであったが、このまま続いていくことにもどういうわけか不安はなかった。
ただ、向こうはそうは思っていなかったらしい。
わたしよりちょっぴり結婚願望が強くて少しばかり従順そうな女を見つけると、あっさりわたしに別れを言い渡して結婚してしまったのだった。
腹を立てるのは惨めだと思っていた。
将来のことを具体的に話したことはない。
まさか捨てられるとは想定していなかったけど、今はまだ行き遅れにならなかったのが幸いだと許してしまうわたしにニシジマはあきれていた。
「慰謝料を取れるくらいの口約束はしておくべきだったわね」と。
だが、逆にむしり取られていたとは。
おしゃれなランチばかりしていたら資金が尽きたといっていたが、なるほど、ランチ代をケチりたくなるわけだ。
わたしたち、ツイてないだけなのかな……。
アスファルトの照り返しを避けるように天を仰ぐ。パラソルの骨組みが見えただけだった。
つられるようにしてニシジマもパラソルを見上げるそぶりをしているのが視界に入ってきた。
そんなところに神様なんているわけない。だけど……。
「わたしもね、合コンより神頼みだなって思ってたの」
そういうとニシジマは「いやいや」と、喉をつまらせそうになりながら首を振った。
「話聞いてた? 合コンより社内恋愛だねっていってたんだよ。まったく共感できないんだけど」
ツレないニシジマの気持ちはよくわかる。
いい加減なようでいて、わりと現実的に人生の節目を通り抜けてきたわたしたちが、紆余曲折辿り着いたよりどころが『神頼み』だなんて。
「神頼みってどういうことよ?」
ニシジマは声が裏返る寸前になりながら問いただす。だが、急にハッとしたように付け加えた。
「べつにいいのよ。宗教観はひとそれぞれだし、何を信じて何を心のよりどころにするのか、いいんだけど。突然さみしい女に見えてきてちょっとびっくりしただけ」
そうなのか。さみしい女に見えたのか。
それをハッキリ言うニシジマもどうかと思うが、理解はできる。
長く付き合っていた恋人と別れたことを知られているだけに、勝手に脳内補完されてしまったんだな。
「気にしないで。ルーティーンみたいなものだから」
軽くあしらうと、ニシジマはぽかんとしていた。
「最近ね、家の近くの神社で毎日顔を合わせる女子高生がいるの」
「ちょっと待って、男子高校生でもなく、女子高生?」
「話しは最後まで聞きなさいよ」
違う方向へ勘違いしはじめたニシジマを制して話しを続けた。
住んでいるアパートからバス停までの道のりには神社がある。
実家を出てからずっとそのアパートに住み続けているわたしにとっては何度も前を通り過ごしていた馴染みある神社だが、祀られているのがどんな神なのかも知らない。
どこにでもありそうな簡素な神社だから、古事記に出てくるような有名な神様を祀っているというのではなく、この土地の氏神や鎮守といったところだろう。
その女子高生は学校に行く前に立ち寄っているようで、制服姿に大きなトートバッグを肩にかけ、神社の階段を下りてくるところによく出くわす。
きっと近くに住んでいて、一番近くにある神社だからついでに参拝しているのだろう。
「足繁く通ってるから大学受験祈願ってところかな。案外、恋愛成就ってことも考えられるけど。それとも普通に小さいころからの日課かな。でも、今どきめずらしいよね、毎日神社に参拝なんて」
「ウエハラ、あなた忘れてるよ。自分が高校を卒業してからもう10年が経とうとしていることに」
10年という年月がさらりと過ぎ去っていることにおののくも、「べつに、女子高生気取ってるわけじゃないし」と、もの申しておく。
ニシジマは諭すように身を乗り出した。
「あのね。もはや高校生なんて異次元だから。移り変わりの早い世の中で、唐突にあそこは御利益あるとかいう都市伝説が生まれたりするし、そもそも彼女たちの間でお百度参りが流行ってるのかもしれない」
「お百度参り?」
「毎日毎日、百日かけて参拝して願い事を成就させること。百日もかけてられないときとか、緊急を要するときは一日で百回お参りするの。鳥居から拝殿の前までを行き来してね」
「神頼みに否定的なのに、そんなことは知ってるのね」
「普通の女子並みにパワースポットとか興味ないわけじゃないよ。でもそれって『すがる』というよりレジャー感覚だよね」
へぇ、と相づちを打つ。
まぁ確かに、占いとかおまじないとか、女子が一度は通る道だ。
スマホを片時も離さず常に情報をチェックしているニシジマなら、やってみようとは思わなくても知っていそうではあった。今日も、お目当てのキッチンカーがここへやってくる情報も得ていたし。
ニシジマは最後までとっておいたミニトマトを名残惜しそうにかみしめた。
「それで。どんな神が祀られているかもわからない神社なのに、その女子高生に感化されてウエハラも参拝を?」
「まぁね。二、三分早く出てくればいいだけのことだし、なんだか、ピピッてきたしね」
「毎日目の前を通っていた神社にいきなり運命感じるとかよくわかんないけど」
わたしとニシジマの間に共感は生まれなかったようだ。
じゃあわたしもやってみようというフットワークの軽い年代はもう過ぎ去ったのかもしれない。
ニシジマは現実的なことを聞いてきた。
「ちなみにお賽銭はいくら?」
「一回十円」
「せこくない?」
ニシジマは甲高い声を上げた。わたしは頬を膨らませて抗議する。
「そんなもんでしょ。それこそ百回で千円だよ。千円の賽銭なんてしたことある?」
「百回も参拝したの?」
「お百度参りなんて知らなかったから数えてないけどさ」
「……ウエハラ。なににやけてるの」
にやけるわたしになにかを察知したのか、ニシジマは背もたれにのけぞって露骨に不機嫌な顔をした。
「別に」と、しらを切る。
「御利益があったのか」
詰め寄るニシジマに首をかしげてすっとぼける。
「やっぱり。やっぱり職場か」
「そんなんじゃないよ」
とぼけてみるが、ニシジマには通用しなかったようだ。すべてを悟って悔しそうに顔をゆがめた。
「わたしより早く当たりを付けていたとは」
「人聞き悪いな。こういうのはね、ピピピだよ。ニシジマもお百度参りしてみなよ。ピピッときた神社ならどこでもいいんだよ。こう、引き寄せるっていうかさ――」
「もういい、もういいよ。神社行くぐらいなら開運アプリでも探すわ」
本当にそのつもりなのか、テーブルに伏せておいたスマホを取って慣れたように片手で操作する。
焦ってないと余裕をかましながら、これはつけ込まれるフラグが立ってるんじゃないかと心配になってくる。
「ねぇ、そのうちマッチングアプリを開運アプリとかいったりしないよね?」
ニシジマは顔も上げず余裕ぶって答える。
「まさか。出会いは社内で求めることにしたんだから。ミキちゃんもそうだけど、ウエハラまで情報をつかんでいなかったとは。不覚だわ」
「情報っていわれても……付き合ってるとかじゃないよ? そんな噂なんてまだなにも――」
「なにのんきなこといってんの。まだ始まってもいないなら、こっちはそのつもりっていうオーラ全開でいきなさいよ。一度失敗してるんだから」
「ニシジマにいわれたくないわ」
口先だけは怒っておいて、腹の中はそうでもなかった。
給湯室で入れてきたマイボトルの冷たいお茶を飲み干す。
実は最近ちょっと接近中のひとがいる。経理部の柊さんだ。
大きくもない会社だから柊さんの顔は前から知っていた。
給湯室で顔を合わせたこともある。
エレベーターで乗り合わせたときにふたりだけの気まずい空間をやり過ごしたこともある。
ついでのように誘われた飲み会で向かい合ったこともある。
駅のホームで肩がぶつかって頭を下げたら柊さんだったこともある。
コピー機の用紙がつまったとき、たまたま通りかかった柊さんが対応してくれて、初めてまともに会話した。
正直いって最初から意識していたわけではない。なのに、柊さんとはなんとなく誰よりも顔を合わせているような気がしていた。
マイボトルはおそろいだ。
とはいっても、一緒に買いに行ったのではない。わたしが持っているのを見て柊さんがちょうどいいサイズ感だと気に入り、どこで購入したかを聞かれたのだ。
コツコツと参拝しているような積み重ねに、「こっちはそのつもり」っていうオーラをまとわりつかせなくても、連絡先を聞かれるまであとちょっとかなって勝手に思っている。
きついこと言われてもニヤついているわたしに気づき、とうとうニシジマは顔を上げた。
「ちょっと、なによ、その余裕。本当の本当にこっちはそんなつもりなかった、ごめんなんて言われたらどうするの。相手は悪くないなんて、かわいこぶってる場合じゃないんだから」
それもわかっている。ドラマじゃないんだから何があっても揺るがない運命の人なんてそういない。
恋愛なんて紙一重で、ちょっとしたことでどう転がっていくかわからない。
マニュアル通りの男がいたらそれはそれで怖いくらいだし。
「ニシジマこそどうなの。うちの会社で、そうそういい人もう残ってないんじゃないの」
「実は、なんだけど……」
ニシジマは急に声を潜めた。
「経理部の柊さんって知ってる?」
「えっ」
「驚くことないでしょ。たしかに、顔は普通だし、どうってことないかもしれないけど、悪い噂聞かないじゃない。可も不可もないけど、いい人そうだもん」
これはまいった。
わたしはこっそりとマイボトルをバッグにしまった。
ニシジマと柊さんを取り合うことになったら泥仕合になりかねない。
ここでズバッといっておかなければニシジマとの間に亀裂が生じるのは避けられないし、だからといって柊さんに興味を持たれていなければ騒ぎ立てても恥をかくだけだ。
そもそもわたし、ちゃんと柊さんに恋してるのかな。柊さんに愛されたいのかな。
ニシジマはやけにすっきりした表情でスマホをポケットにしまった。
「柊さん情報、なんかつかんだから教えてよね」
そんなこといわれても、マイボトル情報なんていえないし。
ニシジマの柊さんに対する本気度も見抜けないわたしは、結局、態度を保留したままになってしまった。