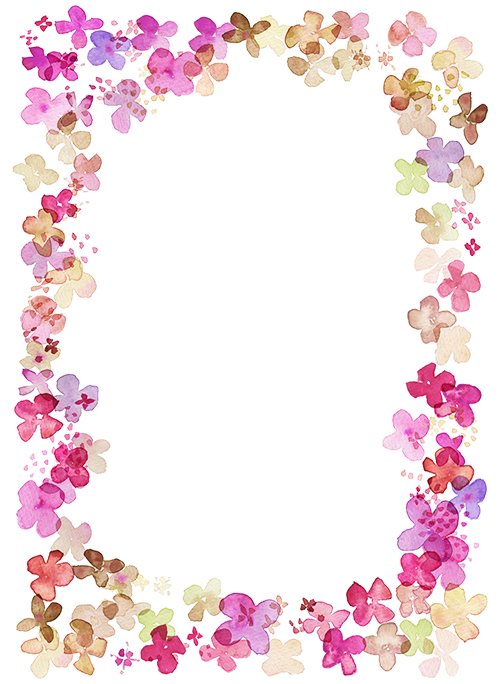時計の秒針は嘘みたいなスピードで進んだ。
俺達は慌ててシャワーを浴び、シーツを洗って証拠隠滅に励んだ。使用済みのゴムすらどう処分すべきか分からずあくせくする。その点未早の方が冷静で、てきぱきと後始末をしていた。
「サンキュー未早。おかげで何とか終わった。多分、母さんはそろそろ帰ってきそう」
「そっか。じゃ、俺ももう退散すんね」
未早は鞄を持って、さっさと襟元を直す。
「あぁ、そういえば泉名にちゃんとワケ話して謝らないとな……成り行きで、お前が突然俺の小説を奪ったってことになってんだ」
「部長はさすがに困るなぁ。俺もやりづらくなっちゃうから説明よろしく。……あ」
「ん?」
「俺達が付き合ってること、別に言ってもいいから」
未早は照れくさそうに言って、乱れた前髪を弄った。
「でもウワサ広まるのは嫌かな。まぁいいや、皐月に任せるよ」
「……うん」
多分俺が思ってるより、彼は俺のことが好きで。
俺も、俺が思ってるより彼のことが好きだ。
「未早」
テーブルに置いておいたあの夢小説を手に取り、彼に手渡した。
「それはお前にやる。煮るなり焼くなり好きにしろよ」
「え、いいのっ?」
「いいよ。何だったらまた続き書くし」
「……話書くのに夢中で、俺のこと放ったらかしにしない?」
「しないよ、今度は約束する」
言うと、未早は嬉しそうに笑った。そして本を大事そうに鞄に仕舞い、手を振る。
「確かに、やっぱ先輩には未《ま》だ早いよ。俺が責任持って預かっとくから」
また、唇が重なった。
「今度は、ちゃんとした設定で書いてね」
「分かった分かった。全年齢対象で書くよ」
彼に読んでもらったから、こんな作品も世界でひとつだけの宝物になった。
もう後悔はしてない。
俺達もそうであるように────これから書くどんな話も、ハッピーエンドにしようと心に決めた。