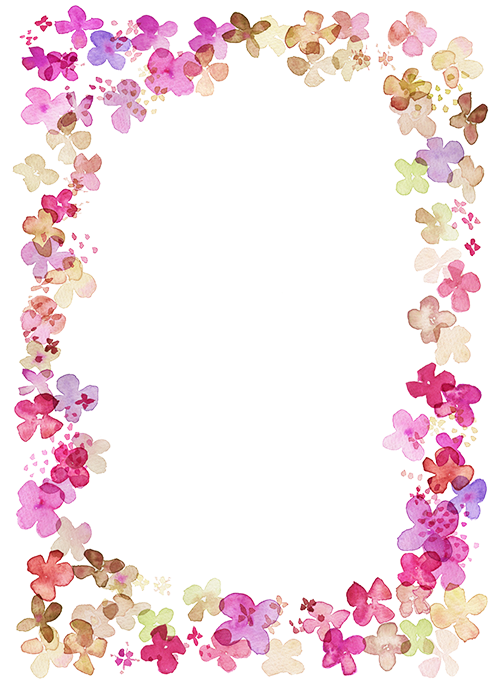分奏を終え、帰りのミーティングも終えた。しかし紅本は空き教室で楽譜に注意点を書き込んでいた。視線はそのままに、近くの椅子に座っている後輩兼恋人に話をする。
「今年の課題曲は去年より相当グレードを下げてる。難しい曲に挑んで審査員にインパクトを与えるより、実力範囲内の選曲で完成度を上げることに徹しよう、と」
「へー。先生の判断ですか? 妥協ですね」
「あぁ。でも分かる。実力以上の選曲して結果がズタボロだったら大恥。他校に汚名が轟くからな。……来年のお前らにも影響が出るだろ」
予想通り外は雨が降り出していた。パッと見は分からないが、窓を叩く雨音が聞こえる。
隣の教室からは居残りしている碧川と重井の力強いロングトーンが聞こえてくる。こちらはメトロノームの寂しい音が小刻みに鳴っているだけだ。
紅本は未早の個人練習に付き合っていた。未早は言われたことを楽譜に書き込み、付箋を取り付けながら低い声で零す。
「無難なラインを狙ってハナから上なんて目指してないスタンスです。メンタル破壊されるような挫折は味わわずに済むけど、そういう学校は永遠にダメ金止まりなんじゃありませんか。本気で全国行きたいなら血反吐吐いてでもグレードの高い曲に挑戦しなきゃ」
未早の辛口は相変わらずだ。過激だけど、理にかなった考え方でもある。
「ははっ、お前には物足りないだろ。俺も一年の頃はそうだった。そもそも部員が少な過ぎてコンクールに出場するどころの話じゃなかったから。あー、この学校で部活に打ち込むのは厳しいかな……って思ってた。だって中学の時は百人近くいたのに、高校じゃ全員合わせても十人ちょっとだぞ? 大編成の楽曲はまず無理だし、アンサンブルをするにはそれぞれの楽器が偏り過ぎてて。どうしたらいいのか分からなかった。いっそ、もうテキトーにやって……やめてもいいかなって」
思ったけど、そうしなかったのは“あいつ”がいたから。
「泉名も強い中学から来てるけど、大会の出場なんか目指してなかったよ。少人数がすごい楽しいんだって言って、一番部活に来てた。正直そん時の俺は全然気持ち分かんなかったけど」
吹奏楽は何十人ものブレスが重なる瞬間とか、ばらばらだった旋律がユニゾンする瞬間とか、ああいうワンシーンに鳥肌が立つものだ。鼓膜が、楽器が、心が震える。大人数の醍醐味を味わうことは言わば快感のひとつで、少人数では不満を覚える自分がいた。その考えを覆したのが泉名だった。
隣にいる人だけじゃない。全員の音、目線、息づかいが手に取るように分かる。自分が吹かなければ欠けてしまう旋律がある。責任感もやり甲斐に変わり、やがて快感となった。どの楽器も自分一人しか存在せず、誰もがソロを任されている状況。冷静に考えたら、刺激的じゃないわけがなかった。