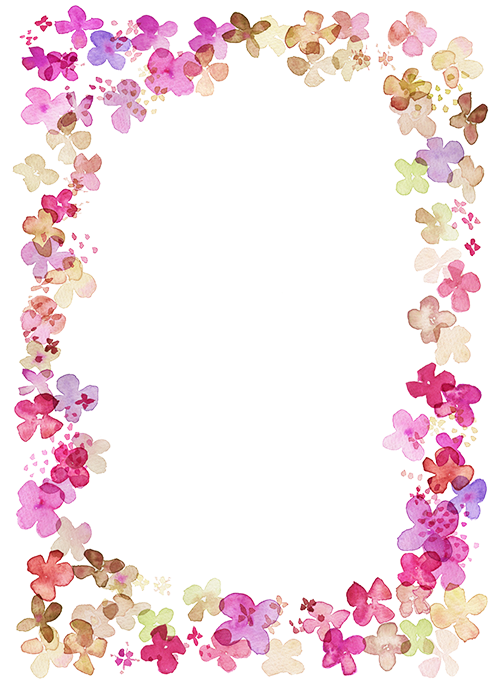「紅が書いたこのBL小説の冒頭だけどさ。『気付いたら今日も何か出してる。必死に隠している後ろの蕾から、男を発情させる淫らな体液を……』ってとこ、『出してる出してる。男が悦ぶ分泌液、今日も今日とて出してます』にしたらどうかな?」
「別にいいけど、無理して韻を踏む必要はないと思うぞ」
「韻を踏んでるつもりはないよ」
「踏んでんだろ」
「踏んでません」
ある日の放課後、紅本はBL研究室(現在は三階別棟の空き部屋)で自身が書いた原稿をデスクに並べていた。中央のソファに座り、公募の為に書いた創作小説の原稿を会長の泉名に確認してもらっている最中だ。
泉名は数多のBL小説を読破している一流の腐男子である。
文才もある気がするし、ないような気もしているので、小説を書き上げた際は必ず見てもらうようにしている。
「ねぇ紅、ひとつ訊きたいんだけど……ラストで主人公が地上千メートルのシンボルタワーから墜落して、服が全て弾け飛ぶ描写があるじゃん。そのあと主人公を追ってヘリコプターから飛び降りたスパダリが彼を後ろから貫いて超融合合体みたいなことしてるけど、そんな上手く挿入できるかな? 多分風圧を直に受けてそれどころじゃないよね」
「そんなんフィクションなんだからどうにでもなるだろ」
「今はリアルを追い求める読者が多いんだよ。大体地上千メートルって……日本にそんなハイパービルディングができるのはしばらく先の未来だよ。編集部は読者のニーズに合わせて作家を採用してる。紅もいい加減現実的な物語を書かなきゃ駄目だよ!」
泉名は強い口調で原稿用紙を隣の座面に置く。
向かい合った紅本は納得のいかない顔で腕を組んだ。
「あぁそうだな、フィクションったって現実感は大事だよな。でもリアルを追求するあまり面白味が欠けたら本末転倒だろ。セッ……する前に念入りにあそこをお掃除する描写が必要か? 大体みんなすっ飛ばして即挿入してるだろ。必要なものは残す。要らないものは削る。これが時代に沿った書き方、考え方だよ。つまり時代遅れはお前の方だ、泉名」
「はぁ……紅が頑固なのは昔っからだけどさ。俺がちゃんと読んでダメ出ししてあげないと余裕で百個は誤字脱字があるくせに、何でさっきからそんな偉そうなの?」