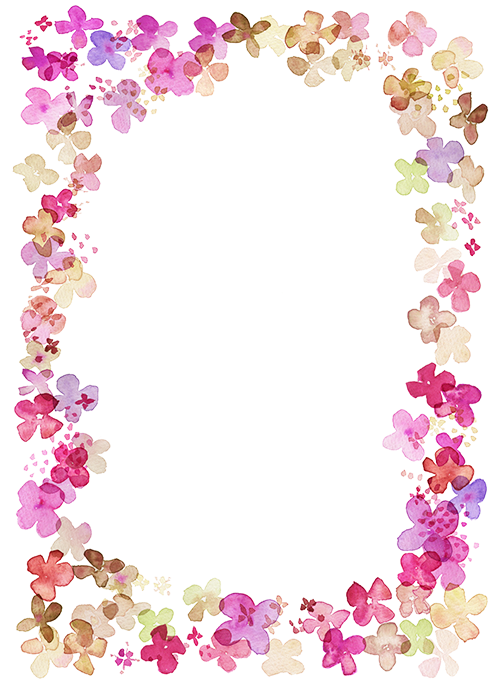「どんな部活も人数に比例してレベルは高くなるけど、少人数だからこそ成長できることも絶対ある。自分が欠けたら成り立たないって責任感が大きいからな。大切な役割って意識すればするほど伸び代になる。……お前は中学のとき、同期何人いたの?」
「俺を入れて、同じパートに四人。全員女子でしたけど」
「へぇ。じゃ、モテただろ」
「三年に上がってから行かなくなりました」
未早の顔に影がかかる。それだけで、話の行く末を何となく察してしまった。
「行かなくなった。って、何で?」
「まぁ色々あって……だからなおさら思うんです。そんなに嫌なら行かなきゃいいって。真面目にやってる人間からしたら、やる気ない奴にダラダラ続けられる方が迷惑でしょ?」
「…………」
完全否定はできない。でもただ事じゃないな。
返す言葉に迷ってると、未早はどうぞと言って俺の口にポテトを入れた。
「ごめんなさい、一々トゲのあること言って」
「いいよ、分かってる。お前は三秒に一回憎まれ口を叩かないと死ぬ病気なんだろ」
「おっしゃる通り」
未早は肩を揺らしながら笑い、また真面目な顔で見つめ返した。
「俺は音楽が好きだけど……それだけじゃ続けられない時がある。その辞めてった先輩達もそうだったんじゃないんですか?」
「そだな。大体人間関係だよ。お前は?」
「俺もそうですね。もう人間関係ぐっちゃぐちゃで、嫌になって、逃げました。だからもう辞めようと思ったのに」
未早は、繋いでいた両手に力を込める。
「紅本先輩の吹いてる姿を見て、またやりたくなっちゃったんです」
「……」
ジュースを飲み切って、空になったグラスを見つめた。
「おし。行くか」
「はい!」
鞄を持って、彼と店を後にする。橙色の街灯が暗がりの中存在感を放っていた。
どんなことでも……誰かに影響を与えられたなら、それはすごいことだと思う。そして、嬉しいこと。自分の頑張りを認められたのと同じぐらい大きなことだから。
やっぱり音楽以外でも教えたいこと、やりたいことがたくさんある。
一年じゃ全然足りない。
「気が早いけど、俺、大学に行っても楽器は続けようと思う」
「良いですね! 紅本先輩は続けるべきですよ!」
「お前も続けろよ。本当に嫌になるまで」
夜の川沿いを歩く。水面に月光が反射し、宝石のように揺れている。俺達は自然と脚を止めた。
「続けて良かったって思える時がきっとくる。仮にこなかったとしても、その時の自分は本気で頑張ってたんだって、胸張って誰かに言えるだろ」
「そう……ですね」
未早は近くにあったベンチに腰掛けた。
「先輩、ちょっと座りません?」
「おう」
隣り合わせで座る。見上げると、綺麗な満月が空に浮かんでいた。
「楽器に会ったことが偶然じゃないなら、紅本先輩と会えたことも偶然じゃないのかな……」