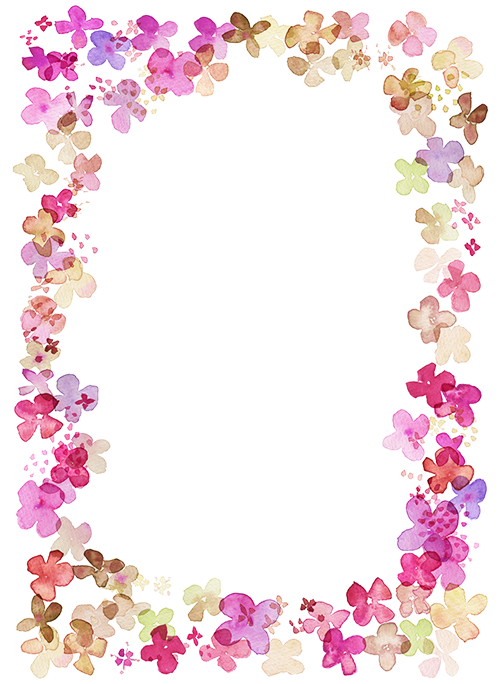「大丈夫?」
「はい……すいません」
謝ることは何もないけど、感じ過ぎてることが負い目なのか、未早は項垂れるように俯いた。
「頑張ったな」
ちょっと息切れしてるけど、彼を強く抱きしめて頭を撫でた。
「悪い。脚、ぬれて気持ち悪いだろ」
「……いっそグチャグチャになって、先輩と繋がれたらいいんですけどね」
はあぁぁぁぁぁあ─────ん!?
「お前どんだけエロい脳内物質が分泌されてんだよ! ホントは何冊BL本読んできた? 正直に吐け!」
「冗談ですけど……。こんなこと言えるの紅本先輩にだけ……ですから」
未早は呼吸を整えながら、俺の背に手を回した。
「先輩……好きです」
「お、おぉ」
「先輩は、俺のこと好きですか?」
変なところで頭が冴える。
これが意思確認か。ゲームやアニメによくある、主人公が心配して、恋人の気持ちを確かめるやつ。
そりゃあもちろん、好きに決まってる。わざわざ答えるまでもない。
大体嫌いだったらこんな事してないだろうがああぁぁぁぁみたいなシーンは画面越しに何百回も見た。
俺だって、未早が好きだからこんなことをした。
むしろもっと、もっと触れたいこと……素直に言えたらいいけど。
まだ、そこまで彼に無理はさせられない。
「俺も、お前が好きだよ。だからこのまま、俺と」
一緒にいよう。
そう言おうとしたけど、言葉が切れてしまった。何でだろう。
「紅本先輩」
「んっ?」
「好きです」
俺の言葉の続きを待たずに、未早はドロドロにとけた部分を擦り合わせた。
「……好き……」
「……」
何回言うんだか。俺の家に呼んだ時みたいに繰り返し呟いてる。
「好き」って、言えば言うほど重みが増すのか。それとも逆に軽くなってしまうのか。
正直まだ分からない。
でも、口に出さなきゃ伝わらない時もあるだろう。
「お前ってほんと、俺のこと大好きだな」
見た目よりずっと細い身体を抱き締めて、その温もりを確かめる。
この感覚を忘れないように。なくさないように、全身で彼を感じた。
「俺も……お前が好きだよ、未早。お前のことが大好きなんだ」
言葉にどれほどの力があるのか分からないけど、これはちょっと怖い。
「未早。好き」
って、一度口に出すとタカが外れたように出続けてしまう言葉みたいだ。
無意識に抑え込んでいた言葉。何だかまったく止まってくれる気がしなかった。