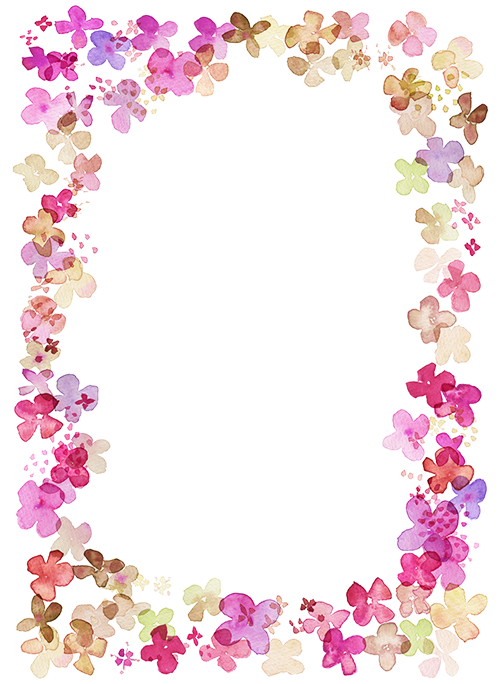予想外の告白を聞いた時、どんな顔をするのがセオリーなんだろう。真顔で真剣に聞いてますアピール? それとも、天然ぶって露骨に驚いてますアピール? いや、俺はどっちも無理だ。また彼を疑ってる。簡単に人を騙す奴だから……すぐ掌返して「冗談ですよ」って言う気がしてる。何故か“その時”は中々やってこないけど。
彼の顔は熱っぽく、初めて彼の方から視線を逸らして逃げている。あぁ、これが演技なら大したもんだな。
彼の頑張りに免じてわざと騙されてやってもいい。茶番に付き合おう。
しばらく黙って待っていると、自嘲にも近い笑いを浮かべて、未早は肩を落とした。
「あーあ。紅本先輩がBL好きだなんて知らなかったら、こんなこと一生言わなかったのに」
「何だよ。いくら俺がイケメンだからって一目惚れして追いかけてくるとか……お前、俺が書いた小説の未早よりよっぽど重症じゃん」
「先輩に言われるとすっごい屈辱なんですけど……実際そうなんで、反論できませんね」
冷静に返すところが面白くて、吹き出してしまった。それには彼もムッとしてたけど、こっちとしては面白くてしょうがない。
これが演技じゃないなら、いっそ清々しいぐらいの告白だ。予兆なんてまるでなかったし、気付けるわけがない。騙されて当然。
「……俺もお前をほっとけない理由がわかったよ。俺以上に人付き合い下手で、不器用なんだな」
上級生に臆せず言いたいことを好き放題言って……怖いもの知らずだと思ってたけど、単純に上手く自分をセーブできてなかっただけみたいだ。
要はコミュ障。
俺の言葉に怒るかと思ったけど、彼は「そうですね」と言ってまた可笑しそうに笑った。
「なぁ。俺に会って、何がしたかったの?」
意地悪な質問かもしれない。
それでも訊かずにいられないのは、彼の本当の気持ちを知りたいから。
「……あなたの小説の台詞を拝借するなら」
未早の眼は泳いでいたけど、ゆっくり瞼を伏せた。そして深いため息をつく。
「色んなことを教わりたいんです。たった一年じゃ足りないと思いますけど……音楽以外のことを、教えてほしい」
あ。そうだ、あれは。
三十頁にも満たない小説だけど、全て俺の願望なんだ。
“こうなったらいいのに”って。
ちょっと扱いづらい後輩が、本当は俺に惚れてたら……なんていう身勝手な願望。そんな身勝手な小説を書いたんだ。
「あんなもん見せたってのに、まだそんなこと言ってくれんだな。……お前」
「それ、八頁の台詞でしょ。 何かデジャブです」
「まぁな。でもそう言わないと」
ハッピーエンドにならない。
二人はずっと結ばれない。
「よし! じゃあもう一緒にいるか。心配だから」
「ちょっ……ずーっと小説の引用じゃないですか! もうちょっとひねってくださいよ」
「はぁ。俺から告白してんのに文句ばっかだな」
「その告白がコピペだからですよ!」
未早はひたすら不満をもらすけど、俺の告白はこれ一本。
現実でも小説でも、この台詞は決して嘘じゃないから……変える必要はないんだよな。