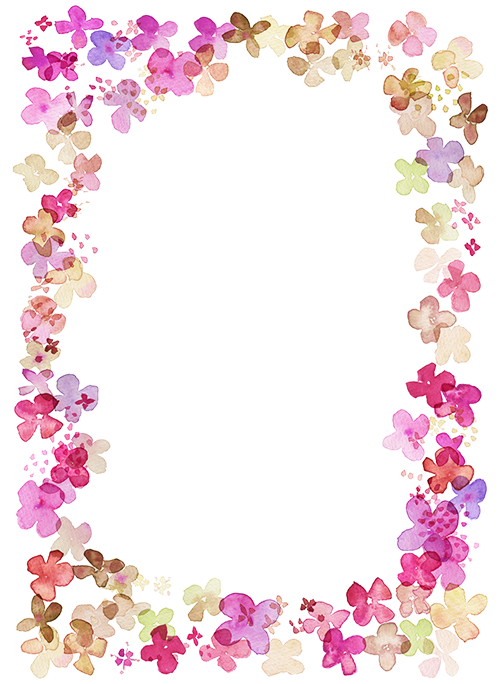「未早、泣くほど気持ちいいの?」
紅本先輩は目元にキスしてくる。その仕草、表情、声───。何もかも初めて過ぎて見蕩れてしまった。
「気持ち、いい……」
いつの間にか、普通に脚を開いていた。恥ずかしくて堪らないのに、先輩から与えられる快感に抗えない。
もっと触ってほしい。
そんな俺の心を読み取ったかのように、先輩は俺の胸や首筋にキスして、甘噛みした。
「未早、自分でやってみてよ。いつも自分でやるみたいに」
「えっ」
先輩は俺の手を掴み、高まった中心に添えた。
「お前がひとりでシてるとこ見せてよ。そしたら、最後はちゃんと手伝ってあげるから」
そんな……そんなの無理だ。
でもそれを乗り越えた先の、先輩の言葉に期待して、無我夢中で自慰をした。
こんな恥ずかしい所を、紅本先輩に見られてる。泣きたい。……って、いやもう涙はずっと流れてる。
「未早、かわいい」
先輩は俺に深く口付けすると、一緒に性器を扱いた。激しくって、強くて痛いぐらいだった。それなのに、気持ちいい。他は何にも分からない。
「せんぱ……あ、イッちゃう……っ!」
先端を指でグリグリされたとき、射精してしまった。
もうどうなってもいい。そう思えるほどの快感が身体中を支配して、先輩の胸に抱かれる。つま先の痙攣が止まらない。
「未早、気持ち良かった? たくさん出したもんな」
「ひっ……ぁ……っ」
イッたばかりの性器を弄られて、また快感に震えた。
「先輩、ごめんなさ……っ」
けど、これは間違いなく異常だ。先輩の手を汚してしまったから、また涙が出る。でも、優しく頭を撫でられた。
「大丈夫。ていうか俺も共犯だし」
優しく囁いて、先輩は俺を抱いた。
「もう一緒にいるか。心配だから」
溶けそうなほど熱い部分が触れ合って、もういっそ繋がってしまえばいいのにと思う。
「あんな真正面から好きって言われたら、普通びっくりするだろ。それでも意識しないように心掛けてたのにさ。……無理だった」
「それは……つまり、OKってことですか? 俺と、恋人同士になってくれるって」
「うん。そうなる」
先輩は苦笑しながら俺の額にキスをした。
マジか。
ちょっと色々ありすぎて心の整理がつかないけど。……こうして、俺は紅本先輩とお付き合いできることになった。