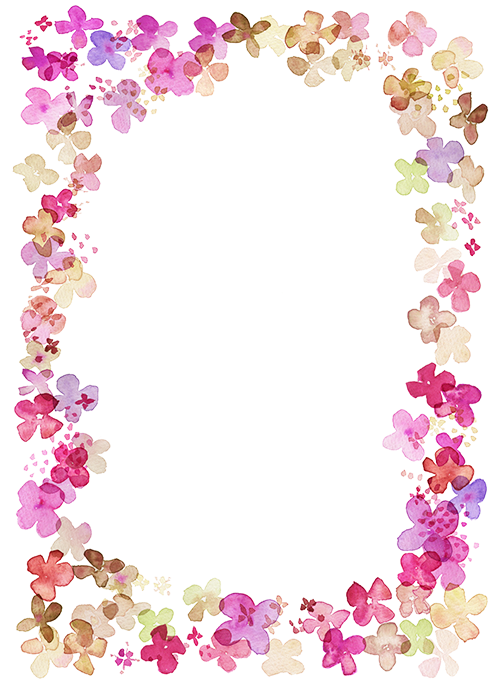「え、そうなの? 未早くん大丈夫?」
「……だ、大丈夫です。すいません」
心配してくれた明野先輩に何とか笑顔で答えると、会長が真面目な顔でドアを開けてくれた。
「謝ることないでしょ、そういう時は無理しちゃ駄目だよ。早く保健室行っておいで」
「ありがとうございます……」
原因が原因なだけに、心配されるたび罪悪感が募る。ほんとにすいません。
「行くよ、未早」
「は、はい」
紅本先輩の機転とブレザーに助けられ、何とか部屋を出ることができた。
道中、特に会話もなく。先輩に連れられた先は、何故か静まり返ったトイレの個室だった。
「ブレザー、ありがとうございます。でも先輩、保健室は……」
「ほんとに保健室行ってどうすんだよ。先生も生徒も来るだろ」
蓋をしてから、便座の上に座らせられる。トイレの中は電灯が点いてないせいで、暗くて怖かった。
「だから言ったろ。お前にアレはまだ早いって」
確かに、結果的にはその通りだけど。
こんな状態だからなのか、何だか耐えられなくなった。
「じゃあ、先輩は何で普通に見れるんですか。昨日は俺が告白しただけで二回も失神したのに! 理不尽じゃないですか!」
「あのなぁ……」
それを言うと先輩はまた真っ赤になった。しかし今度は失神せず、ため息まじりに諭してきた。
「現実と創作は全然違うだろ。創作じゃ何とも思わないことも、現実でされたらすごい意識しちまう。俺にとってお前は、そういう存在なんだよ」
おぉ。
わかるような、わからないような……。
「あの、昨日の……返事は」
「ちゃんと返すよ。でも先にコッチを何とかしようぜ」
金属音が耳に入る。手際良くベルトを外され、ズボンを下着ごと下ろされてしまった。
「うわわわわ! ちょっと、何してんですか!?」
「抜くの手伝ってやる。要するに俺の監督不足だもんな。お前がこうなっちゃったのは」
先輩の暖かい掌が、硬くなったそこを包んで優しく擦る。信じられなかった。これは現実なんだろうか。
紅本先輩が、俺のものを扱いてるなんて。
「ぅ……っ、ん……っ」
根元から先端へ、時間をかけて刺激を与えられる。腰までビクビクと震えてしまった。
本当……こんな事できんのに、何で告白ぐらいであんな狼狽えたんだよ……!