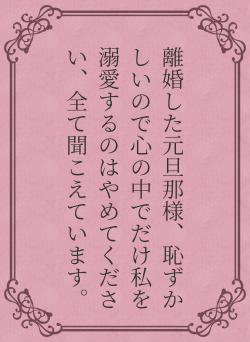ピンポーンと、来客を報せるチャイムが鳴る。
──そういえば、お母さんに荷物を受け取るよう言われてたっけ。
新垣月夜は、重い足を住処である自室から玄関へと運んだ。
誰が来たかも確かめずに、玄関のドアを開ける。
すると、見たことのない自分と同年代とおぼしき女性が笑顔を浮かべて玄関先に立っていた。
メイクにもロングコートを着こなす服装にも、一切の隙のない美しいひとだった。
外から吹き込んできた寒風を浴びて、ああ、季節は冬なんだなあ、と実感する。
自分のくたびれた部屋着のジャージと、女性の清潔感溢れる服装とのギャップに、月夜は赤面する。
穴があったら入りたい心地になりつつも、荷物を受け取るという使命感だけで立っているが、女性が何か荷物を持っている様子はない。
配達員ではないのなら、早くドアを閉めてしまおう。
そう思ってドアノブに手をかけようとした月夜の動きを、女性の少し慌てたような声が遮る。
「ちょっと、月夜、あたしのことわからないの?」
馴れ馴れしい女性の言葉に、眉をひそめた月夜は、相手の顔をぶしつけに睨んで、ふと動きを止めた。
女性の顔に、見覚えがあったからだ。
悪寒にも似た予感が、月夜の背筋を這い上がってくる。
この女性は、もしかしたら、月夜がこの世で一番会いたくなかった人物ではないだろうか。
「もしかして……瑠亜?」
女性は、輝くような、心底嬉しそうな笑顔を月夜に向ける。
改めてよくよく観察すると、彼女は、月夜がよく知っている人物だった。
予感は、残念ながら当たってしまった。
「そう!
もー、忘れられたってショックだったんだから!
でも思い出してくれて良かった、嬉しい!」
女性──瑠亜は、月夜の知っている朗らかな声で、人懐こい笑みで、ばしばしと無遠慮に肩の辺りを叩いてくる。
興奮している瑠亜を振り切るようにしてドアを閉めようとすると、「何で!?待って待って!」と瑠亜がドアの隙間に強引に手を挟んで妨害してくる。
──『何で』?
会いたくなかったからだよ、瑠亜にだけは。
「ねえ、待って、これ持ってきたの」
瑠亜が必死の形相で、封筒を月夜の手にねじ込む。
仕方なく封筒に目を落とすと、「同窓会のお知らせ」と声に出して読み上げる。
「そう、幹事から、月夜と連絡が取れないって相談されて、だったらあたしが渡してくるって約束しちゃったから、受け取ってもらわないと困るの。
月夜、大学辞めて引きこもってるって噂聞いたから、実家にいるんじゃないかと思って」
月夜は無言のまま封筒を握りしめる。
「同窓会なんて、行かない。
どうせマウントの取り合いで、見栄の張り合いでしょ」
月夜の言葉に、「そうだね、その通りだと、あたしも思うよ」と瑠亜が同意する。
「瑠亜は勝ち組でしょ。
負け組の私の気持ちなんかわからないよ」
月夜が強い口調で突き放すと、「……そうかな」と瑠亜が寂しそうに小さく笑った。
「ねえ、少し話さない?
同窓会のことは、断っていいからさ。
あたしも行くつもりないし。
今日は、話し相手が欲しくてきたの」
月夜は、自分のみすぼらしい身なりに視線をやる。
とてもではないが、外を出歩ける格好ではなかった。
「近くに公園あったよね?
あそこなら、誰も来ないんじゃない?」
月夜の心理を推し量ったのか、瑠亜がそう提案する。
月夜は、小さくうなずくと、サンダルのまま外へと一歩踏み出した。
新垣月夜は、人付き合いが得意ではない。
気ばかり遣ってしまって、他人からどう見えるか気になってしまって、上手く人間関係を構築できない。
自分は友達を作ることは諦めたほうがいいと悟った小学2年生のとき、クラスに瑠亜が転校してきた。
どうしてそんな勇気が出たのかは今となってはわからないが、月夜は瑠亜に話しかけた。
ふたりはすぐに仲良くなった。
瑠亜は、勉強ができてスポーツ万能、顔も可愛くて、何より、強かった。
何をやらせても、隙のない完璧な優等生だった。
対して月夜は、成績は人並み以下、走るのも遅くて、運動会ではみんなに迷惑をかけっぱなしだった。
外見も十人並みで、そんなだから、当然自分に自信など持てなかった。
瑠亜は、自信が持てない月夜の心理を、ずばりと突き、月夜の心の内を見通してみせた。
瑠亜にはかなわないと、いつしか月夜は瑠亜に憧れを抱き始めた。
かけがえのない親友となったふたりだったが、別々の高校に進学したあとは連絡を一切取らなくなった。
連絡が途絶えたのは月夜が原因である。
高校に馴染めず、友達も作れず勉強にもついていけなくなった惨めな自分を、瑠亜に見られたくなかったからだ。
何とか大学には進学したが、今度は変わりすぎた環境について行けず、親の期待を裏切って中退してしまった。
それからは、実家の自室で引きこもり生活を送っている。
そして現在、月夜は24歳になってしまった。
暗い部屋で、SNSをさまよっていると、かつての同級生の結婚や出産の投稿に出くわす機会も増え、内心穏やかでなく、焦りが膨らんだ。
劣等感にまみれ、惨めで情けない自分の今を誰にも知られたくなくて、部屋に閉じこもり鬱々とする益体もない日々を浪費していた。
「ちゃんと食べてる?」
遊具ひとつない猫の額ほどの公園のベンチに座るなり、瑠亜はそう切り出した。
「……コンビニのお弁当だけど、一応食べてるよ」
「家族と一緒に住んでるんでしょ?」
「生活時間が違うから、起きるとテーブルにお金が置いてあって、それでお弁当買ってる」
話せば話すほど、自分がクズな生活をしていることを自覚して、胸が重たくなる。
本当はこんなこと話したくない。
見栄を張っていたい。
自慢できるような生活を送りたい。
今の暮らしから、抜け出さねばならないと、誰よりも、月夜自身がよくわかっている。
でももう、社会は月夜が入り込む余地など残してくれていない。
「ねえ、うちにご飯食べに来ない?」
唐突に、あまりに突然、瑠亜がそう言い出した。
「は?」
「あたしね、結婚してるの」
「!」
あまりの衝撃に、月夜は後頭部を殴られたのかと思った。
一瞬息ができなくなる。
まず思ったのは、『置いて行かれた』ということ。
瑠亜は否定したけれど、やはり勝ち組ではないか、というやっかみ。
ぎゅう、と拳を握り込む。
時が止まっているのは自分だけで、周りは月夜など置き去りにして、変化を受け入れ、大人として社会人として、自分より大切な誰かを見つけて、あるいは大切な誰かをその身に宿して進んでいく。
恋愛をして、結婚をして子どもを授かって、やがて子どもが巣立って……。
自分の証を残して大切なひとを増やして生きていく……それが当然の人生だと思っていたし、月夜自身、自分も将来はそういう『当たり前』の人生を過ごすのだろうと、幼いころから漠然と思っていた。
それができると思っていた。
でも、現実は優しくなかった。
「いつ、結婚したの?」
目の前が暗くなりながらも、月夜は必死で言葉を絞り出した。
「1年前。
大学卒業して、すぐに結婚しちゃったから、働く機会もほとんどなかった。
夫は10歳上の弁護士」
「成功者じゃん……」
打ちのめされている月夜の隣で、瑠亜は昏い声で続ける。
「あたし、料理が好きで、毎晩、夫のために料理を作って帰りを待ってるの。
専業主婦だし、家事を完璧にこなすのは、当たり前だと思って、この1年やってきた。
でもね、夫は帰って来ないの。
外に愛人を何人も作って、子どもまで作って浮気しているのに、あたしとは別れようとしない。
夫の仕事先で妻として表に出されるのはあたしなのに、裏では愛人の家に入り浸ってる。
自分で言うのもあれだけど、若くて見た目のいいあたしは夫にとってお飾りにすぎない。
いつか、お飾りの子どもができるんじゃないかと、密かに怯えてる。
毎日毎日広い家であたしはひとり。
作った料理はごみになって棄てられていく。
もう、あたしたちに愛はない」
一点を見つめて、独白するように、瑠亜は長い長い告白を続ける。
話し相手がほしい、と瑠亜は言っていた。
もしかしたら、瑠亜は夫との破綻した結婚生活について誰にも話せずに、つらい境遇を誰かに聞いてほしかったのかもしれない。
「だからね、夕飯、うちで食べない?
夫の代わりに、料理を食べてほしいの。
今のあたしの存在意義は、料理だと思うから。
本当に、それだけだから、あたしは」
瑠亜の言葉に、胸がきゅっと縮む思いがした。
同じクラスにいたころの、友達に囲まれて笑っている瑠亜からは、想像もできない陰のある表情。
月夜にとっては羨ましい人生を生きているように見えた瑠亜にも、悩みがあると知り、簡単に『勝ち組』などと言ってしまったことを恥じた。
「ね、だから、うちに来て」
外に出れば、知り合いに会ってしまうかもしれない。
しかし、思い詰めた様子の瑠亜を放っておくのも残酷な気がして、仕方なしに月夜は申し出にうなずいた。
高級住宅街にある一際目を引く白亜の豪邸。
中世ヨーロッパの城を想起させるような、高台にそびえ立つ一軒家。
厳しい立派な門柱に、『北条』と表札が取り付けられていることを確認した月夜は、ここが瑠亜の住む家であるとわかり、ぽかんと口を開けた。
気後れしながらも、門柱のチャイムを押す。
自分の服装にざっと目を走らせる。
何年前に袖を通したかわからないブラウスにいつかの春先に買ってクローゼットに入ったままだったトレンチコート、膝丈のスカート。
大学に通っていたときに揃えたメイク道具を引っ張り出し、久々に申し訳程度にメイクを施した。
伸ばしっぱなしの髪も、お団子にまとめて瑠亜を見習って清潔感を感じられるように努力した。
靴はやはり大学時代の名残りのパンプスだ。
「はいは〜い、待ってたわよ、月夜!」
今日も今日とて、一分の隙もない完璧なビジュアルの瑠亜が玄関から続く階段を駆け下りてくる。
本当に同い年かと疑いたくなるような大人っぽさ、妖艶さだ。
高級住宅街の中の、さらに存在を誇示するような豪邸。
旦那さんは、よっぽど腕利きの弁護士なんだろうなあ、とぼんやり考えていた月夜の前で、門を開けた瑠亜が手を引っ張ってくる。
「どうぞどうぞ、入って」
促されるままに階段をのぼり玄関に辿り着いた月夜は、内装に目を瞠る。
映画でしか見たことがないような、大階段が中央にあり、2階はそこから左右に分岐している。
玄関は吹き抜けで、毛足の長いカーペットが敷き詰められている。
外観と同じ、室内の壁も真っ白で、壁には絵画が飾られ、棚に並べられた花瓶には、色とりどりの花が活けられている。
「ダイニング、こっちなんだ」
屋敷のあまりの壮麗さに呑み込まれてしまって、動けない月夜の腕を引きながら、瑠亜が苦笑する。
「引くよね、こんなお城みたいなうち。
こんな大きな家いらないって言ったのに、夫が家は大きいほどいいって聞かなくてさ。
掃除も一苦労だから、結局お手伝いさんに週一で入ってもらって、余計な出費ばかり」
心底うんざりしたように、瑠亜は不満を口にする。
月夜には、贅沢な悩みにしか思えないが、瑠亜の夫は、見た目にこだわる、見栄を張りたいタイプなのだろう。
長い廊下を抜けて、ダイニングに入る。
その道中にも、西洋の骨董品が整然と置かれていたり、ガラスケースにトロフィーや賞状が陳列されていたりと、自己顕示欲満載の光景に、何となく瑠亜の気持ちがわかってきてしまった。
白いテーブルクロスが敷かれたダイニングテーブルは、10人ほどがかけてもまだあまりある大きさで、夜、料理を並べて夫の帰りを待って、ぽつんと椅子に座る瑠亜の姿を想像すると、どれだけ心細いか、まざまざと思い知らされる。
月夜をダイニングテーブルに座らせ、瑠亜がアイランドキッチンへと向かう。
時刻は夜7時。
昼夜逆転の生活を送る月夜にとっては活動時間だ。
普段なら、コンビニに食料を買いに行く時刻でもある。
家族はもう帰宅しているだろう。
月夜がコンビニ以外に出かけるなど、想像もしていないだろうな、どこに行ったか気にならないかな、とふと考える。
いや、両親にはもう見放されているし、弟は引きこもりの姉を蔑んでいる。
今更月夜のことなど気にしてもいないだろう。
いてもいなくても変わらない、空気のような存在。
瑠亜はそこから、月夜を引っ張り上げようとしている。
「気合入れすぎて、作りすぎちゃったから、たくさん食べて」
木目調の温かな茶色の空間に、小振りなシャンデリアが吊るされている。
パーティーでも開けそうなラグジュアリーなインテリアばかりだ。
欠点がなさすぎて、怖いくらいだ。
瑠亜は、高級な食器に盛り付けた料理を、次々運んでくる。
「今日は中華に挑戦してみたんだ」
ほかほかと湯気を立てる料理から、ほのかにスパイシーな香りがする。
テレビのグルメ番組でしか見たことのないフカヒレ料理や、酢豚、アワビなどの高級食材が次々と並べられていく。
松茸だって食べたことがないのに、次から次へと現れるテレビの向こうにしか存在しなかった食材の海に、今にも溺れそうだ。
最後に、白米とスープを置いて、瑠亜は「どうぞ、食べて。味に自信はないけど」と遠慮がちに付け足すが、これだけ材料が良いのだから、よほど味音痴でない以上、不味くなるはずがない。
こんな食事を、毎日食べているのだろうか。
信じられない思いがしながらも、緊張を隠しもせずに、震える手で箸を料理に伸ばす。
「あ、いただきます」
言い忘れていたことに気づき、慌ててそう口にする。
「どうぞ、ごゆっくり」
にっこりと瑠亜が笑う。
酢豚をひとくち含むと、甘酸っぱい味付けに白米が欲しくなりぱくりと放り込む。
初めて口にするアワビはこりこりとした食感で、オイスターソースがよく合う。
「……これは?」
スープを指差して聞くと、「ツバメの巣が入ってるの」と教えてくれた。
ゼラチンのような透明な塊がゼリーのように、つるんと喉を通っていく。
こんな温かい料理を、自分以外の誰かと食べたのは、いつぶりだろう。
まるでお店で食べているような気分だ。
瑠亜は、本当に料理が好きなのだとわかる。
それゆえ、食べてくれないひとがいる寂しさもひしひしと伝わってくる。
コンビニ弁当を温めもしないまま、ただ空腹を満たすために食べていたときとは明らかに違う、舌の上で温度を持った食材が飛び跳ね、食べることを楽しむ根源的な本能が刺激される。
「美味しい……」
食に無頓着だった月夜がぱくぱくと料理を平らげている姿を、瑠亜は満足げに眺めている。
「……瑠亜は、食べないの?」
「何か、感動しちゃって。
自分が作った料理をそんなに美味しそうに食べてくれるの見てるだけで充分だよ」
ふと箸を止め、ぽつりと月夜が呟く。
「こんな美味しい料理を作って待っててくれるお嫁さんがいるのに、旦那さん、本当にもったいないことしてるね」
瑠亜が複雑な表情で微笑む。
「あたしね、つまらないんだって。
何でも完璧にこなそうとして、隙がない。
優等生すぎて一緒にいると、息が詰まるって。
あたしはただ、好きなひとのために一生懸命頑張ってるのに、逆効果みたい」
「そんな!
そんなの、旦那さんのほうがおかしいよ!
瑠亜は完璧なお嫁さんなのに、料理もこんなに美味しいのに、贅沢だよ」
言ってしまってから、月夜が顔を赤くする。
「……こんなこと言うの恥ずかしいけど、私、何でも完璧にこなす瑠亜に憧れてたんだ。
瑠亜は何でもできて、友達なのに、追いつけなくて、劣等感持って卑屈になってた」
「月夜、勉強も運動もできなくて、足手まといだったもんね」
他人に言われると、さすがに、かちんとくるだろうが、瑠亜の言葉は、どんなに辛辣であろうと、すんなり受け止められる。
本質をついているからだ。
食事も終わりに近づいたころ、「ワインでも開けようか?」と瑠亜が聞いてきた。
月夜は首を横に振って拒否を示した。
「働いてもいないのに、お酒飲むなんてクズみたいな贅沢できないよ」
くすり、と瑠亜が笑う。
「そういう、変なこだわりがあるの、変わってないね」
話しているうちに、離れていた時間の空白が埋まっていき、親友だったころの調子を取り戻してきた。
「ご馳走さまでした」
お腹いっぱいになった月夜が箸を置く。
「お粗末さま」
瑠亜が皿をキッチンに片付け、食後のコーヒーを持ってやってくる。
お礼を言ってカップを受け取ると、対面に座った瑠亜が、頬杖をつきつつ月夜の顔を眺める。
「月夜が引きこもりかあ……。
さもありなんって感じだよね。
月夜、人付き合い下手だったもんね」
ずばりと急所を突いてくるのは、相変わらず瑠亜といったところか。
「中学卒業して、あたしがいなくて大丈夫かと思ったけど、やっぱり駄目だったみたいね」
顔を赤くした月夜がうつむこうとしたとき、吐息混じりに瑠亜が憂いを帯びた声音で続けた。
「でもね、あたし、そんな抜けてる月夜のこと、羨ましいと思ってたんだよね」
「羨ましい?クズみたいな私のどこが?」
心底意外そうに月夜が聞き返す。
「あたしが知ってる限り、月夜って、どんくさいんだけど、周りが手を貸してくれるっていうか、ほっとけない雰囲気があって、いじめられたりはしなかったでしょ?
あたしは他人から頼られることはあっても、甘えさせてくれるひとはいなかったからさ、自覚はないだろうけど、
愛されキャラっていうのかな、そういう月夜を、羨ましいなって思ってたの」
「……」
勉強も運動もできて、学級委員もやって、たくさんの友達に囲まれて、眩しい笑顔を振りまいていた瑠亜は、頼りにされることを、喜んでいるのだと思っていた月夜は、目を見開いた。
「ま、そんなだから、旦那にも逃げられるんだろうけどね。
甘え上手な愛人と、今夜も楽しく過ごしてるんだろうね。
あたしにはできないことをしてくれる愛人を何人も作ってさ。
来週のパーティーには、あたしを連れて行くのに」
「……旦那さんとは、どこで知り合ったの?」
コーヒーを一口飲むと、ため息をつきつつ、瑠亜は話し出した。
「大学のとき、インターンシップで弁護士事務所に行ったときに、知り合ったの。
年上で、落ち着きがあって、大手企業の顧問弁護士やってたり、やり手の彼に惹かれて、でも告白は向こうからしてくれて、世間を知らない大学生だったあたしは、彼と付き合って、すぐに結婚しちゃったの」
「え、瑠亜、弁護士になろうとしてたの?」
「まあね。
でも、彼が家庭に入ってほしいっていうから、その夢は諦めた。
今考えると、もったいないことしたなあって思うよ。
今のあたしは、社会と遮断されて、誰の役にも立ててないんだなあって思うと、働いてるひとが羨ましいなって思うときがある」
「家事をそつなくこなす主婦だって、立派だよ?
私、家事なんてしたことないもん」
「本当に月夜は何もできない子だよねえ。
将来のために料理くらい覚えたほうがいいよ?
何なら、教えてあげようか?
そうだ、明日……いや、毎日暇か、料理、一緒に作らない?
明日、カレーにしようと思ってるの、簡単だから、月夜でも作れるよ、ね、そうしよ」
どんどん話は進み、ずんずんと瑠亜の顔が近づいてくる。
戸惑う月夜に、やはりというべきか、瑠亜が痛いところを突いてくる。
「今の生活のままじゃいけないってこと、自分でも思ってるんじゃない?
今を逃したら、外に出る次のきっかけはしばらくないと思うよ。
このまま何年も引きこもり続けるつもり?
親だって、歳取るんだよ?
いつまでも、スネかじることは、できないんだよ」
目を逸らしていた現実を、否応なしに言葉にされ突きつけられると、ぐうの音も出ない。
「ま、無理強いはしないけどさ。
コーヒー、おかわりいる?」
「……たよ」
「え?」
月夜の声が聞き取れず、瑠亜が問う。
「わかったよ、明日、また来る」
うつむきながらも、悲壮な決意とともに、月夜が言った。
「本当?
じゃあ、明日も待ってるね。
楽しみだなあ」
新しくコーヒーを淹れながら、上機嫌な瑠亜に、月夜は自分の決断が正しかったのだとわかり、心を決めた。
愛されないという瑠亜の心の空白を、自分が埋めてあげよう、そう強く思った。
翌日も、主不在の北条家を訪ねた。
「本当に、旦那さん帰って来ないんだね」
「まあね、結婚して半年が経ったころからたまにしか帰ってこなくなったよ。
最後に会った日、何て言ったと思う?
不倫のこと責めたら、『君はひとりでもやっていける。でも彼女は、ぼくがいないと駄目なんだ』だってよ。
信じられる?
告白してきたのは向こうなのに。
あたしの経験が足りないばかりに、ひとを見る目が養われてなくて、あのひとの甘い言葉にほだされて結婚までしちゃった。
あのひとの本質を見抜ける経験があれば、あんなひとと結婚なんてしなかったのに」
ざく、と人参を憎い相手でもあるかのように勢いよく切った瑠亜に、月夜は少し引いてしまう。
自分は、結婚に幻想を抱きすぎていたのかもしれない。
瑠亜が結婚していると知ったとき、先を越された、負けた、と思ったけれど、必ずしも結婚したら幸せになるわけでもないようだ。
「いただきまーす」
ほかほかのカレーをテーブルに並べると、ふたりは手を合わせてスプーンを手に伸ばした。
瑠亜が、まるで母親のように温かく見守るような視線で聞いた。
「どう?
自分で作った初めての料理の味は?」
カレーを一口食べた月夜は、頬をほころばせた。
「ちょっと辛いけど、美味しい。
自分がこんな美味しいもの作れるなんて、思わなかった」
「なに調子に乗ってんのよ、月夜は野菜切っただけじゃない。
味つけはあたしがしたんだから、自分の手柄みたいに言わないでよね」
「うう……野菜切ったのだって、ほとんど初めてみたいなものなんだから、もうちょっと褒めてくれても……」
「まあ、それはそうか。
指も切らなかったし、包丁の使い方も悪くなかったし、上出来かもね」
瑠亜も、カレーを口に運びながら、満足したように笑みを深くする。
ごろごろと入った野菜は大きさがまちまちで、不格好ではあったが、瑠亜が味つけでフォローしてくれたので、あまり気にすることなく食べられた。
食後、瑠亜がこんなことを切り出した。
「ねえ、一緒に買い出しに行かない?」
「え?」
「スーパーに行って、月夜の好きなもの買って、また一緒に料理作ろうよ」
そういって、いつも行っている、というスーパーの店名を聞いた月夜は、顔色を青くした。
「どうかした?」
「いや……そこって、セレブが行くお店だよね。
こんな格好して行けないよ……」
瑠亜は不思議そうに瞬きしながら言った。
「じゃあ、服を買えばいいじゃない」
パンがなければ、という、有名な迷言が脳裏に浮かぶ。
何だかんだ言って、瑠亜もパンの代わりにケーキが買える生活水準にすっかり染まっているのだ。
「外に行くリハビリだと思ってさ」
今まで、出歩くと、知り合いに会うのではないかと怯えて昼の外出は避けてきた。
しかし、これは自分を変えるいいきっかけなのかもしれない。
大きすぎる家に瑠亜をひとり残して、月夜は家路に就いた。
「お母さん、お金ちょうだい」
就寝前の母親をつかまえ、たかりにも似た、金の無心をすると、ため息混じりに疲れた顔の母親が言葉を吐き出した。
「お金なら、毎日テーブルに置いていくでしょ。
あれで足りないの?」
母親は明らかに怪訝な様子で月夜を見据えた。
特段裕福ではない我が家では、母親がパートで稼いたお金は、出来のいい弟の教育費に充てられている。
「……服を、買いたいの」
「……は?」
月夜の言葉に、母親は信じられないものを見るような目で月夜を無言で眺めている。
「服って、あんた……何のために?」
「そりゃあ、出かけるためだけど……」
母親は、かっと、限界まで目を見開き叫んだ。
「出かけるために、新しく服がほしいってこと?
コンビニ以外の場所に行くってこと?」
「う、うん……。
友達とちょっと……。
いつも同じ服じゃ、あれかなって……」
「友達!?誰よ?」
母親の剣幕に圧倒されながらも、月夜はぼそぼそと言い訳するように答える。
「……瑠亜……。
渋谷瑠亜って子、覚えてる?」
「渋谷……。
小学校のときに仲良かった子?
明るくて、しっかりした子だったわね。
何度か親御さんと話したこともあったかしらね。
あの子とどこかへ行くの?」
瑠亜が結婚していたこと、一緒に高級スーパーに行きたいことをまとめて報告すると、母親はとろけるような笑顔になった。
「そのスーパーなら知ってるけど、セレブ御用達のお店よね。
確かに、あんたが持ってる服じゃ、恥をかくわね。
わかった、好きな服、買ってきなさい!
待ってて、今お金持ってくるから!」
スキップでもしそうな母親の上機嫌な顔を、久しぶりに見た気がする。
引きこもりという親の期待を裏切った負い目から、少しだけ解放されたような気分だった。
「月夜、そのパプリカ取って」
瑠亜の指示に、月夜が首をかしげる。
「パプリカって、どれ?」
カートを押していた瑠亜は、落胆したような顔で野菜売り場の一角を指し示した。
「これ」
見覚えのある形ではあるが、月夜の認識する野菜とは色が異なる気がして月夜は聞き返す。
「これ、ピーマンとは違うの?
パプリカって、ピーマンが進化した姿とか?」
「本当に何も知らないね、月夜は。
品種が違うの、いいから早く取って」
「あ、うん、ごめん」
赤面しながらピーマンの形をしたパプリカをカートに放り込む。
24歳にもなって、自分は本当に何も知らないことに瑠亜といると、痛感させられる日々だ。
再会を果たした日からしばらく経つが、北条家に頻繁に出入りしているにも関わらず、瑠亜の旦那さんと顔を合わせることは一度もなかった。
セレブ御用達のこのスーパーにくるのも、3回目だ。
売り場が広くて、清潔で、商品の品質は折り紙付きだが、ひとつひとつの商品が高く、いかんせん庶民に出せる価格ではない。
値段も確認せずに、ぽんぽんと野菜や魚や肉をカートに放り込む瑠亜は、すでに自分とは住む世界が違うのだと実感させられる。
新しい服を買い、メイクをするようになって、出かけるたびに、月夜の奥深くに眠っていた自信を、瑠亜が引っ張り出してくれるようだ。
瑠亜は料理がプロ級に上手く、レパートリーも多彩だった。
和食、イタリアン、創作フレンチ、中華以外にも、月夜の知識の中にはない多国籍な料理を瑠亜は作った。
どれを取っても、本格的な味がして、自分がちょっとだけ手伝ったというだけで、美味しさは段違いだった。
この日も、食材を買い込み帰宅すると、瑠亜は早速月夜を手伝わせ、夕食作りを始めた。
完成したパエリアをほくほく顔で口に運んでいると、ワインを一口飲んだ瑠亜が、何でもないことのようにさらりと告げた。
「離婚しようと思うの」
ふーん、とだけ相槌を打って、絶品のパエリアを食べていた月夜は、ん?とスプーンを持った手を止めた。
「今、何て言った?」
「だから、離婚しようと思ってるの」
「えっえっ?
離婚?
本当に?」
動揺してしまって、言葉につかえてしまう。
「うん、もう完全にあたしは旦那への気持ちは消滅してるし、向こうだって、あたしを愛してはいないだろうし、次の人生を考えるなら、決断は早いほうがいいと思って。
やり直すなら、今なんじゃないかって思うの」
瑠亜の表情は晴れ晴れとしていて、自信と確信に溢れている。
「本当に、離婚、するの?」
「うん、もう決めたの。
次に旦那に会ったら言おうと思ってる。
金銭的に何の不自由もない暮らしを、あたしが捨てるわけないって、旦那は思ってる。
でも、富と名声であたしを縛りつけようとしたって、そうはいかない。
あたしは、人生をやり直す。
もう、あんな旦那なんか、いらない」
きっぱりと断言する瑠亜の姿を、眩しそうに月夜は目を細めて見る。
「やっぱり、瑠亜は強いね。
憧れるよ」
素直な気持ちを吐露すると、珍しく瑠亜が恥ずかしそうに微笑んだ。
「決心がついたのは、月夜のおかげでもあるの」
「私の?
私、何かした?」
「うん。
月夜のおかげで、本当にやりたいことがわかったの。
次の目標が決まった」
「目標?」
「月夜が、美味しいって言ってご飯を食べてくれたの、すごく嬉しくて。
ああ、あたし、誰かの役に立ってるって、思えたの。
自分には料理しかない。
大好きな料理で、誰かを幸せにしたい。
自分の店を持ちたいなって」
「お店!?」
はにかんだように瑠亜が笑う。
「離婚はすんなりできると思う。
不貞行為を働いたのは向こうだし、多額の慰謝料を請求する権利があると思う。
それを元手に、まずはキッチンカーから始めようと思ってるの。
それで、良かったら、なんだけど……」
言い淀む瑠亜の言葉を待っていると、凛々しい顔つきになった瑠亜が、一息に言った。
「大したお給料は出せないかもしれないんだけど、お店の手伝い、お願いできないかなって……思ってるん……だけど……」
瑠亜からの提案に、月夜は目を見開く。
「月夜に好評だったカレーをメインにしようと思うの。
軌道に乗ったら、他の料理も作りたいし、最終的には店舗を出店したい。
あたしの腕でどこまで通用するかわからないけど、挑戦してみたいの。
……ああ、何か博打に誘ってるみたい、こんな不安定な話に乗れないよねえ」
苦笑混じりに話を引っ込めようとする瑠亜に先んじて、月夜は渾身の声を張った。
「私、やるよ!
瑠亜の仕事、手伝いたい。
瑠亜のおかげで、私、外に出ることができたし、服にもメイクにも気を使うようになって、料理もちょっとずつだけどできるようになって……。
変わりたいって思うようになった。
瑠亜といると、自分に自信が持てるようになったの。
瑠亜が必要としてくれるなら、私は瑠亜と一緒に働きたい」
「そっか、ありがとう。
月夜が役に立つか怪しいけど、頼りにしてるよ。
引きこもりからの卒業おめでとう!」
辛辣な評価を挟みながらも、瑠亜は月夜に握手を求める。
月夜は、その手をしっかりと両手で包み込んだ。
「握手じゃないんだ」と、瑠亜に笑われてしまい、月夜は顔を赤くした。
その後、離婚は円満に成立し、瑠亜は、耳を疑う額の慰謝料を手にした。
──月夜が、引きこもりを卒業して1年が経った。
開業に必要な資格を取得し、キッチンカーを購入して、本格的に営業を始めるまで、思ったより時間がかかってしまった。
北条から渋谷に苗字が戻った瑠亜は、北条の屋敷とは比べものにならない、ささやかな広さのアパートに居を構え、月夜と一緒に暮し始めた。
瑠亜の鬼のような手ほどきを受けて、月夜の料理の腕もやや上達したと、自分では思っている。
始めたばかりのキッチンカーが、上手く行くかはわからない。
でも、月夜は、紛れもなく、人生で一番充実した日々を送っていた。
ふたりの夢を乗せた努力の結晶は、今日も誰かに美味しい料理と幸せを届けるため、街中を走り続けている。