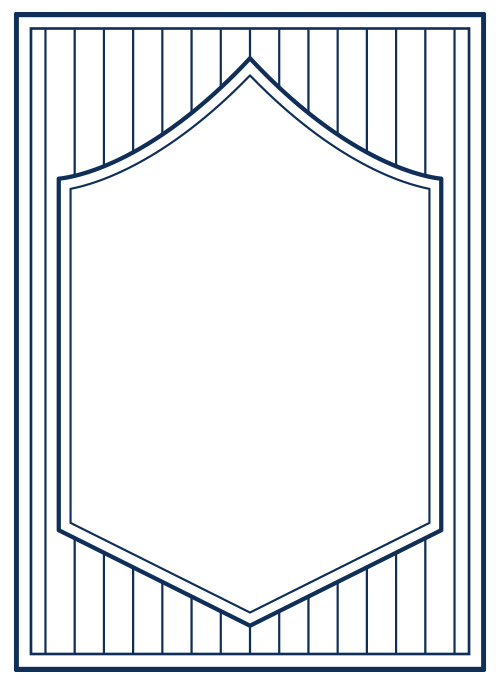四
夕食後、翌日の弁当の仕込みをしていると楸矢が入ってきた。
「何か残ってるものある?」
「残り物じゃないですけど」
小夜はエビフライを五個ほど皿に載せて渡した。
「え、お弁当用でしょ。明日のお弁当、おかずなしなんて嫌だよ」
「それは明日の楸矢さんのおやつ用に作っておいたものです」
「じゃあ、明日はおやつなし?」
「何か簡単なものを作ります」
「じゃ、遠慮なく。いただきます」
楸矢は箸を取ってエビフライを食べ始めた。
「あの、楸矢さん」
「何?」
「柊矢さんの知り合いに『さよ』って人、いたんですか?」
小夜は榊の言った「『さよ』って名前好きだね」と言う言葉が気になっていた。
「さよ? ああ、霍田沙陽ね。柊兄の元カノ。何で知ってんの?」
楸矢が露骨に顔をしかめた。どうやらその人にいい感情は持ってないようだ。
楸矢さんってお兄さんの彼女に嫉妬するタイプには見えないけど。
「この前、柊矢さんの大学のお友達が……」
「沙陽のことは気にしなくていいよ」
「べ、別に気にしてるわけじゃ……」
小夜が頬を染める。その様子を窺うように見ていた楸矢が箸を置いた。
「前にさ、祖父ちゃんが死んだときのこと話したでしょ」
「はい」
「俺は十一歳で、柊兄は十九歳。そのとき付き合ってたのが霍田沙陽。同じ大学の声楽科に通ってたの。柊兄は音大行ってて外国のコンクールで優勝したりして将来を嘱望されてたんだ」
「そんなにすごいヴァイオリニストだったんですか!?」
家の中にトロフィーの類が一つも飾られてないから知らなかった。
「そ。で、なんかのコンクールで優勝者を海外留学させてくれることになったの。柊兄が優勝して留学するだろうってみんな言ってたらしい。事故がそのコンクールの一週間前」
「それで、どうなったんですか?」
小夜は話に引き込まれていた。
「ケガはしてなかったからコンクールに出ようと思えば出られたけど、祖父ちゃんが死んじゃったから働いて俺の面倒見なきゃならなくなったでしょ。オレ、まだ小学生だったし。だから柊兄はコンクール辞退したんだ。て言うか、音大やめたの。音大に通ってちゃ仕事や俺の面倒見ることは出来ないからね」
「そうだったんですか」
「でも、沙陽も柊兄のライバルだった桂ってヤツもそれを知らなかった。ちょっと考えれば分かるのにね」
そう言ってから、首を傾げて、
「いや、分からなかったかな。俺のことは親戚に預けるとでも思ったのかも。親戚はいないんだけどね」
と肩をすくめた。
「沙陽は柊兄と桂と二股かけてたんだ。で、桂の方を選んだ。コンクールの当日、沙陽は入院してる祖母ちゃんが危篤だから車で送って欲しいって言ってきたんだ」
「柊矢さんがコンクールに出られないようにするために?」
「そ。で、柊兄は連れてった。そんな嘘、すぐにバレるのにね。て言うか柊兄は最初から知ってて嘘に付き合ったみたい。どうせコンクールは辞退してたからね。それで帰ってきてお終い」
恋人にそんな裏切りをされたら、自分だったら立ち直れないくらい傷つくだろう。
柊矢さんもきっと辛かったんだろうな。
柊矢さんが自分を名前で呼んでくれないのも同じ『さよ』という名前だからだろうか。柊矢さんが笑ったところも見たことがない。
意地悪な笑みでからかうことはあっても素直に笑うところは見たことがない。
小夜が辛そうな表情を浮かべたのを楸矢は黙って見ていた。
小夜が柊矢に対して淡い思いを抱いているのは気付いていた。
もっと煽ったら本気で好きになったりして。
誰かに恋をしてれば、祖父や家を失った悲しみも忘れられるかもしれない。
とはいえ、小夜と沙陽ではタイプが違いすぎる。
柊矢がどういうつもりで小夜を引き取ることにしたのか分からない。
恋愛対象として見ていなくて、今後もそうなることがないようなら小夜は失恋して更に傷付くことになるだろう。
楸矢はやめておくことにした。
「柊矢さんがヴァイオリンをやめたのはそのためですか?」
「いや、音大やめたから。まぁ、それもあったかもしれないけど。音大やめた後、普通の大学の夜間部に入り直したんだ。最初の頃は昼間に経理とか不動産関係の事務とか教えてくれるセミナーみたいなのにも通って祖父ちゃんがやってた不動産管理の仕事の勉強したりしてヴァイオリンなんて弾いてる暇なかったからね」
「小学生で親代わりだった人を亡くしたなんて、楸矢さんも辛かったですよね」
「俺には柊兄がいたから」
それで話は終わり、と言うように楸矢はエビフライを食べ始めた。
小夜も弁当作りに戻ったが、心は今聞いた話に揺れていた。
でも、楸矢さんが十一歳の時と言うことは七年も前の話だ。
柊矢さんはとっくに乗り越えただろう。
そういえば、柊矢さんはそのとき十九歳だったってことは、今は二十六歳くらいなんだ。
やっぱり柊矢さんは大人だ。
自分みたいな子供を相手にするわけがない。
「小夜ちゃん、焦げてる焦げてる!」
楸矢の声に小夜は我に返った。
野菜炒めから煙が上がっている。
「きゃ! 大変!」
小夜は慌てて火を止めると中華鍋の中を覗き込んで被害状況を調べ始めた。
「小夜、ダイエットでもしてんの?」
清美が小夜の弁当の中身を見て言った。
今日の小夜の昼飯は、弁当箱一杯の野菜炒めだった。
夕辺、野菜炒めを焦がしてしまったため柊矢と楸矢の弁当に入れる分の野菜炒めを急遽自分のエビフライに差し替えて、自分の分は失敗した野菜炒めにしたのだ。
外では朝から土砂降りの雨が続いていた。強い風も吹いている。
「参るよね~。この時期にこんな嵐なんてさぁ」
「そうだね」
小夜は雨音に交じってムーシカが聴こえて来るのが気になっていた。
歌っているのは一人だけのようだ。女性の声が雨を煽るように歌っていた。
柊矢さんや楸矢さんはこのムーシカのこと、なんて言うかな。
小夜が家に帰ると楸矢が台所のゴミ箱を覗いていた。
「楸矢さん! そんなにお腹が空いてるんですか!?」
「え、ああ、違うよ。いや、お腹は空いてるけど」
楸矢が慌てて手を振った。
「夕辺の野菜炒め、お弁当に入ってなかったからどうしたのかと思って」
「あれなら私がお昼に食べましたけど」
「小夜ちゃん、少し失敗したくらい、俺達は気にしないよ」
「でも、失敗したのを見られるのは恥ずかしいですから」
しかも、失敗したとき考えていたことが考えていたことだ。とても恥ずかしくて失敗した理由なんて言えない。
小夜は思わず赤くなった。
「いいなぁ。なんか初々しくて」
「は?」
思いもよらない言葉に、どう反応したらいいのか分からなかった。
「いや、俺の彼女にはもうそんな初々しさなんてないからさ。女子高生の彼女って言うのもいいかもなぁ」
そういえば楸矢さんの彼女って年上なんだっけ。
「彼女に怒られますよ、そう言うこと言うと」
「平気平気。彼女の方も婚活してるし」
楸矢がどうでも良さそうに手を振った。
「楸矢さんがいるのに?」
「俺じゃ結婚相手にはならないでしょ。俺が大学卒業するまで待ってたら、彼女アラサーになっちゃうし」
てことは柊矢さんと同い年くらいなんだ。
「それにさぁ、大学卒業したとして、フルートで食っていけると思う?」
「それは……」
楸矢に限らず、音楽家が食べていくのは大変そうだというのは容易に想像が付いた。
いくら音楽が好きでも人間である以上霞を食べて生きていくことは出来ないのだ。
「結婚相手に食べさせてもらうなんてヒモみたいで嫌だしさ。音大への進学はもう決まってるけど、このまま行ってもなぁって思ってるんだよね」
「…………」
「柊兄は確かに才能あったけど、俺は、ね」
「楸矢さん」
「けど、柊兄が諦めた音大を俺が投げ出すのも……」
確かに、柊矢は楸矢のために音大をやめた。それを思うとやめるわけにはいかない、と思ってしまう気持ちも分かる。
「柊矢さんは楸矢さんが無理に続けても喜ばないんじゃないですか?」
もし柊矢が楸矢に期待していたとしても中途半端に続けるのはどちらにとってもいい結果にはならないような気がした。
「そうだね。今スランプでさぁ。だからかな、弱気になってるのかもね。どっちにしろ俺の成績じゃ普通の大学に入れるか分からないし」
「あの、今朝から気になってたんですけど……」
小夜は話題を変えようと話を逸らした。
「どうかした?」
「ムーシカ、聴こえませんか? 小さい声だから聴き取りづらいですけど……」
その言葉に、ムーシカに耳を傾けた楸矢の顔がこわばった。
夕食後、翌日の弁当の仕込みをしていると楸矢が入ってきた。
「何か残ってるものある?」
「残り物じゃないですけど」
小夜はエビフライを五個ほど皿に載せて渡した。
「え、お弁当用でしょ。明日のお弁当、おかずなしなんて嫌だよ」
「それは明日の楸矢さんのおやつ用に作っておいたものです」
「じゃあ、明日はおやつなし?」
「何か簡単なものを作ります」
「じゃ、遠慮なく。いただきます」
楸矢は箸を取ってエビフライを食べ始めた。
「あの、楸矢さん」
「何?」
「柊矢さんの知り合いに『さよ』って人、いたんですか?」
小夜は榊の言った「『さよ』って名前好きだね」と言う言葉が気になっていた。
「さよ? ああ、霍田沙陽ね。柊兄の元カノ。何で知ってんの?」
楸矢が露骨に顔をしかめた。どうやらその人にいい感情は持ってないようだ。
楸矢さんってお兄さんの彼女に嫉妬するタイプには見えないけど。
「この前、柊矢さんの大学のお友達が……」
「沙陽のことは気にしなくていいよ」
「べ、別に気にしてるわけじゃ……」
小夜が頬を染める。その様子を窺うように見ていた楸矢が箸を置いた。
「前にさ、祖父ちゃんが死んだときのこと話したでしょ」
「はい」
「俺は十一歳で、柊兄は十九歳。そのとき付き合ってたのが霍田沙陽。同じ大学の声楽科に通ってたの。柊兄は音大行ってて外国のコンクールで優勝したりして将来を嘱望されてたんだ」
「そんなにすごいヴァイオリニストだったんですか!?」
家の中にトロフィーの類が一つも飾られてないから知らなかった。
「そ。で、なんかのコンクールで優勝者を海外留学させてくれることになったの。柊兄が優勝して留学するだろうってみんな言ってたらしい。事故がそのコンクールの一週間前」
「それで、どうなったんですか?」
小夜は話に引き込まれていた。
「ケガはしてなかったからコンクールに出ようと思えば出られたけど、祖父ちゃんが死んじゃったから働いて俺の面倒見なきゃならなくなったでしょ。オレ、まだ小学生だったし。だから柊兄はコンクール辞退したんだ。て言うか、音大やめたの。音大に通ってちゃ仕事や俺の面倒見ることは出来ないからね」
「そうだったんですか」
「でも、沙陽も柊兄のライバルだった桂ってヤツもそれを知らなかった。ちょっと考えれば分かるのにね」
そう言ってから、首を傾げて、
「いや、分からなかったかな。俺のことは親戚に預けるとでも思ったのかも。親戚はいないんだけどね」
と肩をすくめた。
「沙陽は柊兄と桂と二股かけてたんだ。で、桂の方を選んだ。コンクールの当日、沙陽は入院してる祖母ちゃんが危篤だから車で送って欲しいって言ってきたんだ」
「柊矢さんがコンクールに出られないようにするために?」
「そ。で、柊兄は連れてった。そんな嘘、すぐにバレるのにね。て言うか柊兄は最初から知ってて嘘に付き合ったみたい。どうせコンクールは辞退してたからね。それで帰ってきてお終い」
恋人にそんな裏切りをされたら、自分だったら立ち直れないくらい傷つくだろう。
柊矢さんもきっと辛かったんだろうな。
柊矢さんが自分を名前で呼んでくれないのも同じ『さよ』という名前だからだろうか。柊矢さんが笑ったところも見たことがない。
意地悪な笑みでからかうことはあっても素直に笑うところは見たことがない。
小夜が辛そうな表情を浮かべたのを楸矢は黙って見ていた。
小夜が柊矢に対して淡い思いを抱いているのは気付いていた。
もっと煽ったら本気で好きになったりして。
誰かに恋をしてれば、祖父や家を失った悲しみも忘れられるかもしれない。
とはいえ、小夜と沙陽ではタイプが違いすぎる。
柊矢がどういうつもりで小夜を引き取ることにしたのか分からない。
恋愛対象として見ていなくて、今後もそうなることがないようなら小夜は失恋して更に傷付くことになるだろう。
楸矢はやめておくことにした。
「柊矢さんがヴァイオリンをやめたのはそのためですか?」
「いや、音大やめたから。まぁ、それもあったかもしれないけど。音大やめた後、普通の大学の夜間部に入り直したんだ。最初の頃は昼間に経理とか不動産関係の事務とか教えてくれるセミナーみたいなのにも通って祖父ちゃんがやってた不動産管理の仕事の勉強したりしてヴァイオリンなんて弾いてる暇なかったからね」
「小学生で親代わりだった人を亡くしたなんて、楸矢さんも辛かったですよね」
「俺には柊兄がいたから」
それで話は終わり、と言うように楸矢はエビフライを食べ始めた。
小夜も弁当作りに戻ったが、心は今聞いた話に揺れていた。
でも、楸矢さんが十一歳の時と言うことは七年も前の話だ。
柊矢さんはとっくに乗り越えただろう。
そういえば、柊矢さんはそのとき十九歳だったってことは、今は二十六歳くらいなんだ。
やっぱり柊矢さんは大人だ。
自分みたいな子供を相手にするわけがない。
「小夜ちゃん、焦げてる焦げてる!」
楸矢の声に小夜は我に返った。
野菜炒めから煙が上がっている。
「きゃ! 大変!」
小夜は慌てて火を止めると中華鍋の中を覗き込んで被害状況を調べ始めた。
「小夜、ダイエットでもしてんの?」
清美が小夜の弁当の中身を見て言った。
今日の小夜の昼飯は、弁当箱一杯の野菜炒めだった。
夕辺、野菜炒めを焦がしてしまったため柊矢と楸矢の弁当に入れる分の野菜炒めを急遽自分のエビフライに差し替えて、自分の分は失敗した野菜炒めにしたのだ。
外では朝から土砂降りの雨が続いていた。強い風も吹いている。
「参るよね~。この時期にこんな嵐なんてさぁ」
「そうだね」
小夜は雨音に交じってムーシカが聴こえて来るのが気になっていた。
歌っているのは一人だけのようだ。女性の声が雨を煽るように歌っていた。
柊矢さんや楸矢さんはこのムーシカのこと、なんて言うかな。
小夜が家に帰ると楸矢が台所のゴミ箱を覗いていた。
「楸矢さん! そんなにお腹が空いてるんですか!?」
「え、ああ、違うよ。いや、お腹は空いてるけど」
楸矢が慌てて手を振った。
「夕辺の野菜炒め、お弁当に入ってなかったからどうしたのかと思って」
「あれなら私がお昼に食べましたけど」
「小夜ちゃん、少し失敗したくらい、俺達は気にしないよ」
「でも、失敗したのを見られるのは恥ずかしいですから」
しかも、失敗したとき考えていたことが考えていたことだ。とても恥ずかしくて失敗した理由なんて言えない。
小夜は思わず赤くなった。
「いいなぁ。なんか初々しくて」
「は?」
思いもよらない言葉に、どう反応したらいいのか分からなかった。
「いや、俺の彼女にはもうそんな初々しさなんてないからさ。女子高生の彼女って言うのもいいかもなぁ」
そういえば楸矢さんの彼女って年上なんだっけ。
「彼女に怒られますよ、そう言うこと言うと」
「平気平気。彼女の方も婚活してるし」
楸矢がどうでも良さそうに手を振った。
「楸矢さんがいるのに?」
「俺じゃ結婚相手にはならないでしょ。俺が大学卒業するまで待ってたら、彼女アラサーになっちゃうし」
てことは柊矢さんと同い年くらいなんだ。
「それにさぁ、大学卒業したとして、フルートで食っていけると思う?」
「それは……」
楸矢に限らず、音楽家が食べていくのは大変そうだというのは容易に想像が付いた。
いくら音楽が好きでも人間である以上霞を食べて生きていくことは出来ないのだ。
「結婚相手に食べさせてもらうなんてヒモみたいで嫌だしさ。音大への進学はもう決まってるけど、このまま行ってもなぁって思ってるんだよね」
「…………」
「柊兄は確かに才能あったけど、俺は、ね」
「楸矢さん」
「けど、柊兄が諦めた音大を俺が投げ出すのも……」
確かに、柊矢は楸矢のために音大をやめた。それを思うとやめるわけにはいかない、と思ってしまう気持ちも分かる。
「柊矢さんは楸矢さんが無理に続けても喜ばないんじゃないですか?」
もし柊矢が楸矢に期待していたとしても中途半端に続けるのはどちらにとってもいい結果にはならないような気がした。
「そうだね。今スランプでさぁ。だからかな、弱気になってるのかもね。どっちにしろ俺の成績じゃ普通の大学に入れるか分からないし」
「あの、今朝から気になってたんですけど……」
小夜は話題を変えようと話を逸らした。
「どうかした?」
「ムーシカ、聴こえませんか? 小さい声だから聴き取りづらいですけど……」
その言葉に、ムーシカに耳を傾けた楸矢の顔がこわばった。