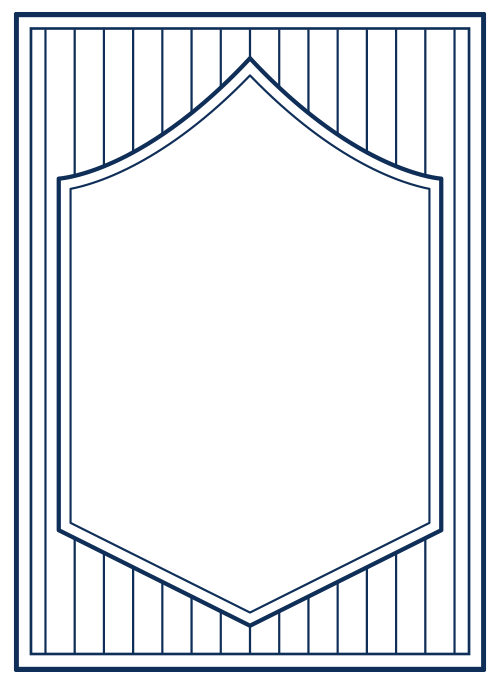二
「あの……」
三人が夕食の席に揃って付くと小夜が口を開いた。
小夜の改まった様子に、楸矢は食べかけていた手を止めた。
「今までお世話になりました」
小夜が頭を下げた。
「どういうこと?」
「お金が入ったら、これ以上ご迷惑をおかけするわけにはいかないので、この家を出ようと思います」
一気に言い切ると、大きく息を吐いた。
言えた。
ここを出ていくのはつらいけれど、いつまでも甘えているわけにはいかない。
「ダメだ」
「え?」
「俺はお前の後見人だ。俺が後見してる限り一人暮らしは認めない」
「でも、柊矢さん……」
「小夜ちゃん、どっちにしろ行くとこないでしょ」
「それは……部屋を探して」
「わざわざ探さなくてもこの家の部屋は余ってる」
「え、でも……」
「育児放棄して児童虐待で訴えられても困るからな」
「い、育児放棄って……」
「保護者が被保護者を放り出すのは育児放棄だろ」
「毎日食事作ってくれればそれでいいよ。ね、柊兄」
「そうだな」
勝手に進んでいく話に小夜は口を挟むことも出来ずにおろおろするだけだった。
「どう? 小夜ちゃん。うちにいるのが嫌じゃなければここに住みなよ」
「嫌ではないですけど……」
「じゃ、決まり」
楸矢はそう言うと食事を始めた。
柊矢も話は決まったという顔で食べ始めた。
小夜は戸惑いながらも、ここに住み続けられることに安心もしていた。
柊矢と話し合い小夜は食事を作る係になった。掃除は自分の部屋以外は三人で分担する、洗濯は自分のものだけ、その代わり部屋代や食費、光熱費などはただと決まった。
小夜は少しでも払うと言ったのだが、家事をしてもらうのだし、保護者が被保護者から受け取るわけにはいかないといって聞き入れてもらえなかった。
小夜の祖父のお骨は初七日に霞乃家の菩提寺に預けることになった。遺体が帰ってくるまでに一ヶ月以上かかったので初七日のときに四十九日の法要もすることになった。
翌日、休み時間に次の授業の用意をしていると、
「さーよ!」
清美が後ろから抱きついてきた。
「きゃ!」
後ろにひっくり返りそうになった小夜が悲鳴を上げた。
「あれ? ここになんかある」
清美は後ろから小夜の胸元を探った。
「ちょ、ちょっと、清美」
「ね、それ、何? ねぇ、何?」
清美の追求に小夜は柊矢に貰ったことを話した。
「えーっ、そこまでしてくれるなんて、その人、小夜に気があるんじゃない?」
この手の話は清美の大好物だ。
「そんなわけないでしょ。柊矢さんは大人なんだから」
小夜は自分に言い聞かせるように否定した。
「あたし達だってもう子供じゃないじゃん」
「でも、柊矢さんは違うの。楸矢さんだって柊矢さんはロリコンじゃないって言ってたし」
「だからあたし達はもう子供じゃないってば!」
清美は苛立ったように言った。
そういえば、清美は前に告白した相手に子供扱いされたって言ってすごく怒ってたっけ。
「柊矢さんから見たら子供だよ」
「そんなに年上なの? いくつ?」
「さぁ?」
「ダメじゃん、そう言うところはちゃんとチェックしなきゃ。ところで楸矢さんって誰?」
清美が訊ねた。
小夜は清美に柊矢の弟で十八歳だと説明した。
「その人は? 優しい? 身長は? 顔は?」
「楸矢さんは彼女いるよ。大人の付き合いしてるって言ってたもん」
「えーっ! 大人の付き合い!? すごーい!」
清美は「大人の付き合い」の意味が分かるんだ。
「大人の付き合いって何?」
「やだもう、小夜ってば!」
清美が思いきり小夜の背中を叩いた。
「痛っ!」
小夜が顔をしかめる。
結局、小夜にはまだ早いと言って「大人の付き合い」というのがなんなのか教えてくれなかった。
学校が早く終わったので小夜は、いつもと違ってバスに乗らず、超高層ビル群に向かった。
いつものように歌が風に乗ってながれている。
しかし小夜は足を止めずビル街を抜けて西新宿の自分の家に向かった。
家があった場所がどうなっているのか見てみたかったのだ。
ビルの間を抜け西新宿の住宅街へ入っていく。
小夜の家の跡には何も残っていなかった。瓦礫すらない。ただの空き地になっていた。
小夜は無意識に柊矢からもらった胸元のペンダントを握っていた。
大丈夫。
お祖父ちゃんが見守ってくれてる。
清美も柊矢さんや楸矢さんもいる。
きっとこれからも頑張れる。
泣いてばかりいるのはもうお終い。
空き地の片隅に花束が置かれていた。近所の人が置いてくれたのだろう。
小夜は花の前にしゃがんで手を合わせた。
小夜が帰ると柊矢はいつも音楽室でキタラを爪弾いていた。学校にいるときはキタラの音は聴こえてないから小夜が帰ってくる時間にあわせて音楽室に来ているのだろう。
小夜は自分の部屋に鞄を置くと着替えもしないまま音楽室へ向かった。
小夜が入っていくと柊矢がキタラを弾き始めた。それにあわせて歌い始めると、どこからか重唱や斉唱が聴こえてきた。徐々に歌声や演奏が加わっていく。
そのうちに楸矢も帰ってきて笛を吹き始めた。
そのまま数曲終えると小夜は夕食の支度を始めるために台所へ向かった。
柊矢も部屋に戻り、楸矢は一人残ってフルートの練習を始めた。
小夜が夕食の支度をしていると楸矢が入ってきた。
楸矢が椅子に座ったのを見て小夜は夕辺の残りのきんぴらごぼうをさっと暖めて出した。
いつも夕食の支度をしていると楸矢が台所へやってきてつまみ食いをするので最近はおやつを用意してある。大抵は前夜の残り物だ。
「有難う。いただきまーす!」
楸矢はすぐに食べ始めた。
「柊兄は?」
「部屋だと思いますよ」
「じゃ、仕事だね」
楸矢は空になった食器を差し出しながら言った。
小夜が残っているきんぴらごぼうを全部入れながら、
「柊矢さんって何のお仕事してるんですか?」
と訊ねた。
前から気になっていたのだ。出勤する様子はないし、かといって学生にも見えない。
そもそも二人家族で楸矢が高校生なのだから柊矢が働いていなければ食べていけないはずだ。
あ、でも、お祖父様が亡くなったって言ってたから遺産があるとか?
「あれ? 言ってなかったっけ? 不動産管理だよ」
「不動産屋さんなんですか?」
「不動産屋じゃなくて、不動産管理。俺の祖父ちゃんがいくつか不動産を残してくれてさ。それの家賃収入で食ってるんだ。柊兄がやってるのはその不動産の管理」
「そうだったんですか」
小夜は野菜を切りながら言った。
都内に不動産をいくつも持っているのだとしたらかなりの資産家と言うことになる。
「結構色々仕事あるらしいよ。管理人さんじゃ対応出来ない事務処理とか、保険関係のこととか」
そんなに忙しいのに小夜の祖父の保険等の手続きをしてくれたのだ。
色々な連絡も全部柊矢のところに行くようにして対応してくれていたのだろう。
小夜は改めて柊矢に感謝した。
「サラダのドレッシングは何がいいですか?」
「中華」
「和風がいい」
柊矢が台所へ入ってきながら言った。
「じゃあ、サラダは取り分けられるようにしておきますね」
夕食が出来上がり、三人が食卓に着くと食事が始まった。
「この前、森が出たとき歌った歌、覚えてるか?」
柊矢が話しかけてきた。
「ああ、あれ。確か……」
「え、森が出たの? いつ?」
「しばらく前だ」
「えっと……メーニナエイデテアーペーレーイーアデオーアキレーオス」
小夜は旋律を思い出しながら歌った。
「一体何語なんだろね」
楸矢が小夜の口ずさんだ歌を聴いて言った。
「もしかしたら分かるかもしれない」
「ホント?」
楸矢が疑わしげに言った。
二人とも歌が聴こえるのだ。何語なのか何度も話し合ったに違いない。
「今度の土曜、時間あるか?」
「はい」
「じゃあ、付き合ってくれ」
「はい」
「柊兄は小鳥ちゃんとデートか。じゃあ、俺も彼女、うちに呼ぼうかな」
「で、デートじゃありません」
小夜は赤くなって反論した。
「小鳥ちゃんの奥手は相変わらずだな」
柊矢がからかうように言った。
「二人してからかわないでください!」
「あの……」
三人が夕食の席に揃って付くと小夜が口を開いた。
小夜の改まった様子に、楸矢は食べかけていた手を止めた。
「今までお世話になりました」
小夜が頭を下げた。
「どういうこと?」
「お金が入ったら、これ以上ご迷惑をおかけするわけにはいかないので、この家を出ようと思います」
一気に言い切ると、大きく息を吐いた。
言えた。
ここを出ていくのはつらいけれど、いつまでも甘えているわけにはいかない。
「ダメだ」
「え?」
「俺はお前の後見人だ。俺が後見してる限り一人暮らしは認めない」
「でも、柊矢さん……」
「小夜ちゃん、どっちにしろ行くとこないでしょ」
「それは……部屋を探して」
「わざわざ探さなくてもこの家の部屋は余ってる」
「え、でも……」
「育児放棄して児童虐待で訴えられても困るからな」
「い、育児放棄って……」
「保護者が被保護者を放り出すのは育児放棄だろ」
「毎日食事作ってくれればそれでいいよ。ね、柊兄」
「そうだな」
勝手に進んでいく話に小夜は口を挟むことも出来ずにおろおろするだけだった。
「どう? 小夜ちゃん。うちにいるのが嫌じゃなければここに住みなよ」
「嫌ではないですけど……」
「じゃ、決まり」
楸矢はそう言うと食事を始めた。
柊矢も話は決まったという顔で食べ始めた。
小夜は戸惑いながらも、ここに住み続けられることに安心もしていた。
柊矢と話し合い小夜は食事を作る係になった。掃除は自分の部屋以外は三人で分担する、洗濯は自分のものだけ、その代わり部屋代や食費、光熱費などはただと決まった。
小夜は少しでも払うと言ったのだが、家事をしてもらうのだし、保護者が被保護者から受け取るわけにはいかないといって聞き入れてもらえなかった。
小夜の祖父のお骨は初七日に霞乃家の菩提寺に預けることになった。遺体が帰ってくるまでに一ヶ月以上かかったので初七日のときに四十九日の法要もすることになった。
翌日、休み時間に次の授業の用意をしていると、
「さーよ!」
清美が後ろから抱きついてきた。
「きゃ!」
後ろにひっくり返りそうになった小夜が悲鳴を上げた。
「あれ? ここになんかある」
清美は後ろから小夜の胸元を探った。
「ちょ、ちょっと、清美」
「ね、それ、何? ねぇ、何?」
清美の追求に小夜は柊矢に貰ったことを話した。
「えーっ、そこまでしてくれるなんて、その人、小夜に気があるんじゃない?」
この手の話は清美の大好物だ。
「そんなわけないでしょ。柊矢さんは大人なんだから」
小夜は自分に言い聞かせるように否定した。
「あたし達だってもう子供じゃないじゃん」
「でも、柊矢さんは違うの。楸矢さんだって柊矢さんはロリコンじゃないって言ってたし」
「だからあたし達はもう子供じゃないってば!」
清美は苛立ったように言った。
そういえば、清美は前に告白した相手に子供扱いされたって言ってすごく怒ってたっけ。
「柊矢さんから見たら子供だよ」
「そんなに年上なの? いくつ?」
「さぁ?」
「ダメじゃん、そう言うところはちゃんとチェックしなきゃ。ところで楸矢さんって誰?」
清美が訊ねた。
小夜は清美に柊矢の弟で十八歳だと説明した。
「その人は? 優しい? 身長は? 顔は?」
「楸矢さんは彼女いるよ。大人の付き合いしてるって言ってたもん」
「えーっ! 大人の付き合い!? すごーい!」
清美は「大人の付き合い」の意味が分かるんだ。
「大人の付き合いって何?」
「やだもう、小夜ってば!」
清美が思いきり小夜の背中を叩いた。
「痛っ!」
小夜が顔をしかめる。
結局、小夜にはまだ早いと言って「大人の付き合い」というのがなんなのか教えてくれなかった。
学校が早く終わったので小夜は、いつもと違ってバスに乗らず、超高層ビル群に向かった。
いつものように歌が風に乗ってながれている。
しかし小夜は足を止めずビル街を抜けて西新宿の自分の家に向かった。
家があった場所がどうなっているのか見てみたかったのだ。
ビルの間を抜け西新宿の住宅街へ入っていく。
小夜の家の跡には何も残っていなかった。瓦礫すらない。ただの空き地になっていた。
小夜は無意識に柊矢からもらった胸元のペンダントを握っていた。
大丈夫。
お祖父ちゃんが見守ってくれてる。
清美も柊矢さんや楸矢さんもいる。
きっとこれからも頑張れる。
泣いてばかりいるのはもうお終い。
空き地の片隅に花束が置かれていた。近所の人が置いてくれたのだろう。
小夜は花の前にしゃがんで手を合わせた。
小夜が帰ると柊矢はいつも音楽室でキタラを爪弾いていた。学校にいるときはキタラの音は聴こえてないから小夜が帰ってくる時間にあわせて音楽室に来ているのだろう。
小夜は自分の部屋に鞄を置くと着替えもしないまま音楽室へ向かった。
小夜が入っていくと柊矢がキタラを弾き始めた。それにあわせて歌い始めると、どこからか重唱や斉唱が聴こえてきた。徐々に歌声や演奏が加わっていく。
そのうちに楸矢も帰ってきて笛を吹き始めた。
そのまま数曲終えると小夜は夕食の支度を始めるために台所へ向かった。
柊矢も部屋に戻り、楸矢は一人残ってフルートの練習を始めた。
小夜が夕食の支度をしていると楸矢が入ってきた。
楸矢が椅子に座ったのを見て小夜は夕辺の残りのきんぴらごぼうをさっと暖めて出した。
いつも夕食の支度をしていると楸矢が台所へやってきてつまみ食いをするので最近はおやつを用意してある。大抵は前夜の残り物だ。
「有難う。いただきまーす!」
楸矢はすぐに食べ始めた。
「柊兄は?」
「部屋だと思いますよ」
「じゃ、仕事だね」
楸矢は空になった食器を差し出しながら言った。
小夜が残っているきんぴらごぼうを全部入れながら、
「柊矢さんって何のお仕事してるんですか?」
と訊ねた。
前から気になっていたのだ。出勤する様子はないし、かといって学生にも見えない。
そもそも二人家族で楸矢が高校生なのだから柊矢が働いていなければ食べていけないはずだ。
あ、でも、お祖父様が亡くなったって言ってたから遺産があるとか?
「あれ? 言ってなかったっけ? 不動産管理だよ」
「不動産屋さんなんですか?」
「不動産屋じゃなくて、不動産管理。俺の祖父ちゃんがいくつか不動産を残してくれてさ。それの家賃収入で食ってるんだ。柊兄がやってるのはその不動産の管理」
「そうだったんですか」
小夜は野菜を切りながら言った。
都内に不動産をいくつも持っているのだとしたらかなりの資産家と言うことになる。
「結構色々仕事あるらしいよ。管理人さんじゃ対応出来ない事務処理とか、保険関係のこととか」
そんなに忙しいのに小夜の祖父の保険等の手続きをしてくれたのだ。
色々な連絡も全部柊矢のところに行くようにして対応してくれていたのだろう。
小夜は改めて柊矢に感謝した。
「サラダのドレッシングは何がいいですか?」
「中華」
「和風がいい」
柊矢が台所へ入ってきながら言った。
「じゃあ、サラダは取り分けられるようにしておきますね」
夕食が出来上がり、三人が食卓に着くと食事が始まった。
「この前、森が出たとき歌った歌、覚えてるか?」
柊矢が話しかけてきた。
「ああ、あれ。確か……」
「え、森が出たの? いつ?」
「しばらく前だ」
「えっと……メーニナエイデテアーペーレーイーアデオーアキレーオス」
小夜は旋律を思い出しながら歌った。
「一体何語なんだろね」
楸矢が小夜の口ずさんだ歌を聴いて言った。
「もしかしたら分かるかもしれない」
「ホント?」
楸矢が疑わしげに言った。
二人とも歌が聴こえるのだ。何語なのか何度も話し合ったに違いない。
「今度の土曜、時間あるか?」
「はい」
「じゃあ、付き合ってくれ」
「はい」
「柊兄は小鳥ちゃんとデートか。じゃあ、俺も彼女、うちに呼ぼうかな」
「で、デートじゃありません」
小夜は赤くなって反論した。
「小鳥ちゃんの奥手は相変わらずだな」
柊矢がからかうように言った。
「二人してからかわないでください!」