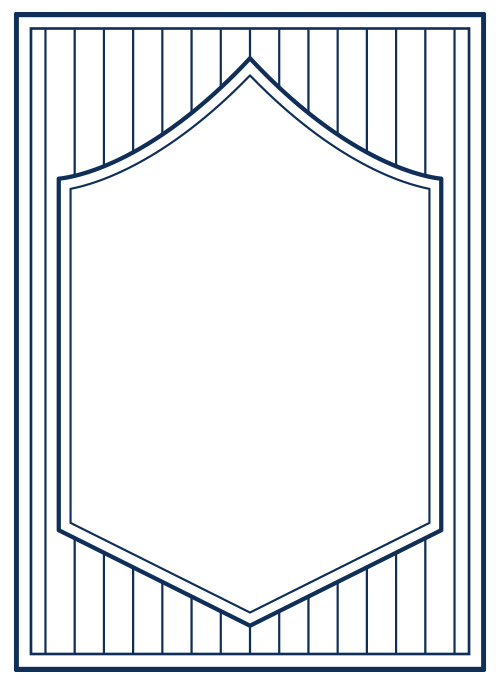第八章 惑星の子守唄
一
柊矢は小夜が作っている野菜の天ぷらの中からニンジンをつまむと口に入れた。
「柊矢さん、つまみ食いなんてダメですよ。楸矢さんみたいなことしないで下さい」
「じゃあ、他のものならいいのか?」
「他のものって、まだ天ぷらしか……」
「例えば……」
柊矢が小夜の耳元で囁こうとしたとき、
「柊兄、小夜ちゃんといちゃいちゃするなら俺も彼女と同棲するの認めてよ」
「い、いちゃいちゃなんて……」
小夜が赤くなって抗議した。
「ダメだ。同棲したらお前、彼女と寝るだろ。俺が出来ないのにお前だけするのは不公平だ」
「ととと、柊矢さん、何を……」
小夜が耳まで真っ赤になった。
「柊兄だって小夜ちゃんとすればいいじゃん」
「楸矢さん!」
「お前、こんな子供と寝て罪悪感持たずにいられるのか!」
柊矢が小夜を指さした。
「柊矢さんまで何言ってるんですか!」
「確かに……」
楸矢と目が合った小夜は赤くなったまま俯いた。
何を言っても墓穴を掘りそうだった。
それに、自分はもう子供じゃない、と言って、じゃあしようという話になっても困ると思うと何も言えなかった。
「大体、今はフルートの練習の時間だろう。見たくなければ音楽室で練習してろ」
「はいはい」
楸矢は大人しく音楽室へ向かった。
「これで二人きりだな」
柊矢は後ろから小夜に腕を回した。
「柊矢さん、私今夕食作ってるんですよ」
そのとき楸矢が笛で小夜のムーシカを吹き始めた。
すぐに他のムーソポイオスが歌い始める。
小夜が真っ赤になった。
「あいつ……」
柊矢は音楽室の方を睨んだ。
「俺は部屋で仕事してくる」
「支度が出来たら呼びますね」
「分かった」
柊矢はそう言うと出ていった。
楸矢は小夜のムーシカを吹き終えると気が済んだのかフルートの練習を始めた。
沙陽は昔柊矢が使っていたマグカップを床に叩き付けた。
自分のムーシカを無視しただけではなく小夜のムーシカに応えた。
ムーシコスの誰もが分かっただろう。
柊矢や小夜や沙陽を知らなくても、三人が三角関係だったことも沙陽が振られたことも。
同じ男に二度も振られるなんて。
こんな屈辱はない。
覚えてなさいよ。
絶対に許さない。
あの子も、柊矢も。
「やっぱりさぁ、ホワイトデーまで一ヶ月もいらないと思わない? 一週間もあれば準備出来るじゃん。男はチョコ作らないんだからさ」
清美がぼやいた。
未だに誰からも返事がないらしい。
もっとも返事をする気ならチョコを貰ったときにしただろう。
休み時間、小夜は清美とお喋りをしていた。
「清美の六号君が隣のクラスの坂田さんと歩いてったよ」
「嘘!」
清美が廊下の方を振り返った。
「ホントだ! 他の子選ぶならチョコ受け取るなっての!」
悔しそうに机を叩いた。
「受け取るよ。貰った数、競ってるんだもん」
「でも、まだ三十三人いるし」
「そんなに渡してたら皆義理だと思うって」
しかもそのうち十九人はバレンタインの翌日渡されたのだ。
「ちゃんと渡すとき本命だって言ったもん」
清美のことだから、なんの恥じらいもなく明るい口調で言ったのだろう。
想いを告げるのはムーシコスも地球人も大変だ。
歌うとそれがムーシコス全員に知られてしまうのも恥ずかしいが、チョコレートを渡しても本気にしてもらえないというのも困りものだ。
もっともバレンタインにあげるから義理だと思われるのではないのだろうか。
何もないときに告白すれば義理だと思われることは絶対ないだろう。
いや、清美の様に三十四人に同時に告白したら、からかわれたと思うのがオチか。
そもそも本命って普通一人なんじゃ……。
「ねぇ、楸矢さん、いつ紹介してくれるの?」
「分かったってば。今日、帰ったら聞いてみる」
「ありがと」
「でも、彼女いるんだからね」
「分かってるって」
本当に分かってるか怪しいが紹介するだけなら構わないだろう。
楸矢の彼女は婚活していると言っていたから結婚相手が見つかったら別れるだろうし。
その日、楸矢がおやつを食べに台所に現れたところをつかまえて清美の話をした。
「小夜ちゃんの友達? この前、小夜ちゃんが危ないって連絡くれた子?」
「そうです。楸矢さんに彼女がいることは話してあるんですけど……」
「いいよ。そういえば、小夜ちゃん、うちに友達連れてきたことなかったね。連れてきなよ」
「いいんですか?」
今まで居候だからと言うことで友達を呼ぶのを遠慮していたのだ。
「いいよ。どんどん連れてきて紹介してよ。ちなみに、俺、明日は学校ないから」
楸矢は高校三年の上に音大への進学もとっくに決まっているから三学期はあまり学校へ行っていなかった。
「ありがとうございます」
そう言ってから、
「楸矢さん、二股かけるのだけはやめてくださいね」
と釘を刺した。
「ホント?」
小夜が楸矢がOKしたと伝えると清美が嬉しそうな顔をした。
「うん。柊矢さんもいいって言ってくれたし、良かったら今日来ない?」
「行く! やった!」
その日の放課後、清美と一緒に柊矢の車で家に帰るとリビングに楸矢が紅茶とクッキーを用意して待っていた。
「いらっしゃい」
「こんにちは!」
清美は礼儀正しくお辞儀した。
「ま、座って」
清美に続いて小夜も座ろうとしたとき、
「小夜、ちょっと来てくれ」
柊矢に呼ばれた。
「はい。清美、ゴメンね。楸矢さんとお話ししてて」
「こっちは気にしなくていいからごゆっくり」
「清美!」
小夜は赤くなって清美を睨んでから柊矢と音楽室へ入った。
柊矢がガラス棚の戸を開く。
「キタラ弾くんですか?」
「いや、彼女はムーシコスじゃないんだろ」
「はい」
「楸矢にだけ聴こえたらまた文句言われるからな」
柊矢はそういってヴァイオリンを出した。
あ……。
ヴァイオリン、弾いてくれるんだ……。
「何年も弾いてないから腕は鈍ってると思うが……」
柊矢は調弦をした後、ヴァイオリンを弾き始めた。
うわぁ……。
これで鈍ってるなんて信じられない……。
綺麗な音色……。
小夜は感動して柊矢のヴァイオリンを聴いていた。
「これだよ……」
清美と話をしていた楸矢は頭を抱えた。
音楽室からヴァイオリンの音色が聴こえてくる。
防音とは言え隣の部屋だとどうしても聴こえてしまう。
「楸矢さん、この曲って……」
清美が音楽室の方を見ながら訊ねた。
「セレナーデ。小夜ちゃんへの」
「これがセレナーデっていう曲なんですか?」
「いや、曲名は『Love's Greeting』 、日本名は『愛の挨拶』。セレナーデって言うのは音楽のジャンルでもあるけど、恋人のために窓の下とかで演奏する場合も指す言葉。今がまさにそう。窓の下じゃないけど」
「こういうの、毎日聴かされてるんですか?」
「そんなとこ」
「うわ、きっつ……」
「分かってくれる?」
楸矢が身を乗り出した。
「分かります!」
清美が力強く頷いた。
「ありがとう~。分かってくれる人がいて嬉しいよ」
「柊矢さんってもっとドライで冷静沈着な人だと思ってました」
「俺も」
柊兄って周りが見えなくなるタイプだったんだなぁ……。
とはいえ恋してる最中というのを抜きにしてもここまで見えなくなるとは思ってなかった。
少なくとも沙陽と付き合っていた時はこんな風にはなってなかった。
あの頃ならまだ十代だったから、こうなったとしても若いからと言うことで納得できたが今はもう二十六だ。
柊矢の話だと、沙陽は柊矢と桂のどちらかがムーシコスだと当たりを付けて二人に近付いてきてムーシコスの振りをした桂を選んだらしい。
多分、沙陽と付き合っていたのは綺麗な女の子が言い寄ってきたからというだけで元々好みは小夜みたいなタイプだったのだろう。
「楸矢さんも大変ですねぇ」
柊矢と小夜、二人して毎日こんな調子なんだとしたら楸矢はたまったものではないだろう。
清美は心底同情した。
「清美ちゃん、また来てね」
「はい! 小夜、またね」
清美は柊矢の車の窓から手を振ると柊矢に送られて帰っていった。
一
柊矢は小夜が作っている野菜の天ぷらの中からニンジンをつまむと口に入れた。
「柊矢さん、つまみ食いなんてダメですよ。楸矢さんみたいなことしないで下さい」
「じゃあ、他のものならいいのか?」
「他のものって、まだ天ぷらしか……」
「例えば……」
柊矢が小夜の耳元で囁こうとしたとき、
「柊兄、小夜ちゃんといちゃいちゃするなら俺も彼女と同棲するの認めてよ」
「い、いちゃいちゃなんて……」
小夜が赤くなって抗議した。
「ダメだ。同棲したらお前、彼女と寝るだろ。俺が出来ないのにお前だけするのは不公平だ」
「ととと、柊矢さん、何を……」
小夜が耳まで真っ赤になった。
「柊兄だって小夜ちゃんとすればいいじゃん」
「楸矢さん!」
「お前、こんな子供と寝て罪悪感持たずにいられるのか!」
柊矢が小夜を指さした。
「柊矢さんまで何言ってるんですか!」
「確かに……」
楸矢と目が合った小夜は赤くなったまま俯いた。
何を言っても墓穴を掘りそうだった。
それに、自分はもう子供じゃない、と言って、じゃあしようという話になっても困ると思うと何も言えなかった。
「大体、今はフルートの練習の時間だろう。見たくなければ音楽室で練習してろ」
「はいはい」
楸矢は大人しく音楽室へ向かった。
「これで二人きりだな」
柊矢は後ろから小夜に腕を回した。
「柊矢さん、私今夕食作ってるんですよ」
そのとき楸矢が笛で小夜のムーシカを吹き始めた。
すぐに他のムーソポイオスが歌い始める。
小夜が真っ赤になった。
「あいつ……」
柊矢は音楽室の方を睨んだ。
「俺は部屋で仕事してくる」
「支度が出来たら呼びますね」
「分かった」
柊矢はそう言うと出ていった。
楸矢は小夜のムーシカを吹き終えると気が済んだのかフルートの練習を始めた。
沙陽は昔柊矢が使っていたマグカップを床に叩き付けた。
自分のムーシカを無視しただけではなく小夜のムーシカに応えた。
ムーシコスの誰もが分かっただろう。
柊矢や小夜や沙陽を知らなくても、三人が三角関係だったことも沙陽が振られたことも。
同じ男に二度も振られるなんて。
こんな屈辱はない。
覚えてなさいよ。
絶対に許さない。
あの子も、柊矢も。
「やっぱりさぁ、ホワイトデーまで一ヶ月もいらないと思わない? 一週間もあれば準備出来るじゃん。男はチョコ作らないんだからさ」
清美がぼやいた。
未だに誰からも返事がないらしい。
もっとも返事をする気ならチョコを貰ったときにしただろう。
休み時間、小夜は清美とお喋りをしていた。
「清美の六号君が隣のクラスの坂田さんと歩いてったよ」
「嘘!」
清美が廊下の方を振り返った。
「ホントだ! 他の子選ぶならチョコ受け取るなっての!」
悔しそうに机を叩いた。
「受け取るよ。貰った数、競ってるんだもん」
「でも、まだ三十三人いるし」
「そんなに渡してたら皆義理だと思うって」
しかもそのうち十九人はバレンタインの翌日渡されたのだ。
「ちゃんと渡すとき本命だって言ったもん」
清美のことだから、なんの恥じらいもなく明るい口調で言ったのだろう。
想いを告げるのはムーシコスも地球人も大変だ。
歌うとそれがムーシコス全員に知られてしまうのも恥ずかしいが、チョコレートを渡しても本気にしてもらえないというのも困りものだ。
もっともバレンタインにあげるから義理だと思われるのではないのだろうか。
何もないときに告白すれば義理だと思われることは絶対ないだろう。
いや、清美の様に三十四人に同時に告白したら、からかわれたと思うのがオチか。
そもそも本命って普通一人なんじゃ……。
「ねぇ、楸矢さん、いつ紹介してくれるの?」
「分かったってば。今日、帰ったら聞いてみる」
「ありがと」
「でも、彼女いるんだからね」
「分かってるって」
本当に分かってるか怪しいが紹介するだけなら構わないだろう。
楸矢の彼女は婚活していると言っていたから結婚相手が見つかったら別れるだろうし。
その日、楸矢がおやつを食べに台所に現れたところをつかまえて清美の話をした。
「小夜ちゃんの友達? この前、小夜ちゃんが危ないって連絡くれた子?」
「そうです。楸矢さんに彼女がいることは話してあるんですけど……」
「いいよ。そういえば、小夜ちゃん、うちに友達連れてきたことなかったね。連れてきなよ」
「いいんですか?」
今まで居候だからと言うことで友達を呼ぶのを遠慮していたのだ。
「いいよ。どんどん連れてきて紹介してよ。ちなみに、俺、明日は学校ないから」
楸矢は高校三年の上に音大への進学もとっくに決まっているから三学期はあまり学校へ行っていなかった。
「ありがとうございます」
そう言ってから、
「楸矢さん、二股かけるのだけはやめてくださいね」
と釘を刺した。
「ホント?」
小夜が楸矢がOKしたと伝えると清美が嬉しそうな顔をした。
「うん。柊矢さんもいいって言ってくれたし、良かったら今日来ない?」
「行く! やった!」
その日の放課後、清美と一緒に柊矢の車で家に帰るとリビングに楸矢が紅茶とクッキーを用意して待っていた。
「いらっしゃい」
「こんにちは!」
清美は礼儀正しくお辞儀した。
「ま、座って」
清美に続いて小夜も座ろうとしたとき、
「小夜、ちょっと来てくれ」
柊矢に呼ばれた。
「はい。清美、ゴメンね。楸矢さんとお話ししてて」
「こっちは気にしなくていいからごゆっくり」
「清美!」
小夜は赤くなって清美を睨んでから柊矢と音楽室へ入った。
柊矢がガラス棚の戸を開く。
「キタラ弾くんですか?」
「いや、彼女はムーシコスじゃないんだろ」
「はい」
「楸矢にだけ聴こえたらまた文句言われるからな」
柊矢はそういってヴァイオリンを出した。
あ……。
ヴァイオリン、弾いてくれるんだ……。
「何年も弾いてないから腕は鈍ってると思うが……」
柊矢は調弦をした後、ヴァイオリンを弾き始めた。
うわぁ……。
これで鈍ってるなんて信じられない……。
綺麗な音色……。
小夜は感動して柊矢のヴァイオリンを聴いていた。
「これだよ……」
清美と話をしていた楸矢は頭を抱えた。
音楽室からヴァイオリンの音色が聴こえてくる。
防音とは言え隣の部屋だとどうしても聴こえてしまう。
「楸矢さん、この曲って……」
清美が音楽室の方を見ながら訊ねた。
「セレナーデ。小夜ちゃんへの」
「これがセレナーデっていう曲なんですか?」
「いや、曲名は『Love's Greeting』 、日本名は『愛の挨拶』。セレナーデって言うのは音楽のジャンルでもあるけど、恋人のために窓の下とかで演奏する場合も指す言葉。今がまさにそう。窓の下じゃないけど」
「こういうの、毎日聴かされてるんですか?」
「そんなとこ」
「うわ、きっつ……」
「分かってくれる?」
楸矢が身を乗り出した。
「分かります!」
清美が力強く頷いた。
「ありがとう~。分かってくれる人がいて嬉しいよ」
「柊矢さんってもっとドライで冷静沈着な人だと思ってました」
「俺も」
柊兄って周りが見えなくなるタイプだったんだなぁ……。
とはいえ恋してる最中というのを抜きにしてもここまで見えなくなるとは思ってなかった。
少なくとも沙陽と付き合っていた時はこんな風にはなってなかった。
あの頃ならまだ十代だったから、こうなったとしても若いからと言うことで納得できたが今はもう二十六だ。
柊矢の話だと、沙陽は柊矢と桂のどちらかがムーシコスだと当たりを付けて二人に近付いてきてムーシコスの振りをした桂を選んだらしい。
多分、沙陽と付き合っていたのは綺麗な女の子が言い寄ってきたからというだけで元々好みは小夜みたいなタイプだったのだろう。
「楸矢さんも大変ですねぇ」
柊矢と小夜、二人して毎日こんな調子なんだとしたら楸矢はたまったものではないだろう。
清美は心底同情した。
「清美ちゃん、また来てね」
「はい! 小夜、またね」
清美は柊矢の車の窓から手を振ると柊矢に送られて帰っていった。