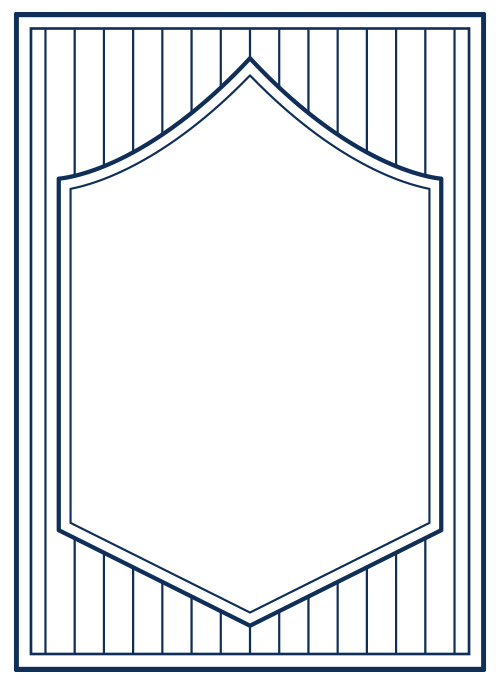五
バレンタインの日、小夜が夕食を作っていると楸矢がおやつを食べに音楽室から出てきた。
チョコレートは朝食の時、二人に同時に渡しておいた。そうすれば恥ずかしくないかな、と思ったからだ。
楸矢に前日の残りのおひたしを出していると、玄関のドアが開く音がした。どこかに出掛けていた柊矢が帰ってきたようだ。
「柊兄、どこに行ってたんだろ」
おやつを食べていた楸矢が言った。
「さぁ?」
小夜が首を傾げたとき柊矢が白いマーガレットの花束を手にして入ってきた。
柊矢は黙って花束を小夜に渡した。
「え?」
訳が分からず戸惑っている間に柊矢は自分の部屋へ上がってしまった。
小夜は楸矢を見た。
「それ、柊兄からの小夜ちゃんへのバレンタインプレゼント」
「でも、バレンタインって……」
柊兄、ちゃんと説明してってよ。
楸矢は溜息をついて、
「女の子がチョコレートを送る習慣って言うのは日本のお菓子会社が作ったもので、欧米では男女ともに恋人に贈り物をしあうの」
と説明した。
「こっ……、や、やっぱり、私宛じゃないですよ!」
小夜が真っ赤になった。
「小夜ちゃんに渡したでしょ」
小夜は耳まで赤くなって俯いた。
「小夜ちゃん、お鍋!」
「あ!」
小夜は慌てて鍋の方に向き直った。
焦げていないのを確認してから花束を花瓶に入れて食卓に飾る。
「小夜ちゃんの部屋に飾った方がいいんじゃないの?」
「でも、本当に私宛か分からないですから」
夕食が終わり、片付けをしているときだった。
楸矢は小夜が翌日の弁当用に作ったきんぴらごぼうのあまりを食べていた。
「楸矢さん、それだけ食べててよく太りませんね」
小夜が呆れたように言ったとき沙陽のムーシカが聴こえてきた。
これ、ラブソングだ。柊矢さんへの。
「声楽科に行ってただけはあるね。技巧はさすがだけど、そっちに神経がいってて心が入ってないな」
楸矢が冷静に批評した。
テクニックに拘りすぎててかなり人工的な印象を受ける。
ムーシカが感情の発露で自然に出来るものだとしたら、沙陽が歌っているのはムーシコスに聴こえると言うだけでムーシカではなく(地球人の)歌だ。
地球人には高く評価されるだろうがムーシコスの心には響かない。
ムーシケーのムーシカは聴いてないが、小夜のムーシカを聴けばどんなものだったのかは想像が付く。
感情よりテクニックに走った〝歌〟を作っているようではムーシケーの気持ちなど分かるわけがない。
クレーイス・エコーから外されるわけだ……。
小夜のムーシカと沙陽の〝歌〟を聴いて、どちらが柊矢への想いが強いかと訊ねたら、ムーシコスは皆小夜だと答えるだろう。
そのとき柊矢が台所に姿を見せた。
「ちょっといいか?」
柊矢が小夜を呼んだ。
「はい」
柊矢は小夜を音楽室に連れていった。
「小夜、お前にだ」
え?
小夜って……私の名前、呼んでくれた?
柊矢は小夜を自分の向かいに座らせると沙陽のムーシカを無視してキタラを弾き始めた。
このムーシカ……。
自分宛のラブソングだと気付くと小夜は真っ赤になった。
柊矢は歌わないので歌詞はないが所々に小夜のムーシカの旋律が使われているから対になっている曲だとすぐに分かった。
「柊矢さん……」
小夜が感激しているとき楸矢は台所でテーブルに頭をぶつけていた。
「こういうことするなら先に言っといてくれれば今夜は彼女の家に泊まったのに」
ムーシカだから彼女の家にいても聴こえてしまうが一人で聴かされるよりは遙かにマシだ。
柊矢は弾き終えると、
「歌詞、付けられるか?」
と訊ねた。
「はい」
柊矢がもう一度弾き始める。
小夜は心の中に湧き上がってくる感情のままに歌詞を付けた。
すぐに他のムーソポイオスがコーラスを重ねる。
歌い終えると、柊矢と小夜の目が合った。
お互い頬が赤く染まって視線を逸らした。
「もう遅い。そろそろ寝た方がいい」
「はい。お休みなさい」
小夜は音楽室を出ようとして、
「あの、さっきの花束、私にですか?」
と訊ねた。
「ああ」
「有難うございます」
小夜は頭を下げると、台所へ入った。楸矢は部屋へ戻ったのか台所にはいなかった。
小夜は花束を入れた花瓶ごと抱えると自室へ戻った。
翌日、学校へ行くと清美が寄ってきた。
「ちょっとマシになってたのに、またぎこちなくなってるけど、なんかあった?」
「その、柊矢さんからお返事があったって言うか……」
「なんて言われたの!」
清美が身を乗り出した。
「あのね、前に柊矢さんは楽器をやってるって言ったでしょ……」
「まさかとは思うけどセレナーデでも弾いたとか」
「あれがセレナーデなのかどうかは分から……」
「ホントに弾いたの!?」
清美が大声を出した。
「清美、声が大きい」
小夜は慌てて左右を見回した。
「あんた達、痛すぎ! 柊矢さんも普段はクールな人なのにそう言うことするんだ!」
清美が信じられないという表情で言った。
「一応聞くけど、それ、柊矢さんの……」
「……オリジナル……」
「あいたたたた……」
清美が額を押さえた。
「そのとき楸矢さんはどこにいたの?」
「台所だけどドアは閉まっ……あ!」
しまった!
あれはムーシカな上に弾いた楽器がキタラだ。音楽室のドアが閉まってても聴こえてしまっていたのだ。
「それで楸矢さん、今朝まともに顔見てくれなかったんだ」
「楸矢さんも可哀相に。とんだバカップル誕生だわ」
「バカップルって言うのやめてよ」
「だって、そうでしょうが」
そんなこと言ったってしょうがないじゃん。
私達、ムーシコスなんだもん。
小夜は俯いた。
それから上目遣いで、
「そんなに痛い?」
と訊ねた。
「痛いなんてもんじゃないわよ」
清美が冷たい声で答えた。
「で、その後どうしたの?」
「柊矢さんの曲に私が歌詞を……」
「歌の話はもういいから、その後よ」
「自分の部屋に帰って寝た」
「それだけ?」
「うん、興奮しちゃってなかなか寝付けなかったけど……」
「念の為に聞くけど一人で?」
「清美! 怒るよ!」
小夜が赤くなった。
「だって、普通想いを確かめ合ったらキスくらいしない?」
「キ……!」
小夜が真っ赤になった。
「清美!」
「あー、もうやってらんない。あたしも早く彼氏作んなきゃ。なんでバレンタインの翌日がホワイトデーじゃないんだろ」
「用意する時間がないからじゃない?」
「こうなったら一日遅れだけど次点にも配ろうっと」
「次点って、渡したの一人だけだったの?」
確か十五人に渡すと言ってたはずだ。
「まさか、ちゃんと十五人に配ったわよ。でも、次点の十九人にも配る」
「十九人!?」
それ次点って言わないんじゃ……。
「小夜、楸矢さん紹介してよ。楸矢さんにも配るから」
配るって……。
『渡す』じゃなくて『配る』?
「清美、今日渡されたって義理の残りだって思われるのがオチだって」
そんな話をしてるうちに予鈴が鳴った。
休み時間、清美は隣の席の小夜に向き直った。
「で、楸矢さん、いつ紹介してくれるの?」
「楸矢さん、彼女いるってば」
「どんな人?」
「さあ?」
小夜は首を傾げた。
そう言えば名前も聞いたことがなかった。
ただ、いるのは嘘ではない。
何度か楸矢の部屋のドアのネームプレートがひっくり返っており中から女性の声がしたことがあった。
「柊矢さんと同い年ってことくらいしか」
「柊矢さんっていくつ?」
「この前、二十六歳になった」
「二十六!? あんたと柊矢さんって十歳も離れてるの!? なんか犯罪臭がする」
「は、犯罪って、清美が言ったんだよ。私達はもう子供じゃないって」
「でもさぁ、しちゃったら犯罪になるよね」
「し、し……清美! そう言うこと言わないでよ!」
小夜が真っ赤になって抗議した。
「あたしは年相応の彼氏作るんだ。しちゃっても犯罪にならない相手」
もう好きにして……。
小夜は溜息をついた。
放課後、柊矢の車に乗ると訊ねてみた。
「あの、夕辺のムーシカ、楸矢さんにも聴こえて……」
「ああ、後で散々文句言われた」
やっぱり……。
小夜は赤くなって俯いた。
バレンタインの日、小夜が夕食を作っていると楸矢がおやつを食べに音楽室から出てきた。
チョコレートは朝食の時、二人に同時に渡しておいた。そうすれば恥ずかしくないかな、と思ったからだ。
楸矢に前日の残りのおひたしを出していると、玄関のドアが開く音がした。どこかに出掛けていた柊矢が帰ってきたようだ。
「柊兄、どこに行ってたんだろ」
おやつを食べていた楸矢が言った。
「さぁ?」
小夜が首を傾げたとき柊矢が白いマーガレットの花束を手にして入ってきた。
柊矢は黙って花束を小夜に渡した。
「え?」
訳が分からず戸惑っている間に柊矢は自分の部屋へ上がってしまった。
小夜は楸矢を見た。
「それ、柊兄からの小夜ちゃんへのバレンタインプレゼント」
「でも、バレンタインって……」
柊兄、ちゃんと説明してってよ。
楸矢は溜息をついて、
「女の子がチョコレートを送る習慣って言うのは日本のお菓子会社が作ったもので、欧米では男女ともに恋人に贈り物をしあうの」
と説明した。
「こっ……、や、やっぱり、私宛じゃないですよ!」
小夜が真っ赤になった。
「小夜ちゃんに渡したでしょ」
小夜は耳まで赤くなって俯いた。
「小夜ちゃん、お鍋!」
「あ!」
小夜は慌てて鍋の方に向き直った。
焦げていないのを確認してから花束を花瓶に入れて食卓に飾る。
「小夜ちゃんの部屋に飾った方がいいんじゃないの?」
「でも、本当に私宛か分からないですから」
夕食が終わり、片付けをしているときだった。
楸矢は小夜が翌日の弁当用に作ったきんぴらごぼうのあまりを食べていた。
「楸矢さん、それだけ食べててよく太りませんね」
小夜が呆れたように言ったとき沙陽のムーシカが聴こえてきた。
これ、ラブソングだ。柊矢さんへの。
「声楽科に行ってただけはあるね。技巧はさすがだけど、そっちに神経がいってて心が入ってないな」
楸矢が冷静に批評した。
テクニックに拘りすぎててかなり人工的な印象を受ける。
ムーシカが感情の発露で自然に出来るものだとしたら、沙陽が歌っているのはムーシコスに聴こえると言うだけでムーシカではなく(地球人の)歌だ。
地球人には高く評価されるだろうがムーシコスの心には響かない。
ムーシケーのムーシカは聴いてないが、小夜のムーシカを聴けばどんなものだったのかは想像が付く。
感情よりテクニックに走った〝歌〟を作っているようではムーシケーの気持ちなど分かるわけがない。
クレーイス・エコーから外されるわけだ……。
小夜のムーシカと沙陽の〝歌〟を聴いて、どちらが柊矢への想いが強いかと訊ねたら、ムーシコスは皆小夜だと答えるだろう。
そのとき柊矢が台所に姿を見せた。
「ちょっといいか?」
柊矢が小夜を呼んだ。
「はい」
柊矢は小夜を音楽室に連れていった。
「小夜、お前にだ」
え?
小夜って……私の名前、呼んでくれた?
柊矢は小夜を自分の向かいに座らせると沙陽のムーシカを無視してキタラを弾き始めた。
このムーシカ……。
自分宛のラブソングだと気付くと小夜は真っ赤になった。
柊矢は歌わないので歌詞はないが所々に小夜のムーシカの旋律が使われているから対になっている曲だとすぐに分かった。
「柊矢さん……」
小夜が感激しているとき楸矢は台所でテーブルに頭をぶつけていた。
「こういうことするなら先に言っといてくれれば今夜は彼女の家に泊まったのに」
ムーシカだから彼女の家にいても聴こえてしまうが一人で聴かされるよりは遙かにマシだ。
柊矢は弾き終えると、
「歌詞、付けられるか?」
と訊ねた。
「はい」
柊矢がもう一度弾き始める。
小夜は心の中に湧き上がってくる感情のままに歌詞を付けた。
すぐに他のムーソポイオスがコーラスを重ねる。
歌い終えると、柊矢と小夜の目が合った。
お互い頬が赤く染まって視線を逸らした。
「もう遅い。そろそろ寝た方がいい」
「はい。お休みなさい」
小夜は音楽室を出ようとして、
「あの、さっきの花束、私にですか?」
と訊ねた。
「ああ」
「有難うございます」
小夜は頭を下げると、台所へ入った。楸矢は部屋へ戻ったのか台所にはいなかった。
小夜は花束を入れた花瓶ごと抱えると自室へ戻った。
翌日、学校へ行くと清美が寄ってきた。
「ちょっとマシになってたのに、またぎこちなくなってるけど、なんかあった?」
「その、柊矢さんからお返事があったって言うか……」
「なんて言われたの!」
清美が身を乗り出した。
「あのね、前に柊矢さんは楽器をやってるって言ったでしょ……」
「まさかとは思うけどセレナーデでも弾いたとか」
「あれがセレナーデなのかどうかは分から……」
「ホントに弾いたの!?」
清美が大声を出した。
「清美、声が大きい」
小夜は慌てて左右を見回した。
「あんた達、痛すぎ! 柊矢さんも普段はクールな人なのにそう言うことするんだ!」
清美が信じられないという表情で言った。
「一応聞くけど、それ、柊矢さんの……」
「……オリジナル……」
「あいたたたた……」
清美が額を押さえた。
「そのとき楸矢さんはどこにいたの?」
「台所だけどドアは閉まっ……あ!」
しまった!
あれはムーシカな上に弾いた楽器がキタラだ。音楽室のドアが閉まってても聴こえてしまっていたのだ。
「それで楸矢さん、今朝まともに顔見てくれなかったんだ」
「楸矢さんも可哀相に。とんだバカップル誕生だわ」
「バカップルって言うのやめてよ」
「だって、そうでしょうが」
そんなこと言ったってしょうがないじゃん。
私達、ムーシコスなんだもん。
小夜は俯いた。
それから上目遣いで、
「そんなに痛い?」
と訊ねた。
「痛いなんてもんじゃないわよ」
清美が冷たい声で答えた。
「で、その後どうしたの?」
「柊矢さんの曲に私が歌詞を……」
「歌の話はもういいから、その後よ」
「自分の部屋に帰って寝た」
「それだけ?」
「うん、興奮しちゃってなかなか寝付けなかったけど……」
「念の為に聞くけど一人で?」
「清美! 怒るよ!」
小夜が赤くなった。
「だって、普通想いを確かめ合ったらキスくらいしない?」
「キ……!」
小夜が真っ赤になった。
「清美!」
「あー、もうやってらんない。あたしも早く彼氏作んなきゃ。なんでバレンタインの翌日がホワイトデーじゃないんだろ」
「用意する時間がないからじゃない?」
「こうなったら一日遅れだけど次点にも配ろうっと」
「次点って、渡したの一人だけだったの?」
確か十五人に渡すと言ってたはずだ。
「まさか、ちゃんと十五人に配ったわよ。でも、次点の十九人にも配る」
「十九人!?」
それ次点って言わないんじゃ……。
「小夜、楸矢さん紹介してよ。楸矢さんにも配るから」
配るって……。
『渡す』じゃなくて『配る』?
「清美、今日渡されたって義理の残りだって思われるのがオチだって」
そんな話をしてるうちに予鈴が鳴った。
休み時間、清美は隣の席の小夜に向き直った。
「で、楸矢さん、いつ紹介してくれるの?」
「楸矢さん、彼女いるってば」
「どんな人?」
「さあ?」
小夜は首を傾げた。
そう言えば名前も聞いたことがなかった。
ただ、いるのは嘘ではない。
何度か楸矢の部屋のドアのネームプレートがひっくり返っており中から女性の声がしたことがあった。
「柊矢さんと同い年ってことくらいしか」
「柊矢さんっていくつ?」
「この前、二十六歳になった」
「二十六!? あんたと柊矢さんって十歳も離れてるの!? なんか犯罪臭がする」
「は、犯罪って、清美が言ったんだよ。私達はもう子供じゃないって」
「でもさぁ、しちゃったら犯罪になるよね」
「し、し……清美! そう言うこと言わないでよ!」
小夜が真っ赤になって抗議した。
「あたしは年相応の彼氏作るんだ。しちゃっても犯罪にならない相手」
もう好きにして……。
小夜は溜息をついた。
放課後、柊矢の車に乗ると訊ねてみた。
「あの、夕辺のムーシカ、楸矢さんにも聴こえて……」
「ああ、後で散々文句言われた」
やっぱり……。
小夜は赤くなって俯いた。