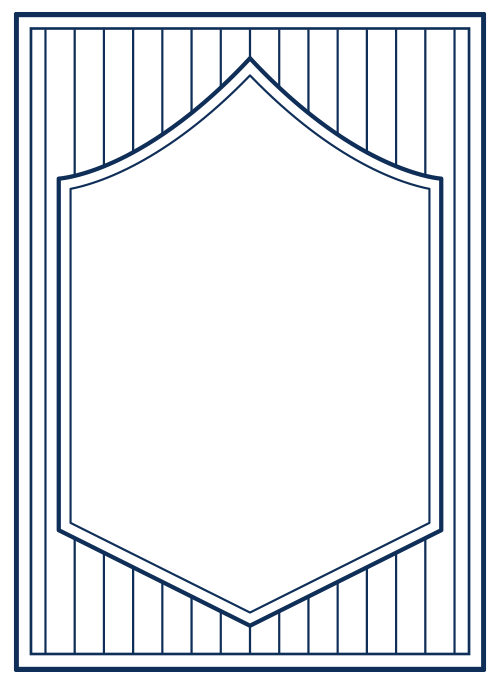二
小夜は夕食が終わると音楽室で、さっきから胸に沸き上がってきていたムーシカを歌っていた。
ムーシケーのラブソングを聴いて浮かんできた曲だった。
新しいムーシカだから他のムーシコスは大人しく聴いていた。
「参ったな」
楸矢は小夜の歌声を聞きながら頭を抱えた。
柊矢はさっきコーヒーカップを持って二階へと上がってしまった。
「小夜ちゃん、ストレートすぎ」
歌詞に、恋とか愛とか好きとか言う言葉は入っていないが、これは明らかに柊矢を想うムーシカだった。
柊矢もそれに気付いたから楸矢と顔を合わせづらくて自室へ逃げたのだろう。
「ムーシカってムーシコスの感情そのものだったんだなぁ……」
小夜が喉を治してくれたお礼のムーシカを歌ったことがあったが、それ以外ではムーシカが創られるところに居合わせたことがなかったから、ここまではっきり感情が表れるものだとは知らなかった。
今日、小夜がムーシケーのムーシカがラブソングだったと言ったとき、歌詞がなかったのになんでラブソングだって言い切れるんだろうと思ったが、確かにこれだけ露骨に感情が表れてれば歌詞がなくてもはっきり分かる。
喉が治ったときのムーシカはお礼の意味で歌われたが、多分お礼のムーシカとして創られたものではなかったのだろう。
おそらく歌えなかった時期に出来たムーシカだったのだ。
だからピアノを教えて欲しいと頼んできたのだろう。
自分が創ったムーシカを伝えられるようになりたかったのだ。
椿矢の祖父の伯母(大伯母)が地球人と駆け落ちしたらしいが創ったムーシカにここまで剥き出しの感情が表れてしまうのだとしたら、
「そりゃ、地球人と逃げたくなるよなぁ」
楸矢は椿矢の大伯母に深く共感した。
椿矢の家はムーシコスの家系らしいから周囲にいるのはムーシコスばかりだったはずだし、そうだとするとこういう場面に出くわすこともよくあっただろう。
こんなことが頻繁にあったら身が持たない。
椿矢がムーシコスの血は大分薄れてきていると言っていたらしいが、四千年という時間経過のせいだけではなく、多分これに耐えかねて地球人を選んだ者が多かったのではないだろうか。
いくらムーシコスが音楽に弱いとは言え、これが平気なのは相当な音楽バカだけだろう。
俺も絶対地球人と結婚しよう。
楸矢はそう心に誓った。
小夜のムーシカを聴きながら、
「明日からどんな顔して会えばいいんだろ」
と独りごちた。
「小夜、なんかあったの?」
教室に入るなり清美が聞いてきた。
車から降りたときの柊矢と小夜のぎこちない様子を見ていたらしい。
「清美……、どうしよう……、私、柊矢さんのこと好きになっちゃったみたい」
「小夜、それ今更過ぎだから」
清美が冷めた口調で言った。
「今までも好きだと思ってたの! 柊矢さんの前で好きって言っちゃったこともあったけど、それが恋だと思ってたけど、全然違った! どうしよう! どうしたらいい?」
小夜は狼狽えた様子で言った。
「どうしようって、どうしようもないでしょ。もう告白したなら……」
「してない!」
小夜が強く否定した。
それから自信がなさそうに、
「したことになるのかな?」
と首を傾げた。
「してなかったら柊矢さんまであんな態度取るわけないじゃん」
清美が冷たい声で言った。
「柊矢さんの聞いてるところでム……歌、歌ったの。柊矢さんを想う歌……」
小夜の声がだんだん小さくなっていった。
「でも、あんなにはっきり意思表示するつもりはなかったの」
小夜が言い訳するように言った。
「楸矢さんまでまともに顔あわせてくれないし」
「二人の目の前で歌ったの?」
清美が信じられないという顔をした。
「目の前じゃなくて、別の部屋だけど……」
「一応確認のために聞くけど、その歌って小夜のオリジナルソング?」
小夜は頷いた。
「うわ、それ痛すぎ!」
清美が大袈裟に仰け反った。
「そりゃ、どん引きするわ」
ムーシコスではない清美には歌――ムーシカ――で想いを伝えてしまったというのは理解できないのだ。
四千年も共存してきたのに、まだムーシコスと地球人の間には分かり合えない溝がある。
そのとき夕辺小夜が歌ったムーシカが聴こえてきた。
嘘!
突然真っ赤になった小夜に、
「小夜、どうしたの?」
清美が驚いた様子で顔を覗き込んできた。
「もうダメ。死にたい」
小夜は机に突っ伏した。
小夜のムーシカは、素直な感情表現に好感を持たれたのか、新曲のラブソングだからなのか、日に一度は歌われるようになった。多い日は二度、三度のこともあった。
授業中にも容赦なく聴こえてくる。
「霞乃、どうした、顔が赤いぞ」
数学の教師が小夜を見て言った。
「な、なんでもないです」
小夜は真っ赤な顔で俯いた。
「熱でもあるんじゃないのか?」
「だ、大丈夫です」
「ただの恋煩いだもんね~」
隣の席の清美が小声で呟いた。
「清美!」
小夜が横目で睨んだ。
「小夜、はっきり聞いていい?」
二人は校門の前で柊矢の車を待っていた。
小夜が清美に相談したいことがあるから一緒に待って欲しいと頼んだのだ。
「何?」
「柊矢さんと何かあった?」
「何もないよ。あったらこんなに悩まないって」
柊矢とはあれ以来ぎこちないままで必要最低限のことしか話していなかった。
「突然真っ赤になったりするのって、Hしちゃって、それ思い出してるからじゃないの?」
「清美! ホントに怒るよ!」
小夜が頬を朱に染めて言った。
「奥手の小夜に限ってそれはないかぁ。柊矢さんだって両手が後ろに回っちゃうしね」
「え! 清美! それどういうこと?」
小夜は身を乗り出した。
柊矢の友達が同じ事を言っていた。
あのとき意味が分からなかったのだ。
「大人が未成年の子と寝ると犯罪でしょ」
そう言う意味だったんだ!
小夜は更に赤くなった。
「ちょ、ちょっと、小夜! あんた、ホントに……」
清美が小夜に詰め寄った。
「ち、違うって!」
小夜は慌てて両手を振った。
「柊矢さんの友達が同じこと言って柊矢さんをからかったことがあったの! そのとき意味が分からなかったから……」
「それならいいけど……」
「もしかして、大人の付き合いって、そう言うこと?」
小夜が訊ねた。
「そうだよ」
じゃあ、ひょっとして、楸矢さんが言ってた後部座席っていうのも……。
清美に聞いてみようかと思ったが、もしホントにそう言う意味だったりしたら、車に乗る度に顔が赤くなってしまいそうなのでやめた。
「色々ごたごたしてて忘れてたけど、もうすぐ柊矢さんの誕生日なの。プレゼント、何がいいと思う?」
「あんたあげたら? 自分にリボンかけて」
「清美! 真面目に答えてよ!」
「柊矢さんの好みなら楸矢さんに聞いた方が早いんじゃない?」
「そっか」
そんな話をしているうちに柊矢の車が来た。
「柊兄の好み?」
小夜は台所で夕食を作りながら、おやつを食べている楸矢に柊矢の好きなものを訊ねてみた。
「もうすぐ柊矢さんのお誕生日なんですよね? プレゼント、何がいいかと思って」
「小夜ちゃんプレゼントすれば?」
「楸矢さんまで清美と同じこと言わないでください!」
小夜は真っ赤になって抗議した。
友達にも同じこと言われたんだ。
楸矢は苦笑した。
考えることはみんな同じか。
「柊兄の好みねぇ」
楸矢は天井を見上げた。
「分かってるつもりだったけど、最近自信ないんだよね」
小夜ちゃんと沙陽じゃタイプ違いすぎだし。
「考えておくよ」
「お願いします。今日の夕食のリクエスト、聞きますよ」
「ホント? じゃあ、ねぇ……」
楸矢は身を乗り出した。
夕食の最中に小夜のムーシカが聴こえてきた。
小夜が真っ赤になって俯く。
柊矢は料理に目を落としたまま無言で食べていた。
「まさか、こんなに流行るとはねぇ」
楸矢が他人事のように言った。
沙陽は小夜のムーシカを忌々しげに聴いていた。
なんでみんなあんなムーシカをもてはやすのよ!
あんな稚拙なムーシカ。
自分のムーシカには誰一人賛同してくれないのに小夜が歌うムーシカには参加する。
柊矢もあんなつまらない子にいつまでも拘って。
最初は珍しがってるだけだと思ってた。
沙陽がムーシコスだとは知らなかったから家族を除けば小夜が初めて会ったムーシコスのはずだし、音大付属高校の音楽科に通っていたから普通科の女子高生が新鮮に映ったのだと。
だからすぐに飽きると思っていた。
だが、あの二人はどう見ても相思相愛だ。
あの子はともかく、柊矢まで初恋をした少年みたいな態度を取ってる。
ひっぱたいて目を覚ましてやりたいが、どうすれば近付けるのか分からない。
沙陽が柊矢を呼び出しても素直に来るとは思えない。
あの子なら来るかしら……。
榎矢の呼び出しのムーシカには引っかかったらしいけど……。
小夜は夕食が終わると音楽室で、さっきから胸に沸き上がってきていたムーシカを歌っていた。
ムーシケーのラブソングを聴いて浮かんできた曲だった。
新しいムーシカだから他のムーシコスは大人しく聴いていた。
「参ったな」
楸矢は小夜の歌声を聞きながら頭を抱えた。
柊矢はさっきコーヒーカップを持って二階へと上がってしまった。
「小夜ちゃん、ストレートすぎ」
歌詞に、恋とか愛とか好きとか言う言葉は入っていないが、これは明らかに柊矢を想うムーシカだった。
柊矢もそれに気付いたから楸矢と顔を合わせづらくて自室へ逃げたのだろう。
「ムーシカってムーシコスの感情そのものだったんだなぁ……」
小夜が喉を治してくれたお礼のムーシカを歌ったことがあったが、それ以外ではムーシカが創られるところに居合わせたことがなかったから、ここまではっきり感情が表れるものだとは知らなかった。
今日、小夜がムーシケーのムーシカがラブソングだったと言ったとき、歌詞がなかったのになんでラブソングだって言い切れるんだろうと思ったが、確かにこれだけ露骨に感情が表れてれば歌詞がなくてもはっきり分かる。
喉が治ったときのムーシカはお礼の意味で歌われたが、多分お礼のムーシカとして創られたものではなかったのだろう。
おそらく歌えなかった時期に出来たムーシカだったのだ。
だからピアノを教えて欲しいと頼んできたのだろう。
自分が創ったムーシカを伝えられるようになりたかったのだ。
椿矢の祖父の伯母(大伯母)が地球人と駆け落ちしたらしいが創ったムーシカにここまで剥き出しの感情が表れてしまうのだとしたら、
「そりゃ、地球人と逃げたくなるよなぁ」
楸矢は椿矢の大伯母に深く共感した。
椿矢の家はムーシコスの家系らしいから周囲にいるのはムーシコスばかりだったはずだし、そうだとするとこういう場面に出くわすこともよくあっただろう。
こんなことが頻繁にあったら身が持たない。
椿矢がムーシコスの血は大分薄れてきていると言っていたらしいが、四千年という時間経過のせいだけではなく、多分これに耐えかねて地球人を選んだ者が多かったのではないだろうか。
いくらムーシコスが音楽に弱いとは言え、これが平気なのは相当な音楽バカだけだろう。
俺も絶対地球人と結婚しよう。
楸矢はそう心に誓った。
小夜のムーシカを聴きながら、
「明日からどんな顔して会えばいいんだろ」
と独りごちた。
「小夜、なんかあったの?」
教室に入るなり清美が聞いてきた。
車から降りたときの柊矢と小夜のぎこちない様子を見ていたらしい。
「清美……、どうしよう……、私、柊矢さんのこと好きになっちゃったみたい」
「小夜、それ今更過ぎだから」
清美が冷めた口調で言った。
「今までも好きだと思ってたの! 柊矢さんの前で好きって言っちゃったこともあったけど、それが恋だと思ってたけど、全然違った! どうしよう! どうしたらいい?」
小夜は狼狽えた様子で言った。
「どうしようって、どうしようもないでしょ。もう告白したなら……」
「してない!」
小夜が強く否定した。
それから自信がなさそうに、
「したことになるのかな?」
と首を傾げた。
「してなかったら柊矢さんまであんな態度取るわけないじゃん」
清美が冷たい声で言った。
「柊矢さんの聞いてるところでム……歌、歌ったの。柊矢さんを想う歌……」
小夜の声がだんだん小さくなっていった。
「でも、あんなにはっきり意思表示するつもりはなかったの」
小夜が言い訳するように言った。
「楸矢さんまでまともに顔あわせてくれないし」
「二人の目の前で歌ったの?」
清美が信じられないという顔をした。
「目の前じゃなくて、別の部屋だけど……」
「一応確認のために聞くけど、その歌って小夜のオリジナルソング?」
小夜は頷いた。
「うわ、それ痛すぎ!」
清美が大袈裟に仰け反った。
「そりゃ、どん引きするわ」
ムーシコスではない清美には歌――ムーシカ――で想いを伝えてしまったというのは理解できないのだ。
四千年も共存してきたのに、まだムーシコスと地球人の間には分かり合えない溝がある。
そのとき夕辺小夜が歌ったムーシカが聴こえてきた。
嘘!
突然真っ赤になった小夜に、
「小夜、どうしたの?」
清美が驚いた様子で顔を覗き込んできた。
「もうダメ。死にたい」
小夜は机に突っ伏した。
小夜のムーシカは、素直な感情表現に好感を持たれたのか、新曲のラブソングだからなのか、日に一度は歌われるようになった。多い日は二度、三度のこともあった。
授業中にも容赦なく聴こえてくる。
「霞乃、どうした、顔が赤いぞ」
数学の教師が小夜を見て言った。
「な、なんでもないです」
小夜は真っ赤な顔で俯いた。
「熱でもあるんじゃないのか?」
「だ、大丈夫です」
「ただの恋煩いだもんね~」
隣の席の清美が小声で呟いた。
「清美!」
小夜が横目で睨んだ。
「小夜、はっきり聞いていい?」
二人は校門の前で柊矢の車を待っていた。
小夜が清美に相談したいことがあるから一緒に待って欲しいと頼んだのだ。
「何?」
「柊矢さんと何かあった?」
「何もないよ。あったらこんなに悩まないって」
柊矢とはあれ以来ぎこちないままで必要最低限のことしか話していなかった。
「突然真っ赤になったりするのって、Hしちゃって、それ思い出してるからじゃないの?」
「清美! ホントに怒るよ!」
小夜が頬を朱に染めて言った。
「奥手の小夜に限ってそれはないかぁ。柊矢さんだって両手が後ろに回っちゃうしね」
「え! 清美! それどういうこと?」
小夜は身を乗り出した。
柊矢の友達が同じ事を言っていた。
あのとき意味が分からなかったのだ。
「大人が未成年の子と寝ると犯罪でしょ」
そう言う意味だったんだ!
小夜は更に赤くなった。
「ちょ、ちょっと、小夜! あんた、ホントに……」
清美が小夜に詰め寄った。
「ち、違うって!」
小夜は慌てて両手を振った。
「柊矢さんの友達が同じこと言って柊矢さんをからかったことがあったの! そのとき意味が分からなかったから……」
「それならいいけど……」
「もしかして、大人の付き合いって、そう言うこと?」
小夜が訊ねた。
「そうだよ」
じゃあ、ひょっとして、楸矢さんが言ってた後部座席っていうのも……。
清美に聞いてみようかと思ったが、もしホントにそう言う意味だったりしたら、車に乗る度に顔が赤くなってしまいそうなのでやめた。
「色々ごたごたしてて忘れてたけど、もうすぐ柊矢さんの誕生日なの。プレゼント、何がいいと思う?」
「あんたあげたら? 自分にリボンかけて」
「清美! 真面目に答えてよ!」
「柊矢さんの好みなら楸矢さんに聞いた方が早いんじゃない?」
「そっか」
そんな話をしているうちに柊矢の車が来た。
「柊兄の好み?」
小夜は台所で夕食を作りながら、おやつを食べている楸矢に柊矢の好きなものを訊ねてみた。
「もうすぐ柊矢さんのお誕生日なんですよね? プレゼント、何がいいかと思って」
「小夜ちゃんプレゼントすれば?」
「楸矢さんまで清美と同じこと言わないでください!」
小夜は真っ赤になって抗議した。
友達にも同じこと言われたんだ。
楸矢は苦笑した。
考えることはみんな同じか。
「柊兄の好みねぇ」
楸矢は天井を見上げた。
「分かってるつもりだったけど、最近自信ないんだよね」
小夜ちゃんと沙陽じゃタイプ違いすぎだし。
「考えておくよ」
「お願いします。今日の夕食のリクエスト、聞きますよ」
「ホント? じゃあ、ねぇ……」
楸矢は身を乗り出した。
夕食の最中に小夜のムーシカが聴こえてきた。
小夜が真っ赤になって俯く。
柊矢は料理に目を落としたまま無言で食べていた。
「まさか、こんなに流行るとはねぇ」
楸矢が他人事のように言った。
沙陽は小夜のムーシカを忌々しげに聴いていた。
なんでみんなあんなムーシカをもてはやすのよ!
あんな稚拙なムーシカ。
自分のムーシカには誰一人賛同してくれないのに小夜が歌うムーシカには参加する。
柊矢もあんなつまらない子にいつまでも拘って。
最初は珍しがってるだけだと思ってた。
沙陽がムーシコスだとは知らなかったから家族を除けば小夜が初めて会ったムーシコスのはずだし、音大付属高校の音楽科に通っていたから普通科の女子高生が新鮮に映ったのだと。
だからすぐに飽きると思っていた。
だが、あの二人はどう見ても相思相愛だ。
あの子はともかく、柊矢まで初恋をした少年みたいな態度を取ってる。
ひっぱたいて目を覚ましてやりたいが、どうすれば近付けるのか分からない。
沙陽が柊矢を呼び出しても素直に来るとは思えない。
あの子なら来るかしら……。
榎矢の呼び出しのムーシカには引っかかったらしいけど……。