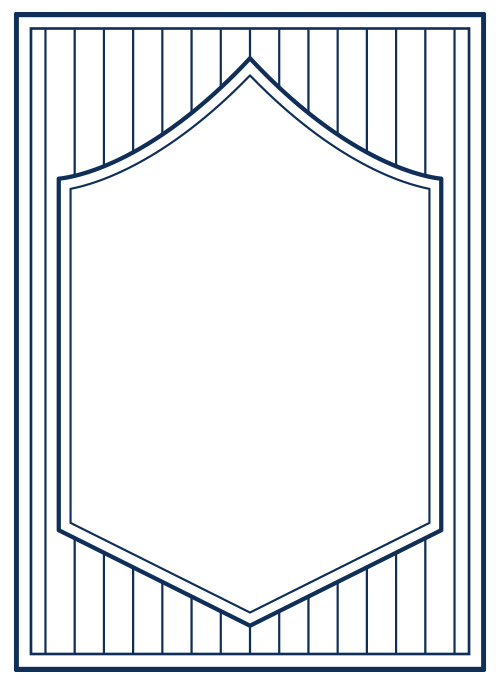三
「ただいま」
玄関から声が聞こえてきた。
廊下を歩く足音がしたので振り返るのと、足音の主が台所を覗くのは同時だった。
入ってきたのは小夜と同い年くらいの男子だった。
背は柊矢と同じくらい高い――百七十センチ前後だ――が、顔は幼い感じがした。眼が大きいせいかもしれない。短い茶色の髪は緩い巻き毛だった。
柊矢は黒髪だから脱色しているのだろうか。耳にはきれいな緑色の石の小さなピアスをしていた。
高校からの帰宅だから制服を着ている。ブレザーの色は小夜の高校のものと似ていたがネクタイの色は違う。
カバンの他に細長い楽器のケースを持っていた。フルートのケースだろう。
「あ」
二人は同時に声を出した。
「君が……鳥さん?」
「は?」
小夜は面食らって瞬きしたとき、鍋が噴きこぼれる音がした。慌ててガス台の方を向くと、火を弱くした。
「君、歌ってる人だって柊兄から聞いたけど」
「はい、そうです」
小夜は鍋の中を覗き込みながら返事をした。
焦げ付いてはいないみたい。
自分から作るなんて言いだしておいて失敗したら恥ずかしい。
そういえば、さっき話の流れで楸矢も歌が聴こえると言っていた。
「霞乃……さやちゃん? さよちゃん?」
楸矢はスマホの画面に目を落としながら訊ねた。
柊矢の送ったメールを見ているのだろう。
「さよです」
「小夜曲の小夜か」
「小夜曲?」
「セレナーデのこと。君が歌う人だからその名前にしたのかな」
「さぁ? 名前の由来については聞いてなかったので……」
まだ聞いてないことが一杯あった。
名前の由来も、誰が付けたのかも、両親はどんな人だったのかも。
聞きたかったけれど聞けなかった。だから、いつか話してくれるのを待とうと思っていた。
でも、もう「いつか」は来ない。
こんなことなら無理にでも聞いておけば良かった。
小夜は浮かんできた涙を見られないようにと、鍋の方を向いた。
楸矢もしまった、と言う表情で再びスマホに目を落とした。
「そ、そうそう、歌う人なんだよね。俺達は鳥って呼んでたんだ」
だから鳥さん?
「元はバードなんだけどね」
「バード?」
小夜は振り返って小首を傾げた。
「バードは鳥って意味もあるけど、吟遊詩人って意味もあるんだ。人前で話をするとき、バードより鳥の方が人の注意を引かないでしょ」
どうやら普通の人には聴こえない歌の話をするときの隠語として使っていたらしい。
「でも、君は吟遊詩人って言うより小鳥ちゃんだね」
「小鳥ちゃんって……同い年ぐらいじゃないですか」
「小夜ちゃん、俺のこといくつだと思ってる?」
「十六、七歳くらいですか?」
「俺、十八。もう彼女とは大人の付き合いしてるんだよ」
大人の付き合いがどういう意味なのかは分からなかったが、とりあえず自分より年上と言うことは理解できた。
「部屋のドアにかかってるネームプレートが裏返ってるときは彼女が来てるって意味だから声かけないでね」
「はい」
小夜は返事をすると、煮物の味見をした。
「ね、俺もそれ味見していい?」
「いいですよ」
小夜が小皿を取ろうとすると、楸矢は中鉢を取り出して差し出してきた。
少しだけ入れると、
「もっとどーんと入れてよ」
と言われて多めに入れる。
「夕食、食べられなくなりますよ」
「この程度で腹いっぱいになんかならないよ。おかわり」
小夜が溜息をついて再度入れていると柊矢が入ってきた。
「いい匂いだな」
「美味いよ」
「俺にもくれ」
柊矢はそう言うと大皿を出した。
今日は煮物、諦めよう。
さっき柊矢が二日分といった意味がよく分かった。
柊矢のお椀に煮物を目一杯入れた。
小夜は男二人の食欲を甘く見ていた。
確か肉を買ってあったし、白滝はないけどジャガイモもあるし、新しく肉じゃがを作ろう。
肉は牛肉だけど、関西は牛肉で肉じゃがを作るらしいし、味付けが関東風なら牛肉でも多分この二人は気にしないだろう。
味を濃いめにすれば量が少なくてもご飯が沢山食べられるはずだから多めに炊こう。
楸矢の皿に煮物の残りを全部入れると、ジャガイモを洗い始めた。
「小夜ちゃん、行くところがないならずっとうちにいれば?」
夕食を食べ終えた後、そのまま台所でコーヒーを飲みながら楸矢が言った。
柊矢は先に部屋に引き上げていて、小夜と楸矢だけが残っていた。
「そこまでご迷惑をかけるわけには……」
「料理毎日作ってくれるならそれだけでいいよ。俺、家庭料理に飢えてたんだよね」
「でも……」
「あ、もしかして、男所帯だから警戒してる? それなら大丈夫だよ。俺、大人の彼女いるし、柊兄もロリコンじゃないから、襲ったりしないよ」
「そ、そう言うことを心配してるわけじゃ……」
小夜は赤くなって俯いた。
「ま、冗談は置いといて」
楸矢が真顔になった。
「うち、下宿やってるんだ。今は下宿人いないけど。料理作ってくれるんなら安くしてくれるよ」
「でも、お祖父ちゃんのお葬式もまだですし、お家賃も……」
小夜はバイトをしたことがない。
自分にどんな仕事が出来るのかすらよく分からない。
「その辺の手配は柊兄が何とかするよ。そういうの詳しいし。それにお金のことも大丈夫だと思うよ」
「え……」
「まぁ、そう言うことはまた改めて。片付けは俺がするから小夜ちゃんはもう休むといいよ」
楸矢はそう言って小夜を台所から送り出した。
台所を出た小夜は客間に行こうとして、二階から下りてきた柊矢に会った。
「丁度良かった。着替えが必要だろ」
「はい」
小夜は着の身着のままで、エコバッグに入れていた殆ど金の入ってない財布とスマホ以外は何も持っていない。
柊矢は小夜を連れて空き部屋に入ると、部屋に置かれている箪笥の引き出しを開けた。中に入っていたのは女物の服だった。ぎっしりと詰まっている。
「この箪笥の中は全部女物だ。とりあえずこの中のものを使ってくれ。明日、必要なものを買いに行こう」
「これ、どなたのなんですか?」
「俺や楸矢が昔付き合ってた相手が置いてったものだ。誰の物でもないから遠慮なく使ってくれ。風呂は沸いてる。中から鍵をかけられるから」
「有難うございます」
小夜が頭を下げると柊矢は出ていった。
中を見てみると、大人物ばかりだった。服やパンティのサイズはS、M、Lくらいだからいいとして、ブラジャーだけはそうはいかない。自分に合うサイズのものを捜して箪笥の中の物を全部出し、ようやく一つだけ見つけた。
柊矢はともかく、楸矢の元カノの物もあるならもっと高校生らしいのもあって良さそうなのに、と考えてから彼氏の家に泊まり込む女子高生が子供っぽいものを着てるわけがないと思い至った。
小夜のクラスメイトでも、彼氏のところに泊まってるような子は大抵大人びていた。もし自分だったとしても、恋人の家に泊まることになったら思い切り大人びたものを着ていくだろう。
そのとき、不意に柊矢の顔が浮かんだ。整った顔立ち、切れ長の目、額にかかって揺れる前髪。
小夜は慌ててその顔を振り払う。
別に自分は柊矢のことなんて何とも思ってない。柊矢の方だってそうだ。楸矢も、柊矢はロリコンじゃないといっていたし。優しくしてくれたから、それで気になっただけだ。
でも、なんで優しくしてくれるんだろう。
私が歌う人間だからだろうか。
色々な考えが頭の中をぐるぐる回りだした。小夜はそれを払いのけるようにして下着と寝間着に出来そうな服を持つと、風呂場に向かった。
翌朝。窓からレースのカーテン越しに朝日が差し込んでいた。見慣れぬ部屋に、なんで自分はこんなところにいるんだろう、と一瞬パニクりそうになって、火事のことを思い出した。
やっぱり夢じゃないんだ。
お祖父ちゃんはもういない。
口数は少なかったけど、優しいお祖父ちゃんだった。
その優しさにいつも感謝していたけど、それを口にしたことはなかった。
言えば良かった。
一言「有難う」って言いたかった。
でも、もう二度と言えない。
西新宿の家ももう無い。
写真一枚残ってない。全部焼けてしまった。
泣きそうになったが、そのとき、ここは柊矢の家だと言うことを思い出した。
お世話になってるんだからご飯くらい作らなきゃ。
小夜は慌てて服を着替えると、台所へ向かった。
幸い、まだ二人は起きてないようだった。
和食なのか洋食なのか聞いてなかったことに気付いて、どうするか迷ったが、トーストならすぐに作れると考えて、ご飯を炊いて味噌汁を作り始めた。
丁度味噌汁が出来たとき、楸矢が入ってきた。
「おはようございます」
「おはよう。わぁ、お味噌汁かぁ」
楸矢が目を輝かせた。
「パンの方が良ければ、すぐにトーストを……」
「折角ご飯とお味噌汁があるのに? ご飯の方がずっといいよ」
それを聞いてご飯と味噌汁をよそうと楸矢の前に出した。
「コーヒーはないの?」
「あ、気付かなくてすみません」
小夜は慌ててマグカップを取り出すと、インスタントコーヒーの瓶を探した。
「いいよ。コーヒーは俺が入れるから」
楸矢はそう言うと、コーヒー豆とコーヒーメーカーを取り出した。
わ、本格的。
小夜はコーヒーの入れ方を覚えるために楸矢の手元を見ていた。
「小夜ちゃん、コーヒーくらい、自分で入れるよ」
楸矢が苦笑して言った。
「でも、私も入れられるようになりたいですから」
「そう」
楸矢はコーヒーメーカーをセットすると、食卓に着いて、
「いただきます」
と言ってすぐに食べ始めた。
「俺の彼女って料理はダメなんだよね。前は柊兄が作っくれてたんだけど、今はめんどくさがって作ってくれないんだ」
「もう子供じゃないんだから自分で作れ」
そう言いながら柊矢が入ってきた。
「あ、おはようございます。柊矢さんもご飯とお味噌汁でいいですか?」
柊矢が首肯すると、小夜はすぐにご飯と味噌汁をよそって差し出した。楸矢は立ち上がると、マグカップにコーヒーを注いだ。
「小夜ちゃんも飲む?」
「あ、じゃ、少しだけ」
楸矢が自分と柊矢と小夜の分をマグカップに注ぐと、小夜は柊矢にマグカップを渡した。
小夜は恐る恐るコーヒーに口を付けた。
苦っ!
思わず顔をしかめると、楸矢が微笑った。
「小鳥ちゃんにコーヒーは似合わないね」
「小鳥ちゃんって言うのやめてください」
楸矢に抗議しながらマグカップを置いた。
小夜は祖父と二人暮らしだったこともあってコーヒーを飲んだことがなかった。
「まぁ、小夜ちゃんはお茶にしておいたら?」
「そうします」
「ただいま」
玄関から声が聞こえてきた。
廊下を歩く足音がしたので振り返るのと、足音の主が台所を覗くのは同時だった。
入ってきたのは小夜と同い年くらいの男子だった。
背は柊矢と同じくらい高い――百七十センチ前後だ――が、顔は幼い感じがした。眼が大きいせいかもしれない。短い茶色の髪は緩い巻き毛だった。
柊矢は黒髪だから脱色しているのだろうか。耳にはきれいな緑色の石の小さなピアスをしていた。
高校からの帰宅だから制服を着ている。ブレザーの色は小夜の高校のものと似ていたがネクタイの色は違う。
カバンの他に細長い楽器のケースを持っていた。フルートのケースだろう。
「あ」
二人は同時に声を出した。
「君が……鳥さん?」
「は?」
小夜は面食らって瞬きしたとき、鍋が噴きこぼれる音がした。慌ててガス台の方を向くと、火を弱くした。
「君、歌ってる人だって柊兄から聞いたけど」
「はい、そうです」
小夜は鍋の中を覗き込みながら返事をした。
焦げ付いてはいないみたい。
自分から作るなんて言いだしておいて失敗したら恥ずかしい。
そういえば、さっき話の流れで楸矢も歌が聴こえると言っていた。
「霞乃……さやちゃん? さよちゃん?」
楸矢はスマホの画面に目を落としながら訊ねた。
柊矢の送ったメールを見ているのだろう。
「さよです」
「小夜曲の小夜か」
「小夜曲?」
「セレナーデのこと。君が歌う人だからその名前にしたのかな」
「さぁ? 名前の由来については聞いてなかったので……」
まだ聞いてないことが一杯あった。
名前の由来も、誰が付けたのかも、両親はどんな人だったのかも。
聞きたかったけれど聞けなかった。だから、いつか話してくれるのを待とうと思っていた。
でも、もう「いつか」は来ない。
こんなことなら無理にでも聞いておけば良かった。
小夜は浮かんできた涙を見られないようにと、鍋の方を向いた。
楸矢もしまった、と言う表情で再びスマホに目を落とした。
「そ、そうそう、歌う人なんだよね。俺達は鳥って呼んでたんだ」
だから鳥さん?
「元はバードなんだけどね」
「バード?」
小夜は振り返って小首を傾げた。
「バードは鳥って意味もあるけど、吟遊詩人って意味もあるんだ。人前で話をするとき、バードより鳥の方が人の注意を引かないでしょ」
どうやら普通の人には聴こえない歌の話をするときの隠語として使っていたらしい。
「でも、君は吟遊詩人って言うより小鳥ちゃんだね」
「小鳥ちゃんって……同い年ぐらいじゃないですか」
「小夜ちゃん、俺のこといくつだと思ってる?」
「十六、七歳くらいですか?」
「俺、十八。もう彼女とは大人の付き合いしてるんだよ」
大人の付き合いがどういう意味なのかは分からなかったが、とりあえず自分より年上と言うことは理解できた。
「部屋のドアにかかってるネームプレートが裏返ってるときは彼女が来てるって意味だから声かけないでね」
「はい」
小夜は返事をすると、煮物の味見をした。
「ね、俺もそれ味見していい?」
「いいですよ」
小夜が小皿を取ろうとすると、楸矢は中鉢を取り出して差し出してきた。
少しだけ入れると、
「もっとどーんと入れてよ」
と言われて多めに入れる。
「夕食、食べられなくなりますよ」
「この程度で腹いっぱいになんかならないよ。おかわり」
小夜が溜息をついて再度入れていると柊矢が入ってきた。
「いい匂いだな」
「美味いよ」
「俺にもくれ」
柊矢はそう言うと大皿を出した。
今日は煮物、諦めよう。
さっき柊矢が二日分といった意味がよく分かった。
柊矢のお椀に煮物を目一杯入れた。
小夜は男二人の食欲を甘く見ていた。
確か肉を買ってあったし、白滝はないけどジャガイモもあるし、新しく肉じゃがを作ろう。
肉は牛肉だけど、関西は牛肉で肉じゃがを作るらしいし、味付けが関東風なら牛肉でも多分この二人は気にしないだろう。
味を濃いめにすれば量が少なくてもご飯が沢山食べられるはずだから多めに炊こう。
楸矢の皿に煮物の残りを全部入れると、ジャガイモを洗い始めた。
「小夜ちゃん、行くところがないならずっとうちにいれば?」
夕食を食べ終えた後、そのまま台所でコーヒーを飲みながら楸矢が言った。
柊矢は先に部屋に引き上げていて、小夜と楸矢だけが残っていた。
「そこまでご迷惑をかけるわけには……」
「料理毎日作ってくれるならそれだけでいいよ。俺、家庭料理に飢えてたんだよね」
「でも……」
「あ、もしかして、男所帯だから警戒してる? それなら大丈夫だよ。俺、大人の彼女いるし、柊兄もロリコンじゃないから、襲ったりしないよ」
「そ、そう言うことを心配してるわけじゃ……」
小夜は赤くなって俯いた。
「ま、冗談は置いといて」
楸矢が真顔になった。
「うち、下宿やってるんだ。今は下宿人いないけど。料理作ってくれるんなら安くしてくれるよ」
「でも、お祖父ちゃんのお葬式もまだですし、お家賃も……」
小夜はバイトをしたことがない。
自分にどんな仕事が出来るのかすらよく分からない。
「その辺の手配は柊兄が何とかするよ。そういうの詳しいし。それにお金のことも大丈夫だと思うよ」
「え……」
「まぁ、そう言うことはまた改めて。片付けは俺がするから小夜ちゃんはもう休むといいよ」
楸矢はそう言って小夜を台所から送り出した。
台所を出た小夜は客間に行こうとして、二階から下りてきた柊矢に会った。
「丁度良かった。着替えが必要だろ」
「はい」
小夜は着の身着のままで、エコバッグに入れていた殆ど金の入ってない財布とスマホ以外は何も持っていない。
柊矢は小夜を連れて空き部屋に入ると、部屋に置かれている箪笥の引き出しを開けた。中に入っていたのは女物の服だった。ぎっしりと詰まっている。
「この箪笥の中は全部女物だ。とりあえずこの中のものを使ってくれ。明日、必要なものを買いに行こう」
「これ、どなたのなんですか?」
「俺や楸矢が昔付き合ってた相手が置いてったものだ。誰の物でもないから遠慮なく使ってくれ。風呂は沸いてる。中から鍵をかけられるから」
「有難うございます」
小夜が頭を下げると柊矢は出ていった。
中を見てみると、大人物ばかりだった。服やパンティのサイズはS、M、Lくらいだからいいとして、ブラジャーだけはそうはいかない。自分に合うサイズのものを捜して箪笥の中の物を全部出し、ようやく一つだけ見つけた。
柊矢はともかく、楸矢の元カノの物もあるならもっと高校生らしいのもあって良さそうなのに、と考えてから彼氏の家に泊まり込む女子高生が子供っぽいものを着てるわけがないと思い至った。
小夜のクラスメイトでも、彼氏のところに泊まってるような子は大抵大人びていた。もし自分だったとしても、恋人の家に泊まることになったら思い切り大人びたものを着ていくだろう。
そのとき、不意に柊矢の顔が浮かんだ。整った顔立ち、切れ長の目、額にかかって揺れる前髪。
小夜は慌ててその顔を振り払う。
別に自分は柊矢のことなんて何とも思ってない。柊矢の方だってそうだ。楸矢も、柊矢はロリコンじゃないといっていたし。優しくしてくれたから、それで気になっただけだ。
でも、なんで優しくしてくれるんだろう。
私が歌う人間だからだろうか。
色々な考えが頭の中をぐるぐる回りだした。小夜はそれを払いのけるようにして下着と寝間着に出来そうな服を持つと、風呂場に向かった。
翌朝。窓からレースのカーテン越しに朝日が差し込んでいた。見慣れぬ部屋に、なんで自分はこんなところにいるんだろう、と一瞬パニクりそうになって、火事のことを思い出した。
やっぱり夢じゃないんだ。
お祖父ちゃんはもういない。
口数は少なかったけど、優しいお祖父ちゃんだった。
その優しさにいつも感謝していたけど、それを口にしたことはなかった。
言えば良かった。
一言「有難う」って言いたかった。
でも、もう二度と言えない。
西新宿の家ももう無い。
写真一枚残ってない。全部焼けてしまった。
泣きそうになったが、そのとき、ここは柊矢の家だと言うことを思い出した。
お世話になってるんだからご飯くらい作らなきゃ。
小夜は慌てて服を着替えると、台所へ向かった。
幸い、まだ二人は起きてないようだった。
和食なのか洋食なのか聞いてなかったことに気付いて、どうするか迷ったが、トーストならすぐに作れると考えて、ご飯を炊いて味噌汁を作り始めた。
丁度味噌汁が出来たとき、楸矢が入ってきた。
「おはようございます」
「おはよう。わぁ、お味噌汁かぁ」
楸矢が目を輝かせた。
「パンの方が良ければ、すぐにトーストを……」
「折角ご飯とお味噌汁があるのに? ご飯の方がずっといいよ」
それを聞いてご飯と味噌汁をよそうと楸矢の前に出した。
「コーヒーはないの?」
「あ、気付かなくてすみません」
小夜は慌ててマグカップを取り出すと、インスタントコーヒーの瓶を探した。
「いいよ。コーヒーは俺が入れるから」
楸矢はそう言うと、コーヒー豆とコーヒーメーカーを取り出した。
わ、本格的。
小夜はコーヒーの入れ方を覚えるために楸矢の手元を見ていた。
「小夜ちゃん、コーヒーくらい、自分で入れるよ」
楸矢が苦笑して言った。
「でも、私も入れられるようになりたいですから」
「そう」
楸矢はコーヒーメーカーをセットすると、食卓に着いて、
「いただきます」
と言ってすぐに食べ始めた。
「俺の彼女って料理はダメなんだよね。前は柊兄が作っくれてたんだけど、今はめんどくさがって作ってくれないんだ」
「もう子供じゃないんだから自分で作れ」
そう言いながら柊矢が入ってきた。
「あ、おはようございます。柊矢さんもご飯とお味噌汁でいいですか?」
柊矢が首肯すると、小夜はすぐにご飯と味噌汁をよそって差し出した。楸矢は立ち上がると、マグカップにコーヒーを注いだ。
「小夜ちゃんも飲む?」
「あ、じゃ、少しだけ」
楸矢が自分と柊矢と小夜の分をマグカップに注ぐと、小夜は柊矢にマグカップを渡した。
小夜は恐る恐るコーヒーに口を付けた。
苦っ!
思わず顔をしかめると、楸矢が微笑った。
「小鳥ちゃんにコーヒーは似合わないね」
「小鳥ちゃんって言うのやめてください」
楸矢に抗議しながらマグカップを置いた。
小夜は祖父と二人暮らしだったこともあってコーヒーを飲んだことがなかった。
「まぁ、小夜ちゃんはお茶にしておいたら?」
「そうします」