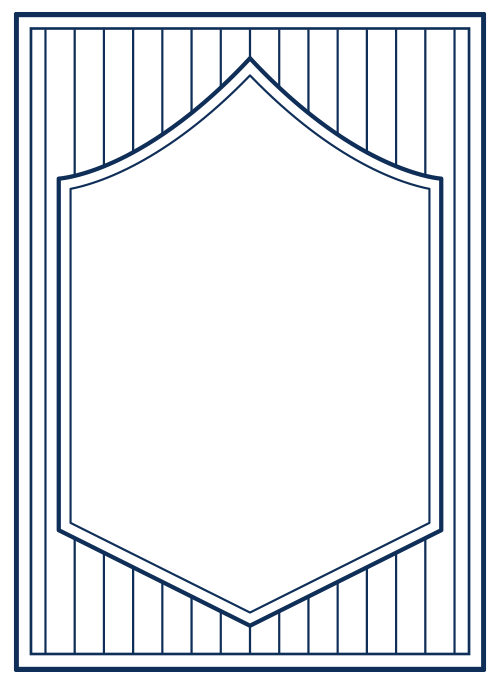一
柊矢に、今日は迎えに行けないから楸矢を行かせる、と言われたので校門の前で待っていると、いきなり腕を掴まれ思わずつられて一緒に歩き出してしまった。
横を見ると腕を掴んでいるのは沙陽だった。
「あ、あの、私、楸矢さんを待ってないと……」
「話をするだけよ。話が終わったら戻ればいいわ」
沙陽は命令するようにそう言うと小夜の腕を掴んだまま歩いていく。
小夜は引っ張られるままに跟いていくしかなかった。
「柊矢さんのことなら……」
「柊矢も楸矢も関係ないわ」
沙陽が遮った。
「最初からあなたときちんと話しをすべきだった」
小夜が訳が分からない、と言う顔で沙陽を見上げると、
「森の事よ。あなたにはあの森の素晴らしさが分かるでしょ」
前を向いたままで断定するように言った。
「それは……」
確かにあの森への憧憬は唯一沙陽と共有できる想いだろう。
柊矢さんへの想いもかな?
「あの森を凍り付かせてる旋律が溶けたときのことを想像したことがあるでしょ」
勿論、何度もある。
たった一滴の旋律でさえ、あれほど美しかったのだ。
全て溶けたら惑星上の全てのものが素晴らしい音色を奏でるだろう。
その旋律に包まれることが出来たらどれだけ幸せな気持ちになれるだろう。
その場にいるためならどんな犠牲を払ってもいいとすら思う、ムーシコスには抗えない魅力のある場所。
沙陽も小夜と同様、あの森にすっかり魅せられている。取り憑かれていると言ってもいいほどに。
「旋律の溶けた森に行ってみたいでしょ」
「それは……思います。でも、行けません」
「どうしてよ! 行きたいんでしょ!」
沙陽は腕を掴む手に力を込めた。
痛みに思わず小夜は顔をしかめた。
しかし沙陽は小夜のそんな様子には気付かないようだった。
「あなたには行ける手段だってあるじゃない! どうしてそれを使わないのよ!」
「それは、ムーシケーが私達が行くことを拒んでいるからです。私はクレーイス・エコーとして、ムーシケーの意志に逆らうことは出来ません」
「逆らえないんじゃないでしょ! 逆らわないだけでしょ!」
「私にとっては同じ事です」
沙陽が腕を掴む力を更に強める。
痛っ!
小夜は顔を顰めた。
「沙陽さん、私、もう戻らないと」
沙陽は無表情のまま前を見ていた。
二人は交差点の歩道の端に立っていた。
右側からすごいスピードでバスが迫ってくる。
まさか……。
このままバスの前に突き飛ばす気じゃ……。
小夜は青くなった。
そのとき不意に腕から圧力が消えた。
見ると楸矢が沙陽の手首を掴んでいる。
「消えて。女の人に暴力振るいたくない」
沙陽は楸矢を睨むと丁度青に変わった信号を渡っていった。
「楸矢さん。校門の前で待ってなくてすみませんでした」
小夜は頭を下げた。
「いや、間に合って良かったよ。小夜ちゃんの友達が前に襲ってきた女が小夜ちゃん連れてったって電話くれて、慌てて飛んできたんだ」
以前、沙陽が清美を使って脅迫してきたとき、また同じ事があったときのために清美に柊矢と楸矢の連絡先を教えておいたのだ。
「清美が……。助けてくれて有難うございました」
小夜は頭を下げた。
「どういたしまして。友達に連絡する?」
「はい」
小夜はスマホで清美に無事を伝えて礼を言った。
「じゃ、帰ろうか」
楸矢はそう言って小夜と共にバス停に向かって歩き始めた。
「それにしても分からないよなぁ。確かに幻想的で綺麗な森だとは思うけどさぁ、あそこまで執着するほどのものかね」
「ムーシコスにとってあの森以上に心を惹かれる場所はないと思いますけど」
「そんなに魅力的かなぁ」
楸矢が理解できない、と言うような表情をした。
小夜も首を傾げる。
なんで同じムーシコスなのにこんなに淡泊なんだろう。
どうもあの森の素晴らしさが今一つ分かってないように思える。
もしかして……。
「あの、楸矢さん、あの森の旋律、聴いたことあります?」
「初めて封印のムーシカ歌ったとき以外でって事?」
小夜が頷いた。
「ないけど」
やっぱり。
柊矢も楸矢も椿矢も、森に大して関心を示してないから変だと思っていたのだ。
あの凍り付いている旋律を聴いたことがなければ、ただの綺麗な森だとしか思えない。
綺麗なだけの森では帰りたいと思うわけがない。
柊矢達からすれば、あの森に帰りたい、というのは、居住禁止の国立公園の真ん中に、景色が綺麗だから住みたい、と駄々をこねているのと同じだろう。
「小夜ちゃんはあるの?」
「はい」
小夜は初めて森を見たときのことを話した。
「旋律の雫、か」
惑星一杯に凍り付いた旋律はきっと、何億、何兆という膨大な音楽のはずだ。
一生かかっても全てを聴くことは出来ないほど沢山の美しい旋律。
「まぁ、それなら確かにムーシコスは惹かれるだろうけどさ、ムーシケーは帰ってくるなって言ってるわけでしょ」
楸矢もムーシコスだから旋律に満ちた世界がどれほど魅惑的かは理解できる。
しかし、今は全て凍り付いている。
「どうしてムーシケーは拒絶するんでしょう。ムーシコスはムーシケーから生まれたのに」
「SFとかだと、ムーシコスが、惑星を破壊しかけたから、とかだよね」
確かに良くありそうな話ではある。
「ムーシコスって、イメージ的に音楽を愛する平和な種族に思えますけど」
正確には音楽以外は眼中にない種族だろうか。
音楽を奏でていられれば満足だから争いの起きる余地がないというか。
柊矢の、音大付属を選んだ理由が音楽の授業が多かったからと言う言葉にもそれがよく表れている。
ヴァイオリニストにしても、なってもいい程度だったというのもそうだ。
楽器の演奏をしていたいだけだから、音楽で身を立てようとか言う発想はないし、楸矢が音大に行くかどうかや将来どうするかは本人が勝手に決めればいいと考えているようだ。
勿論、楸矢が困っていたり悩んでいたりすれば助けるだろうが、それ以外で干渉する気はないのだろう。
家族に対してさえそうなのだから他人との対立など起きようがない。
帰還派のように向こうから何か仕掛けてくれば別だが。
小夜が音楽室で歌い始めると柊矢も楸矢もすぐにやってきて演奏を始める。
特に柊矢はそれが顕著だ。
他のムーシコスも多分、柊矢同様ムーシカを聴くと、そのときやっていたことを放り出して歌や演奏を始めてしまうのだろう。
個人差はあるが、ムーシコスはそれくらい音楽――というかムーシカ――に弱い。
「そう思いたいのは山々だけどさ、沙陽みたいのだっているじゃん。それに危険な兵器を使ってとかじゃなくてムーシカが惑星を壊しそうになったとか」
「歌で惑星を壊せるものなんですか?」
「嵐を起こせるくらいだからねぇ。案外、旋律が溶けると惑星が崩壊する、とかかもよ」
そんな話をしているうちにバスがバス停に着いた。
小夜がバスから降りる。
「買い物に行くんだ」
楸矢が一緒に降りながら言った。
霧生家の最寄りのバス停は次である。ここで下りたと言うことはスーパーで買い物をすると言うことだ。
「今日の夕食、何?」
「まだ材料買ってませんから何でもいいですよ」
「そっかぁ。何にしようかな」
楸矢はそう言いながら嬉しそうに小夜の隣を歩き始めた。
「今度こそ決めた! カツ丼と肉じゃが!」
楸矢は散々迷った末その二つに決めた。
なかなか決まらないのでスーパーの中をうろうろしてしまった。
材料をカゴに入れるとレジに向かった。
「小夜ちゃん、お礼にいいこと教えてあげる。柊兄の誕生日、来月だよ。二月五日」
「そうだったんですか。楸矢さんはいつなんですか?」
「え、俺? 俺はいいじゃん。内緒」
「教えてくれないんですか?」
「そ、秘密」
何か嫌なことでもあったのかな?
もしかしてお祖父様の命日だとか?
それなら無理に聞かない方がいいだろう。
小夜は深く追求しなかった。
小夜が肉じゃがを作っているとき柊矢が帰ってきた。
「お帰りなさい」
「ただいま。今日は肉じゃがか」
柊矢は小夜の肩越しに鍋を覗き込んだ。
と、柊矢さん、顔近い!
い、今、頬が触れたような気が……。
小夜は真っ赤になった。
心臓の音が聞こえないといいけど……!
「あ、あの、柊矢さん?」
小夜は俯いたまま、柊矢に声をかけた。
「ん?」
「楸矢さんのお誕生日って……」
「十月十日だが」
「何か嫌なことでもあったんですか?」
「妊娠期間は十月十日って言うだろ。それで子供の頃、元旦に作られたって散々からかわれたんだ」
柊矢の言葉に小夜は耳まで赤くなった。
「もう出来ますから、楸矢さんを呼んできてもらえますか?」
「分かった」
柊矢に、今日は迎えに行けないから楸矢を行かせる、と言われたので校門の前で待っていると、いきなり腕を掴まれ思わずつられて一緒に歩き出してしまった。
横を見ると腕を掴んでいるのは沙陽だった。
「あ、あの、私、楸矢さんを待ってないと……」
「話をするだけよ。話が終わったら戻ればいいわ」
沙陽は命令するようにそう言うと小夜の腕を掴んだまま歩いていく。
小夜は引っ張られるままに跟いていくしかなかった。
「柊矢さんのことなら……」
「柊矢も楸矢も関係ないわ」
沙陽が遮った。
「最初からあなたときちんと話しをすべきだった」
小夜が訳が分からない、と言う顔で沙陽を見上げると、
「森の事よ。あなたにはあの森の素晴らしさが分かるでしょ」
前を向いたままで断定するように言った。
「それは……」
確かにあの森への憧憬は唯一沙陽と共有できる想いだろう。
柊矢さんへの想いもかな?
「あの森を凍り付かせてる旋律が溶けたときのことを想像したことがあるでしょ」
勿論、何度もある。
たった一滴の旋律でさえ、あれほど美しかったのだ。
全て溶けたら惑星上の全てのものが素晴らしい音色を奏でるだろう。
その旋律に包まれることが出来たらどれだけ幸せな気持ちになれるだろう。
その場にいるためならどんな犠牲を払ってもいいとすら思う、ムーシコスには抗えない魅力のある場所。
沙陽も小夜と同様、あの森にすっかり魅せられている。取り憑かれていると言ってもいいほどに。
「旋律の溶けた森に行ってみたいでしょ」
「それは……思います。でも、行けません」
「どうしてよ! 行きたいんでしょ!」
沙陽は腕を掴む手に力を込めた。
痛みに思わず小夜は顔をしかめた。
しかし沙陽は小夜のそんな様子には気付かないようだった。
「あなたには行ける手段だってあるじゃない! どうしてそれを使わないのよ!」
「それは、ムーシケーが私達が行くことを拒んでいるからです。私はクレーイス・エコーとして、ムーシケーの意志に逆らうことは出来ません」
「逆らえないんじゃないでしょ! 逆らわないだけでしょ!」
「私にとっては同じ事です」
沙陽が腕を掴む力を更に強める。
痛っ!
小夜は顔を顰めた。
「沙陽さん、私、もう戻らないと」
沙陽は無表情のまま前を見ていた。
二人は交差点の歩道の端に立っていた。
右側からすごいスピードでバスが迫ってくる。
まさか……。
このままバスの前に突き飛ばす気じゃ……。
小夜は青くなった。
そのとき不意に腕から圧力が消えた。
見ると楸矢が沙陽の手首を掴んでいる。
「消えて。女の人に暴力振るいたくない」
沙陽は楸矢を睨むと丁度青に変わった信号を渡っていった。
「楸矢さん。校門の前で待ってなくてすみませんでした」
小夜は頭を下げた。
「いや、間に合って良かったよ。小夜ちゃんの友達が前に襲ってきた女が小夜ちゃん連れてったって電話くれて、慌てて飛んできたんだ」
以前、沙陽が清美を使って脅迫してきたとき、また同じ事があったときのために清美に柊矢と楸矢の連絡先を教えておいたのだ。
「清美が……。助けてくれて有難うございました」
小夜は頭を下げた。
「どういたしまして。友達に連絡する?」
「はい」
小夜はスマホで清美に無事を伝えて礼を言った。
「じゃ、帰ろうか」
楸矢はそう言って小夜と共にバス停に向かって歩き始めた。
「それにしても分からないよなぁ。確かに幻想的で綺麗な森だとは思うけどさぁ、あそこまで執着するほどのものかね」
「ムーシコスにとってあの森以上に心を惹かれる場所はないと思いますけど」
「そんなに魅力的かなぁ」
楸矢が理解できない、と言うような表情をした。
小夜も首を傾げる。
なんで同じムーシコスなのにこんなに淡泊なんだろう。
どうもあの森の素晴らしさが今一つ分かってないように思える。
もしかして……。
「あの、楸矢さん、あの森の旋律、聴いたことあります?」
「初めて封印のムーシカ歌ったとき以外でって事?」
小夜が頷いた。
「ないけど」
やっぱり。
柊矢も楸矢も椿矢も、森に大して関心を示してないから変だと思っていたのだ。
あの凍り付いている旋律を聴いたことがなければ、ただの綺麗な森だとしか思えない。
綺麗なだけの森では帰りたいと思うわけがない。
柊矢達からすれば、あの森に帰りたい、というのは、居住禁止の国立公園の真ん中に、景色が綺麗だから住みたい、と駄々をこねているのと同じだろう。
「小夜ちゃんはあるの?」
「はい」
小夜は初めて森を見たときのことを話した。
「旋律の雫、か」
惑星一杯に凍り付いた旋律はきっと、何億、何兆という膨大な音楽のはずだ。
一生かかっても全てを聴くことは出来ないほど沢山の美しい旋律。
「まぁ、それなら確かにムーシコスは惹かれるだろうけどさ、ムーシケーは帰ってくるなって言ってるわけでしょ」
楸矢もムーシコスだから旋律に満ちた世界がどれほど魅惑的かは理解できる。
しかし、今は全て凍り付いている。
「どうしてムーシケーは拒絶するんでしょう。ムーシコスはムーシケーから生まれたのに」
「SFとかだと、ムーシコスが、惑星を破壊しかけたから、とかだよね」
確かに良くありそうな話ではある。
「ムーシコスって、イメージ的に音楽を愛する平和な種族に思えますけど」
正確には音楽以外は眼中にない種族だろうか。
音楽を奏でていられれば満足だから争いの起きる余地がないというか。
柊矢の、音大付属を選んだ理由が音楽の授業が多かったからと言う言葉にもそれがよく表れている。
ヴァイオリニストにしても、なってもいい程度だったというのもそうだ。
楽器の演奏をしていたいだけだから、音楽で身を立てようとか言う発想はないし、楸矢が音大に行くかどうかや将来どうするかは本人が勝手に決めればいいと考えているようだ。
勿論、楸矢が困っていたり悩んでいたりすれば助けるだろうが、それ以外で干渉する気はないのだろう。
家族に対してさえそうなのだから他人との対立など起きようがない。
帰還派のように向こうから何か仕掛けてくれば別だが。
小夜が音楽室で歌い始めると柊矢も楸矢もすぐにやってきて演奏を始める。
特に柊矢はそれが顕著だ。
他のムーシコスも多分、柊矢同様ムーシカを聴くと、そのときやっていたことを放り出して歌や演奏を始めてしまうのだろう。
個人差はあるが、ムーシコスはそれくらい音楽――というかムーシカ――に弱い。
「そう思いたいのは山々だけどさ、沙陽みたいのだっているじゃん。それに危険な兵器を使ってとかじゃなくてムーシカが惑星を壊しそうになったとか」
「歌で惑星を壊せるものなんですか?」
「嵐を起こせるくらいだからねぇ。案外、旋律が溶けると惑星が崩壊する、とかかもよ」
そんな話をしているうちにバスがバス停に着いた。
小夜がバスから降りる。
「買い物に行くんだ」
楸矢が一緒に降りながら言った。
霧生家の最寄りのバス停は次である。ここで下りたと言うことはスーパーで買い物をすると言うことだ。
「今日の夕食、何?」
「まだ材料買ってませんから何でもいいですよ」
「そっかぁ。何にしようかな」
楸矢はそう言いながら嬉しそうに小夜の隣を歩き始めた。
「今度こそ決めた! カツ丼と肉じゃが!」
楸矢は散々迷った末その二つに決めた。
なかなか決まらないのでスーパーの中をうろうろしてしまった。
材料をカゴに入れるとレジに向かった。
「小夜ちゃん、お礼にいいこと教えてあげる。柊兄の誕生日、来月だよ。二月五日」
「そうだったんですか。楸矢さんはいつなんですか?」
「え、俺? 俺はいいじゃん。内緒」
「教えてくれないんですか?」
「そ、秘密」
何か嫌なことでもあったのかな?
もしかしてお祖父様の命日だとか?
それなら無理に聞かない方がいいだろう。
小夜は深く追求しなかった。
小夜が肉じゃがを作っているとき柊矢が帰ってきた。
「お帰りなさい」
「ただいま。今日は肉じゃがか」
柊矢は小夜の肩越しに鍋を覗き込んだ。
と、柊矢さん、顔近い!
い、今、頬が触れたような気が……。
小夜は真っ赤になった。
心臓の音が聞こえないといいけど……!
「あ、あの、柊矢さん?」
小夜は俯いたまま、柊矢に声をかけた。
「ん?」
「楸矢さんのお誕生日って……」
「十月十日だが」
「何か嫌なことでもあったんですか?」
「妊娠期間は十月十日って言うだろ。それで子供の頃、元旦に作られたって散々からかわれたんだ」
柊矢の言葉に小夜は耳まで赤くなった。
「もう出来ますから、楸矢さんを呼んできてもらえますか?」
「分かった」