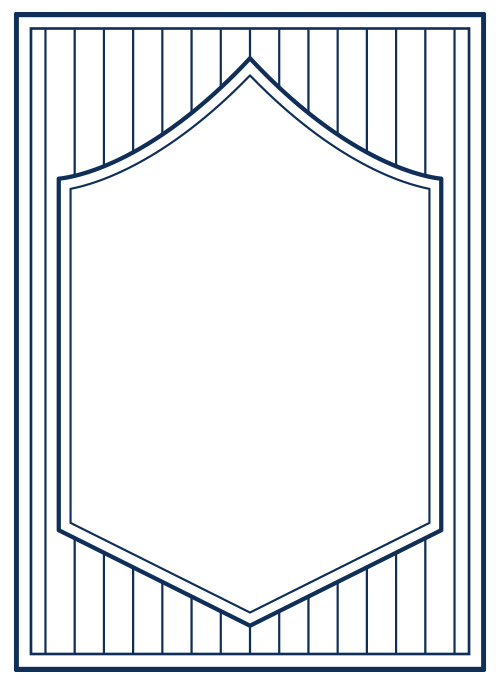三
小夜は風呂に入って着替えると自分の部屋のベッドに横になった。
大丈夫。
柊矢さん達は心配してくれるけど、私はこんなことに負けない。
心の中に大切にしまった想いが輝くから。
柊矢さんのあの胸が痛くなるような優しい笑顔。
これは私だけの秘密。
誰にも奪うことが出来ない私の宝物。
これが心の中で光り続ける限り誰にも負けない。
心の中の光は誰にも消せないから。
そう思うと自然に胸の中に旋律が浮かんできた。
これは……既存のムーシカじゃない!
今、私の中で生まれたムーシカだ。
歌いたい。
せめて柊矢達に伝えられるように楽譜にして残したい。
しかし小夜は旋律を楽譜にする技術は持っていなかった。
柊矢や楸矢なら出来るだろうが伝えるすべがない。
口がきけないことがこんなに不便だったなんて。
もし喉が元通りになったら、これからはもっと大切にしよう。大事な声だから。
柊矢さん達、心配してるだろうな。
心配かけないようにするためにも、いつも通りにしていよう。
朝方、うとうとしたとき包丁を使う音が聞こえてきて柊矢は部屋を飛び出した。
台所で小夜が朝食を作っていた。
「おい、何やってるんだ!」
小夜は包丁を置くとテーブルに置いてあったスマホを手に取って何かを入力した。
柊矢のスマホに着信音が鳴った。
ポケットから取り出すと画面に
朝ごはんです
と書いてあった。
「こんなときにそんなことしなくてもいいだろ」
と言うと、
声が出ないだけで他のことは出来ます
というメッセージが届いた。
「柊兄、どうしたの? って、小夜ちゃん! 何やってるの!」
小夜はスマホの画面を見せた。
「そうは言ってもねぇ」
楸矢は腕を組んで考え込んだ。
確かに声以外に異常はない。
なら、普段通りにさせてやった方がいいのだろうか。
楸矢が柊矢を見ると彼も考え込んでいた。
小夜は考え込んでいる二人に背を向けると包丁を手に取った。
「学校には電話して先生に説明はしておいた」
小夜が頷いた。
柊矢が助手席側のドアを開けると小夜は車から降りてお辞儀をしてから学校に向かった。
「小夜、おはよう!」
清美が声をかけてきた。
小夜は予め入力しておいた、
おはよう
と言う文を指した。
「小夜、声出ないの!?」
小夜が頷いた。
「風邪?」
首を振る。
「怪我でもしたとか?」
近いかな
とメッセージを打ち込んだ。
「治るんだよね?」
清美が恐る恐る訊ねた。
心配をかけたくなかったので頷く。
「そっか。早く治るといいね」
ありがと
友達との会話がスマホになっただけで後は普通だった。
教科書は読めるしノートに字も書ける。
体育の短距離走のタイムが悪いのは元々だ。
家でも学校でも小夜は出来る限りいつも通りに過ごした。
柊矢と楸矢も今まで通りに接してくれるようになった。
一週間後、柊矢は小夜を連れて病院へ行った。
楸矢も一緒に行くといってきかないので連れてきた。
検査結果はまだ出てない、と言われた。既存の薬物ではないらしい。
医師は小夜を先に診察室から出すと、柊矢に二度と声が出ないかもしれない、と告げた。
ムーソポイオスの声を潰す毒か。
長い歴史の間には今回のような対立は何度もあっただろうし、ムーシカで物事の決着が付くことが多いであろうムーシコスなら、声を潰す専用の毒があってもおかしくない。
ムーシコスに詳しい沙陽ならそう言う毒の存在を知っていても不思議はないだろう。
となると、解毒剤の在処か作り方を知っていそうなのは……椿矢か。
小夜は先に診察室を出された時点で声が戻らないのだと察した。でなければ小夜の前で話すはずだ。
もう歌えないんだ。
でも聴こえる。今も。
ムーシカはいつでも優しく響いている。
そうだ!
小夜は、
楸矢さんはピアノが弾けるんですよね?
と打ち込んだ。
画面を見た楸矢は、
「うん。弾けるよ」
と答えた。
教えてもらえますか?
「勿論。そうか、歌えるようになるまではピアノ弾いてればいいんだよね」
楸矢はいい考えだ、と言うように頷いた。
「ムーソポイオス専用の毒?」
小夜に聞かせたくない話は彼女が風呂に入っているときにするようになった。
小夜は男二人からすると長風呂だからだ。
「だろうな。沙陽は薬学には詳しくないはずなのに普通の検査で分からないと言うことは多分そう言うものがあるんだろう」
小夜が二度と歌えないかもしれない。
そう聞いたとき楸矢は頭をコンクリートの塊で思い切り殴られたような衝撃を受けた。
自分がフルートを吹けなくなっても、ここまでのショックは受けなかったに違いない。
小夜がそのことを知ったらどれだけ傷つくだろう。
たとえピアノが上手くなってムーシカが弾けるようになったとしても、その音色は他のムーシコスには届かない。
ムーシコスに聴こえる演奏はキタリステースが特定の楽器で奏でたものだけだ。
「とにかく、何か知ってるとしたら椿矢だ。なんとしてでもあいつを見つけよう」
「分かった。明日からは椿矢を……あ」
「どうした?」
「俺、小夜ちゃんにピアノ教えるって約束しちゃった」
「そうか。なら椿矢は俺だけで捜す」
「柊兄、ゴメン」
楸矢は手を合わせた。
「いや、ピアノで気が紛れるならそれに越したことはない。どうせ捜すといっても中央公園だけだ」
次の日から小夜は楸矢にピアノを教わるようになった。
柊矢も楸矢が帰ってくるまで小夜にピアノを教えていた。
椿矢を捜すといっても歌声が聴こえないときに中央公園に行っても無駄だろう。
ムーソポイオスならベンチに座って鳩に餌をやるよりは歌いたいはずだ。
だから歌っていないなら少なくとも中央公園にはいないと言うことだ。
こんなことなら連絡先を聞いておくべきだった。
ムーシコスといっても現代の日本人だ。スマホくらい持ってるだろう。
今度会ったら聞いておこう。
椿矢は公園で歌ったりして暇そうに見えたが案外忙しいらしい。なかなか彼の歌声は聴こえてこなかった。
小夜は風呂に入って着替えると自分の部屋のベッドに横になった。
大丈夫。
柊矢さん達は心配してくれるけど、私はこんなことに負けない。
心の中に大切にしまった想いが輝くから。
柊矢さんのあの胸が痛くなるような優しい笑顔。
これは私だけの秘密。
誰にも奪うことが出来ない私の宝物。
これが心の中で光り続ける限り誰にも負けない。
心の中の光は誰にも消せないから。
そう思うと自然に胸の中に旋律が浮かんできた。
これは……既存のムーシカじゃない!
今、私の中で生まれたムーシカだ。
歌いたい。
せめて柊矢達に伝えられるように楽譜にして残したい。
しかし小夜は旋律を楽譜にする技術は持っていなかった。
柊矢や楸矢なら出来るだろうが伝えるすべがない。
口がきけないことがこんなに不便だったなんて。
もし喉が元通りになったら、これからはもっと大切にしよう。大事な声だから。
柊矢さん達、心配してるだろうな。
心配かけないようにするためにも、いつも通りにしていよう。
朝方、うとうとしたとき包丁を使う音が聞こえてきて柊矢は部屋を飛び出した。
台所で小夜が朝食を作っていた。
「おい、何やってるんだ!」
小夜は包丁を置くとテーブルに置いてあったスマホを手に取って何かを入力した。
柊矢のスマホに着信音が鳴った。
ポケットから取り出すと画面に
朝ごはんです
と書いてあった。
「こんなときにそんなことしなくてもいいだろ」
と言うと、
声が出ないだけで他のことは出来ます
というメッセージが届いた。
「柊兄、どうしたの? って、小夜ちゃん! 何やってるの!」
小夜はスマホの画面を見せた。
「そうは言ってもねぇ」
楸矢は腕を組んで考え込んだ。
確かに声以外に異常はない。
なら、普段通りにさせてやった方がいいのだろうか。
楸矢が柊矢を見ると彼も考え込んでいた。
小夜は考え込んでいる二人に背を向けると包丁を手に取った。
「学校には電話して先生に説明はしておいた」
小夜が頷いた。
柊矢が助手席側のドアを開けると小夜は車から降りてお辞儀をしてから学校に向かった。
「小夜、おはよう!」
清美が声をかけてきた。
小夜は予め入力しておいた、
おはよう
と言う文を指した。
「小夜、声出ないの!?」
小夜が頷いた。
「風邪?」
首を振る。
「怪我でもしたとか?」
近いかな
とメッセージを打ち込んだ。
「治るんだよね?」
清美が恐る恐る訊ねた。
心配をかけたくなかったので頷く。
「そっか。早く治るといいね」
ありがと
友達との会話がスマホになっただけで後は普通だった。
教科書は読めるしノートに字も書ける。
体育の短距離走のタイムが悪いのは元々だ。
家でも学校でも小夜は出来る限りいつも通りに過ごした。
柊矢と楸矢も今まで通りに接してくれるようになった。
一週間後、柊矢は小夜を連れて病院へ行った。
楸矢も一緒に行くといってきかないので連れてきた。
検査結果はまだ出てない、と言われた。既存の薬物ではないらしい。
医師は小夜を先に診察室から出すと、柊矢に二度と声が出ないかもしれない、と告げた。
ムーソポイオスの声を潰す毒か。
長い歴史の間には今回のような対立は何度もあっただろうし、ムーシカで物事の決着が付くことが多いであろうムーシコスなら、声を潰す専用の毒があってもおかしくない。
ムーシコスに詳しい沙陽ならそう言う毒の存在を知っていても不思議はないだろう。
となると、解毒剤の在処か作り方を知っていそうなのは……椿矢か。
小夜は先に診察室を出された時点で声が戻らないのだと察した。でなければ小夜の前で話すはずだ。
もう歌えないんだ。
でも聴こえる。今も。
ムーシカはいつでも優しく響いている。
そうだ!
小夜は、
楸矢さんはピアノが弾けるんですよね?
と打ち込んだ。
画面を見た楸矢は、
「うん。弾けるよ」
と答えた。
教えてもらえますか?
「勿論。そうか、歌えるようになるまではピアノ弾いてればいいんだよね」
楸矢はいい考えだ、と言うように頷いた。
「ムーソポイオス専用の毒?」
小夜に聞かせたくない話は彼女が風呂に入っているときにするようになった。
小夜は男二人からすると長風呂だからだ。
「だろうな。沙陽は薬学には詳しくないはずなのに普通の検査で分からないと言うことは多分そう言うものがあるんだろう」
小夜が二度と歌えないかもしれない。
そう聞いたとき楸矢は頭をコンクリートの塊で思い切り殴られたような衝撃を受けた。
自分がフルートを吹けなくなっても、ここまでのショックは受けなかったに違いない。
小夜がそのことを知ったらどれだけ傷つくだろう。
たとえピアノが上手くなってムーシカが弾けるようになったとしても、その音色は他のムーシコスには届かない。
ムーシコスに聴こえる演奏はキタリステースが特定の楽器で奏でたものだけだ。
「とにかく、何か知ってるとしたら椿矢だ。なんとしてでもあいつを見つけよう」
「分かった。明日からは椿矢を……あ」
「どうした?」
「俺、小夜ちゃんにピアノ教えるって約束しちゃった」
「そうか。なら椿矢は俺だけで捜す」
「柊兄、ゴメン」
楸矢は手を合わせた。
「いや、ピアノで気が紛れるならそれに越したことはない。どうせ捜すといっても中央公園だけだ」
次の日から小夜は楸矢にピアノを教わるようになった。
柊矢も楸矢が帰ってくるまで小夜にピアノを教えていた。
椿矢を捜すといっても歌声が聴こえないときに中央公園に行っても無駄だろう。
ムーソポイオスならベンチに座って鳩に餌をやるよりは歌いたいはずだ。
だから歌っていないなら少なくとも中央公園にはいないと言うことだ。
こんなことなら連絡先を聞いておくべきだった。
ムーシコスといっても現代の日本人だ。スマホくらい持ってるだろう。
今度会ったら聞いておこう。
椿矢は公園で歌ったりして暇そうに見えたが案外忙しいらしい。なかなか彼の歌声は聴こえてこなかった。