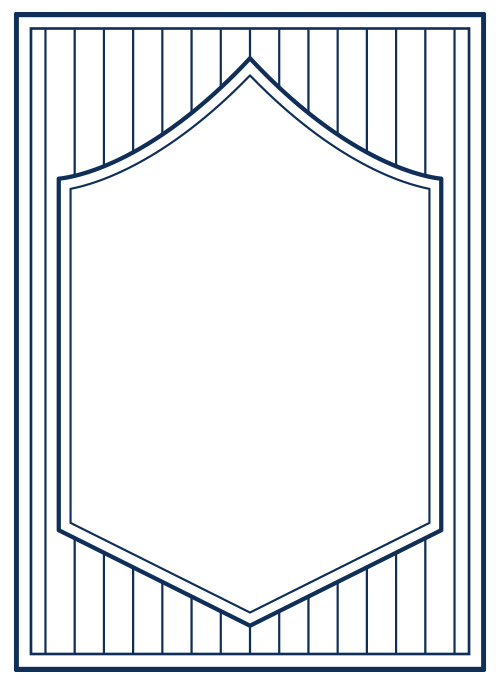二
その日も清美とお茶をし、彼女と別れて柊矢と共に駐車場に来たところだった。
近付いてくるハイヒールの音に振り返ると沙陽だった。
柊矢は小夜を守るように自分のそばに引き寄せた。
沙陽の表情が険しくなる。
「柊矢、今までのことは謝るわ」
その言葉に柊矢は眉をひそめた。
沙陽がそんなことを言うなんて何か企んでいるに違いない。
その程度には沙陽のことを知っているつもりだった。
「私、桂の方がムーシコスだと思ってたの。桂がそんな素振り見せたから。でも嘘だった」
一体何の話だ?
沙陽を理解しているという確信が徐々に崩れてきた。
「あなたがムーシコスだと教えてくれてたら、あなたを選んでた」
柊矢は溜息をついた。
あのとき、『あなた【が】』と言ったのはこう言う意味だったのか。
沙陽は二人のうちの片方がムーシコスだろうと見当を付けたものの、どちらなのかまでは分からなかったのだ。
ムーソポイオスならムーシカを歌うだけだから分かりやすいが、キタリステースは特定の楽器で演奏しないとムーシカであっても〝聴こえない〟から判別が難しいのだ。
それでムーシコスの振りをした桂を選んだ。
自分が情けなかった。
沙陽を好きだったことがではない。
一時でも沙陽に好かれていると自惚れたことが、だ。
「お前は、ムーシコスかどうかで、相手を選ぶのか?」
「そうよ。うちはムーシコスの一族だもの。私もムーシコス以外の相手を選ぶ気はないわ。それにムーシコスじゃなければムーシケーには連れていけないでしょ」
それは動物が自分にふさわしいかどうかで交尾する相手を選ぶのと同じだ。
人間もムーシコスも動物だが、相手を選ぶ基準は他の動物とは違うと思いたい。
でなければ愛も恋も幻想と言うことになるではないか。
「あなただってその子がムーソポイオスだから連れ歩いてるんでしょう」
「違う!」
柊矢は即座に否定した。
その語気の強さに沙陽はたじろいだ。
確かに知り合ったきっかけは互いがムーシコスだったからだ。
しかし小夜がムーシコスでなくても、どこかで知り合っていたら好感を持っただろう。
救急車に同乗したとき小夜が歌う人間かどうかなんて考えなかった。
小夜の素直で思いやりのあるところも、安易に人に頼ろうとしないで自力で頑張ろうとするところも好ましいと思っている。
それは個人の資質でムーシコスかどうかは関係ない。
沙陽はそんなことも分からないのか。
「俺はこいつがムーソポイオスかどうかで判断したんじゃない」
「わ、私、柊矢さんがムーシコスだから好きなったんじゃありません」
小夜は沙陽に睨まれながらも言い切った。
あ、言っちゃった。それも本人の前で。
小夜は赤くなって俯いた。
「本当にムーソポイオスじゃなくてもその子を選ぶのね。その子が歌えなくても」
「ああ、そうだ」
柊矢がそう言った瞬間、沙陽が手を振ったかと思うと小夜に液体がかかった。
手の中に小瓶を隠し持っていたらしい。
小夜は咄嗟に腕で顔を庇った。
「……っ!」
突然、小夜が咳き込みだした。
「何をする! おい、大丈夫か!」
小夜は頷きながら何とか声を出そうとするが咳が出るばかりだった。
「こいつに何をした!」
「歌えなくてもいいんでしょ。だから歌えなくしただけよ。本当にその子が歌えなくてもいいのかよく考えるのね」
沙陽はそう言うと踵を返して去っていった。
小夜は咳をするばかりで声を出さなかった。
いや、出せないのだ。
「ちょっと来い」
柊矢はそう言うとファーストフード店に戻りトイレに連れて行った。
女性用の洗面台に小夜を連れて行くと、
「うがいしろ」
そう言って小夜にうがいをさせた。
しかし、いくらうがいをしても小夜の声は出なかった。
そもそも口どころか顔にもかかっていないからうがいは無駄だ。
皮膚から吸収されたのだろう。
くそ! 側にいたのに守れなかった!
柊矢は小夜を連れてトイレを出ると車で近くの総合病院の救急外来へ向かった。
救急外来では何時間も待たされた。
小夜のことで頭がいっぱいで楸矢へ連絡するのを忘れていた。
「柊兄! 何があったの!」
楸矢がやってきた。スマホのGPSで柊矢の居場所を捜したらしい。
「沙陽にやられた」
「小夜ちゃん? 何されたの?」
柊矢は楸矢に事情を話した。
「それで、口がきけなくなっちゃったの?」
楸矢が信じられない、と言う表情で言った。
「同じムーソポイオスなら歌えなくなることがどれだけ辛いか分かるはずなのに!」
「あいつは他人の気持ちを思いやれるような女じゃない。それに、もしかしたら歌えなくなればクレーイス・エコーじゃなくなるのかもしれない」
「俺達のことを忘れているなら思い出させてやればいい」
楸矢が低い声で言った。
そうなのだ。
ムーシカが必要なとき小夜が歌えなくても柊矢と楸矢が演奏をすれば他のムーソポイオスが歌う。
小夜の声だけ奪っても意味はない。
だが柊矢の腕を傷つけようとはしなかった。
楸矢も狙われていない。
三人同時に狙うつもりならずっと前に家に火を付けてるだろう。
「で、小夜ちゃんは?」
「今検査中だ」
「早く治るといいけど」
だが、そんなに簡単に治るようなものを沙陽が使うはずがない。
きっと治るまでに時間がかかるだろう。
沙陽はクレーイス・エコーとしての小夜を恐れたのではない。
柊矢のそばにいる小夜に嫉妬したのだ。同じ女として。
「楸矢、腹減っただろ。何か食ってこい。こっちが終わったら連絡する」
「小夜ちゃんの一大事に食事なんてする気になれると思う?」
そのとき診察室のドアが開いて小夜が出てきた。看護師が一緒に出てくる。声が出せない小夜の代わりに説明するためだろう。
看護師は、一週間後に検査結果を聞きに来るように、と言った。
「有難うございました」
柊矢と小夜、楸矢は看護師に頭を下げると薬の処方箋を貰って病院を後にした。
「腹は空いてないか?」
小夜は首を振った。
ムーソポイオスが声を失ったのだ。とても食事どころではないだろう。
「それならうちへ帰ろう」
うちへ帰ると小夜が夕食を作ろうとしたので止めた。
柊矢も楸矢も食事をする気分ではなかったのだ。
しかし、それでは小夜が納得しそうになかったので楸矢がデリバリーを注文した。
「今日は休め。また明日考えよう」
小夜は黙って頭を下げると自分の部屋へ上がっていった。
泣いたりしない小夜を見ているのが辛かった。
泣いてくれれば抱きしめて慰めることも出来るのに。
今はそれすらしてやれない自分が歯がゆかった。
柊矢達に迷惑をかけないようにと、そればかり気にしているのだ。
いっそ自分の腕を切ってくれた方がどれだけ気が楽だったか。
こんなことをして柊矢が小夜を捨てて沙陽の元へ行くと本気で思っているのだろうか。
それほどまでに人の感情というものが分からないのだろうか。
そんな怪物と一時でも付き合っていたのか。
何故付き合っているときに分からなかったのだろう。
二股かけられていると分かったときでさえ、こんな女だとは思いもしなかった。
「くそ!」
自分の右手で左手の平を殴った。
本来なら壁か柱を殴りたいところだが小夜が怯えると思ってやめた。
柊矢は守るためにそばにいたのに守れなかったという痛恨の思いに苛まれた。
その日も清美とお茶をし、彼女と別れて柊矢と共に駐車場に来たところだった。
近付いてくるハイヒールの音に振り返ると沙陽だった。
柊矢は小夜を守るように自分のそばに引き寄せた。
沙陽の表情が険しくなる。
「柊矢、今までのことは謝るわ」
その言葉に柊矢は眉をひそめた。
沙陽がそんなことを言うなんて何か企んでいるに違いない。
その程度には沙陽のことを知っているつもりだった。
「私、桂の方がムーシコスだと思ってたの。桂がそんな素振り見せたから。でも嘘だった」
一体何の話だ?
沙陽を理解しているという確信が徐々に崩れてきた。
「あなたがムーシコスだと教えてくれてたら、あなたを選んでた」
柊矢は溜息をついた。
あのとき、『あなた【が】』と言ったのはこう言う意味だったのか。
沙陽は二人のうちの片方がムーシコスだろうと見当を付けたものの、どちらなのかまでは分からなかったのだ。
ムーソポイオスならムーシカを歌うだけだから分かりやすいが、キタリステースは特定の楽器で演奏しないとムーシカであっても〝聴こえない〟から判別が難しいのだ。
それでムーシコスの振りをした桂を選んだ。
自分が情けなかった。
沙陽を好きだったことがではない。
一時でも沙陽に好かれていると自惚れたことが、だ。
「お前は、ムーシコスかどうかで、相手を選ぶのか?」
「そうよ。うちはムーシコスの一族だもの。私もムーシコス以外の相手を選ぶ気はないわ。それにムーシコスじゃなければムーシケーには連れていけないでしょ」
それは動物が自分にふさわしいかどうかで交尾する相手を選ぶのと同じだ。
人間もムーシコスも動物だが、相手を選ぶ基準は他の動物とは違うと思いたい。
でなければ愛も恋も幻想と言うことになるではないか。
「あなただってその子がムーソポイオスだから連れ歩いてるんでしょう」
「違う!」
柊矢は即座に否定した。
その語気の強さに沙陽はたじろいだ。
確かに知り合ったきっかけは互いがムーシコスだったからだ。
しかし小夜がムーシコスでなくても、どこかで知り合っていたら好感を持っただろう。
救急車に同乗したとき小夜が歌う人間かどうかなんて考えなかった。
小夜の素直で思いやりのあるところも、安易に人に頼ろうとしないで自力で頑張ろうとするところも好ましいと思っている。
それは個人の資質でムーシコスかどうかは関係ない。
沙陽はそんなことも分からないのか。
「俺はこいつがムーソポイオスかどうかで判断したんじゃない」
「わ、私、柊矢さんがムーシコスだから好きなったんじゃありません」
小夜は沙陽に睨まれながらも言い切った。
あ、言っちゃった。それも本人の前で。
小夜は赤くなって俯いた。
「本当にムーソポイオスじゃなくてもその子を選ぶのね。その子が歌えなくても」
「ああ、そうだ」
柊矢がそう言った瞬間、沙陽が手を振ったかと思うと小夜に液体がかかった。
手の中に小瓶を隠し持っていたらしい。
小夜は咄嗟に腕で顔を庇った。
「……っ!」
突然、小夜が咳き込みだした。
「何をする! おい、大丈夫か!」
小夜は頷きながら何とか声を出そうとするが咳が出るばかりだった。
「こいつに何をした!」
「歌えなくてもいいんでしょ。だから歌えなくしただけよ。本当にその子が歌えなくてもいいのかよく考えるのね」
沙陽はそう言うと踵を返して去っていった。
小夜は咳をするばかりで声を出さなかった。
いや、出せないのだ。
「ちょっと来い」
柊矢はそう言うとファーストフード店に戻りトイレに連れて行った。
女性用の洗面台に小夜を連れて行くと、
「うがいしろ」
そう言って小夜にうがいをさせた。
しかし、いくらうがいをしても小夜の声は出なかった。
そもそも口どころか顔にもかかっていないからうがいは無駄だ。
皮膚から吸収されたのだろう。
くそ! 側にいたのに守れなかった!
柊矢は小夜を連れてトイレを出ると車で近くの総合病院の救急外来へ向かった。
救急外来では何時間も待たされた。
小夜のことで頭がいっぱいで楸矢へ連絡するのを忘れていた。
「柊兄! 何があったの!」
楸矢がやってきた。スマホのGPSで柊矢の居場所を捜したらしい。
「沙陽にやられた」
「小夜ちゃん? 何されたの?」
柊矢は楸矢に事情を話した。
「それで、口がきけなくなっちゃったの?」
楸矢が信じられない、と言う表情で言った。
「同じムーソポイオスなら歌えなくなることがどれだけ辛いか分かるはずなのに!」
「あいつは他人の気持ちを思いやれるような女じゃない。それに、もしかしたら歌えなくなればクレーイス・エコーじゃなくなるのかもしれない」
「俺達のことを忘れているなら思い出させてやればいい」
楸矢が低い声で言った。
そうなのだ。
ムーシカが必要なとき小夜が歌えなくても柊矢と楸矢が演奏をすれば他のムーソポイオスが歌う。
小夜の声だけ奪っても意味はない。
だが柊矢の腕を傷つけようとはしなかった。
楸矢も狙われていない。
三人同時に狙うつもりならずっと前に家に火を付けてるだろう。
「で、小夜ちゃんは?」
「今検査中だ」
「早く治るといいけど」
だが、そんなに簡単に治るようなものを沙陽が使うはずがない。
きっと治るまでに時間がかかるだろう。
沙陽はクレーイス・エコーとしての小夜を恐れたのではない。
柊矢のそばにいる小夜に嫉妬したのだ。同じ女として。
「楸矢、腹減っただろ。何か食ってこい。こっちが終わったら連絡する」
「小夜ちゃんの一大事に食事なんてする気になれると思う?」
そのとき診察室のドアが開いて小夜が出てきた。看護師が一緒に出てくる。声が出せない小夜の代わりに説明するためだろう。
看護師は、一週間後に検査結果を聞きに来るように、と言った。
「有難うございました」
柊矢と小夜、楸矢は看護師に頭を下げると薬の処方箋を貰って病院を後にした。
「腹は空いてないか?」
小夜は首を振った。
ムーソポイオスが声を失ったのだ。とても食事どころではないだろう。
「それならうちへ帰ろう」
うちへ帰ると小夜が夕食を作ろうとしたので止めた。
柊矢も楸矢も食事をする気分ではなかったのだ。
しかし、それでは小夜が納得しそうになかったので楸矢がデリバリーを注文した。
「今日は休め。また明日考えよう」
小夜は黙って頭を下げると自分の部屋へ上がっていった。
泣いたりしない小夜を見ているのが辛かった。
泣いてくれれば抱きしめて慰めることも出来るのに。
今はそれすらしてやれない自分が歯がゆかった。
柊矢達に迷惑をかけないようにと、そればかり気にしているのだ。
いっそ自分の腕を切ってくれた方がどれだけ気が楽だったか。
こんなことをして柊矢が小夜を捨てて沙陽の元へ行くと本気で思っているのだろうか。
それほどまでに人の感情というものが分からないのだろうか。
そんな怪物と一時でも付き合っていたのか。
何故付き合っているときに分からなかったのだろう。
二股かけられていると分かったときでさえ、こんな女だとは思いもしなかった。
「くそ!」
自分の右手で左手の平を殴った。
本来なら壁か柱を殴りたいところだが小夜が怯えると思ってやめた。
柊矢は守るためにそばにいたのに守れなかったという痛恨の思いに苛まれた。