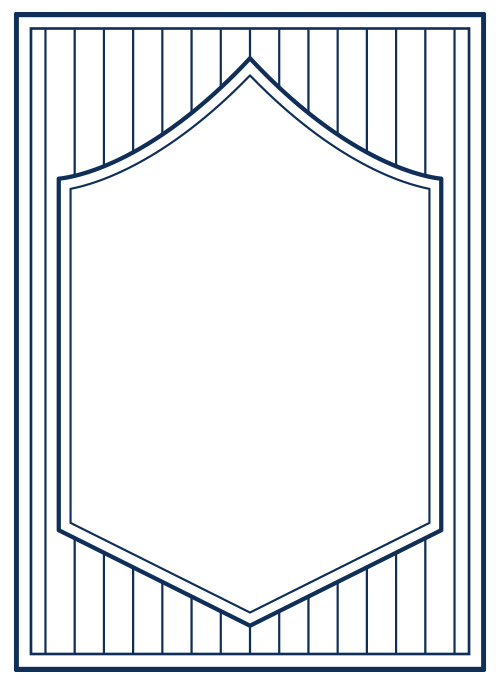五
翌日、柊矢の迎えの車に乗って学校から帰ってくるとスマホが鳴った。
スマホのディスプレイに、清美、と出ている。
何の用だろ。
小夜はスマホに出た。
「きよ……」
「この子は預かったわ。次の電話を待つのね」
沙陽はそう言って通話を切った。
清美が攫われた!
小夜は真っ青になった。
その様子に台所から出てきた楸矢が気付いた。
「小夜ちゃん! どうしたの?」
「楸矢さん」
「何があった」
楸矢の声に柊矢も近寄ってきた。
「清美が、沙陽さん達に攫われたみたいなんです」
「ホントに!? 小夜ちゃん、それは確か?」
「電話してきたのは清美のスマホからでした」
「家にもかけてみろ」
柊矢の言葉に清美の家に電話したが母親が出て、清美はまだ帰ってない、と言われた。
それを伝えると、
「彼女のスマホ、どこのだ?」
柊矢が訊ねてきた。
「え?」
「キャリアによってはスマホの場所を探すサービスがあるだろ」
「あ! そうでした!」
多少もたついたが清美のスマホの場所が分かった。
「新宿の……」
「中央公園、でしょ」
楸矢が小夜の言葉を引き取った。
「森が出てる」
楸矢の言葉に外を見ると確かに森が見えた。
「行こう、小夜ちゃん」
楸矢が言った。
「はい!」
小夜がそう返事をすると柊矢は車の鍵をポケットから取り出した。
楸矢は青いビニールシートにくるまれたものを持ってきた。楽器だろう。
中央公園は森の端だ。
この辺りには樹はなく目の前には池が広がっていた。
小夜達が森に入って行くと森の存在感が一層増した。
「クレーイスが近付いたからだな」
辺りから小さなベルが鳴るように旋律の切れ端が聴こえてきている。
「旋律が溶け始めてるな……」
柊矢が辺りを見回しながら言った。
「森が……喜んでる」
弾むように、旋律の欠片が辺りを漂っていた。
樹々が身じろぎをする。
すると鈴のように旋律の断片が鳴った。
超高層ビルの天辺辺りから溶け始めた旋律が雪のようにふわふわと舞い落ちてくる。
「この旋律は……」
旋律から喜びの感情が伝わってくる。
「嬉しいんだ。凍り付いてるのは本意じゃなかったんですね」
小夜が呟くように言った。
だとしたら何故旋律は凍り付いているのだろうか。
少し歩くと、そこに沙陽と見知らぬ男が立っていた。
清美がいない!
「沙陽さん! 清美は……」
言いかけた小夜にスマホを放ってよこした。
「おい、それを返していいのか」
男が言った。
「スマホに人質としての価値なんかないでしょ」
スマホ?
小夜は自分のスマホから清美の家に電話をしてみた。
すぐに清美が出た。
「もしもし」
「清美!」
「なんだ、小夜か」
清美のがっかりした声が聞こえた。
清美の無事が確認できた小夜はほっとした。
「ゴメン、小夜。今電話待ってるから後でいい?」
「うん。それじゃ」
小夜はそう言うとスマホを切った。
切ってから、清美が待っているのはスマホを見つけたという電話だと気付いたが、今その話をしている時間はない。
後で電話し直そう。
「あなた達にも分かるはずよ。森は起きたがってる。私達を帰れるようにしてちょうだい」
「沙陽……さん、その前に小夜ちゃんに言うことがあるんじゃないの?」
「なにを?」
沙陽は本当に分からないようだった。
「小夜ちゃんの家を火事にしたんでしょ」
「そうだけど、その子は無事じゃない」
なんだ、そんなことか、と言う表情で答えた。
「小夜ちゃんのお祖父さんは亡くなって、小夜ちゃんは家も何もかもなくしたんだぞ!」
「だから?」
「頼み事する前に謝るのが筋ってもんじゃないのか」
「ああ、そ。悪かったわ」
全く悪かったと思ってない顔で言った。
「沙陽……っ!」
楸矢が怒鳴った。
柊矢が楸矢の肩に手を置く。
「あいつには言うだけ無駄だ」
「これじゃ、まだ帰れないわ」
確かに、溶け始めているとは言えまだ森は凍り付いている。
「クレーイスを持っているなら旋律を溶かす歌が歌えるはずよ」
小夜の祖父が死んだのは沙陽のせいだ。
それを思うと沙陽の言いなりになって森を起こすのは抵抗がある。
しかし森は起きたがっている。
森の望みは叶えてあげたい。
小夜はどうすればいいか分からず柊矢を見上げた。
視線に気付いて振り向いた柊矢が驚いたように目を見開いた。
「おい、ポケット!」
柊矢の言葉に下を見るとスカートのポケットが光っていた。
取り出してみるとクレーイスが光を発している。
小夜は手の中のクレーイスを見下ろした。
クレーイスから旋律が溢れてくる。
小夜の知らなかった旋律だ。
このムーシカは……。
クレーイスを柊矢に渡すと彼は理解したようだ。
柊矢が楸矢に手渡すと、彼も分かった、と言う表情で頷いて小夜に返した。
楸矢はビニールシートから楽器を出すと柊矢にキタラを渡した。
柊矢と楸矢が楽器を奏で始める。
小夜がそれに合わせて歌い始めると沙陽が嬉しそうな顔になった。
小夜のムーシカにムーシコスのコーラスや演奏が加わっていく。
沙陽はほくそ笑んだ。
今まで自分の邪魔をしていたムーシコスが何も知らずに協力してると思うと傑作だった。
勿論、自分に賛同してくれなかったことは悔しいが。
だがその喜びも長くは続かなかった。
小夜の歌が森の中を広がっていく。
歌声が優しく旋律の切れ端を包む。
それにつれて溶け始めていた旋律の欠片が凍り付き雪のように大地へと降ってきた。
樹々が嫌がるように身じろぎする。
小夜には森が抗おうとしているのが手に取るように分かった。
嫌だよね。
音のない世界でただ眠っているだけなんて。
昔のように歌っていたいんだよね。
ごめんね。
小夜は心の中で謝りながらも歌うのをやめなかった。
それが自分の、クレーイス・エコーの役目だから。
理由は分からないけれど、自分がクレーイス・エコーだと言うことも、クレーイス・エコーがやらなければいけないことも、心の中で理解したから。
殆どの旋律の欠片が再び凍り付くと樹々も諦めたように次々と眠りについていった。
歌が終わる頃には、また元の凍り付いた森に戻っていた。
「おい!」
「これはどういうこと!」
男と沙陽が同時に叫んだ。
「お前らの言うとおりに奏でただけだが」
「ムーシケーがまだ時期じゃないって……」
小夜が言い訳するように言った。
「なんでそんなことが分かるのよ!」
「それは……」
「ムーシカで分かるだろ。クレーイスから溢れてくるムーシカを歌ったら森は元に戻った」
そうなのだ。
小夜はクレーイスから湧き上がってくる旋律を聴いてすぐに気付いた。
これは封印のムーシカだと。
多分、その昔、ムーシケーを凍らせるために奏でられた旋律。
柊矢と楸矢もすぐに理解した。
他のムーシコスも、これは人を傷つけるムーシカではないと判断したから小夜に同調した。
いつしか森は消えていた。
「これが仕返しってわけ。よく分かったわ」
沙陽はそう捨て台詞を吐くと男と共に歩み去った。
翌日、柊矢の迎えの車に乗って学校から帰ってくるとスマホが鳴った。
スマホのディスプレイに、清美、と出ている。
何の用だろ。
小夜はスマホに出た。
「きよ……」
「この子は預かったわ。次の電話を待つのね」
沙陽はそう言って通話を切った。
清美が攫われた!
小夜は真っ青になった。
その様子に台所から出てきた楸矢が気付いた。
「小夜ちゃん! どうしたの?」
「楸矢さん」
「何があった」
楸矢の声に柊矢も近寄ってきた。
「清美が、沙陽さん達に攫われたみたいなんです」
「ホントに!? 小夜ちゃん、それは確か?」
「電話してきたのは清美のスマホからでした」
「家にもかけてみろ」
柊矢の言葉に清美の家に電話したが母親が出て、清美はまだ帰ってない、と言われた。
それを伝えると、
「彼女のスマホ、どこのだ?」
柊矢が訊ねてきた。
「え?」
「キャリアによってはスマホの場所を探すサービスがあるだろ」
「あ! そうでした!」
多少もたついたが清美のスマホの場所が分かった。
「新宿の……」
「中央公園、でしょ」
楸矢が小夜の言葉を引き取った。
「森が出てる」
楸矢の言葉に外を見ると確かに森が見えた。
「行こう、小夜ちゃん」
楸矢が言った。
「はい!」
小夜がそう返事をすると柊矢は車の鍵をポケットから取り出した。
楸矢は青いビニールシートにくるまれたものを持ってきた。楽器だろう。
中央公園は森の端だ。
この辺りには樹はなく目の前には池が広がっていた。
小夜達が森に入って行くと森の存在感が一層増した。
「クレーイスが近付いたからだな」
辺りから小さなベルが鳴るように旋律の切れ端が聴こえてきている。
「旋律が溶け始めてるな……」
柊矢が辺りを見回しながら言った。
「森が……喜んでる」
弾むように、旋律の欠片が辺りを漂っていた。
樹々が身じろぎをする。
すると鈴のように旋律の断片が鳴った。
超高層ビルの天辺辺りから溶け始めた旋律が雪のようにふわふわと舞い落ちてくる。
「この旋律は……」
旋律から喜びの感情が伝わってくる。
「嬉しいんだ。凍り付いてるのは本意じゃなかったんですね」
小夜が呟くように言った。
だとしたら何故旋律は凍り付いているのだろうか。
少し歩くと、そこに沙陽と見知らぬ男が立っていた。
清美がいない!
「沙陽さん! 清美は……」
言いかけた小夜にスマホを放ってよこした。
「おい、それを返していいのか」
男が言った。
「スマホに人質としての価値なんかないでしょ」
スマホ?
小夜は自分のスマホから清美の家に電話をしてみた。
すぐに清美が出た。
「もしもし」
「清美!」
「なんだ、小夜か」
清美のがっかりした声が聞こえた。
清美の無事が確認できた小夜はほっとした。
「ゴメン、小夜。今電話待ってるから後でいい?」
「うん。それじゃ」
小夜はそう言うとスマホを切った。
切ってから、清美が待っているのはスマホを見つけたという電話だと気付いたが、今その話をしている時間はない。
後で電話し直そう。
「あなた達にも分かるはずよ。森は起きたがってる。私達を帰れるようにしてちょうだい」
「沙陽……さん、その前に小夜ちゃんに言うことがあるんじゃないの?」
「なにを?」
沙陽は本当に分からないようだった。
「小夜ちゃんの家を火事にしたんでしょ」
「そうだけど、その子は無事じゃない」
なんだ、そんなことか、と言う表情で答えた。
「小夜ちゃんのお祖父さんは亡くなって、小夜ちゃんは家も何もかもなくしたんだぞ!」
「だから?」
「頼み事する前に謝るのが筋ってもんじゃないのか」
「ああ、そ。悪かったわ」
全く悪かったと思ってない顔で言った。
「沙陽……っ!」
楸矢が怒鳴った。
柊矢が楸矢の肩に手を置く。
「あいつには言うだけ無駄だ」
「これじゃ、まだ帰れないわ」
確かに、溶け始めているとは言えまだ森は凍り付いている。
「クレーイスを持っているなら旋律を溶かす歌が歌えるはずよ」
小夜の祖父が死んだのは沙陽のせいだ。
それを思うと沙陽の言いなりになって森を起こすのは抵抗がある。
しかし森は起きたがっている。
森の望みは叶えてあげたい。
小夜はどうすればいいか分からず柊矢を見上げた。
視線に気付いて振り向いた柊矢が驚いたように目を見開いた。
「おい、ポケット!」
柊矢の言葉に下を見るとスカートのポケットが光っていた。
取り出してみるとクレーイスが光を発している。
小夜は手の中のクレーイスを見下ろした。
クレーイスから旋律が溢れてくる。
小夜の知らなかった旋律だ。
このムーシカは……。
クレーイスを柊矢に渡すと彼は理解したようだ。
柊矢が楸矢に手渡すと、彼も分かった、と言う表情で頷いて小夜に返した。
楸矢はビニールシートから楽器を出すと柊矢にキタラを渡した。
柊矢と楸矢が楽器を奏で始める。
小夜がそれに合わせて歌い始めると沙陽が嬉しそうな顔になった。
小夜のムーシカにムーシコスのコーラスや演奏が加わっていく。
沙陽はほくそ笑んだ。
今まで自分の邪魔をしていたムーシコスが何も知らずに協力してると思うと傑作だった。
勿論、自分に賛同してくれなかったことは悔しいが。
だがその喜びも長くは続かなかった。
小夜の歌が森の中を広がっていく。
歌声が優しく旋律の切れ端を包む。
それにつれて溶け始めていた旋律の欠片が凍り付き雪のように大地へと降ってきた。
樹々が嫌がるように身じろぎする。
小夜には森が抗おうとしているのが手に取るように分かった。
嫌だよね。
音のない世界でただ眠っているだけなんて。
昔のように歌っていたいんだよね。
ごめんね。
小夜は心の中で謝りながらも歌うのをやめなかった。
それが自分の、クレーイス・エコーの役目だから。
理由は分からないけれど、自分がクレーイス・エコーだと言うことも、クレーイス・エコーがやらなければいけないことも、心の中で理解したから。
殆どの旋律の欠片が再び凍り付くと樹々も諦めたように次々と眠りについていった。
歌が終わる頃には、また元の凍り付いた森に戻っていた。
「おい!」
「これはどういうこと!」
男と沙陽が同時に叫んだ。
「お前らの言うとおりに奏でただけだが」
「ムーシケーがまだ時期じゃないって……」
小夜が言い訳するように言った。
「なんでそんなことが分かるのよ!」
「それは……」
「ムーシカで分かるだろ。クレーイスから溢れてくるムーシカを歌ったら森は元に戻った」
そうなのだ。
小夜はクレーイスから湧き上がってくる旋律を聴いてすぐに気付いた。
これは封印のムーシカだと。
多分、その昔、ムーシケーを凍らせるために奏でられた旋律。
柊矢と楸矢もすぐに理解した。
他のムーシコスも、これは人を傷つけるムーシカではないと判断したから小夜に同調した。
いつしか森は消えていた。
「これが仕返しってわけ。よく分かったわ」
沙陽はそう捨て台詞を吐くと男と共に歩み去った。