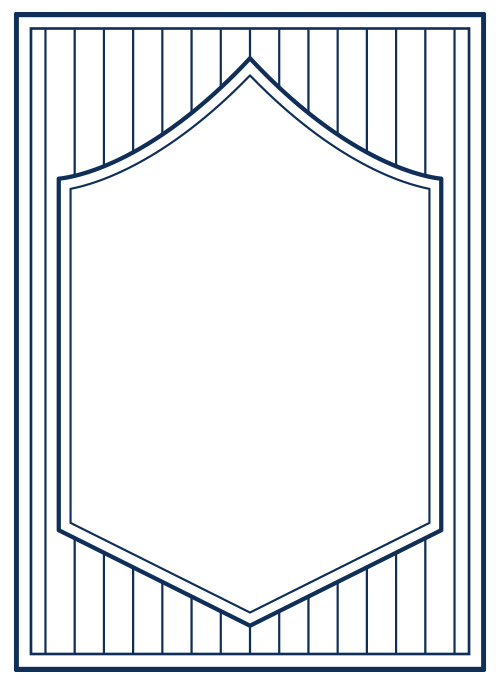四
「さて、話してもらおうか」
柊矢は助手席に向き直った。
「どこから話せばいい?」
「この森はなんだ?」
「ムーサの森だよ」
「沙陽はムーシコスはこの森から来たと言っていたが」
「そ。大昔、ムーシコスはムーシケーから来た。昔のこと過ぎて、ムーシコス自身も知らない人がほとんどだけどね」
「ちょっと待て。この森のことをムーサって言ったのに、今ムーシケーって……」
「ムーサはこの森の地名だよ。今、僕達がいる場所が新宿って言うのと同じ」
この綺麗な旋律の森がムーサ。
「このムーサがある惑星ムーシケーと、あの地平線近くの惑星グラフェー、そしてあの衛星ドラマ。その三つの天体が構成する惑星系の総称がテクネー」
「ちょっと待て! 惑星って何だ」
「君達だってこの森が地球上のものじゃないって事くらい気付いてたんじゃないの?」
柊矢は黙り込んだ。
確かに、白く半透明な巨木や空に浮かんでいる大きな白い天体を見れば、この森があるのは地球ではないんじゃないか、くらいの疑問は涌く。
「この森は本当にあるのか? 幻覚か何かじゃなくて」
「地球からどれくらい離れてるかは知らないけどね、ちゃんとあるよ」
「じゃあ、地球人は古代にこの星から宇宙船でやってきたって言うのか!?」
「地球人じゃなくて、ムーシコス。地球人は元々地球にいたよ。宇宙船は必要ないでしょ。こうして繋がってるんだから歩いてこられる」
それもそうだ。
「でも、どうしてムーシコスはムーシケーを捨てて地球へ来たんですか?」
あれだけ沢山の旋律に満ち溢れた世界はムーシコスにとっては天国のようなものだ。
離れたがった者がいるなんて想像も出来ない。
自分だったらしがみついてでも離れなかっただろう。
「あくまで想像だけど」
椿矢はそう前置きをして、
「旋律が凍り付いたからじゃないかな」
と言った。
「なんで凍り付いたのかなんて聞かないでよ。知らないからね」
確かに旋律で草木も水も凍り付いてしまった世界では生きていけない。
仕方ないから豊かな自然に満ちた地球へ行って暮らそう、となってもおかしくはない。
丁度地球と繋がっているのだし。
「お前の言うとおりテクネーと地球が繋がってるとして、沙陽達は帰りたいなら何故帰らない?」
「テクネーはグラフェーとムーシケーとドラマの総称。繋がってるのはムーシケーだけ。多分ね」
椿矢は柊矢の言葉を訂正した。
「帰ろうにも帰れないらしい。森に入って行っても地球に戻ってきちゃうらしいんだ」
そう言ってから、
「戻ってきちゃう理由も知らないからね」
と先手を打って答えた。
「まぁ、どちらにしても凍り付いた旋律を何とかしないと向こうへ行っても暮らしていけないけど」
「何とかする方法があるのか?」
「手段は知らないけどあるみたいだね」
「ムーシカが離れた所にいるムーシコスに聴こえるのはどうしてなんですか?」
「ムーシケーは音楽の惑星だから音楽は意識の底で共有してるとかじゃないかな」
「知らないことばかりじゃないか」
柊矢が咎めるように言った。
「これでも普通のムーシコスよりは詳しいよ。現に君達は知らなかったでしょ」
椿矢の言うとおりだ。
ムーシカに古典ギリシア語の歌があると言うことは、紀元前二千年頃には地球へ来ていたことになる。
柊矢が使っているキタリステース用の楽器――キタラ――がギリシアのものであることを考えても、ムーシコスの一部が大昔のギリシアにいたことは確かだろう。
もう四千年も地球人に交じって暮らしてきたのだ。
ムーシコスが地球に来た事情など忘れるには十分すぎるほどの時間がたっている。
自分と、このクレーイスがあれば、沙陽さん達はムーシケーに帰れる。
沙陽さん達を帰してあげられないだろうか。
沙陽達を帰して自分も旋律が溶けたムーシケーに時々遊びに行きたい、というのは虫が良すぎるだろうか。
勿論、沙陽のために何かすると言うのに抵抗がないわけではない。
なんと言っても沙陽は祖父を死なせたのだ。
「質問には答えたよ。そろそろ解放してもらえるかな」
「沙陽か、その仲間の連絡先を……」
「悪いけど知らない。連中に関わる気はないからね」
椿矢は柊矢の言葉を遮った。
「確かに旋律に満ちた惑星っていうのは魅惑的だよ。でも考えてもみてよ。現代文明に慣れきった僕達が電気や水道のない世界で生きていけると思う? 大昔に祖先が住んでたってだけで文明のない惑星に行く気はないよ。音楽は地球にだってあるからね」
椿矢は「行く」と言った。沙陽のように「帰る」とは言わなかった。これが残留派と帰還派の意識の違いだろう。
柊矢が車の鍵を開けた。
「それじゃ」
椿矢は車から出ると闇の中に消えていった。
入れ違いに楸矢がやってきた。
スマホのGPSで探してきたらしい。
楸矢は助手席に入ってくるなり、
「柊兄ぃ~。小鳥ちゃんとデートするならそう言っておいてよ。そしたら夕食自分で何とかしたのに」
恨めしげに柊矢を睨みつけた。
「ああ、忘れてた」
「あ、あの、楸矢さん、私達デートじゃなくて……」
「じゃ、なんで小鳥ちゃんは後部座席にいるの?」
小夜は楸矢の言葉に首を傾げた。
「デートなら助手席の方にいるんじゃないんですか?」
その言葉に柊矢と楸矢は顔を見合わせた。
「ホントにデートじゃなかったんだ」
小夜はさっぱり分からない、と言う表情で柊矢と楸矢を交互に見比べた。
「どういうことですか?」
その問いに、
「小鳥ちゃんが大人の付き合いするようになったら分かるよ」
と言う返事が返ってきた。
また大人の付き合い。
ムーシケーが旋律で凍り付いたことといい、大人の付き合いといい、小夜にとっては未知のことが多すぎる。
小夜は溜息をついた。
「柊兄達、夕食は?」
「まだだ。どこかで食べていこう」
柊矢はそう言うと車を出した。
「は? 異星人? 沙陽、本気でそんな話信じてんの?」
「こいつから無理矢理奪おうとしたところから見ても、そうなんだろうな」
「友達まで巻き込んだとなると本気ってことか」
楸矢はステーキの添えられているフライドポテトを口にした。
楸矢さんは半信半疑みたいだけど……。
小夜は椿矢の話を信じていた。
ムーシケーは、ムーサの森は、実在する。
だって、あの森で凍り付いている旋律、あれは本物だもの。
「沙陽ってさ、頭おかしいんじゃないの?」
楸矢は次のフライドポテトにフォークを突き刺した。
「仮にムーシケーだの、クレーイスだのの話が本当だとして、そのペンダントが必要だったら素直にそう頼めばこんなに大変なことにはならなかったのに」
そう言うとフライドポテトを口の中に放り込んだ。
「話しには来たな」
「そういえば、追い返しちゃったんだっけ」
楸矢はやべ、という表情を浮かべた。
「あのとき話を聞かなかったことがこんな大事になるとはな」
柊矢も失敗した、と言う表情でコーヒーを飲んだ。
「まぁ、今更後悔しても仕方ない」
「そうだね」
小夜はポケットの中でクレーイスをいじりながら俯いていた。
今からでも沙陽に協力することは出来ないだろうか。
そう二人に提案したかったが、どうしても口に出せなかった。
これは柊矢と楸矢の祖父の形見だ。
それがなくなるかもしれないことを考えると言うのを躊躇われた。言えば柊矢も楸矢も構わない、と言ってくれる気がした。
でも内心では祖父の形見を利用されるのは気分がいいものではないはずだ。
それに祖父を死なせた沙陽に協力したくないと思ってしまうのも事実だ。
「小夜ちゃん、食べないの?」
小夜の前に置かれたリゾットはまだ半分近く残っていた。
「あ、今食べます」
「急ぐことはないぞ」
「はい」
「さて、話してもらおうか」
柊矢は助手席に向き直った。
「どこから話せばいい?」
「この森はなんだ?」
「ムーサの森だよ」
「沙陽はムーシコスはこの森から来たと言っていたが」
「そ。大昔、ムーシコスはムーシケーから来た。昔のこと過ぎて、ムーシコス自身も知らない人がほとんどだけどね」
「ちょっと待て。この森のことをムーサって言ったのに、今ムーシケーって……」
「ムーサはこの森の地名だよ。今、僕達がいる場所が新宿って言うのと同じ」
この綺麗な旋律の森がムーサ。
「このムーサがある惑星ムーシケーと、あの地平線近くの惑星グラフェー、そしてあの衛星ドラマ。その三つの天体が構成する惑星系の総称がテクネー」
「ちょっと待て! 惑星って何だ」
「君達だってこの森が地球上のものじゃないって事くらい気付いてたんじゃないの?」
柊矢は黙り込んだ。
確かに、白く半透明な巨木や空に浮かんでいる大きな白い天体を見れば、この森があるのは地球ではないんじゃないか、くらいの疑問は涌く。
「この森は本当にあるのか? 幻覚か何かじゃなくて」
「地球からどれくらい離れてるかは知らないけどね、ちゃんとあるよ」
「じゃあ、地球人は古代にこの星から宇宙船でやってきたって言うのか!?」
「地球人じゃなくて、ムーシコス。地球人は元々地球にいたよ。宇宙船は必要ないでしょ。こうして繋がってるんだから歩いてこられる」
それもそうだ。
「でも、どうしてムーシコスはムーシケーを捨てて地球へ来たんですか?」
あれだけ沢山の旋律に満ち溢れた世界はムーシコスにとっては天国のようなものだ。
離れたがった者がいるなんて想像も出来ない。
自分だったらしがみついてでも離れなかっただろう。
「あくまで想像だけど」
椿矢はそう前置きをして、
「旋律が凍り付いたからじゃないかな」
と言った。
「なんで凍り付いたのかなんて聞かないでよ。知らないからね」
確かに旋律で草木も水も凍り付いてしまった世界では生きていけない。
仕方ないから豊かな自然に満ちた地球へ行って暮らそう、となってもおかしくはない。
丁度地球と繋がっているのだし。
「お前の言うとおりテクネーと地球が繋がってるとして、沙陽達は帰りたいなら何故帰らない?」
「テクネーはグラフェーとムーシケーとドラマの総称。繋がってるのはムーシケーだけ。多分ね」
椿矢は柊矢の言葉を訂正した。
「帰ろうにも帰れないらしい。森に入って行っても地球に戻ってきちゃうらしいんだ」
そう言ってから、
「戻ってきちゃう理由も知らないからね」
と先手を打って答えた。
「まぁ、どちらにしても凍り付いた旋律を何とかしないと向こうへ行っても暮らしていけないけど」
「何とかする方法があるのか?」
「手段は知らないけどあるみたいだね」
「ムーシカが離れた所にいるムーシコスに聴こえるのはどうしてなんですか?」
「ムーシケーは音楽の惑星だから音楽は意識の底で共有してるとかじゃないかな」
「知らないことばかりじゃないか」
柊矢が咎めるように言った。
「これでも普通のムーシコスよりは詳しいよ。現に君達は知らなかったでしょ」
椿矢の言うとおりだ。
ムーシカに古典ギリシア語の歌があると言うことは、紀元前二千年頃には地球へ来ていたことになる。
柊矢が使っているキタリステース用の楽器――キタラ――がギリシアのものであることを考えても、ムーシコスの一部が大昔のギリシアにいたことは確かだろう。
もう四千年も地球人に交じって暮らしてきたのだ。
ムーシコスが地球に来た事情など忘れるには十分すぎるほどの時間がたっている。
自分と、このクレーイスがあれば、沙陽さん達はムーシケーに帰れる。
沙陽さん達を帰してあげられないだろうか。
沙陽達を帰して自分も旋律が溶けたムーシケーに時々遊びに行きたい、というのは虫が良すぎるだろうか。
勿論、沙陽のために何かすると言うのに抵抗がないわけではない。
なんと言っても沙陽は祖父を死なせたのだ。
「質問には答えたよ。そろそろ解放してもらえるかな」
「沙陽か、その仲間の連絡先を……」
「悪いけど知らない。連中に関わる気はないからね」
椿矢は柊矢の言葉を遮った。
「確かに旋律に満ちた惑星っていうのは魅惑的だよ。でも考えてもみてよ。現代文明に慣れきった僕達が電気や水道のない世界で生きていけると思う? 大昔に祖先が住んでたってだけで文明のない惑星に行く気はないよ。音楽は地球にだってあるからね」
椿矢は「行く」と言った。沙陽のように「帰る」とは言わなかった。これが残留派と帰還派の意識の違いだろう。
柊矢が車の鍵を開けた。
「それじゃ」
椿矢は車から出ると闇の中に消えていった。
入れ違いに楸矢がやってきた。
スマホのGPSで探してきたらしい。
楸矢は助手席に入ってくるなり、
「柊兄ぃ~。小鳥ちゃんとデートするならそう言っておいてよ。そしたら夕食自分で何とかしたのに」
恨めしげに柊矢を睨みつけた。
「ああ、忘れてた」
「あ、あの、楸矢さん、私達デートじゃなくて……」
「じゃ、なんで小鳥ちゃんは後部座席にいるの?」
小夜は楸矢の言葉に首を傾げた。
「デートなら助手席の方にいるんじゃないんですか?」
その言葉に柊矢と楸矢は顔を見合わせた。
「ホントにデートじゃなかったんだ」
小夜はさっぱり分からない、と言う表情で柊矢と楸矢を交互に見比べた。
「どういうことですか?」
その問いに、
「小鳥ちゃんが大人の付き合いするようになったら分かるよ」
と言う返事が返ってきた。
また大人の付き合い。
ムーシケーが旋律で凍り付いたことといい、大人の付き合いといい、小夜にとっては未知のことが多すぎる。
小夜は溜息をついた。
「柊兄達、夕食は?」
「まだだ。どこかで食べていこう」
柊矢はそう言うと車を出した。
「は? 異星人? 沙陽、本気でそんな話信じてんの?」
「こいつから無理矢理奪おうとしたところから見ても、そうなんだろうな」
「友達まで巻き込んだとなると本気ってことか」
楸矢はステーキの添えられているフライドポテトを口にした。
楸矢さんは半信半疑みたいだけど……。
小夜は椿矢の話を信じていた。
ムーシケーは、ムーサの森は、実在する。
だって、あの森で凍り付いている旋律、あれは本物だもの。
「沙陽ってさ、頭おかしいんじゃないの?」
楸矢は次のフライドポテトにフォークを突き刺した。
「仮にムーシケーだの、クレーイスだのの話が本当だとして、そのペンダントが必要だったら素直にそう頼めばこんなに大変なことにはならなかったのに」
そう言うとフライドポテトを口の中に放り込んだ。
「話しには来たな」
「そういえば、追い返しちゃったんだっけ」
楸矢はやべ、という表情を浮かべた。
「あのとき話を聞かなかったことがこんな大事になるとはな」
柊矢も失敗した、と言う表情でコーヒーを飲んだ。
「まぁ、今更後悔しても仕方ない」
「そうだね」
小夜はポケットの中でクレーイスをいじりながら俯いていた。
今からでも沙陽に協力することは出来ないだろうか。
そう二人に提案したかったが、どうしても口に出せなかった。
これは柊矢と楸矢の祖父の形見だ。
それがなくなるかもしれないことを考えると言うのを躊躇われた。言えば柊矢も楸矢も構わない、と言ってくれる気がした。
でも内心では祖父の形見を利用されるのは気分がいいものではないはずだ。
それに祖父を死なせた沙陽に協力したくないと思ってしまうのも事実だ。
「小夜ちゃん、食べないの?」
小夜の前に置かれたリゾットはまだ半分近く残っていた。
「あ、今食べます」
「急ぐことはないぞ」
「はい」