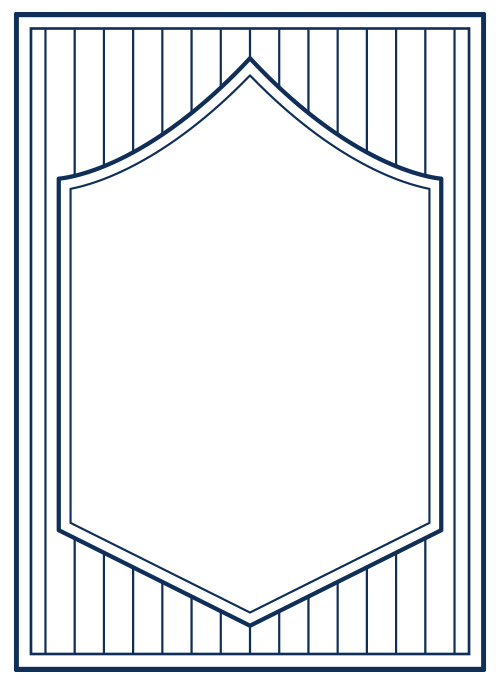第四章 古の調べ
一
学校が終わり柊矢の車を待っているとき、ふと見上げると森が出現していた。
柊矢の車が小夜の前に止まり柊矢が車を降りてきて助手席側に回ってきた。
「柊矢さん! 森が……!」
小夜は森を指さした。
「行ってみるか?」
「はい」
相変わらず森は静かで美しかった。風が吹いても葉の一枚すら動くことなく立っている樹々。
小夜は思わず見とれていた。
旋律が溶けて普通の森に戻ったらどんな景色になるのかな。
きっとすごく素敵だろうな。
沙陽さんの、この森に帰りたいって気持ちがよく分かる。
ふと見ると沙陽が屈んで何かしていた。
「あ」
小夜が思わず声を出すと沙陽が振り返った。
沙陽が立ち上がった。
小夜はポケットの中のペンダントを握りしめた。
柊矢さんのお祖父様の形見を無くすわけにはいかない。
沙陽がこちらに近付いてこようとしたとき、
「おい!」
柊矢が小夜の前に庇うように立った。
「柊矢さん」
小夜は柊矢を見上げた。
別に小夜を選んだわけではないだろうが、それでも守ろうとしてくれたのが嬉しくて顔に出てしまった。
沙陽が何とも言えない顔をして二人を見ていた。
「こんなところで何をしてる」
「ちょっとしたアルバイトよ。スポンサーがこれを欲しがってるから」
沙陽は手にした小さな花を見せた。
この森に生えていたものだから旋律で凍り付いている。
「どうしてそんなものを……」
「この花に触れれば旋律が聴こえるからよ。この花のね」
「何のために?」
「山崎敏夫って言えば分かる?」
確かアイドルの曲などを作っている作曲家だ。
沙陽は二人に背を向けて歩み去ろうとした。
「ちょっと待て」
沙陽が足を止めた。
「こいつの家の火事の晩、歌ってたのお前だな。あの火事はお前の仕業か」
小夜が息を飲んだ。
「その子の家の火事はポイ捨て煙草の火のせいでしょ」
煙草のせいだと知っている。
火事の原因はニュースや新聞には出ていなかった。
無関係なら知っているはずがない。
やはり、あのムーシカは沙陽だったのだ。
あのときは沙陽が森から戻ってたと知らなかったから彼女の声とは思わなかったが思い返してみればあれはこの女の歌声だ。
「タバコだけじゃなくて古新聞も置いたでしょ!」
柊矢は驚いて小夜を振り返った。
「なんのこと?」
沙陽がしらを切った。
「私が家を出たとき、古新聞の束なんかなかった!」
「あなたが外出した後に出したんじゃないの」
「古新聞は濡れたら引き取ってもらえなくなるから古紙回収の日の朝までは外に出さないもの。古紙回収の日はまだ先だったから外に出したりするわけない。燃えやすくなるように古新聞の束を置いたんでしょ!」
「私はタバコなんか吸わないし古新聞の束のことも知らないわ。私が歌ったら風が強くなった。そのせいで煙草の火が燃え上がったとしても、それは私のせいじゃない」
「そんな……」
柊矢は沙陽の方へ行こうとした小夜の肩を掴んで引き留めた。
「お祖父ちゃんがあなたに何をしたの! お祖父ちゃんを返して!」
「行ったでしょ。原因は煙草のポイ捨てだって。でも、出掛けてたなんて運が良かったわね」
「あなたがムーシカを歌わなければあんな大火事にはならなかった! なんで……、なんで……」
小夜が涙が小夜の頬を伝って落ちた。
沙陽はそっぽを向いていた。
柊矢は小夜を抱きしめた。
「悪かった。俺の配慮が足りなかった。お前のいないところで聞くべきだった」
小夜は泣きながら首を振った。
柊矢さんのせいじゃない。
どうして?
どうして、沙陽さんはお祖父ちゃんを殺したの?
「お祖父ちゃん……」
腕の中で泣いている小夜を見下ろしながら自分の迂闊さを悔いていた。
多分、狙われたのは小夜の祖父ではない。小夜だ。でも、それは小夜には言えない。
「消えろ、沙陽。二度と俺達の前に姿を見せるな。これ以上こいつを傷つけることは俺が許さない」
それだけ言うと小夜を落ち着かせようと抱きしめたまま背を撫でた。
沙陽は一瞬、柊矢と小夜を見た後すぐに視線を逸らしてその場から去って行った。
小夜が落ち着くと柊矢は彼女を連れて家に帰った。
「今夜はデリバリーにしよう。お前はしばらく部屋で休め」
柊矢の言葉に小夜は大人しく部屋に入っていった。
願わくば、沙陽を憎まないよう柊矢は祈った。
沙陽のためじゃない。
小夜に、憎しみという醜い感情を持って欲しくないからだ。
汚い感情に小夜のきれいな歌声が穢されて欲しくない。
だから沙陽を憎むな。
「え、それホントなの?」
楸矢が声を潜めて聞き返した。
今、小夜は風呂に入っているから普通に話しても聞こえないはずだが念のため彼女の耳に入らないよう小声で話していた。
「坂本さんに聞いたが、確かに古紙回収の日の大分前だったし、濡れたら引き取ってもらえないから当日の朝まで外に出さないっていうのも本当だった。そうじゃなくても、古新聞の類は火事の原因になるから、外に置かないように町内会で周知徹底しているそうだ」
「じゃあ、わざわざ古新聞の束を置いてから火の付いたタバコを捨てたの? 沙陽ってそこまでやるの!?」
「沙陽自身が置いたわけじゃないだろうがな。沙陽は喉を痛めるタバコの煙を嫌ってるから」
多分ペンダントを奪ったときと同じように誰かにやらせたのだろう。
「だが歌ってたのは沙陽で間違いない。お前も気を付けろ」
「柊兄もでしょ。それにしても当分小夜ちゃんの送り迎えはやめられないね」
あの火事は明らかに小夜を狙ったものだ。
多分、あの森やクレーイス・エコーに関する何かで小夜が邪魔だったのだろう。
だとしたら、またやるに違いない。
あいつらはどうして、そこまでしてあの森に拘るんだ?
小夜は風呂に浸かりながら何度も顔を洗っていた。
散々泣いたので目が腫れぼったいのだ。
沙陽さんは「私は運が良かった」と言った。
柊矢さんは何も言わないけど、あれはお祖父ちゃんじゃなくて私を狙ったって言うこと?
だとしたら、私のせいでお祖父ちゃんは死んだの?
私のせいで……。
また涙が溢れてきて慌てて顔を洗った。
お風呂から出たとき目が赤くなっていたら泣いていたことを気付かれてしまう。
もう泣かないって決めたのに……。
泣いてばかりいたら柊矢さんも楸矢さんも迷惑するだろう。
そうだ、少し歌わせてもらおう。
そうすればきっと元気が出る。
きっとまた明日からやっていける。
小夜は風呂から上がった。
「お先に失礼しました」
「あ、小夜ちゃん、上がったんだ。じゃ、俺もお風呂入ろっと」
楸矢はそう言って立ち上がった。
楸矢が風呂に入ったので小夜は音楽室に入った。
小夜が歌い始めると、追随するように斉唱や重唱、それに演奏が始まった。澄んだソプラノ、華やかなメゾソプラノ、重厚なアルト。
それぞれが織りなす合唱を、歌いながら聴いていると、いつしか悩みや悲しみは薄れていった。
もう大丈夫。
きっと明日はまた笑顔になれる。
柊矢さんの言うとおり、誰かを恨んだり憎んだりしてる暇があったら、もっと勉強や家事を頑張ろう。
歌えばムーシコスのみんなが応えてくれるんだから。
私には柊矢さんも楸矢さんも清美もムーシコスも付いてる。
だから大丈夫。
一
学校が終わり柊矢の車を待っているとき、ふと見上げると森が出現していた。
柊矢の車が小夜の前に止まり柊矢が車を降りてきて助手席側に回ってきた。
「柊矢さん! 森が……!」
小夜は森を指さした。
「行ってみるか?」
「はい」
相変わらず森は静かで美しかった。風が吹いても葉の一枚すら動くことなく立っている樹々。
小夜は思わず見とれていた。
旋律が溶けて普通の森に戻ったらどんな景色になるのかな。
きっとすごく素敵だろうな。
沙陽さんの、この森に帰りたいって気持ちがよく分かる。
ふと見ると沙陽が屈んで何かしていた。
「あ」
小夜が思わず声を出すと沙陽が振り返った。
沙陽が立ち上がった。
小夜はポケットの中のペンダントを握りしめた。
柊矢さんのお祖父様の形見を無くすわけにはいかない。
沙陽がこちらに近付いてこようとしたとき、
「おい!」
柊矢が小夜の前に庇うように立った。
「柊矢さん」
小夜は柊矢を見上げた。
別に小夜を選んだわけではないだろうが、それでも守ろうとしてくれたのが嬉しくて顔に出てしまった。
沙陽が何とも言えない顔をして二人を見ていた。
「こんなところで何をしてる」
「ちょっとしたアルバイトよ。スポンサーがこれを欲しがってるから」
沙陽は手にした小さな花を見せた。
この森に生えていたものだから旋律で凍り付いている。
「どうしてそんなものを……」
「この花に触れれば旋律が聴こえるからよ。この花のね」
「何のために?」
「山崎敏夫って言えば分かる?」
確かアイドルの曲などを作っている作曲家だ。
沙陽は二人に背を向けて歩み去ろうとした。
「ちょっと待て」
沙陽が足を止めた。
「こいつの家の火事の晩、歌ってたのお前だな。あの火事はお前の仕業か」
小夜が息を飲んだ。
「その子の家の火事はポイ捨て煙草の火のせいでしょ」
煙草のせいだと知っている。
火事の原因はニュースや新聞には出ていなかった。
無関係なら知っているはずがない。
やはり、あのムーシカは沙陽だったのだ。
あのときは沙陽が森から戻ってたと知らなかったから彼女の声とは思わなかったが思い返してみればあれはこの女の歌声だ。
「タバコだけじゃなくて古新聞も置いたでしょ!」
柊矢は驚いて小夜を振り返った。
「なんのこと?」
沙陽がしらを切った。
「私が家を出たとき、古新聞の束なんかなかった!」
「あなたが外出した後に出したんじゃないの」
「古新聞は濡れたら引き取ってもらえなくなるから古紙回収の日の朝までは外に出さないもの。古紙回収の日はまだ先だったから外に出したりするわけない。燃えやすくなるように古新聞の束を置いたんでしょ!」
「私はタバコなんか吸わないし古新聞の束のことも知らないわ。私が歌ったら風が強くなった。そのせいで煙草の火が燃え上がったとしても、それは私のせいじゃない」
「そんな……」
柊矢は沙陽の方へ行こうとした小夜の肩を掴んで引き留めた。
「お祖父ちゃんがあなたに何をしたの! お祖父ちゃんを返して!」
「行ったでしょ。原因は煙草のポイ捨てだって。でも、出掛けてたなんて運が良かったわね」
「あなたがムーシカを歌わなければあんな大火事にはならなかった! なんで……、なんで……」
小夜が涙が小夜の頬を伝って落ちた。
沙陽はそっぽを向いていた。
柊矢は小夜を抱きしめた。
「悪かった。俺の配慮が足りなかった。お前のいないところで聞くべきだった」
小夜は泣きながら首を振った。
柊矢さんのせいじゃない。
どうして?
どうして、沙陽さんはお祖父ちゃんを殺したの?
「お祖父ちゃん……」
腕の中で泣いている小夜を見下ろしながら自分の迂闊さを悔いていた。
多分、狙われたのは小夜の祖父ではない。小夜だ。でも、それは小夜には言えない。
「消えろ、沙陽。二度と俺達の前に姿を見せるな。これ以上こいつを傷つけることは俺が許さない」
それだけ言うと小夜を落ち着かせようと抱きしめたまま背を撫でた。
沙陽は一瞬、柊矢と小夜を見た後すぐに視線を逸らしてその場から去って行った。
小夜が落ち着くと柊矢は彼女を連れて家に帰った。
「今夜はデリバリーにしよう。お前はしばらく部屋で休め」
柊矢の言葉に小夜は大人しく部屋に入っていった。
願わくば、沙陽を憎まないよう柊矢は祈った。
沙陽のためじゃない。
小夜に、憎しみという醜い感情を持って欲しくないからだ。
汚い感情に小夜のきれいな歌声が穢されて欲しくない。
だから沙陽を憎むな。
「え、それホントなの?」
楸矢が声を潜めて聞き返した。
今、小夜は風呂に入っているから普通に話しても聞こえないはずだが念のため彼女の耳に入らないよう小声で話していた。
「坂本さんに聞いたが、確かに古紙回収の日の大分前だったし、濡れたら引き取ってもらえないから当日の朝まで外に出さないっていうのも本当だった。そうじゃなくても、古新聞の類は火事の原因になるから、外に置かないように町内会で周知徹底しているそうだ」
「じゃあ、わざわざ古新聞の束を置いてから火の付いたタバコを捨てたの? 沙陽ってそこまでやるの!?」
「沙陽自身が置いたわけじゃないだろうがな。沙陽は喉を痛めるタバコの煙を嫌ってるから」
多分ペンダントを奪ったときと同じように誰かにやらせたのだろう。
「だが歌ってたのは沙陽で間違いない。お前も気を付けろ」
「柊兄もでしょ。それにしても当分小夜ちゃんの送り迎えはやめられないね」
あの火事は明らかに小夜を狙ったものだ。
多分、あの森やクレーイス・エコーに関する何かで小夜が邪魔だったのだろう。
だとしたら、またやるに違いない。
あいつらはどうして、そこまでしてあの森に拘るんだ?
小夜は風呂に浸かりながら何度も顔を洗っていた。
散々泣いたので目が腫れぼったいのだ。
沙陽さんは「私は運が良かった」と言った。
柊矢さんは何も言わないけど、あれはお祖父ちゃんじゃなくて私を狙ったって言うこと?
だとしたら、私のせいでお祖父ちゃんは死んだの?
私のせいで……。
また涙が溢れてきて慌てて顔を洗った。
お風呂から出たとき目が赤くなっていたら泣いていたことを気付かれてしまう。
もう泣かないって決めたのに……。
泣いてばかりいたら柊矢さんも楸矢さんも迷惑するだろう。
そうだ、少し歌わせてもらおう。
そうすればきっと元気が出る。
きっとまた明日からやっていける。
小夜は風呂から上がった。
「お先に失礼しました」
「あ、小夜ちゃん、上がったんだ。じゃ、俺もお風呂入ろっと」
楸矢はそう言って立ち上がった。
楸矢が風呂に入ったので小夜は音楽室に入った。
小夜が歌い始めると、追随するように斉唱や重唱、それに演奏が始まった。澄んだソプラノ、華やかなメゾソプラノ、重厚なアルト。
それぞれが織りなす合唱を、歌いながら聴いていると、いつしか悩みや悲しみは薄れていった。
もう大丈夫。
きっと明日はまた笑顔になれる。
柊矢さんの言うとおり、誰かを恨んだり憎んだりしてる暇があったら、もっと勉強や家事を頑張ろう。
歌えばムーシコスのみんなが応えてくれるんだから。
私には柊矢さんも楸矢さんも清美もムーシコスも付いてる。
だから大丈夫。