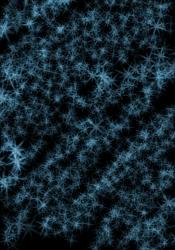授業が終わり、教室を出て本館へと続く渡り廊下を歩く。
「お昼、四人で食べようよ」
青山の話に、樹も小絵も私も喜んで頷いた。
青山は教室に着くなり、鞄から財布を取って
「食堂の場所先にとっとくな」
とすぐに行ってしまった。私は自分の席に行き、鞄からランチバックを取り出した。小絵も財布を取り出す。樹も財布を持って、こっちにやってきた。
「行くか」
小絵が言ったところで、教室に林原先生が入ってきた。
「あれ先生、どうしたの?」
小絵がそう言い、林原先生はこっちに近づいてきた。
「いや、ちょっとさ」
「二村に用事?」
小絵がきょとんとした顔でそう聞き、樹も林原先生を見る。
「二村じゃなくて……澤田、ちょっと職員室来てほしいんだ」
林原先生の表情が少し深刻な様子なので、眉を寄せながらも
「はい」
と返事をした。すると小絵が、私のランチバックを持ち
「じゃあ私、二村と先いってるね。食堂の席の場所教えるから終わったら電話して」
と言うので、私は鞄にいれっぱなしのままだった携帯を手に持ち、頷いた。樹は私を何故か深刻そうに見ている。
「終わったらすぐに行くね」
と伝えたが、樹は目線をそっとそむけて返事をしなかった。
「二村行くよ」
小絵に呼ばれて
「うん……」
と樹は生半可に返事をする。二人は教室を出ていく。その途中樹は心配そうな顔をして一度だけ振り向いて私を見た。
「行こうか」
と林原先生が言うので、私は頷いた。
無言のまま職員室に到着して、林原先生に促され、職員室内にある応接室の中に入りソファーに向かい合わせで座る。
「何でしょうか?」
私が話しかけると、林原先生は、私から少し目線をそらした後、まっすぐと私を見た。
「澤田。聞きたいことがあって」
「聞きたいこと?」
「……お前誰かいじめてる?」
「え!?」
険しい表情を浮かべ話す林原先生を見て、私はパニックになりながらも落ち着かなければと思い、一度口をきゅっと閉じた後で
「私が、いじめてるんですか?」
「……うん」
「だ、誰を?」
静かに聞くと
「それは言えないんだけど……」
と林原先生が口ごもった。
「私、そんなことしません」
林原先生をまっすぐと見て伝える。伝えてからも頭の中は混乱したままだ。けど、林原先生は険しい表情は崩し、ほっとため息をついた。
「だよな、澤田に限ってそんな……」
「先生、何言い出すかと思えば……」
「一応、そういう話を持ちかけられたら聞かなきゃならなくてな、教師は」
「信用が落ちますよ、先生」
「ごめんな、澤田」
気まずそうにする林原先生に、私は息をはいて、首を横に振った。
「でも良かった。これで嘘つけとか言われたら、私はどうしようもできないから」
「澤田」
困った表情を浮かべる林原先生を見て、私ははっとする。
「あ、その子の名前、無理矢理聞き出したりしないよ」
「うん」
「私戻っていいですか? 食堂でみんな待ってるから」
「ああ。本当ごめんな、澤田」
私は首を振る。
「いえ。教師が本当大変なの分かってるから。頑張れ林原先生」
「……澤田はいい子だな」
「何かあったらまた言ってください」
職員室を出て扉を閉めた時、私は一息ついた。
とんだ濡れ衣だった。
林原先生の前では強がったがやはり傷つく。
改めて考えてみると思いの丈をぶつければよかったかもしれない。
でも食堂に早く行こうと、手に持ったままの携帯を強く握りしめた。
歩き出したとしたところで
「何だ、もう出てきたの?」
と後ろから声がして振り返る。そこには、前に私のことを睨み付けていたクラスメートの四人が不気味な笑顔を浮かべて立っていた。
「林原先生、もっと言ってくれるのかと思ったのに」
一人が話したところで私は瞬時に考え、なるほどと思い、彼女たちに向きを変えて立ち止まる。
私は四人を静かに睨み付けた。
「何なの? その目」
その時、四人のうちの一人が私の腕を強く掴んだ。
「澤田さん、ちょっと来てくれる?」
「な、嫌!」
腕を振り払おうとしたが、相手はがっちりと掴み離そうとしない。あっという間に他の三人に囲まれて、
「来て」
と言い彼女たちが進むままに、腕を引っ張られながら、意思に反して私は歩いていくしかなかった。
ーー
連れてこられたのは本館と別館をつなぐ渡り廊下だった。お昼だからか、他に誰もいなかった。壁のないその廊下からはみ出し、建物の壁に追いやられて、掴んでいた私の腕を乱雑に離し、逃げられないようになのか、また囲まれた。
「調子に乗らないでくれる?」
「……何のこと?」
強かに四人を見ると、そのうちの一人に胸ぐらを捕まれた。
「何なの、その態度」
私は言い返すのを堪えて、黙ったままじっとその子を睨み付けた。
「ねえ、最近樹くんに近寄りすぎじゃない?」
「……樹?」
私はさらに眉を寄せる。
「アンタみたいな子が、近寄っていい存在じゃないの」
「どういう……?」
「樹くんに一方的に言い寄るのやめてくれる?」
胸ぐらをつかんでいる手の力が強くなった。
「樹くんにあなたのようなバイ菌がついたら大変だからさっさと消えてくれないかな? あなたの自転車に忠告しておいたことまだ分からない? それかもう少し痛い目見て、分かりやすく教えてほしい?」
そう言われて、緊迫した中でも私は少し考える。そして内心で納得して、捕まれている手を上から掴みにかかる。
手を離してはくれないけど、そこで私は静かに口を開いた。
「嫉妬、してるわけ?」
「何だって?」
「よく見てるんだね、私のこと。それであなただったのね、私の自転車のタイヤに穴開けてパンクさせたの」
「誰に対してどういう口の聞き方してるか、考えた方がいいんじゃない?」
「なるほどね。樹と話したいけど上手く話すタイミングが分からなくて、いつも樹と一緒にいる私に八つ当たりしてるって訳ね?」
「な……」
「あなたからちゃんと話しかければいいじゃない。樹は普通に話してくれると思うけど? あなたが樹に話せない理由は私じゃない」
「……生意気ね」
掴んでいた手を押すような形で強く離されて、私は壁に後頭部を打ち付けて、座り込んだ。思わず目を閉じたとき、バシャっと何かが勢いよくかかって、目を開けると、バケツの水をかけられたことが分かった。その子が、空になったバケツを軽く投げ捨て
「今日はこれぐらいにしてあげる。行こう」
と言うと、四人は何事もなかったかのように本館の方に歩いていった。
少し放心し、何が起きたのか理解するまでに時間がかかった。
下唇をかんで立ち上がると、大量の水滴がぽたぽたと早い速度で落ちる。
髪を片手で掴み、水滴を落とす。
どうしようと思った。
私は携帯を見つめる。
電話をかけて状況を話せば、みんなが来てくれるかもしれない。
でもその後が心配だ。
樹のことが頭を過る。
樹は私を見て、彼女たちを責め立てに行くだろう。そこで揉めたりなんかして、逆に樹の評価が落ちたらどうしよう。
樹は来週大事なオーディションを控えている。それに響いたらどうしよう。
考えすぎだろうか? でも考えてしまう。
樹は優しいから。
幼い頃から、樹はいつも私のことを優先してきた。
大事にしてる夢でさえ、私と天秤にかければ、樹は少しも迷わず私を選ぶだろう。
だから怖い。
今やっと掴めそうな樹の夢が、私のせいでなくなっては困る。
病気であることをずっと隠してきたのに、今その夢が崩れていきそうでならない。
何とかしなくてはと思ったが、このままでお昼を食べに来ない私を不審がるに違いない。
この携帯には、時期に連絡がやって来る。
「どうしよう……」
考え込んでいると、本館から姿は見えないが、誰かがこっちに向かってきている。
このまま別館に逃げ込んでもいいが、ばったり誰かと会ったら明らかに気まずい。
私は別館の入り口には入らずにその建物のわき道に急いで逃げ込んだ。
「あれ、誰かいなかった?」
「え、そう?」
二人の女の子の声がしてぎくりとする。
のぞきこみもせずに、私は壁に背中をつけて声を聞いていた。
「あー、掃除用にくんでたバケツの水がない!」
「え、何で!?」
「ひっくり返したの誰? てかやっぱ今人いたよね? あっちに逃げたんじゃない?」
足音がゆっくりこちらへやってくる。
まずいと、人一人がやっと通れる細い道を足音に気を付けて私は奥へ進む。しかし多少奥には行けてもすぐに行き止まりである。どうしようと横に目をやると、開いている窓を見つけた。高さは、よじ登れるかどうかきわどいところだったが、迷っている時間はなく、私はすぐに手を伸ばした。
「……あれ? いないや」
間一髪、窓から音に注意して部屋に飛び込んだところでそう声が聞こえた。
「勘違い?」
「そうだったみたい」
「もー早く別館の廊下掃除しようよ。まずは三階から」
「めんどくさい。何でお昼に掃除……」
「決まりなの、行くよ!」
声はだんだんと遠ざかっていって、私はほっとした。
床に転がった先で、目に入る。
長方体で全体が木製で作られた教壇があった。
「何で教壇が窓の近くに?」
疑問に思いながらも上半身を起こして、辺りを見回す。誰もいなかったので安心した。
ここは、どこなのだろう。
部屋の両側に設置している棚には、画用紙や木材など色々なものが整頓されている。
私は教壇から少し顔を出す。
この教壇に隠れていれば、万が一扉から誰かが入ってきても見つからず、しのげそうである。
「ふう……」
教壇に隠れて私は体育座りをして、ふと窓から空を眺めた。
「太陽の光じゃすぐに乾かないよね」
なんて呟く。
太陽の光が温かくても、濡れているせいか寒い。
せめて拭くものがあればいいけど、それもない。
私はため息をつく。そしてこう思った。
「私、よく泣かないでいられるよね……」
すると、いきなり扉が勢いよく開いた。
声が出そうなくらい驚いて教壇からそっと覗くと、そこに樹の姿が見えた。
私はすぐに隠れようと顔を引っ込めた。樹はこっちを見ていなかった。だから私には気づいていないはずだ。
何でここにいるのとドキドキした。
「樹、あったー?」
青山の声も聞こえる。私は体育座りのまま丸まり、息をひそめる。
「あった。やっぱりここに忘れてた、携帯」
「忘れた場所が教材室で良かったな。他のとこだと誰かに見られてたかもしれないし」
「だな」
その会話を聞き、私は分からなかったこの場所を理解した。
ここは、教材室だと。
「小絵ちゃんが一人ぼっちになってるから、早く帰ろ」
「何でお前はついてきたんだよ。青山はちゃんとその胸ポケットに携帯あるだろ?」
「まあ、いいじゃん」
と、二人の会話が聞こえる。出ていくべきかどうかと迷っていると
「菜穂ちゃん、話し終わったかな?」
と青山が言って、私はぎくりとする。
「どうかな。……電話かけてみよう」
「心配性だな、樹は」
その話を聞き慌てたが、四時間目授業終わりの私の携帯は現在サイレントモードになっていることを思い出す。
「菜穂出ないな……」
「話が長引いてるのかな?」
「本当、何の話なんだろう?」
「さぁ? 携帯に気づかないだけで、小絵ちゃんと合流してるかもよ? 戻ろう?」
「うん」
樹がそう言ってから、私はまた教壇から少し顔を出して様子を伺う。
青山は先に廊下に出て、それに続き扉から樹が出ていくのが見えた。
とりあえず、バレなかったと私はほっとした。
でも、分かっている。
これは一時的にどうにかなっただけだ……なんて考えた時、そこで意識が急にぷつっと途切れて、私は床に倒れこんだ。
すぐに意識は取り戻すことができて目を開けたが、その瞬間に胸に激しい痛みが襲ってきた。
「……っ」
私は胸を押さえたまま、体を丸める。
息も若干しずらい。
激しい痛みだが、声は極力押さえた。
嘘でしょ、何で今なのと思った。
樹は扉を出ていったけど、まだ近くにいる。
見つかったら、まずい。
意識をまた失ってしまいそうな中で、大丈夫、いつもみたいにまた元に戻ると、心の中で自分を励ました。
「う……あぁっ」
ただ、我慢していた声が、もう押さえられないほどに痛くて、思わず目をつぶる。
一体どうしたら……どうしたらいいだろう? 携帯にも手を伸ばせそうにない。
……本当に今日はついてないなと思った。
朝から調子が悪いし、濡れ衣はきせられるし。水はかけられるし。
でもそんなことを考えるよりも今の状況を何とかしなければならない。
襲いかかる痛みにどうにか耐えながら、ふと目を開けると、いつの間にか樹は私のすぐ横に立っていた。
怯えきったような、樹のその表情を見た時に、何とか、何とかごまかさなくちゃと思った。でも、痛くて苦しくて、動けなくて、私にはどうしようもできない。
「いつ……き」
嫌だ。見ないでほしい。
見ないでほしい、けど……。
樹はしゃがみこんで、黙ったまま両腕を伸ばして私を引き寄せ横抱きに抱きかかえた。
樹の温もりが温かい。けど、激しい痛みがすぐにそれをかき消した。
「樹……っ……ごめ……」
私はぎゅっと樹にしがみつく。
そこに、青山が戻ってきた。
「樹、何教材室に戻ってるの? 早く行くぞー」
樹は私を抱えたまま振り向いた。その時、樹に近づいた青山も異変に気づく。
「え……菜穂ちゃんどうした!? どうしてここに……それに何でそんな濡れてるんだ?」
樹は静かに言った。
「青山、救急車……」
「え……?」
「救急車呼んで」
「……でも樹。まず、先生に……」
「早く!」
樹がそう悲痛に叫んだとき、青山は強く頷いた。胸ポケットから慌てて携帯を取り出す。
樹は私を横に抱えて、立ち上がった。ぼやけた視界と激しい痛みの中で、必死にしがみつきながら樹を見ていたその時、ぷつっと私の意識は完全に途切れてしまった。