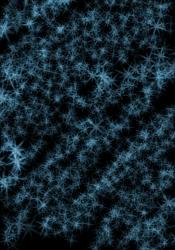慌てて振りかえると、樹は頬を私の背中にくっつけていた。
私を包み込んで座り、足を伸ばしている。
私はすぐに目をそらした。いつの間にか頭の中は真っ白になっていた。
樹が抱きしめてきたのは初めてだった。
何とかフル回転させて
「は、離れてください……」
と呟いた。
「嫌です」
樹はそのままの姿勢で、すぐにはっきりと答えを返した。
「ゲ、ゲームやるん……だよね?」
出なくなりそうな声を必死に出す。
「菜穂は馬鹿だな。高校生になったんだから少しは警戒しないと」
「警戒?」
「いくら俺が実家暮らしでもゲームやるよとか言っても、男の家に誘われたら何かされるかもしれないなぁ、って」
何それ!? と叫び逃げ出そうと樹の腕に力が入り、私の体がまた元に戻った。頭の中がさらに真っ白になり、
意を決して私はゆっくりと少しだけ振り返った。
「な……何かするの? 樹が? いつも何もしないのに?」
「分かんないよ? 俺も男だし」
樹がそんなことを言うのが信じられなかった。抱きしめられている時点で、これはもう何かをしているんじゃないか……? と思い、もう一度そっと逃げようとした。けれど樹の腕に力が入り
「菜穂の力で俺には勝てないよ」
と諭すように答えた。それもそうだとそこだけは冷静に考え、抵抗するのをやめた。真っ白な頭で何を話したらいいかも分からず、無言のままで必死に考える。けれど考えれば考えるほど、無情にもこの背中が温かく感じる。その温かさにやられ、気を抜くと安心しきってしまいそうだった。
「樹……」
すると突然ぱっと樹の手が私から離れた。
「なんてね。さ、ゲームやろう?」
ベッドの上から降りて、樹はテレビのリモコンを手に取り電源を入れた。
「菜穂は、どのキャラクターにする?」
話しかける樹はいつも通りで、ベッドには座らず、立ったままの姿勢で私を見ている。私も視線を合わせると、樹は驚いて固まった。
「菜穂」
「何?」
「……顔、赤い」
私は樹からすぐさま目をそらし、慌てて立ち上がった。
「わ、たし今日用事あった、またね樹!」
樹の返答を待つこともなく、急いで樹の家を出た。
自分の家の扉を開けて、階段をかけ上がる。
自分の部屋に入ると力が抜けてその場に座り込む。片方の手の甲で顔を隠した。
「どうしよう……鳴りやめ……」
思い返そうとしているわけではないのに何度も思い返してしまい、鼓動の速度が増していく。あれは樹のいたずらだったのか?
「……樹のバカ」
取り乱さない心がほしいと強く思った。