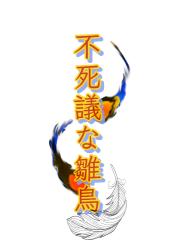* * *
7月、初夏の昼下がり、4限目終わり。教室の窓際の席からふと外を見ると、入道雲がもくもくと空に伸びていた。青いキャンバスに落とした絵の具のように広がるそれは、梅雨の空気をどこかへ押しやってしまったようだ。正しく夏晴れ、きっとここは空気が綺麗だからなんだろうな。
昨年の秋からこの地にいる、初めて経験する17の夏。今年は何かありそうな気がする、そんな風に思った。
「希美ー」
窓の外をぼんやり眺めていると、私の名を呼ぶ声が聞こえる。目線を向けると2人の男女が私の元へ歩いてきた。
「望月、飯食おうぜ」
「あ、うん。食べよっか」
男の子の手には惣菜パンが3つ、女の子の手にはお弁当の手提げ、それらを揺らして私の席へ。周りの机をくっつけて簡単な班にする。かれこれ9ヶ月になるだろうか。彼らとお昼ご飯を食べる、いつものルーティーンだ。
「なになに?外なんか見ちゃって。アンニュイ?」
私を希美と呼んだ女の子、星那はお弁当箱を広げながら私にそう尋ねてきた。
「いやいや、違うよ」
「望月が考えごとなんて珍しいな」
「ちょっと春斗、それどういう意味?」
「…言葉通りの意味だけど」
「春斗めっちゃ失礼でウケる」
私の軽口に戯ける春斗とそれを茶化してアハハと笑う星那。いつも通り、変わらないお昼休み。
私は高校1年の秋に都会から少し離れたこの土地に越してきた。そこまで都会から離れていない空気の良い片田舎。バスもそこそこの本数があり、駅前は栄えているものの、夜は明かりが少なく星空も楽しめる。学校からは見える小さな山々は秋になると紅葉が魅力的だった。
2人は、そんな少し時期外れの転入で不安だったところにできた友達だった。
夕凪 星那はいわゆる流行りものが好きな今どきな子で、都会から来てくれた私にも気さくに話しかけてくれた。彼女とはメイクやファッションについて意気投合することも多々あり、仲良くなるのに時間はかからなかった。今では休みの日なんかに2人で片道2時間くらいかけて都内に遊びに行くほどである。
北浦 春斗はそんな星那と幼馴染の男の子で、誰とでも仲良くなれるような温和な雰囲気を持つ子だった。転校したての自分に対しても垣根なく接してくれて、一緒にいると安心する子だった。2人きりでどこかに行くなどはないが、彼になら何でも話せてしまう。大人になったらきっといい父親になるんだろうなと、彼の温厚さや優しさは純粋に尊敬している。
まだ少しだけなれない片田舎での生活で、欠かせなくなった大切な友達2人だ。
「それで希美、なにを考えてたの?」
星那が唐揚げを頬張りながら尋ねてくる。逃がしてはくれないようだった。
「いやぁ特にこれと言ってはないけど…」
「黄昏てた的な?ちょっと意外」
「ますます珍しい」
私はいったいなんだと思われているのだろう。
「それ普段からやかましいってこと?」
「否定はしない。望月は思慮深い方ではないと思うしな。映え写真がどうのとか、メイクノリがどうだとか、そんな感じのことしか考えてないかと思ってた」
「わかる。それは同感」
「ちょっと」
隣に座っていた春斗を軽く小突く。ニヤニヤしながらもどこか嬉しそうだった。星那はそんな様子を微笑ましそうに眺めるばかりだった。
「まったく…でも本当に大したこと考えてなかったよ。なんとなく、ここに来て初めての夏だなぁって」
「あー。越してきてまだ1年経ってないもんな。8月の中頃くらいに花火が打ち上がる大きなお祭りが近くであるよ。ちょうどあの山を背にしてみる感じ。華星祭っていうんだ」
春斗が窓の外の山を指さしてそう言う。
「そうそう!結構有名で県外からも人がたくさん集まるんだ」
「へぇ…2人は毎年行ってるの?」
「んー、すごく混むからなぁ。小さい頃は行ってたけど家からも花火は見えるし、行ったり行かなかったりって感じ」
「私もたまーに行くくらいかな」
2人の反応はどこか同じで、一大イベントも地元の人からすれば見慣れたものなのかもしれない。
「あと妙なジンクスもあるしね」
「ジンクス?」
「この辺って空気が綺麗だろ?流星群もよく見えるんだが、『流れ星と花火が重なったときに願いを込めるとなんでも叶う』っていうジンクスがあるんだ。実際は花火が明るすぎて流れ星なんて見えないし、重なったっていう表現も曖昧だしな」
「そんなジンクスに便乗して告白するーみたいな人たちも多いからねぇ。カップル専用のお祭りみたいなもんよ」
「いいじゃん、ロマンチックで」
私の引っ越す前の地元にはそういうのはなかったから、純粋な気持ちでそういった。
「そうなんだけどねぇ。半分もうオカルトよ」
「夢がないなぁ…。でもせっかくならそのお祭り行ってみたい」
「春斗、一緒に行ってあげたら?」
「えっ?」
星那から話を振られた春斗がチラッとこちらを見る。
「あー…どうすっか?」
肯定とも否定とも取れるように考える素振りを見せる春斗だが、その考えには集中できていないような目線の動きだった。
しかし当の私は、どちらかと言うと星那の発言の方が気になった。
「なんで?どうせなら星那も一緒に行こうよ」
「…んー」
「え、ちょっと嫌なの?」
「いや、嫌なわけじゃないけど…」
星那がちらりと春斗に目線を向ける。
「…人混みあんま得意じゃないし」
「大きい休みの日は一緒に渋谷とか行くじゃない」
「あと…暑いし」
「……」
「夏なんだから当たり前じゃない?てかそれなら今年の夏は都内に出るのやめとく?」
「いやそれは…なんていうか……んー」
「……」
妙に歯切れが悪い。いつもスパスパものをいう性格の星那にしては珍しかった。春斗も微妙な顔で黙っている。
「カップル専用みたいな祭りだし行きにくいのよ」
「えー、そうなの?でもどうせならみんなで楽しみたいじゃん」
「…そうだよ、星那も行こうぜ」
「え?……まぁでも、うん。今年は考えとくよ。近くになったら予定合わせよ」
「やったー」
春斗が誘うと星那は頷いてくれた。8月の頭に予定が出来て、私のテンションがちょっと上がる。
そっか、有名な花火かぁ…楽しみだ。
「まぁまぁ!そんなことより希美!またフォロワー増えてたよ?」
「え?まじ?」
閑話休題、と言った感じで星那がスマホを弄り始める。タッタッと軽快にスマホを操作し、『ピクスタ』の私のプロフィールを見せてきた。
「ほら」
「うわ!ほんとだ!5000人超えてる!」
ピクスタの私のフォロワー数を見ると5012という数字が並んでいた。
「へー、そんなにいるのか」
この手の話題にあまり興味がなさそうにしている春斗も同じ画面を覗き込み、感嘆の声を上げた。
「やっぱりこの前出た雑誌の影響だって!」
「この前?」
「あー、ゴールデンウィークくらいに2人で原宿行った時にモデルのスカウトされちゃって…」
「え、初耳なんだが」
「いや、だって春斗そういう話題興味ないじゃん」
「まぁ…」
ピクスタは一般人からあらゆるインフルエンサーが集う、いわゆる写真投稿SNSの呼称。日々の生活や映えを意識した写真を投稿しているもので、私たちのような中高生にはなくてはならないものと化している。ここ最近それが大きくバズっていた。
「スカウトって…ついて行ったのかよ。怪しさ満点なんだが…」
「私も最初は怪しいと思ったけど…星那が乗り気になっちゃって」
「だってそんな機会滅多にないじゃん!」
「星那もスカウト受けたのか?」
「……いや、私は受けてないんだけどね」
「じゃあなんでお前が乗り気になったんだよ」
「だってだって!」
嬉々として言い訳をする星那に、春斗が的確にツッコミを入れていく。見慣れた光景に頬が緩んだ。
「というか、普通に危ないだろ。連れてかれていたらどうするつもりだったんだ」
「最悪私の健脚で逃げるつもりだった!」
「望月が置いていかれるだろ」
「もち、担いで」
「無茶なこと言うなよ、お前」
「まぁまぁ…最悪私もお母さんの名前出せば下手なことされないだろうなと思ったし」
「あー…それもそうか。…いや、そうか?」
「そうなの!てか聞いて、そのスカウトの人なんて──」
思い出し笑いをしながら、ずいっと言う効果音が聞こえるほど向かいあった席から星那が身を乗り出す。
「希美からお母さんのこと聞かされた時に『あの国民的女優、望月 朔良の娘!?』なーんて声裏返っちゃってさ!」
スカウトの人の似ても似つかない声までしながら、私の母の名を言う星那はどこか誇らしげだった。
私の母、望月 朔良は女優だ。私を産んだ後もモデル業などをしていて、今でもドラマやバラエティ番組に出ている。芸能界という栄華の短い職業の中、息はかなり長い方で、こんな風に驚かれることもしばしばあった。転校したての頃はそれが話題でクラスの子たちとも打ち解けられたところもある。そんな母は私のなによりの誇りだ。
テレビの中で見る母への憧れは日に日に大きくなり、いつしか自分もこうなりたいと思うようになるのも必然といったところ。演技はからっきしだが、なにか彼女と近しい職業に就きたいとは思っている。追いつけるように日々ファッションやメイクなど勉強中だ。
とはいえ最近は、映え写真ばかりを投稿しているが。
7月、初夏の昼下がり、4限目終わり。教室の窓際の席からふと外を見ると、入道雲がもくもくと空に伸びていた。青いキャンバスに落とした絵の具のように広がるそれは、梅雨の空気をどこかへ押しやってしまったようだ。正しく夏晴れ、きっとここは空気が綺麗だからなんだろうな。
昨年の秋からこの地にいる、初めて経験する17の夏。今年は何かありそうな気がする、そんな風に思った。
「希美ー」
窓の外をぼんやり眺めていると、私の名を呼ぶ声が聞こえる。目線を向けると2人の男女が私の元へ歩いてきた。
「望月、飯食おうぜ」
「あ、うん。食べよっか」
男の子の手には惣菜パンが3つ、女の子の手にはお弁当の手提げ、それらを揺らして私の席へ。周りの机をくっつけて簡単な班にする。かれこれ9ヶ月になるだろうか。彼らとお昼ご飯を食べる、いつものルーティーンだ。
「なになに?外なんか見ちゃって。アンニュイ?」
私を希美と呼んだ女の子、星那はお弁当箱を広げながら私にそう尋ねてきた。
「いやいや、違うよ」
「望月が考えごとなんて珍しいな」
「ちょっと春斗、それどういう意味?」
「…言葉通りの意味だけど」
「春斗めっちゃ失礼でウケる」
私の軽口に戯ける春斗とそれを茶化してアハハと笑う星那。いつも通り、変わらないお昼休み。
私は高校1年の秋に都会から少し離れたこの土地に越してきた。そこまで都会から離れていない空気の良い片田舎。バスもそこそこの本数があり、駅前は栄えているものの、夜は明かりが少なく星空も楽しめる。学校からは見える小さな山々は秋になると紅葉が魅力的だった。
2人は、そんな少し時期外れの転入で不安だったところにできた友達だった。
夕凪 星那はいわゆる流行りものが好きな今どきな子で、都会から来てくれた私にも気さくに話しかけてくれた。彼女とはメイクやファッションについて意気投合することも多々あり、仲良くなるのに時間はかからなかった。今では休みの日なんかに2人で片道2時間くらいかけて都内に遊びに行くほどである。
北浦 春斗はそんな星那と幼馴染の男の子で、誰とでも仲良くなれるような温和な雰囲気を持つ子だった。転校したての自分に対しても垣根なく接してくれて、一緒にいると安心する子だった。2人きりでどこかに行くなどはないが、彼になら何でも話せてしまう。大人になったらきっといい父親になるんだろうなと、彼の温厚さや優しさは純粋に尊敬している。
まだ少しだけなれない片田舎での生活で、欠かせなくなった大切な友達2人だ。
「それで希美、なにを考えてたの?」
星那が唐揚げを頬張りながら尋ねてくる。逃がしてはくれないようだった。
「いやぁ特にこれと言ってはないけど…」
「黄昏てた的な?ちょっと意外」
「ますます珍しい」
私はいったいなんだと思われているのだろう。
「それ普段からやかましいってこと?」
「否定はしない。望月は思慮深い方ではないと思うしな。映え写真がどうのとか、メイクノリがどうだとか、そんな感じのことしか考えてないかと思ってた」
「わかる。それは同感」
「ちょっと」
隣に座っていた春斗を軽く小突く。ニヤニヤしながらもどこか嬉しそうだった。星那はそんな様子を微笑ましそうに眺めるばかりだった。
「まったく…でも本当に大したこと考えてなかったよ。なんとなく、ここに来て初めての夏だなぁって」
「あー。越してきてまだ1年経ってないもんな。8月の中頃くらいに花火が打ち上がる大きなお祭りが近くであるよ。ちょうどあの山を背にしてみる感じ。華星祭っていうんだ」
春斗が窓の外の山を指さしてそう言う。
「そうそう!結構有名で県外からも人がたくさん集まるんだ」
「へぇ…2人は毎年行ってるの?」
「んー、すごく混むからなぁ。小さい頃は行ってたけど家からも花火は見えるし、行ったり行かなかったりって感じ」
「私もたまーに行くくらいかな」
2人の反応はどこか同じで、一大イベントも地元の人からすれば見慣れたものなのかもしれない。
「あと妙なジンクスもあるしね」
「ジンクス?」
「この辺って空気が綺麗だろ?流星群もよく見えるんだが、『流れ星と花火が重なったときに願いを込めるとなんでも叶う』っていうジンクスがあるんだ。実際は花火が明るすぎて流れ星なんて見えないし、重なったっていう表現も曖昧だしな」
「そんなジンクスに便乗して告白するーみたいな人たちも多いからねぇ。カップル専用のお祭りみたいなもんよ」
「いいじゃん、ロマンチックで」
私の引っ越す前の地元にはそういうのはなかったから、純粋な気持ちでそういった。
「そうなんだけどねぇ。半分もうオカルトよ」
「夢がないなぁ…。でもせっかくならそのお祭り行ってみたい」
「春斗、一緒に行ってあげたら?」
「えっ?」
星那から話を振られた春斗がチラッとこちらを見る。
「あー…どうすっか?」
肯定とも否定とも取れるように考える素振りを見せる春斗だが、その考えには集中できていないような目線の動きだった。
しかし当の私は、どちらかと言うと星那の発言の方が気になった。
「なんで?どうせなら星那も一緒に行こうよ」
「…んー」
「え、ちょっと嫌なの?」
「いや、嫌なわけじゃないけど…」
星那がちらりと春斗に目線を向ける。
「…人混みあんま得意じゃないし」
「大きい休みの日は一緒に渋谷とか行くじゃない」
「あと…暑いし」
「……」
「夏なんだから当たり前じゃない?てかそれなら今年の夏は都内に出るのやめとく?」
「いやそれは…なんていうか……んー」
「……」
妙に歯切れが悪い。いつもスパスパものをいう性格の星那にしては珍しかった。春斗も微妙な顔で黙っている。
「カップル専用みたいな祭りだし行きにくいのよ」
「えー、そうなの?でもどうせならみんなで楽しみたいじゃん」
「…そうだよ、星那も行こうぜ」
「え?……まぁでも、うん。今年は考えとくよ。近くになったら予定合わせよ」
「やったー」
春斗が誘うと星那は頷いてくれた。8月の頭に予定が出来て、私のテンションがちょっと上がる。
そっか、有名な花火かぁ…楽しみだ。
「まぁまぁ!そんなことより希美!またフォロワー増えてたよ?」
「え?まじ?」
閑話休題、と言った感じで星那がスマホを弄り始める。タッタッと軽快にスマホを操作し、『ピクスタ』の私のプロフィールを見せてきた。
「ほら」
「うわ!ほんとだ!5000人超えてる!」
ピクスタの私のフォロワー数を見ると5012という数字が並んでいた。
「へー、そんなにいるのか」
この手の話題にあまり興味がなさそうにしている春斗も同じ画面を覗き込み、感嘆の声を上げた。
「やっぱりこの前出た雑誌の影響だって!」
「この前?」
「あー、ゴールデンウィークくらいに2人で原宿行った時にモデルのスカウトされちゃって…」
「え、初耳なんだが」
「いや、だって春斗そういう話題興味ないじゃん」
「まぁ…」
ピクスタは一般人からあらゆるインフルエンサーが集う、いわゆる写真投稿SNSの呼称。日々の生活や映えを意識した写真を投稿しているもので、私たちのような中高生にはなくてはならないものと化している。ここ最近それが大きくバズっていた。
「スカウトって…ついて行ったのかよ。怪しさ満点なんだが…」
「私も最初は怪しいと思ったけど…星那が乗り気になっちゃって」
「だってそんな機会滅多にないじゃん!」
「星那もスカウト受けたのか?」
「……いや、私は受けてないんだけどね」
「じゃあなんでお前が乗り気になったんだよ」
「だってだって!」
嬉々として言い訳をする星那に、春斗が的確にツッコミを入れていく。見慣れた光景に頬が緩んだ。
「というか、普通に危ないだろ。連れてかれていたらどうするつもりだったんだ」
「最悪私の健脚で逃げるつもりだった!」
「望月が置いていかれるだろ」
「もち、担いで」
「無茶なこと言うなよ、お前」
「まぁまぁ…最悪私もお母さんの名前出せば下手なことされないだろうなと思ったし」
「あー…それもそうか。…いや、そうか?」
「そうなの!てか聞いて、そのスカウトの人なんて──」
思い出し笑いをしながら、ずいっと言う効果音が聞こえるほど向かいあった席から星那が身を乗り出す。
「希美からお母さんのこと聞かされた時に『あの国民的女優、望月 朔良の娘!?』なーんて声裏返っちゃってさ!」
スカウトの人の似ても似つかない声までしながら、私の母の名を言う星那はどこか誇らしげだった。
私の母、望月 朔良は女優だ。私を産んだ後もモデル業などをしていて、今でもドラマやバラエティ番組に出ている。芸能界という栄華の短い職業の中、息はかなり長い方で、こんな風に驚かれることもしばしばあった。転校したての頃はそれが話題でクラスの子たちとも打ち解けられたところもある。そんな母は私のなによりの誇りだ。
テレビの中で見る母への憧れは日に日に大きくなり、いつしか自分もこうなりたいと思うようになるのも必然といったところ。演技はからっきしだが、なにか彼女と近しい職業に就きたいとは思っている。追いつけるように日々ファッションやメイクなど勉強中だ。
とはいえ最近は、映え写真ばかりを投稿しているが。