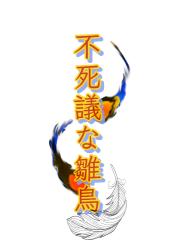夕刻の蝉音が滲む7月の屋上。あぁ今年も夏が来たなと感慨に耽ける。
「……」
僕は目を閉じ、昔のことを思い出す。
この時期は毎年、父と流星群を見ていた。ペルセウス座流星群、日本のほとんどの場所で見ることが出来る。堕ちゆく星々に、幼き僕はいくつも願いを込めたものだ。毎年来るそんなありふれたことが、夏休みの楽しみだった。
今年の流星群は例年に比べて特に極大らしい。今の僕は流星になにを願うだろう?これから全てを終えようとしてるのに、そんなことをふと思った。
「……」
夏風と共に一羽の鳥が山から天に飛んでいくのが見えた。羽ばたく鳥を見て、また思いを馳せる。
夜鷹と言う僕の名は、父がつけたもの。宮沢賢治の小説からとったそうだ。天に昇り、最後は星になった夜鷹。幾度も聞かされた夢物語。
「……」
傍らに置いてある望遠鏡を指でなぞる。父に買ってもらった少し高価な望遠鏡。天文学部は僕独り。
父は…本当に星が好きな人だった。だから僕も同じように好きになった。父の名残として様々なことが僕に根付いている。
だからこそ、心の底から憂鬱になった。
「…どうしようもない」
本当に、どうしようもない人だった。
潤んだ夏風が頬を撫でる。もうすぐ盆だ。
「……」
陽光に温められたフェンスに手をかける。焼けるような熱が手に伝播したが、手を離す必要などない。軽微な火傷など死に体には些末なものだ。
今日、僕は死ぬ。今、この場で。
天を仰ぐ。夜鷹が堕ちる。物語の端末は存外あっけないものだ。
フェンスを乗り越えようと身を乗り出したその刹那──
ギィッ!
屋上の重厚な扉が開く音がした。
「……」
僕は目を閉じ、昔のことを思い出す。
この時期は毎年、父と流星群を見ていた。ペルセウス座流星群、日本のほとんどの場所で見ることが出来る。堕ちゆく星々に、幼き僕はいくつも願いを込めたものだ。毎年来るそんなありふれたことが、夏休みの楽しみだった。
今年の流星群は例年に比べて特に極大らしい。今の僕は流星になにを願うだろう?これから全てを終えようとしてるのに、そんなことをふと思った。
「……」
夏風と共に一羽の鳥が山から天に飛んでいくのが見えた。羽ばたく鳥を見て、また思いを馳せる。
夜鷹と言う僕の名は、父がつけたもの。宮沢賢治の小説からとったそうだ。天に昇り、最後は星になった夜鷹。幾度も聞かされた夢物語。
「……」
傍らに置いてある望遠鏡を指でなぞる。父に買ってもらった少し高価な望遠鏡。天文学部は僕独り。
父は…本当に星が好きな人だった。だから僕も同じように好きになった。父の名残として様々なことが僕に根付いている。
だからこそ、心の底から憂鬱になった。
「…どうしようもない」
本当に、どうしようもない人だった。
潤んだ夏風が頬を撫でる。もうすぐ盆だ。
「……」
陽光に温められたフェンスに手をかける。焼けるような熱が手に伝播したが、手を離す必要などない。軽微な火傷など死に体には些末なものだ。
今日、僕は死ぬ。今、この場で。
天を仰ぐ。夜鷹が堕ちる。物語の端末は存外あっけないものだ。
フェンスを乗り越えようと身を乗り出したその刹那──
ギィッ!
屋上の重厚な扉が開く音がした。