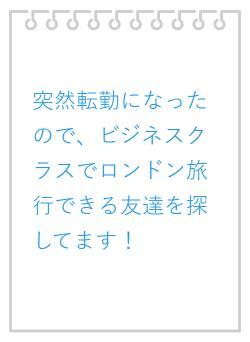黒い乗用車の扉が静かに開いた。そこから降りてきたのは、小柄な少女と長身の青年だった。
「桜さん、気をつけて。何かあったらすぐ逃げるんだ。中で電話が通じるかわからないけど…」
「分かってるよ。先生もそう言ってたし、大丈夫だから。じゃ、家で待っててね。」
桜は笑顔で手を振りながら、降り積もる雪の中をざくざくと進んでいった。青年はその小さな背中を見守るしかなかった。
◇◇◇◇◇
関東なのか東北なのか。
北海道なのか九州なのか。
だれも詳しく答えられない、不思議な場所。
そこにあるのが平凡な高校生、八神橘平《やがみきっぺい》の住む村だ。
村の四方は高低さまざまな山に囲まれ、その中心には円形の広い森が鎮座している。そして森を囲うように人家が広がっていた。
現代において、そんな不確かな場所にある村は限界集落、もしくは人口の大幅な減少に歯止めがきかないと思われるかもしれない。
しかしこの村の人口は、平安時代からか江戸時代か定かではないけれど、とにかく、大昔から今も変化はない。
気味が悪いほどに。
かといって、世間から隔絶されているポツン村かというと、そうでもない。車を一時間弱走らせれば街に出ることだってでき、通勤も可能だ。田んぼ畑が広がるのどかな景色とはいえ、農林業だけで生計を立てる家はそう多くないのが現状。街に働きへ行く大人は割といるのだ。
非常に閉じられた世界に見えながらも、社会とのつながりが持てる地域。
何もかもが「ない」ようで「ある」。あいまいな存在の村。
あいまいな村の中で、たった一つだけ確かな存在がある。
それが、村唯一かつ周辺地域でも最大の規模を誇る神社だ。
お伝え様と呼ばれるその神社、確かな名前は、何だったか。村人は誰も知らない。けれど、誰も疑問に思わないのだった。
おかしいことなんか、ない。
◇◇◇◇◇
2月も中旬のある日曜日のことだった。
その日は珍しく、深く積もる雪が降った。大昔は毎年のように大雪だったらしいが、橘平が記憶する範囲では、ぱらぱら雪だけだ。積もっても5センチくらいがせいぜい、降ったか降っていないか。その程度であった。
橘平はそんな雪が珍しくてワクワクしていた。朝から降り積もる雪に両親から「寒いし、大雪に慣れてないからなるべく家に居てほしい」と言われ、仕方なく一日中、居間で柴犬を撫でたり、弟と遊んだりしていた。夜中の12時頃、家族みんなが眠ったことを確かめてから、そっと家を出た。「どこに行くの?」「誰と行くの?」などと聞かれるのは面倒し、親にだまって夜中に出かけるという、ちょっと悪いことにときめく年頃であった。
玄関を出た瞬間に、体の中から凍るような感覚が橘平を襲った。頭からつま先まで巡る血が止まってしまったかのようで、一歩目が踏み出せない。家に閉じこもっていたためもあるだろうが、橘平がこれまで経験してきた、どんな冬の日よりも寒かった。高校の指定ジャージの上に、厚みのあるアウトドア系ダウンコート、ネックウォーマー、ニット帽に毛糸の手袋、長靴でも歯が立たない。橘平はカイロでも取りに行こうか迷ったが、せっかく家族にバレないよう家を出たのに、という気持ちが勝った。
工場の大きな冷凍庫に入ったらこんな感じだろうか、などと思いながら、橘平は意を決して、ゆっくりと歩き始めた。
一面、足跡一つない真っ白な世界が続く。白と黒しかない世界を、橘平はスマホのライトとたまに出現する街灯を頼りに進んだ。見慣れた道が、知らない街に来たかのようで迷いそうだった。
しかし、夜空の星が降ってきたかと思えるようなきらきらとした雪は、さまざまな写真集や画集で見た作品よりも、橘平の心を震わせた。寒さを忘れるほどの感動だった。
寒さと白い世界のせいか、時間間隔はよく分からなくなっている。30分、一時間近くは歩き続けただろうか。橘平は村の真ん中にある森の近くまでやってきた。
橘平はそこで立ち止まり、ふと、雪景色の写真を撮ってみようという気持ちになった。
学校の女子など周りの同級生たちはよく、友達同士で写真を撮っている。ほかにも、かわいいとかキレイとか言って、お菓子や犬猫などの写真や動画を撮りまくっていた。
ところが、橘平は特に撮りたいとは思わない。周りの物事に対して、撮るほどの興味が持てないのだ。彼のカメラロールには家で飼っている可愛い愛犬の写真すらない。
そんな橘平が、この日の雪は「撮りたい」と思った。スマホのカメラを起動させた。
「雪がきらきら、星のように光って見える写真が撮りたいな……」
ほとんどカメラアプリを使ったことがない少年は、角度はどうだ、何とかモードはなんだと機能を確認しつつ、立ったりしゃがんだり、座ったり、いろいろな態勢で撮影した。手袋を外しているため指がすでに痛いほど冷えているが、写真に夢中で気にならない。
橘平は寝転んで、空から降ってくる雪を撮影してみた。
なかなかよく撮れたと起き上がり、次の撮影に取り掛かろうとしたところ、画面に人が映し出された。
橘平は、「うえあ!?ゆーれー!?」と裏返った変な声をあげ、思わずスマホを落とした。
彼の姿とその声に女の子も驚いたようで、目を見開いてぴたっと静止する。
落ち着いてよく見れば「ゆーれー」ではなく、橘平と同じ年頃と思われる小柄な女の子。生きている人間だった。大き目のメガネにダッフルコート、もこもこしたマフラーと手袋、ニットガイドを身に着けている。
なぜこんな夜遅く、人気のない場所に女の子が一人でいるのだろうか。
橘平が女の子に話しかけようとするも、彼女は彼を無視してさっさと歩き出した。
「え、ちょっと!」
村人で同年代ともなれば、ほとんどの顔は見知っている。小学校からずっと一緒なのだ。しかし橘平は、その女の子を全く見たことがなかった。
こんな夜中に知らない女の子。つまり「よそ者」の可能性が高い。最近、女子中学生の自殺のニュースが世間を騒がせていたこともあり、橘平はそれを彼女に重ねた。村人だったとしても、だ。雪の降る真夜中に一人ででかけるなんて、ただことではない、自殺か家出か。それを見逃したとしたら後味が悪い。
橘平も夜中に出歩く一人なのだがそれはさておき、女の子に呼びかけた。
「待って!」
女の子が心配な橘平はスマホを急いで拾い、なれない雪に足がとられつつ、ざくざくと彼女の後をついていった。
雪はひざ下まで迫っているのに女の子は意外とさくさくと歩くものだから、橘平は距離を縮められないでいる。
「夜中に危ないよ、女子一人で出歩くなんて!」
「あなた様も夜中に出歩いておりますが、男子なら危険はないのでしょうか」
「いや、俺は家がまあまあすぐそこだし!よその人でしょ?雪の日に知らない村へ来るなんて危険だよ。もう一回言うけど危ないよ!家帰りなよ!」
女の子は橘平を無視し、ずんずん進む。彼女が向かう先には、村の中心にある円形の森。もう目の前だ。
森。
もうこれは自殺か家出か、とにかく、いいことではないはずだ。そう考えた橘平は、追いつこうと必死になる。
どこの誰なのかさっぱりわからない女の子を、なぜここまで必死になって追いかけるのか。心配だからといえばそうなのだが、それ以上の何かが、橘平を突き動かしていた。
女の子が突然、歩みを止めて、肩越しに少しだけ振り返る。
「なぜ、付いてくるのですか」
「さっきも言ったけど、よその人には危険だから」
「…私、この村の者です。おそらく、村の誰よりもこのあたりの地理は熟知しておりますゆえ、ご心配なさらぬよう」
「え、村の人?全く知らないけど。高校生くらいだよね?学校で見かけたことがないし」
女の子は顔に比して大きなメガネをくっとかけ直し、また前を向いてさくさく歩き始めた。
「そっちは森なんだよ、森!すっごく暗くて怖い、森!危ないって!」
「あなたこそ危ないですよ、お帰りになったほうがよろしいと存じます」
同級生の使わないような堅苦しい言葉遣いが、橘平のカンに触ってきた。そう年齢は変わらなそうなのに、妙に偉そうでつんけんしている。彼の親切を全く聞き入れる様子はない。
「ケガしても知らないからな!」
そう叫んでも、女の子はずんずんと雪道を進んでいく。橘平は無視し続ける彼女の背中だけを見て、必死に追いかける。
橘平が周りがやけに暗いと気が付いた時には、すでに二人は森の中だった。
「やばっ!」
橘平は恐怖を感じた。
親や祖父母、先祖の誰かに「入るな」と言われたわけでもないのに、村の人々は絶対に森には近づかない。橘平は好奇心で一度だけ足を踏み入れたことがあるけれど、恐ろしさに一瞬で引き返してしまった。
何が待ち受けているのか分からない、未知の場所。
木々が生い茂り、空も満足に拝めない真っ暗闇。
無事でいられるのか。ここから出られるのか。見通しが全くつかない。
しかも、今日は稀にみる大雪。五体満足で帰れる自信はないが、橘平は女の子をどうしても放っておけなかった。子供のころに教わったおまじないを手のひらに書き、心を決めて彼女を追い続けた。
ほんの少しの救いは、彼女が持つ懐中電灯の光だった。それを頼りに後ろを歩く。
「俺は八神橘平!あなたは!?」
橘平が名乗ると、女の子は立ち止まり、橘平の方を振り返りぼそりと呟いた。
「八神家…南地域の方ですか」
村では名字ごとにだいたい家の場所が決まっており、八神の人々は村の南側に住んでいる。
さらに言えば、南地域は他の地域より範囲が狭く、ほぼ八神しかいないような場所だ。橘平の家の地域を知っているということは、やはり彼女は村人なのかもしれない。
彼女はしっかり橘平の目を見て「一宮桜《いちのみやさくら》です」と名乗った。
そういうと桜は前を向き、またずんずんと歩き始めた。
「いちの…一宮!?一宮ってお伝え様んち?!」
お伝え様とは村にある唯一の神社、総じて、一宮本家のことも指す。
昔から村をまとめている家であり、みなから頼られ、敬われている。家のもめごとから村の運営に関わる事、何か問題があればお伝え様に相談する。村議会ですら、お伝え様の一言を大事にしていた。
村の同年代とはみな知り合いのはずだが、やはり桜のことは全く分からない。そもそも、一宮本家に同年代の娘がいたことすら、今初めて知った橘平だった。
「そうですよ」
桜は黙々と歩みを止めない。疲れた様子も見えない。
体力はあるほうだと思っている橘平だったが、慣れない雪道と履きなれない長靴のせいで、足がぐったりしている。一歩を前に出すのもつらくなってきた。
それでもなんとか気合で桜に食らいついていくと、真っ暗闇の森の中に突然、大きな桜の木が現れた。
真冬のはずなのに、満開の桜の木。
何千年、何万年もそこで生きているかのような佇まい。太く立派な幹。
桜の木の周りだけ草木は生えておらず、地面がむき出しの広場のようになっていた。雪が降っているはずなのに、それも一切無い。月明かりがスポットライトのように桜だけを照らしている。
お伝え様の境内や裏山、その周辺にも見事で美しい桜の木がある。しかし、毎年村人を楽しませているその桜たちよりも存在感があり、心を惹かれる壮麗さを持っていた。
橘平はその光景に心を奪われた。しかし桜は全く何も感じていないようで、桜の木をめがけて進む。もう少し美しさに浸っていたかった橘平だが、彼女についていった。
ぴたりと桜は木の下で立ち止まり、足元に視線を移した。橘平も立ち止まり、彼女が見ているものを彼も見る。
目線の先には、神社のミニチュアのような置物があった。
「なんだこれ、おもちゃ?神社の?」
「神社ですよ。見た目通りです」
橘平はしゃがみこみ、神社のミニチュアをまじまじと眺めた。とても精巧につくられており、確かにお伝え様の拝殿にそっくりである。屋根には二重丸のような模様が描かれていて、じっと見ていると誰かに見つめられているようだった。
「ふーん、ミニ神社か。にしても、不思議だなあ。冬なのに桜。そういや寒くもないし、ここだけ春なのか?」
「そう、不思議ですよね。ここだけ世界が違うなんて…」
バキっ。
橘平の目の前で、神社のミニチュアが破壊された。破壊したのは桜の右足である。
「は?」
桜は右手でメガネを上にずらした格好で、潰れた神社を見下ろす。
「粉々になったかな。まだ足りないか」
そう言って何度も足で踏みつける。いきなりの出来事に放心していた橘平だが、すくっと立ち上がり、彼女を問い詰めた。
「一宮さん、神社の娘でしょ!?ちっちゃくても神社なのに、なんで壊してんの、おかしいでしょ!?」
桜はきりっと吊り上がった目で、橘平を睨んだ。
すべての光を吸収してしまうような漆黒の瞳が、橘平の極薄茶色の瞳を射る。橘平という存在そのものが飲み込まれるような、消えてしまいそうな瞳だった。
雪の中を平然と歩き続ける体力もそうだが、同級生と比べそう大きくない自分よりもさらに小柄な体に、どれだけの破壊力が潜んでいるのか。
橘平はつばをごくりと飲み込む。
「…おかしいのは、村をおかしいと思わない村人のほうです」
と桜が言うと、二人の左右から何かが勢いよくせりあがり、激しい風が吹いた。
二人が風に抗いながら上空に目を移すと、桜の木と同等の高さと空を覆いつくほどの体躯を持った怪物が二匹。
怪物が着地した。それと同時に、巨大ビルが爆破されたような轟音と地面が割れそうなほどの揺れが発生した。不安定な地面に二人は立っていられなくなり、橘平はしりもちを付く。桜は四つ這いの形になった。
「っあー!!!!お、おにー!?!?!ようかい!?!?」
「な、なにこれ、聞いてないわ!」
左の怪物は角が一つ生え、目と鼻は無く、口は真一文字に引き締まっている。右の怪物も目鼻はないが、角が二本、口は大きく開いており、今にも二人を食べようとしているように見える。ともに体の上から下まで、ありえないほどの筋骨隆々さと重量感を持っている。
怪物はのっそりと二人の頭上に顔を揺らし、二匹同時に腕を振り上げた。
橘平はとっさに桜の手を取り、全速力で走った。かろうじてその腕からは逃げられたが、怪物はまた襲ってくる。
「に、逃げるわけには」
「ごちゃごちゃ言うなって!」
橘平は桜の背と膝に手を添えてさっと持ち上げ、走り続けた。
広場を抜け、森の中に戻る。真っ暗闇の中、同じように見える木々と積もった雪のせいで、どこを進んでいるのか分からない。足も思うように進まない。
ただ、この森は村の中心にある。進んでいけば、東西南北、どこかの地域には出られるはずだ。
そう信じて、橘平はひたすら走った。
「降ろして!八神さん!」
反論に答えるほどの余裕も体力も、橘平には残っていなかった。
顔も耳も、目も指も限界まで真っ赤、内臓という内臓がいまにも破れそうに苦しい。
橘平は陸上部だ。走ることには慣れている。とはいえ、人間を抱えて走ったことなど無い。初めてだ。
そでもなぜか、桜を抱えて走り続けることができた。
「桜さん、気をつけて。何かあったらすぐ逃げるんだ。中で電話が通じるかわからないけど…」
「分かってるよ。先生もそう言ってたし、大丈夫だから。じゃ、家で待っててね。」
桜は笑顔で手を振りながら、降り積もる雪の中をざくざくと進んでいった。青年はその小さな背中を見守るしかなかった。
◇◇◇◇◇
関東なのか東北なのか。
北海道なのか九州なのか。
だれも詳しく答えられない、不思議な場所。
そこにあるのが平凡な高校生、八神橘平《やがみきっぺい》の住む村だ。
村の四方は高低さまざまな山に囲まれ、その中心には円形の広い森が鎮座している。そして森を囲うように人家が広がっていた。
現代において、そんな不確かな場所にある村は限界集落、もしくは人口の大幅な減少に歯止めがきかないと思われるかもしれない。
しかしこの村の人口は、平安時代からか江戸時代か定かではないけれど、とにかく、大昔から今も変化はない。
気味が悪いほどに。
かといって、世間から隔絶されているポツン村かというと、そうでもない。車を一時間弱走らせれば街に出ることだってでき、通勤も可能だ。田んぼ畑が広がるのどかな景色とはいえ、農林業だけで生計を立てる家はそう多くないのが現状。街に働きへ行く大人は割といるのだ。
非常に閉じられた世界に見えながらも、社会とのつながりが持てる地域。
何もかもが「ない」ようで「ある」。あいまいな存在の村。
あいまいな村の中で、たった一つだけ確かな存在がある。
それが、村唯一かつ周辺地域でも最大の規模を誇る神社だ。
お伝え様と呼ばれるその神社、確かな名前は、何だったか。村人は誰も知らない。けれど、誰も疑問に思わないのだった。
おかしいことなんか、ない。
◇◇◇◇◇
2月も中旬のある日曜日のことだった。
その日は珍しく、深く積もる雪が降った。大昔は毎年のように大雪だったらしいが、橘平が記憶する範囲では、ぱらぱら雪だけだ。積もっても5センチくらいがせいぜい、降ったか降っていないか。その程度であった。
橘平はそんな雪が珍しくてワクワクしていた。朝から降り積もる雪に両親から「寒いし、大雪に慣れてないからなるべく家に居てほしい」と言われ、仕方なく一日中、居間で柴犬を撫でたり、弟と遊んだりしていた。夜中の12時頃、家族みんなが眠ったことを確かめてから、そっと家を出た。「どこに行くの?」「誰と行くの?」などと聞かれるのは面倒し、親にだまって夜中に出かけるという、ちょっと悪いことにときめく年頃であった。
玄関を出た瞬間に、体の中から凍るような感覚が橘平を襲った。頭からつま先まで巡る血が止まってしまったかのようで、一歩目が踏み出せない。家に閉じこもっていたためもあるだろうが、橘平がこれまで経験してきた、どんな冬の日よりも寒かった。高校の指定ジャージの上に、厚みのあるアウトドア系ダウンコート、ネックウォーマー、ニット帽に毛糸の手袋、長靴でも歯が立たない。橘平はカイロでも取りに行こうか迷ったが、せっかく家族にバレないよう家を出たのに、という気持ちが勝った。
工場の大きな冷凍庫に入ったらこんな感じだろうか、などと思いながら、橘平は意を決して、ゆっくりと歩き始めた。
一面、足跡一つない真っ白な世界が続く。白と黒しかない世界を、橘平はスマホのライトとたまに出現する街灯を頼りに進んだ。見慣れた道が、知らない街に来たかのようで迷いそうだった。
しかし、夜空の星が降ってきたかと思えるようなきらきらとした雪は、さまざまな写真集や画集で見た作品よりも、橘平の心を震わせた。寒さを忘れるほどの感動だった。
寒さと白い世界のせいか、時間間隔はよく分からなくなっている。30分、一時間近くは歩き続けただろうか。橘平は村の真ん中にある森の近くまでやってきた。
橘平はそこで立ち止まり、ふと、雪景色の写真を撮ってみようという気持ちになった。
学校の女子など周りの同級生たちはよく、友達同士で写真を撮っている。ほかにも、かわいいとかキレイとか言って、お菓子や犬猫などの写真や動画を撮りまくっていた。
ところが、橘平は特に撮りたいとは思わない。周りの物事に対して、撮るほどの興味が持てないのだ。彼のカメラロールには家で飼っている可愛い愛犬の写真すらない。
そんな橘平が、この日の雪は「撮りたい」と思った。スマホのカメラを起動させた。
「雪がきらきら、星のように光って見える写真が撮りたいな……」
ほとんどカメラアプリを使ったことがない少年は、角度はどうだ、何とかモードはなんだと機能を確認しつつ、立ったりしゃがんだり、座ったり、いろいろな態勢で撮影した。手袋を外しているため指がすでに痛いほど冷えているが、写真に夢中で気にならない。
橘平は寝転んで、空から降ってくる雪を撮影してみた。
なかなかよく撮れたと起き上がり、次の撮影に取り掛かろうとしたところ、画面に人が映し出された。
橘平は、「うえあ!?ゆーれー!?」と裏返った変な声をあげ、思わずスマホを落とした。
彼の姿とその声に女の子も驚いたようで、目を見開いてぴたっと静止する。
落ち着いてよく見れば「ゆーれー」ではなく、橘平と同じ年頃と思われる小柄な女の子。生きている人間だった。大き目のメガネにダッフルコート、もこもこしたマフラーと手袋、ニットガイドを身に着けている。
なぜこんな夜遅く、人気のない場所に女の子が一人でいるのだろうか。
橘平が女の子に話しかけようとするも、彼女は彼を無視してさっさと歩き出した。
「え、ちょっと!」
村人で同年代ともなれば、ほとんどの顔は見知っている。小学校からずっと一緒なのだ。しかし橘平は、その女の子を全く見たことがなかった。
こんな夜中に知らない女の子。つまり「よそ者」の可能性が高い。最近、女子中学生の自殺のニュースが世間を騒がせていたこともあり、橘平はそれを彼女に重ねた。村人だったとしても、だ。雪の降る真夜中に一人ででかけるなんて、ただことではない、自殺か家出か。それを見逃したとしたら後味が悪い。
橘平も夜中に出歩く一人なのだがそれはさておき、女の子に呼びかけた。
「待って!」
女の子が心配な橘平はスマホを急いで拾い、なれない雪に足がとられつつ、ざくざくと彼女の後をついていった。
雪はひざ下まで迫っているのに女の子は意外とさくさくと歩くものだから、橘平は距離を縮められないでいる。
「夜中に危ないよ、女子一人で出歩くなんて!」
「あなた様も夜中に出歩いておりますが、男子なら危険はないのでしょうか」
「いや、俺は家がまあまあすぐそこだし!よその人でしょ?雪の日に知らない村へ来るなんて危険だよ。もう一回言うけど危ないよ!家帰りなよ!」
女の子は橘平を無視し、ずんずん進む。彼女が向かう先には、村の中心にある円形の森。もう目の前だ。
森。
もうこれは自殺か家出か、とにかく、いいことではないはずだ。そう考えた橘平は、追いつこうと必死になる。
どこの誰なのかさっぱりわからない女の子を、なぜここまで必死になって追いかけるのか。心配だからといえばそうなのだが、それ以上の何かが、橘平を突き動かしていた。
女の子が突然、歩みを止めて、肩越しに少しだけ振り返る。
「なぜ、付いてくるのですか」
「さっきも言ったけど、よその人には危険だから」
「…私、この村の者です。おそらく、村の誰よりもこのあたりの地理は熟知しておりますゆえ、ご心配なさらぬよう」
「え、村の人?全く知らないけど。高校生くらいだよね?学校で見かけたことがないし」
女の子は顔に比して大きなメガネをくっとかけ直し、また前を向いてさくさく歩き始めた。
「そっちは森なんだよ、森!すっごく暗くて怖い、森!危ないって!」
「あなたこそ危ないですよ、お帰りになったほうがよろしいと存じます」
同級生の使わないような堅苦しい言葉遣いが、橘平のカンに触ってきた。そう年齢は変わらなそうなのに、妙に偉そうでつんけんしている。彼の親切を全く聞き入れる様子はない。
「ケガしても知らないからな!」
そう叫んでも、女の子はずんずんと雪道を進んでいく。橘平は無視し続ける彼女の背中だけを見て、必死に追いかける。
橘平が周りがやけに暗いと気が付いた時には、すでに二人は森の中だった。
「やばっ!」
橘平は恐怖を感じた。
親や祖父母、先祖の誰かに「入るな」と言われたわけでもないのに、村の人々は絶対に森には近づかない。橘平は好奇心で一度だけ足を踏み入れたことがあるけれど、恐ろしさに一瞬で引き返してしまった。
何が待ち受けているのか分からない、未知の場所。
木々が生い茂り、空も満足に拝めない真っ暗闇。
無事でいられるのか。ここから出られるのか。見通しが全くつかない。
しかも、今日は稀にみる大雪。五体満足で帰れる自信はないが、橘平は女の子をどうしても放っておけなかった。子供のころに教わったおまじないを手のひらに書き、心を決めて彼女を追い続けた。
ほんの少しの救いは、彼女が持つ懐中電灯の光だった。それを頼りに後ろを歩く。
「俺は八神橘平!あなたは!?」
橘平が名乗ると、女の子は立ち止まり、橘平の方を振り返りぼそりと呟いた。
「八神家…南地域の方ですか」
村では名字ごとにだいたい家の場所が決まっており、八神の人々は村の南側に住んでいる。
さらに言えば、南地域は他の地域より範囲が狭く、ほぼ八神しかいないような場所だ。橘平の家の地域を知っているということは、やはり彼女は村人なのかもしれない。
彼女はしっかり橘平の目を見て「一宮桜《いちのみやさくら》です」と名乗った。
そういうと桜は前を向き、またずんずんと歩き始めた。
「いちの…一宮!?一宮ってお伝え様んち?!」
お伝え様とは村にある唯一の神社、総じて、一宮本家のことも指す。
昔から村をまとめている家であり、みなから頼られ、敬われている。家のもめごとから村の運営に関わる事、何か問題があればお伝え様に相談する。村議会ですら、お伝え様の一言を大事にしていた。
村の同年代とはみな知り合いのはずだが、やはり桜のことは全く分からない。そもそも、一宮本家に同年代の娘がいたことすら、今初めて知った橘平だった。
「そうですよ」
桜は黙々と歩みを止めない。疲れた様子も見えない。
体力はあるほうだと思っている橘平だったが、慣れない雪道と履きなれない長靴のせいで、足がぐったりしている。一歩を前に出すのもつらくなってきた。
それでもなんとか気合で桜に食らいついていくと、真っ暗闇の森の中に突然、大きな桜の木が現れた。
真冬のはずなのに、満開の桜の木。
何千年、何万年もそこで生きているかのような佇まい。太く立派な幹。
桜の木の周りだけ草木は生えておらず、地面がむき出しの広場のようになっていた。雪が降っているはずなのに、それも一切無い。月明かりがスポットライトのように桜だけを照らしている。
お伝え様の境内や裏山、その周辺にも見事で美しい桜の木がある。しかし、毎年村人を楽しませているその桜たちよりも存在感があり、心を惹かれる壮麗さを持っていた。
橘平はその光景に心を奪われた。しかし桜は全く何も感じていないようで、桜の木をめがけて進む。もう少し美しさに浸っていたかった橘平だが、彼女についていった。
ぴたりと桜は木の下で立ち止まり、足元に視線を移した。橘平も立ち止まり、彼女が見ているものを彼も見る。
目線の先には、神社のミニチュアのような置物があった。
「なんだこれ、おもちゃ?神社の?」
「神社ですよ。見た目通りです」
橘平はしゃがみこみ、神社のミニチュアをまじまじと眺めた。とても精巧につくられており、確かにお伝え様の拝殿にそっくりである。屋根には二重丸のような模様が描かれていて、じっと見ていると誰かに見つめられているようだった。
「ふーん、ミニ神社か。にしても、不思議だなあ。冬なのに桜。そういや寒くもないし、ここだけ春なのか?」
「そう、不思議ですよね。ここだけ世界が違うなんて…」
バキっ。
橘平の目の前で、神社のミニチュアが破壊された。破壊したのは桜の右足である。
「は?」
桜は右手でメガネを上にずらした格好で、潰れた神社を見下ろす。
「粉々になったかな。まだ足りないか」
そう言って何度も足で踏みつける。いきなりの出来事に放心していた橘平だが、すくっと立ち上がり、彼女を問い詰めた。
「一宮さん、神社の娘でしょ!?ちっちゃくても神社なのに、なんで壊してんの、おかしいでしょ!?」
桜はきりっと吊り上がった目で、橘平を睨んだ。
すべての光を吸収してしまうような漆黒の瞳が、橘平の極薄茶色の瞳を射る。橘平という存在そのものが飲み込まれるような、消えてしまいそうな瞳だった。
雪の中を平然と歩き続ける体力もそうだが、同級生と比べそう大きくない自分よりもさらに小柄な体に、どれだけの破壊力が潜んでいるのか。
橘平はつばをごくりと飲み込む。
「…おかしいのは、村をおかしいと思わない村人のほうです」
と桜が言うと、二人の左右から何かが勢いよくせりあがり、激しい風が吹いた。
二人が風に抗いながら上空に目を移すと、桜の木と同等の高さと空を覆いつくほどの体躯を持った怪物が二匹。
怪物が着地した。それと同時に、巨大ビルが爆破されたような轟音と地面が割れそうなほどの揺れが発生した。不安定な地面に二人は立っていられなくなり、橘平はしりもちを付く。桜は四つ這いの形になった。
「っあー!!!!お、おにー!?!?!ようかい!?!?」
「な、なにこれ、聞いてないわ!」
左の怪物は角が一つ生え、目と鼻は無く、口は真一文字に引き締まっている。右の怪物も目鼻はないが、角が二本、口は大きく開いており、今にも二人を食べようとしているように見える。ともに体の上から下まで、ありえないほどの筋骨隆々さと重量感を持っている。
怪物はのっそりと二人の頭上に顔を揺らし、二匹同時に腕を振り上げた。
橘平はとっさに桜の手を取り、全速力で走った。かろうじてその腕からは逃げられたが、怪物はまた襲ってくる。
「に、逃げるわけには」
「ごちゃごちゃ言うなって!」
橘平は桜の背と膝に手を添えてさっと持ち上げ、走り続けた。
広場を抜け、森の中に戻る。真っ暗闇の中、同じように見える木々と積もった雪のせいで、どこを進んでいるのか分からない。足も思うように進まない。
ただ、この森は村の中心にある。進んでいけば、東西南北、どこかの地域には出られるはずだ。
そう信じて、橘平はひたすら走った。
「降ろして!八神さん!」
反論に答えるほどの余裕も体力も、橘平には残っていなかった。
顔も耳も、目も指も限界まで真っ赤、内臓という内臓がいまにも破れそうに苦しい。
橘平は陸上部だ。走ることには慣れている。とはいえ、人間を抱えて走ったことなど無い。初めてだ。
そでもなぜか、桜を抱えて走り続けることができた。