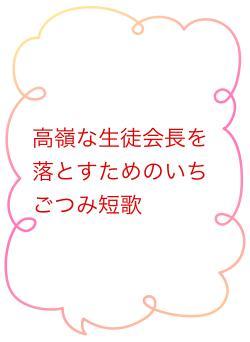――姫様ならどうするだろう。
身代わりになってからというもの、松緒は自分の中の「姫様」によく問いかけるようになった。
「姫様らしく」を求められているからだけれども、松緒にとっては「姫様を思い出す行為」でもあるのでそれはそれで幸せだったりもする。
――わたくしなら、こうするかしら。
松緒が問えば、松緒の想像した姫様が、ふわっとその場に現れて、松緒に答えを教えてくれる気がした。
彼女はそれだけ長い間かぐや姫と一緒にいたのだから、脳内で姫様を再現することなど余裕なのである。
これを「イマジナリー姫様」と呼ぶ。「イマジナリーフレンド」ならぬ、「イマジナリーな姫様」である。
松緒はこの時も「イマジナリー姫様」を発動した。
松緒が思うだけで、かぐや姫は微笑みながら松緒の前に現れる。
『姫様、主上からお尋ねがあったのです。なんとお答えすればよいでしょうか?』
『主上は何をおっしゃったの?』
『「かぐや姫」に対して、自分はこれからどうしたらよいのか、と……。主上のお考えがよくわからないのです』
『そうね……』
かぐや姫は面を伏せてしばらく考えた後に、
『松緒は覚えている? あの時のこと。ほら、前の関白様のお誘いをお断りした時の……。あんな感じでよいのではないかしら』
『で、ですが、姫様。あの時は夢中でしたし……』
『ふふふ。きっとできるわ。あなたなら』
「イマジナリー姫様」はフッ、と消えてしまった。妄想のわりに都合よくお話ししてくれないのだ(そんなところも姫様らしいのだが)。
松緒は、今、現実にいた。「かぐや姫」として帝と東宮の二人を御簾越しに相手をしなければならない。
ふたりは松緒の答えを待っているのだ。
「『おのが身は、この国に生まれて侍らばこそ使ひ給はめ、いと率いておはし難くや侍らむ』と申します」
――わたしの身がこの国に生まれていたならお召しできましょうが、お連れなさるのはとても難しいことでしょう。
『竹取物語』でかぐや姫が帝を拒む時の台詞だ。
かつてはしつこくかぐや姫を口説こうとした前の関白を追い払うために、松緒が必死で考えた断り文句でもある(室内に入り込んでこようとしたのを叫びながら制止した。危なかった)。
「尚侍として、お仕えする気持ちに偽りはございません。もしも主上がこの御簾を越えていらっしゃった場合、わたくしはするりと逃げて、月に帰ってしまうやもしれません」
くくっ、と笑い声が漏れた。東宮の肩が揺れていた。
「「主上」のところだけは訂正せねばならないだろう? そなたは、どんな男だろうとも受け入れるつもりがないのでは? それこそ物語の「かぐや姫」をそのままなぞるように生きるのか?」
松緒は何も言わなかった。理解してもらえるとも思っていなかった。
彼女は、「姫様」にずっと仕えるつもりだったし、年老いたら寺の近くで椿餅を細々と売って、姫様と暮らしていたかったのだ。
かぐや姫はすべての求婚を断り、だれの手も取らなかったから。
――そんな姫様がいなくなってしまった。私の気持ちはだれにも理解してもらえないのでしょうね。
半身をもがれたような喪失感を、身代わりをするために無理やり気づかないふりをしているのだ。
「よいのだ、墨宮」
帝が「かぐや姫」の沈黙を掬うように口を開いた。
兄に釘を刺された東宮は不機嫌になった様子もなく引き下がる。
「尚侍。そなたの気持ちを尊重しよう。ところで、ひとつ、頼みがある」
帝の「頼み」とは、ほぼ勅命と同義である。
場を乗り切ってほっとしたのも束の間、松緒は背筋を伸ばして、帝の言葉に耳を澄ませたのだった。
「そなたには、行事をひとつ、取り仕切ってもらいたい」
庚申待ちと呼ばれる風習がある。
暦で庚申に当たる日が年に数度あるのだが、その日の夜に寝てしまうと、普段体の中にいる三尸《さんこ》という虫が、天帝のところにいって、宿主の悪行を報告し、宿主の寿命が縮まってしまうという。
よって、庚申の夜には眠らずに過ごすのが、庚申待ちだ。この時に、眠くならないよう人が集まり、管弦の宴を催したり、歌を詠んだり、碁を打ったりなどする。
宮中でも同じようなことが行われていて、帝が打診したのも、庚申待ちの時に人々が楽しめる行事を取り仕切ってほしいとのことだった。
「それで、主上にはなんとお返事なされたのでしょうか」
「謹んでお引き受け申し上げます、と」
帝と東宮との対面後、須磨との緊急会議である。近くには、相模《さがみ》も控えている。
須磨は、粛々と「かぐや姫」の話を聞き、まず第一声として「仕方がありませんね」と発した。
「尚侍さまに何か、お考えはございますか?」
「これぞ、というものはまだ……」
松緒は言葉を濁した。
松緒がすぐに考えつくようなものは、すでに行われているし、飽きているだろう。
「かぐや姫」が関わるからこその「趣向」が求められている。
行事の内容はともかくとして、「かぐや姫」にはまずはやらなければならないことがあった。
「しかし、帝がお任せしてくださった以上、わたくしはしっかりやり遂げたいと思っております」
松緒は、意を決して口を開いた。
「わたくしひとりで行事を取り仕切ることはできるわけもございません。どうしても、須磨や、他のみなの力が必要となりましょう。……どうか、わたくしを助けてもらえないでしょうか」
松緒はちらっと扇をかざしたまま、須磨の様子を伺った。松緒から見えるのは、座っている彼女の袴の辺り。膝の上に扇を持ち、両手を揃えて置いていた。
須磨はおもむろに立ち上がる仕草をした。
「お話の方はわかりました。わたくしめはこれにて一度失礼いたします」
――あれ、だめかも。
須磨はきっぱりした態度で立ち去ろうとしている。
正直、彼女にまず頼ることしか考えられなかった松緒は内心、焦った。
「え、あの……姫様のお話のほうは?」
傍の相模も松緒と同じように思ったのか、こらえきれない様子で声を上げる。須磨がちらとそちらを見やり、
「尚侍さまにはお勉強していただく必要がございましょう。尚侍になられたばかりで宮中のしきたりにも疎いのです」
「は……?」
「尚侍さまはいまだお考えがまとまってないご様子。……庚申待ちの記録は、内侍所《ないしのどころ》にわずかにございます。それをお持ちしようかと思ったまでですが」
松緒と相模は一瞬、戸惑ったが、胸を撫でおろす。
須磨は「かぐや姫」を見捨てたわけではなかったらしい。
「ありがとう、須磨。助かります」
「何を当然のことをおっしゃるのですか。わたくしめは尚侍を補佐する典侍《ないしのすけ》でございます。尚侍《ないしのかみ》がお望みであれば、従いますので」
まずは須磨が持ってくる過去の記録を読みながら、庚申待ちに行うことを決めることになった。
次の庚申の日まで、およそ一か月。準備のことを思えば、時はあるようでなかった。
三日経った。
行事の内容がさっぱり思いつかない。寝ても醒めても行事のことが頭をよぎる。
今や松緒の失敗は「かぐや姫」の失敗になってしまう。松緒ひとりが恥をかけば済む問題ではなかった。
「かぐや姫」が庚申待ちの行事をとりしきることは、すぐ噂が出回ったらしい。次の日にはかぐや姫の父親である桃園大納言に伝わっていた。
「やりおおせるのであろうな。宮中の耳目がおまえに集まっているのだぞ」
「は、はい……」
松緒は冷や汗をだらだらかきながらそう返事するほかなかった。
かぐや姫がいたころはまだおだやかな気質だった桃園大納言も、今となっては鬼上司。圧のかけ方が半端ないのだが、この世界にはハラスメントを訴える手段がない。
――姫様も、周囲の期待に応えることに耐えられなかったから、いなくなったのかな。
松緒は無邪気にかぐや姫の背中を追いかけていればよかったが、かぐや姫自身はどう考えていたのだろう。松緒が見る限りでは、重圧を気にした様子もなく、いつも穏やかに微笑んでいたが……。
桃園大納言が帰ったので、松緒がひとりで物思いにふけっていると。
「やや! 鈴命婦はこちらへ参っていませんかナ!」
男の声と、足音が殿舎に響く。
松緒はさっと檜扇を広げて顔を隠す。
ちりんちりん。小さな鈴の音も遅れて響き、松緒の膝の上に白い毛玉が乗り上げて、くりくりお目目でにゃあと啼く。
「猫だ……」
松緒はあまり触れたことがないので、そのまま固まってしまった。
傍の几帳の帷子が左右に割れて、黒い烏帽子がにゅっと突き出す。
「尚侍サマ、ごきげんよう!」
「ごきげんよう……」
「晴明ですヨ!」
「知っています」
膝の上で白い猫は丸くなっていた。
晴明は肘で這いより、器用に猫を持ち上げた。猫は嫌がるわけでもなくおとなしくしている。
「鈴命婦はすぐに逃げてしまうのですヨ。だからワタシがいつも追いかけています」
「……あなた、陰陽師でしょう。なぜ猫を?」
「はて、なんででしょう? なぜかよく命じられるんですよねェ……?」
そんなやりとりをするうちに、別の人影が後方から彼に迫った。
「この野良陰陽師めが! 無礼もはなはだしい! 恥を知れッ!」
危機を察知した猫は、すぐさま陰陽師の腕から逃れたが、陰陽師自身は逃げられなかった。
アッ、となまめかしい声をあげたピンク髪がずるずると後方へ引きずられていく。
几帳の帷子が閉じていった……。
うぎゃ、うぎょ、うべっ。……ばたんばたんと暴れる音と不可思議な悲鳴が聞こえてくるので、さすがに松緒は几帳の反対側へ回りこむ。
「何をしているのですか……」
扇をかざす松緒にすべて見えていたわけではなかったものの、松緒には板敷の床にへばりついて意地でも動かないという姿勢をした晴明と、その晴明の足をつかみ、どうにか外へ引きずりだそうとしたが、動きにくい袴に足を取られてやむなく倒れ込んでしまった……。
「お見苦しいところをお見せしております、尚侍さま」
声だけは平常だった。怖いぐらいに。
「今すぐこの野良陰陽師を放り出しますので、お待ちを」
「須磨。体格が違うのですから、無理しないほうがよいですよ」
「いえ。この者を御簾の内に入れたのは、わたくしめの不徳の致すところでございます。責任を果たします」
「相手も人なのですから、きちんと話せばわかってくれます。そうでしょう、晴明殿」
妙な沈黙がその場に落ちた。
フフフ、とピンク髪の陰陽師が笑う。
「そうですネ。ワタシ、聞き分けがよいのですヨ。ささ、御簾の外に出まショウ」
チチチ、と晴明が舌打ちをすると、白猫も彼の傍に寄ってきた。抱き上げて、御簾をくぐる。
須磨はいつ晴明が振り返って戻ってきやしないかと神経を尖らせているようだった。
「……あ、そうだ、尚侍サマ」
「野良陰陽師!」
オオ、怖い怖い、と肩を竦める晴明。
「宮中には魑魅魍魎《ちみもうりょう》が多くいるものですナア。ひとところに集まれば、百鬼夜行《ひゃっきやぎょう》ができますナ」
不気味な笑い声とともに不審人物は去っていった。
――『百鬼夜行』、か……。
この世界の人びとはあやかしがいると信じている。だからこそ陰陽師もいるし、祈祷も行う。
夜に都のあやかしたちが列をなして練り歩く。それが百鬼夜行というものだが……。
「あ、そうか」
「尚侍《ないしのかみ》さま?」
「いえ。今、ふと、庚申待ちの行事について、思いついたことがあったのですよ」
松緒は自分の考えをこそこそと話した。
はじめのうちは不審そうにしていたものの、やがて唇を一文字に引き結ぶ須磨。
「それは……前例がないことでございますね」
「はい。記録にもありませんでしたね。しかし、主上は面白がると思われませんか?」
「……否定しません。喜々として食いつかれるさまが目に浮かぶようです」
須磨は、額に手を当て、天を仰いでいる。
「承知いたしました。その方向で行事の内容を詰めて参りましょう。尚侍さま、時は有限でございます。決めることもたくさんございます」
「それは覚悟しております。共にがんばりましょう」
「かぐや姫」と須磨は頷き合ったのだった。