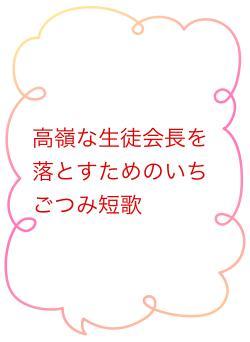月が白く輝く夜のこと。
姫様は丸い月を見上げて泣いていらっしゃった。はらはらと涙の粒が真珠のように見えました。
どうされたのですか、と声をおかけすれば、この世のものとも思えない美しい顔を私に向け、
「わたくしとともに逝ってくれますか?」
かすれた声で囁かれた。私はすぐに頷き、力強くこう申し上げました。
「はい。黄泉の国にもお供いたしますよ 」
その言葉は私にとって真実だったのに。
私には、幼いころから姫様しかいなかったのに。
今でも時々思い出すのです。涙に濡れた頬はそのままに、かすかに口の端に笑みを湛えた姫様は、いつになく私にもの言いたげでいらっしゃった。けれどその時は気付きもしないで。
ただただ姫様のお傍にいられることがうれしかったのです。姫様と過ごせる時間があの頃には少なくなっていたものだから。
どこまでもついていくつもりでした。行き先が黄泉の国でも、月の国でも。地獄でも構わなかったのです。
それなのに。
どうして。
私の主人――かぐや姫は私を置いていってしまわれた。
時は平安。ところは桃園第。絶世の美女が住むと京中に評判の邸だ。
姫君の名は「かぐや」。有名な物語から名付けられた。桃園大納言が年経てからやっと恵まれた子で、人の目を隠すように育てられた。しかし、愛らしさと美しさは広く知れ渡っていた。
かぐや姫が年頃になると、都中の貴公子から結婚の申込みが殺到した。しかし、姫君はどんな求婚にも頷かず、父の大納言は困り果てた。
「大納言よ。そなたの娘を朕も見てみたいぞ」
美女の評判は宮中にも届かないわけがなく、帝から宮中へ入内するよう催促が届くようになった。帝の度重なる仰せに耐えかねた大納言は、妃ではなく女官ならとどうにか娘の承諾を取り付けた。
こうして都中の注目を集めた出仕が決まった。宮中へ参入する日取りに向けて、邸中がその準備に大忙しとなった。
出仕前日には、常にお仕えする女房までもが、姫君の傍を離れざるを得なくなった。
姫君は邸の一室でひとりきりとなった。
女房が異常に気付いたのは、夜半のころ。出仕の準備を終え、やっと姫君の元に参上した時には、その姿は忽然と消えていた。
「姫様……? 姫様、姫様、どちらにいらっしゃいますか」
初めは邸内にいるだろうと思ったのだが、どこを探してもいない。
「姫様っ! お願いです、出てきてくださいッ!」
女房はだんだんと半狂乱になって、邸内をさまよう。騒ぎはやがて父大納言の耳にも届き、ひそかに邸内の大捜索が行われた。
しかし、懸命の捜索もむなしく姫君はいなくなっていたのだ。
父の桃園大納言は進退窮まった。明朝には姫君を乗せた牛車は宮中に向かわねばならない。だが、肝心の姫君がいない。宮中に、帝になんと言い訳できようか。これまでの姫君の評判はおろか、連綿と続いてきた名家の矜持にも著しく傷がつく。御先祖様に申し訳が立たない。
滝のような汗をかいた父大納言は正気を失っていた。こともあろうか、傍にいた女房――最初に姫君がいなくなったことに気付き、今もまだすすり泣いている者に、魔が差したとしか思えない命を下した。
「わしの娘がいなくなったのは、目を離したおぬしの責任である。よっておぬしが事態を収拾せよ。おぬしがかぐやの身代わりとなれ。かぐや姫として、宮中に出仕するのだ!」
その命にだれもが仰天した。まして、当の女房はあまりのことに言葉を失う。
無理ですよ、と別の女房がとりなそうとするのだが、大納言は血走った眼で、身代わり指名をした、若い女房の腕を掴んで、立ち上がらせた。
「この者は最も長く姫の傍に仕えてきた。年恰好も似ておる。幸いにも姫君の美しさは噂ばかりで、本当の容姿を知る者はほとんどいない! よいか悪いかではない、やるのだ! このことは他言無用である。ばれたら命はないと思えっ!」
「そ、そんな……。わたしに、姫様の代わりなど」
大納言に腕を掴まれた女房は涙でぐちょぐちょになった面差しを主人に向ける。だが、主人は冷たく彼女を見下ろし、傍らでびくつく若侍の腰に下がった太刀《たち》を抜く。
「四の五の言うでない! よいな、松緒。……おぬしの正体がばれたら、この邸にいる者みなが、帝を欺いた罪に問われるだろう。だがその前に……わしがこの太刀で! おぬしを斬り殺してくれようぞ」
「ひいっ」
太刀を振りかぶる大納言はまるで悪鬼のようだった。力任せに振り下ろされた太刀は畳に突き刺さった。
その大納言に腕を掴まれ、逃げられぬように脅された松緒は悲鳴を上げた。恐ろしさのあまり腰を抜かしてへたり込む。
「他の者たちも同じだ!」
次に大納言は周囲の者たちを睨みつけた。
「かぐやのことがばれてみろ、わしが地獄の果てでも追い回し、もういやだと泣き叫んだとしても容赦せずなぶり殺してくれるわ! よいな、こころせよ!」
だれもが平伏するほかなかった。邸の主人の命令には逆らえない。そして、出仕せよという帝の命令に背くことも、できはしないのだから。
結局、本来のかぐや姫がいないまま、宮中への出仕は行われた。かぐや姫の身代わりとなったのは、松緒と呼ばれていた傍仕えの女房である。
彼女は後宮へ向かう牛車で頭を抱えていた。大納言の姫らしく着飾られていても、松緒はただの女房だ。幼いころに市場で買われ、運よく姫君にお仕えできただけの……。
身体を震わせながら、何度も何度も、想像の中のかぐや姫に話しかける。
――どうして、私を置いていったのですか、姫様。
――姫様がおっしゃるなら、どこへなりともついていきました。
――まさか、こんなことになるなど思いませんでした。『ゲーム』にもそんな筋書きはありませんでした。
姫様の一番の女房は私だ。
松緒はそう自負しているほど、長い間かぐや姫に仕えていた。
彼女の現世における最初の記憶は、かぐや姫が市場で売られていた幼い彼女を見つけ、父親にねだった時のこと。
――父上。この子を私の女房にして!
かぐや姫の、滅多に言わないわがままだったという。娘に甘かった父大納言は悩んだ挙句、どこのだれとも知れぬ子を買った。
その時の松緒はぼろ布をまとった薄汚い子どもで、わけのわからないまま市場にいた(その時もどうして市場で売られていたのかの記憶もない)が、月の輝くような愛らしい子が目の前に現れたことはよく覚えている。
――とってもきれいな子……!
かぐや姫に拾ってもらえなかったら、きっと野垂れ死にしていた人生だった。かぐや姫は、人生の恩人であり、敬愛する主人だ。ともに成長し、いつも一緒にいた。松緒の人生のほとんどは、かぐや姫でできている。
そして、かぐや姫を大好きな理由はもうひとつ。彼女は、松緒が前世で大好きだった乙女ゲームのヒロインだということ。
松緒の前世は、現代日本で働く平凡な事務職のOLだった。残業が多く、ストレスも多かったが、隙間を縫って乙女ゲームをプレイするのが日々の生活の癒しになっていた。ただ急な事故に巻き込まれて若くして死んだらしい。
松緒が一番好きだったゲームは「平安雅恋ものがたり」だ。ヒロインのかぐや姫が、架空の平安宮廷でさまざまなタイプの貴公子と恋に落ちる王道シンデレラストーリー。メインヒーローは帝だったと記憶している。
松緒が転生したのはまさにこの乙女ゲームの世界だ。それもかぐや姫にお仕えする「お邪魔虫女房」という立場だった。
本来の「松緒」は、各ルートでかぐや姫の邪魔をする役どころだ。理由は……かぐや姫の美しさと幸福に嫉妬したから。彼女は周囲の人間が幸せになるのを許せない人間だったのだ。
「松緒」はどのルートでも結局は悪巧みが発覚して、ヒーローの手により破滅させられることになっている。
しかし、今の松緒の中身は疲れ果てていた未婚OLだったし、前世の記憶を取り戻す前には幼いかぐや姫の愛らしさにノックアウトされていた。成長とともに前世の思い出が蘇っても、松緒の「姫様大好き」加減が増すだけだったし、「お邪魔虫」になるはずもない。
毎日毎日、かぐや姫の傍でお世話ができることが幸せだったし、なんなら乙女ゲームがはじまらなくてもよいと思っていた。
――「かぐや姫の出仕」はイベントだったのかしら。
松緒の記憶も万全ではない。前世に置いてきたと思われる歯抜けの部分もある。「平安雅恋ものがたり」のルート詳細もそのひとつだ。かぐや姫の身の回りで起きることは気になってしまう。
松緒が「お邪魔虫女房」でなくなったことで起こるはずのイベントが起こらず、乙女ゲームの筋書きからすでに外れているのかもしれない。それか、そもそも始まっていないか、進行中か。
かぐや姫には特定の相手はいなかった。どんな求婚にもなびかなかった。帝からの婉曲な誘いも反故にしていたほどだ。
「もしも姫様がご結婚されなかったら、一緒に商売でもはじめましょう。二人でがっぽがっぽ稼いで、悠々自適に暮らすんです」
松緒は結婚しようとしないかぐや姫に、半分夢みたいなことを話すこともあった。
かぐや姫も松緒の戯れにのってくれた。
「ふふ。楽しそうね。何を売りましょうか?」
「椿餅です。今おいしい椿餅の作り方を研究しているんです。うまく作れるようになったら寺院のそばに屋台を構えましょう。ご利益がありそうだって、みんな買いますよ」
松緒が胸を張る。半分は夢でも、半分は本気だった。椿餅の作り方を研究しているのは本当だったし、かぐや姫が未婚を貫き、父親から追い出されることがあってもかぐや姫と二人で暮らせるよう、床下に隠した甕に銭を貯めている。
「いいですね。その時はわたくしも売り子になりましょう」
「いけません。姫様がいらっしゃったらあまりの美しさに大騒ぎになってしまいます……!」
老いも若きもかぐや姫目当てに大挙するのが目に見えるようで、松緒は慌てたが。
「儲かりませんか?」
かぐや姫の問いには正直に答えざるを得なかった。
「うぅ……姫様が手ずから売れば、売れるに決まっているじゃないですか…! 都に御殿を建てられますよ……!」
かぐや姫はころころと笑っていた。その表情ははっとするほど華やかで、思わず目を惹きつけられてしまう。
無表情でいれば満月のようにぞっとするほど美しく、微笑めば花のように柔らかな人だった。
松緒はかぐや姫のもっとも近くにいたという自負はあるが、かぐや姫ではない。だれもあの人の代わりにはなれない。彼女に心酔していた松緒がだれよりも知っていた。
――私が姫様の代わりなんてなれるはずがないのに。
桃園大納言の意志は固かった。彼は宣言通りに即席で松緒をかぐや姫に仕立て上げ、後宮に送り込んだ。
松緒は「かぐや姫」として尚侍という役職についた。
尚侍とは内侍司(宮中の礼法などを司る部署)の長官である。帝の妃が正式に入内する前につく地位でもあるが、その点はかぐや姫が承諾していなかったからすぐに帝の寵愛を得ることにはならなかった。
しかし、「かぐや姫」は注目の的だ。宮中暮らしに慣れるよりも早く、次から次へと客人が訪ねてきた。彼女の美しさを一目見たい者が宮中には大勢いた。
松緒は自分の顔を見られないよう隠すほかなかった。自分の顔はさして美しいものではない。すぐに偽物だとバレてしまう。
住まいの殿舎には御簾を下ろし、几帳や壁代を幾重にも張り巡らせた。松緒はその奥に座り、肌身離さず扇を持った。だれかが入ってきても、扇をかざして顔を隠せるようにだ。
声を発することも抑えた。かぐや姫の声を知る者もほとんどいなくても、かぐや姫は声までも美しかったから正体がバレてしまうかもしれないからだ。
実家から引き連れてきた信頼できる者だけ、居所に入ることを許した。
松緒は人を近づけさせたくなかった。訪問者たちの誘いをことごとく断り続けたのだ。
そうしてもなお、訪問を拒み続けられない相手がいた。桃園大納言が松緒のところまでやってきて、
「よいか、『かぐや姫』。この書状に名のある者たちには逢いなさい」
「ですが『父上』、それでもしものことがあれば」
「そのようなことはない。顔を見せなければよいだけではないか」
桃園大納言の目は血走っている。かぐや姫に書状を押し付けて立ち上がった。
「できぬとは言わせぬ。わしにも立場があるのだ」
松緒が引きこもっていることで、彼にも圧力がかかっているのだろう。口調ももはや投げやりに近いようにも感じる。
松緒はせめて、と声をひそめて尋ねた。
「あの、姫様の行方は……」
「見つかっていない」
大納言の答えは簡潔だった。足音激しく出ていく。胸に書状を抱えたまま、松緒はうなだれた。
――どうしよう。……どうしよう。
いくぶんか経ってから、松緒はそろそろと書状に目を通し、すぐに天を仰ぐ。
――どの方も「知っている」お名前……。本来なら姫様ご自身で出会うはずの……。ここにいるのが私だなんて、何から何まで間違っているのに。
――姫様が見つかったら、身代わりは終わる。その時のために、『この場所』は守らないと……。姫様の、ため。
目尻に滲んだ涙を拭いながら、書状に書かれた名前を何度も何度も読んだ。
――やらなくちゃ。私は『姫様』になる。
もう逃げられないと悟った。
姫様のことは何年も見てきたから。どんな表情でも、どんな声でもまざまざと思い出せる。
この身代わりが、かぐや姫を守ることになるのだ。松緒はそう信じた。
けれど――
『そなたはかぐや姫の……偽物だな?』
それからほどなくして、ある男から冷水を浴びせられるような言葉をかけられることになる。